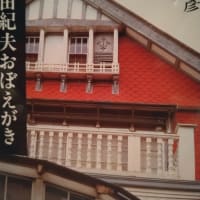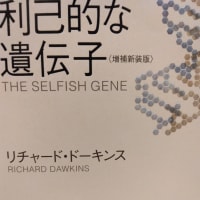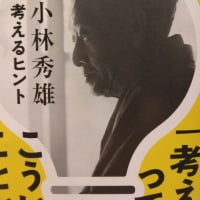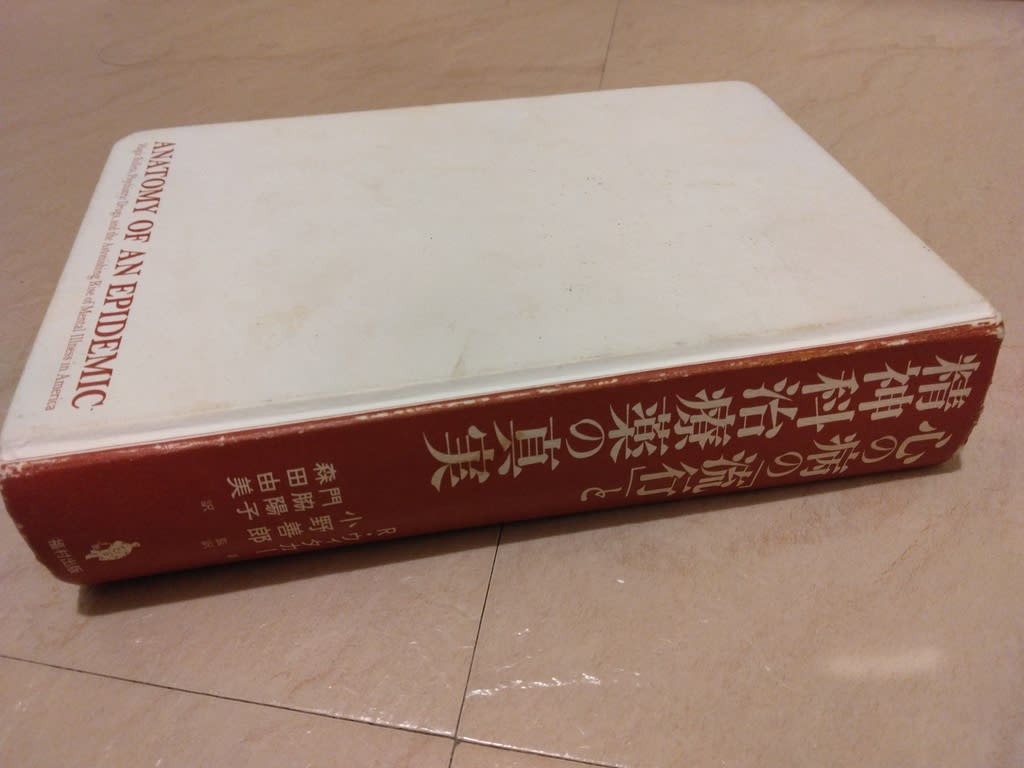
シュテファン・ツヴァイク(1881~1942年)は、死の直前に書いた回想録『昨日の世界』の序文で
「常に人は国家の要請に従わなければならず、最も愚劣な政治の餌食となり、最も空想的な変化に適応せねばならなかった。
......(中略)......この時代を通って歩んだ、あるいはむしろ駆り立てられ、嗾けられた者はだれでも、その祖先の人間が体験した以上の歴史を体験したのである」
と書いている。
実際、19世紀末から20世紀初頭は、生きにくい時代であったようである。
政治的には、国家主義が台頭してきており、経済的には資本主義が発達し、マルクスが「人間の疎外」と言い、チャップリンが『モダン・タイムス』で描いたような人間の機械化・商品化が進んだ。
とりわけ、19世紀に生まれた人間にとって、この急激な変化は耐え難いものだった。
なにしろ、彼ら/彼女らは、人間が疎外されず、人間らしく生を謳歌できた『昨日の世界』を(たとえ、それが、いくぶん美化されたもであったとしても)体験していたからである。
彼ら/彼女らにとって、まさに20世紀は人間が破壊されてゆく過程であり、その痛ましさに疲れ果てると、必然的に「昨日の世界」への郷愁の眼差しを向けずにいられないのかもしれない。
これは、ロシアでも事情はあまり変わらなかったようである。
ロシア音楽はリムスキー・コルサコフたちを代表とする「国民音楽派」、つまり、ロシア民謡やロシア独特のメロディーといった、ロシアの土着性に根ざした音楽を中心に発達してきた。
その系譜に連なる最後の代表的作曲家がラフマニノフである。
彼の音楽もまた、母なるロシアの大地、というイメージに溢れている。
しかし、20世紀になると、それも「昨日の世界」となってしまうのである。
革命の嵐が吹き荒れ、
「労働者による新社会の建設」が始まったのである。
ラフマニノフに比べて、アレクサンドル・グラズノフ(1865~1936年)の名前は有名とは言い難い。
しかし、「昨日の世界」では、グラズノフこそ、ロシア音楽界の重鎮だったのある。
1881年、無名の作曲家の交響曲第1番が初演された時、そのあまりにも洗練されたスタイル、美しいメロディーに聴衆は熱狂した。
熱狂する聴衆の前に呼び出された作曲家は、学生服を着た16歳の少年であった。
神童グラズノフのデビューである。
それからのキャリアは華々しいものがある。
書く曲はロシアのみならず西側諸国でも喝采を浴び、その重厚な作風からは「ロシアのブラームス」と称され、やがて1905年、ペテルブルク音楽院院長として後進の指導にあたるようになる。
しかし、時代は激動期に入りつつあった。
ペテルブルク音楽院院長に就任した年には、「血の日曜日事件が発生」、戦艦ポチョムキンが暴動を起こし、ツァーリ支配は、揺らぎ始めていた。
革命の気運が、新しい世界を目指す熱気が、ロシアを覆った。
「昨日の世界」は忘れ去られようとしていた。
そして、ソビエト体制が発足すると、グラズノフの音楽は過去のもの、と、なった。
新しい世界には、新しい音楽が求められたのである。
時代に取り残されたグラズノフは、やがてフランスに亡命し、そこで客死するのだが、彼の死亡のニュースは世界を驚かせた。
「なんだ、まだグラズノフって生きていたのか!」と......。
そのころには、彼の音楽はあまりに古くさいものと捉えられていたため、世界は、グラズノフはとっくの昔に亡くなっていると思っていたようである。
一時は、世界的名声を浴びながらも、グラズノフは歴史から忘れ去られた。
彼の名を音楽史にとどめているのは、その創作の絶頂期(1904年)に書かれたヴァイオリン協奏曲ただのみによってと言っても過言ではない。
しかしながら、その音楽は正に傑作である。
物憂げなロシア的叙情にあふれ、協奏曲として不可欠な技巧の見せ場にも富み、形式と内容とが完全なバランスを保っている。
まさに、大地と共に生き暮らしたロシアの「昨日の世界」、その太陽が沈みゆくときの最後の残照、暮れなずむ夕映えにも似た味わいがある、と、私は思う。
そしてそれを聴く、私は、同時に、時代に取り残された天才の悲哀をも感じるのである。
ここまで、読んで下さり、ありがとうございます。
見出し画像は、またまた、今回の文章とは関係ないのですが^_^;
私が病気と病気治療の後遺症と闘うときに助けになった本のひとつです。
今日も、頑張りすぎず、頑張りたいですね。
では、また、次回。