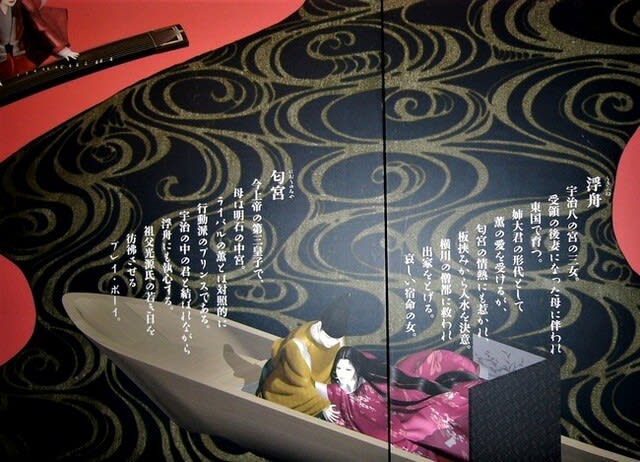キハナ(季華)という名の女の子の孫がいる。いつのまにか、女の子とも言えないほど成長してしまったけれど。その命名には、私も関わりがある。四季折々に咲いている花のようにあってほしい、という思いを込めた名前だった。彼女が花のように育っているかどうかは、まだわからない。いつのまにか高校生になったと思ったら、もうすぐ卒業しようとしている。
何かをたずねると、「わからへん(わからない)」という答えがかえってくる。それが口癖になっているのかもしれない。本当にわからないのかわかっているのか、よくわからない。「わからへん」と言いながら、何事もすいすいとこなしてしまう。脳天気ともいえるが、善意に解釈すれば、いつも自分でわかっていることよりも、さらに先の未知の部分をみつめているのかもしれない、ともいえる。未知のことは、誰でもわからへん(わからない)ものなのだ。
昨年の夏には、通っている高校の学園祭があり、招待券をもらったので参観に行った。クラスで創作劇をすることになり、彼女は尻込みしたが、皆んなに背中を押されて出ることになったと聞いた。劇が始まってみると、彼女はなんと劇中のヒロイン役だった。演技はぎこちなかったが、現代っ子らしい激しい動きのダンスや、さまざまな場面転換の雰囲気を、それなりに楽しんでこなしているようにみえた。
いつからか、大学は東京に出たいというのが彼女の夢になった。家庭の経済のことも考えて、寮のある国立の某女子大がターゲットになった。かなり手ごわい大学だが、推薦入学の一次審査を通り、先日は東京の大学まで二次の面接試験を受けに行った。あいかわらず、どこまでわかっているのかわかっていないのか、試験が楽しみだと言いながら、るんるん気分で出かけていったようだ。
だが面接試験が終わると、とたんにどん底に落ち込んでしまった。まさか面接官の質問に「わからへん」とは答えなかったと思うが、面接官に椅子をすすめられる前に、さっさと自分から座ってしまったし、終わったあとも退席の挨拶もしなかったような気がするという。前もって高校で指導された、面接の基本的なことをミスしてしまった。だからもう駄目だという。
本人は緊張することもなかったというが、あがっていることもわからへんほど、舞い上がっていたのかもしれない。それから3週間、彼女にとっては珍しく暗い日々がつづいた。
合格発表は大学のホームページにアップされると聞いていたので、指定された日のその時間を待って、パソコンにアクセスしてみた。そこには彼女の受験番号があった。なんども確かめた。まるで受験生本人のように動悸がした。さっそく彼女に電話をすると、ほんまに?ほんまに?と、信じられないといった声。パソコンがなぜか繋がらなくて焦っていたという。パソコンが不調だったのか彼女の操作が間違っていたのか、そのことはたぶん、彼女にも「わかれへん」かっただろう。
かくて、彼女の新しい進路も決まった。いまは喜びが大きすぎて、どう喜んでいいのかわからずに戸惑っているようだ。東京での生活は、ほんとの「わかれへん」ものが、もっとたくさん待っているだろう。そこでも「わかれへん」という呪文で、なんとか乗り切っていくのだろうか。
「2024 風のファミリー」