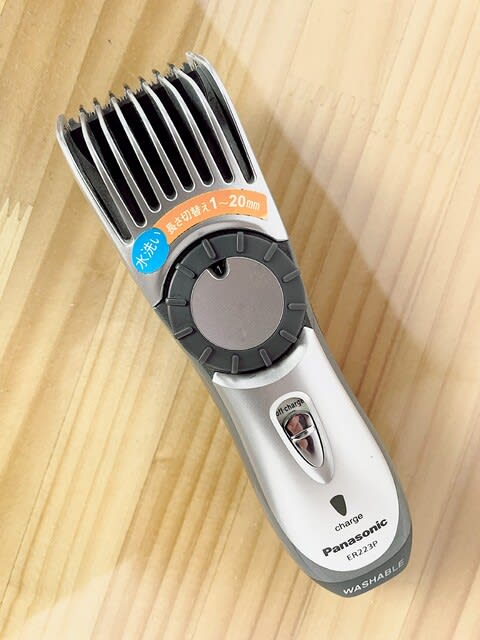【はじめに】
まあ、出だしから何ですがスマホで撮影などの一般の方々にはナンジャラホイのチンプンカンプンの日記になってしましました。
まとめでも書いてはいるのですが、最初のミノルタ・フラッシュメーターⅣで脱落する方は多いかもしれませんが、アマチュアカメラマンでなくとも、このような時代があったことを知りたい方は一読してみても良いかもしれません。なんせ、その昔プロのカメラマンが開発に関係した教授に、教えを乞うレベルの内容です。
そんなに難しい話ではなく、そこを分かりやすく書いたつもりですが、気軽にどうぞでもないですが興味のある方はどうぞ!
【露出計・フラッシュメーター&スポットメーターとは】
写真撮影時など天気や室内照明の明るさの違いによって「絞り値」「シャッター速度」を決定させ適正な露出を決める機械です。近年では標準内蔵されフルオートで意識することはあまりないことでしょう。
一般的には、「フラッシュ光」「定常光」を測るタイプに分かれますが同じメーターで一緒にスポット測光(反射光)も可能な機種は私の若い頃にはまだ少数派です。白い小さなドームは受光球で(入射光)を測ります。電源も必要なタイプと不必要なタイプに分かれます。電気的なものが完全に不必要という訳ではないみたいです。でも乾電池は不要なセレン光電池式もあります。他にも様々あり詳しく知りたい方は調べてみるとよいでしょう。ここでは自前の露出計などのお話となります。当初の予定より長くなってしまったのですが、宜しければご覧ください。
アマチュアカメラマンの多くは35mm一眼レフが多いならばその点は、云十年前からほぼ不必要でしょうか。ニコンFでは標準では無く必要ですが、ニコンFAでは確か初の分割測光(マルチパターン測光)が登場しますし、スポット測光の得意なOLYMPUS OM-4Tiなどの高級機には憧れました。
カメラ内蔵の露出計で「スポット」「中央部重点」「分割測光」と揃ったのは意外と古い話でして、ニコンですとF4(銀塩カメラ)を待たなくてはなりませんでした。
それでも「露出補正」は未だに必要な要素でしょうか。つまり銀塩カメラ内蔵は反射光の測光です。18%グレーに相当するものがない場合、ことは単純ではありません。3D-RGBマルチパターン測光ですと更にF5を待つこととなります。現在のデジタルカメラでは基本的に撮像素子で測るようです。
現代でもミラーレス一眼、絞りやシャッター速度を操作可能なカメラを所有している場合、いずれかの露出計があると便利なことは多いでしょうか?こと照明器具を使用する場合便利ですし、照明比を設定する場合も必要です。デジタルカメラでも露出は最初から決まっている場合が一番よろしく、いくら補正可能っても画質は落ちてしまいます。
カメラ側の露出補正は使い方にもよるのですが全てのシーンに対応しているわけでもないのが大方でしょうか?
初めて使った露出計はカメラ内蔵のを別にすれば、写真学校の備品でセコニックの露出計でした。見た目は、その黒くてよく覚えておりませんが相当古いです。多分スタジオデラックスだとは思うのですが。スタジオでタングステンライト照明での測光ですと、穴の開いたHIGHの板(ハイスライド)を外します。動かない!って怒っちゃダメぽ。日中屋外で針が振り切れる場合は受光球の頭に差し込みます。(通常は背中に格納されています)スタジオはそれなりに広いのに暑かったのをよく覚えております。
4×5でアオリ、照明の当て方、接写ですので露光倍数、それからシートフィルムの露出の乗せ方が課題でしたでしょうか?最初から答えを教えてくれる先生方ではないので苦労した記憶がありますが、その分ためになった部分も多いでしょうか?
仕事では、いくら経費として使えるとはいえポラをバンバン撮ると「お前さん、いい加減にしろよ」とお叱りを受けます。
それから嫌な思い出として、撮影実習時落下させてしまい自腹で点検です。学割が利くとは言え貧乏学生としては正直懐は痛かったです。電車賃も自腹で市ヶ谷までです。( ;∀;)
無電源で小型なのですが。現在のLEDや蛍光灯の照明器具の明るさやライティングレシオを決めるのには必要です。まあ、LEDとかですと見た目である程度判断できるので不要な方には無用の長物となるか、まあ要らないでしょう。ただ特にプロカメラマンや本格派には必要です。コンパクトなタブレットカメラでは不必要でしょう。フルオートのカメラでもそれほど現代では必要ないと思われます。デジタルカメラ全般、ミラーレスカメラ、動画カメラ、その他、見たままほぼその通りに再現されます。もしくは自動で夜間モードに切り替わるなど。ただ、その昔は必要不可欠な道具でした。現代はほぼ何も考えなくて済みます。それより何を撮るか、どういったテーマにするかなどに専念可能なことでしょう。動画を配信する方の不思議な照明セットを見るに、どうやってたどり着いたか聞きたくなるようなライティングも多いですが気になるライティングも中にはあり、どうした?もあります。
それでもプロは必要だと思います。特に照明器具を扱う人は。ライトマンも必要です。もっとも大手のレンタルスタジオには常備されている場合もありますが。CM撮影もフィルムのころ、一緒に撮影していると露出は良く聞かれたほどシビアなポジフィルムです。
個人的には屋外での風景写真を中判&大型カメラでの使用も多く、風景撮影のスポットライト測光。それからスタジオでの大型フラッシュの測光が多かったので、当時高額だったのですが購入しました。いちいち35mm一眼レフを露出計の代わりに持ち歩くのはどうも。それにフラッシュはクリップオンタイプでカメラで完全に測れる時代に後に移行する時期でしたがプロはオート半分でもなく不信感しかなかった記憶が、ほぼマニュアルって感じでしょうか?それでもジェネレーター使用の大型等の測光にはなくてはならず、クリップオンのフラッシュでもスタンドに立て使用する場合は必要なことが多いのもプロならではでしょうか?時代は3D-RGBマルチパターン測光になろうともフルオートには頼らないカメラマンは当時多い傾向でしたでしょうか。これから紹介する露出計はそれ以前のモデルが多いです。
若いころ約9万円のメーターを購入するには度胸がいります。今なら銀塩カメラかちょっとしたオールドレンズ数本購入でき、酒を飲みながら肴にできる値段です。
これらは20世紀を代表するハイテク露出計です!またミノルタだけではありませんがカメラのみならず露出計の老舗でもあります。
前置きが長くなりました。失礼!

【ミノルタ・フラッシュメーターⅣ】
もう使い方のほとんどを忘れてしまいましたが、これが自費で初購入の露出計です。そうです、SONYでもなくコニカミノルタでもなく、正真正銘のミノルタです!
単三電池1本で動きますが4SR44もあったはずですが通常使用は単三電池1本です。当時初心者用としてはやや難解なメーターでもありました。本格派のフラッシュメーターには三脚ネジ穴があります。他に何台か販売されていましたがこれは高級機です。他は当時唯一カラーメターもありました。
まあ普通にフラッシュメーター、スポットメーター、受光部で定常光を測るとして使う分には、基本的なことは何も問題ないのですが。(;^ω^)
pdfにもあるように露出解析付き多機能露出計...、とあるように本格的にハイテク露出計です。また当時α-9000、α-7000にデータ送信可能なマシンです。
ミノルタをはじめ、まだまだカメラの露出計では一発で決められない時代でもありましたでしょうか?シネマ撮影用とかコントラスト表記も可能なのですが、話がやや複雑になりますので一旦置きます。
当時、露出計の中でもフラッシュメーターと言えばセコニックかミノルタが人気でしたでしょうか。

ビューファインダー5°(接近時視差のポイント表示あり)

ビューファインダー5°装着時。首は向かって左45°回転し、右に180°回転します。ガンのように握り測光スイッチを押しやすかったです。親指で測光ボタンを押す形になります。
ビューファインダーは向かって右側に装着も可能です。これだけで高さは同じになります。

ケースセット。ビューファインダー5°を取り付けたまま収納も可能でした。これだけ時代を経てもペイントが薄れた以外ほころびひとつ無いのはさすがです。
色々設定があるのですが、特徴としては簡単に申し上げますとフラッシュ光と定常光が測れます。オプションで当時5°と10°のスポット測光可能なレンズも別売りでありました。名称は「ビューファインダー10°II」「ビューファインダー5°」です。それから各部測光し、メモリー可能で①ハイライト基準露光②シャドー基準露光③アベレージが演算表記できることです。それらを表示させるには各箇所測光しメモリーすることが条件ですが。まあ結果的に評価測光をしているのとは異なります。個人的には露出計としては有り得ない豪華な使い方冊子をなくしてしまったことが悔やまれます。
これは早い話、ポジフィルムでのハイライト基準露光、ネガフィルムでのシャドー基準露光のための露出計と言ってよく使用してみると、これほどポジフィルムやネガフィルムに合った露出計はありませんでした。
他の露出計にもメモリー機能が付いているものは当時なくはありませんでしたが、単純に各所測光してメモリーしアベレージを出す、まあ結果的に評価測光をやっているのとは異なりますがやや平均測値を求めているにすぎないでしょうか?(それは言い過ぎ?)
これは正直いきなりやや難解なフラッシュメーターを購入したと反省するとともに、使い慣れるとこれほどポジフィルムやネガフィルムに有難いメーターはありませんでした。しかも仕事ではフラッシュも測れるのです。ガイドバリューやコントラスト表示とか、メモリー表示とか、あの時代一般的には混乱を招きかねないかもしれません。つまり安い露出計にそんなものは無いのです。
最後の点検は1999年です。古い機種なんですが思い返せば名機です。ただシンプルに使いこなすことが難しい機種でもあり、どちらかと言えば嫌われたメーターでもあったでしょうか?私は使い方のコツをつかむとこれほど便利なメーターはないと、ぞれは随分と使用したものです。
一般的な風景写真ですと1°のスポットメーターが人気でしたでしょうか?ゾーンシステムでも1°のスポットメーターを推奨していたようですが、わたくし個人の解釈はやや異なります。まず1°のスポットは厳密過ぎて自然界では使いにくいことが多いのです。大陸では別でしょうが日本では広葉樹など葉の色やテカリなどで微妙なバラツキが出てしまいます。個人的には5°のスポットが一番使いやすかったでしょうか?
それから液晶モニターには絞りが横軸で分かりやすく表記されるのも見やすかったです。よって左サイドのスイッチはFナンバーにセット。右側のスイッチはシャッター速度表示(TIME)にしてあります。ほぼこの状態です。TIMEの方が絞り優先表示でレンズシャッターなど使用しやすいです。

「ハイライト基準露光とは」
当時のポジフィルムはハイライトがメモリー基準値露出より-2.3です。
つまりフレーミングした画面内、一応ハイライトにしたい、あるいはなるであろう明るさの太陽光の当たる白壁などをスポット測光し、メモリーさせ、最後に正面やや右上の「H」ボタンを押すのです。
すると一発でハイライトが飛ばない、撮影時ぎりぎりの露出を表示してくれるものです。太陽光をワイドで入れてハイライト測光はきわどいので「f16/フィルム感度がシャッター速度」と覚えてしまうと楽でしたっス。(ハイライトを詰める場合はです)
そもそも5°で測光できるハイライトがない場合、18%グレー的な物を見つけ測光で済ますこととなります。それから色により補正でしょうか。
写真の例は、ハイライトになるであろう部分をスポット測光し、メモリーします。後にHのスイッチを押します。
ISO100で1/30秒、f16がハイライトの飛ばない露光値として表示されます。メモリーは2回まででしたでしょうか?それ以上ですとエラーが出ます。メモリーすると画面右端に小さくドットが表示されます。二回メモリーでドット2個です。モニターにはハイライト基準露光のHが表示されます。AMBI表示もされます。
絞りの横表示はf1~f90まで。実際そんな絞りないよ!と思われるかもしれませんが昔のカメラでf128とかありました。また比率をみるのにも使いやすいのです。
この場合、ハイライトにする明るい箇所は最初f32.3となっていたはずです。そこから‐2.3するだけなんですが、f値がコンマ1単位で表示されシャッター速度もスライドさせると、実際はやや混乱しやすいのです。ハイライトの決定に困ったら2か所メモリーしても良いかもしれません。ハイエストライトは含まず、その分は明るく計算されていたはずです。
最初のf32.3のバーと演算されたf16のバーが表示されます。これで比率が見やすくなります。なお雪景色では必ずこれが有効でもないです。晴天ですと雪景色にグラデーションを作りたい場合或いはそうなる場合、スポット測光し比率を見極めることが必要です。個人的にはスポットして+1.5~+2が基本だったような?反射角度によります。また朝陽を受けているときも異なります。
で、テスト測光の日の天候を考慮すれば大体こんな露出表示でしょうか?なお測光場所が薄暗いと自動でグリーンのライトが点灯してくれるのを思い出しました。
また入射光でも機能はするのですがフラッシュですと、どちらもちょっと使いにくいかもしれません。
個人的には白い雲などを飛ばさないよう明るく撮影したい時など重宝しました。
考え方としてはフィルム用なのでデジタルカメラでこれを、そのまま応用でドンピシャでは来ないと思います。でもデジタルカメラもハイライト基準が一般的ではあります。あまり他を計算せずハイライトに拘るとアンダー傾向に陥ります。またかなりのシャドーになるであろう部分が画面にある場合潰れますが、そういう作風であれば問題なしとなります。ここは注意が必要です。
とにかくフレーミングした画面内のハイライトを決定、若しくはそれ以上飛ばさない測光です。応用としては薄暗い森のグリーンも、グラデーションを作り、ハイライトを決めるのにも便利な機能です。一応スポット測光の部類に入るので比率を測ることは重要です。
「シャドー基準露光とは」
これはネガフィルムのシャドー部が抜けてしまい諧調が得られなくなることを防ぐための機能で「+2.7」補正されるものです。フィルムでいうと35mmや120,220サイズまでの機能でしょうか。そもそもフレーミングした画面内や近辺にシャドウに相当するものがない場合は18%グレーに相当するものを測光し、補正を加えることとなります。グレーと言っても、砂や砂利などは意外と明るいので注意が必要です。アスファルトも古いと明るく反射しています。モニターにはシャドウ基準露光のSが表示されます。
いずれもゾーンシステムの解釈とはやや異なります。4×5や8×10などのシートネガフィルムにも応用は、シートフィルムのネガフィルムに更に二~三段は最低乗せます。プリントは大変ですがシャドー部までの諧調は最高です。現在ですと、ネガフィルムもスキャンしてからのプリントですので結果どうなるかはやったことはありません。自分で焼きこみの場合は問題ないですがハイライトはそれなりに時間がかかるはずです。

テストでは適当なシャドーが見当たらなかったので、まあこの辺だろうと測光しました。結果はSスイッチを押しf11.4です。先ほどのポジフィルムでのハイライト基準からすれば、半絞りのっけめの露出となりますが、シャドー部の諧調を重要視する場合ほぼ誤差の範囲の測光でしょうか。
ただシートフィルムのポジにはこのままハイライト基準露光やアベレージが使えます。
ここまでは主にスポット測光の「反射光」での演算となります。頭で覚えておけばいい話ですが現場は混乱しやすく、この機能は当時正直助かりました。
いずれにせよフィルムでは太陽光の当たっている部分と日陰を混ぜてフレーミングするにはハーフNDなど使用しなくてはならないのは現代と同じなのですが、銀塩の場合絞り込んで風景写真を撮ることが多かったのでNDのぼかしがバレてしまいます。山の稜線もごまかし切れないです。現在もハーフNDやセンターNDなどはデジタル時代に合わせて進化しておりますが、中々使いこなすのは大変です。最初から画面を欲張らず日陰は日陰、日向は日向と割り切った方がきれいな諧調が得られやすいです。強引にかなりのコントラストで画面に収める場合も一応シャドー基準露光となるでしょうか。
(これらはすんなり理解するのは実際測って現像の結果を見ないと理解しにくいと思われます。開発の一端を担った方の話を聞くに「日本版ゾーンシステム」だそうです。
アベレージを別にすれば、確かにポジのハイライト決定、ネガのシャドー決定で、風景写真ではほぼ話は決まりです。フラッシュ測光では難しいのですがスポット測光では一応可能となりますが、そもそもスタジオワークの場合照明はカメラマンが設定してしまうので不必要な作業です。ここがユーザーに難解、もしくは不要な機能となることが多かったようです。それからモノクロ現像は自分で作業する場合新液では、硬調なうえかなり強くでます。一般的に良好な結果は出せません。現像液の管理も重要です)
「アベレージとは」
これはスポットでなくともよいのですが、ミノルタの場合二か所メモリーさせAボタンを押せば、中間値が演算され、それは一応「平均測光」となりますが、カメラ内蔵の平均測光とは異なります。ニコンでいう「マルチパターン測光」でもないです。またの名を「分割測光」言い方は各メーカーそれぞれですが、平均値という意味では「平均測光」の露出計とも異なります。露出計での測り方次第でしょうか?
フラッシュメーターⅣではハイライトとシャドーをメモリーさせAを押せば、ほぼ中間値が表示されます。微妙な18%グレーゾーンをスポットなどで測光し平均値を出させる手段もあります。これは入射光や反射光(ビューファインダー使用)でも使えます。ただ先ほども書いたように照明機材を使用した場合は一般的に不要な機能でしょうか?
ただ実際には、f値がコンマ1表示なので、余計悩むと思います。これは、どの測り方でも同様です。あまり気にならないのはスタジオデラックスなどの針ですが、そもそも測り方を間違えている場合は、露出は合いません。
カメラ内蔵の平均測光や中央部重点測光では逆光時太陽が画面に入る場合、若しくは明るい背景ですとアンダーです。また白や黒は苦手。肌の色も明るく健康的になら露出計の表示を鵜吞みにはできないのが一般的なカメラの露出計です。赤や黄色、オレンジも若干補正が入りますが、それこそプロの味とでもいえばよかったのでしょうか?今は、ほぼそのまんまです。
反射光を測光する場合18%グレーと同じ条件での場所なら、それを使用すれば一応一発で決まることにはなりますが、遠景の風景写真などではそうはいきません。
また表現上の理由で、そのままの露出で決めない事も多いです。(ハイキーが好きとか)
現代のカメラではRGB測光(カラー露出)も同時に計算しており、色によって露出が極端に左右されることも比較的少ないでしょうか。スマホカメラもその恩恵は受けているはずです。
ニコンがRGB測光を始めたとき不評だらけでしたが、時代に早すぎたとしか言いようがありませんでした。確かに露出が変わるので。でも「白」「黒」にかなり対応するのは現在でも完全ではないようです。プロは瞬時に露出補正をかけてしまうのでRGB測光は、当時、逆にカメラマンを悩ませる部分でもあったでしょうか。これらの露出計にはRGB測光はありませんが一眼レフでいうとNikon F5あたりでしたでしょうか?ただ後にデジタル一眼レフ時代には必要不可欠な要素となります。
話を戻しますと、評価測光のできるカメラに小さなズームレンズがあれば、それは代わりになるかもしれませんが重く大きくなります。メインカメラが35mmなら反射光ではそれ程不満はないでしょうか。
またフラッシュ光もカメラ内蔵の露出計やスポットメーターでは測れません。(TTL自動調光はありましたが)
それからメモリー解除やH、A、Sとか表示させ、次のシーンを測光する時はメモリークリアします。メモリーさせる場所を間違えた時もクリアです。
欠点は個人的にビューファインダー5°が落下しやすくなってしまったことです。それだけ使い込むとは自分でも当初予想していませんでした。
他には平面受光板は付属品として欲しかったです。スタジオでは照明比を測るのにらくちんなのです。
なお、30秒など長時間露光に表示させた場合「相反則不軌」の補正なしを保証することではないので、現在でも特にポジフィルムで長時間露光をされる方は気を付けてください。夜景ですとネガフィルムでも条件により強く起こします。
つまり、露光した分、明るさが出ないのです。ポジフィルムですと雨の日の森の中とかでは早速この現象が現れ始めます。
取説のpdfファイルがありましたので添付いたします。これは貴重だ!!
https://www.kenko-tokina.co.jp/konicaminolta/support/manual/meter/fm4j0.pdf

【セコニック・L-508 ZOOM MASTER】
これ確か生活防水にフラッシュメーターと定常光、他にズームスポットメーターが最初から合体で販売され衝撃を受けました。

写真は受光球を下げた状態とズームの覗き穴です。ズーム光学はシンプルな作りですが測光には十二分です。ついでにズームスポットか入射光受光部の切り替えもここで決めます。奮発してかスポットは青いマークがあります。液晶パネルでも表示されます。この2つは回転式で二択です。ズームスポットは、どちらかというとやや厳密な方でシビアに測れたでしょうか?実際のところフラッシュメーターⅣの5°より厳しすぎで大変ですが、厳密に1°かアバウトに3~4°など便利でした。
やや大型化したものの、ミノルタ・フラッシュメーターⅣはビューファインダー5°が外れやすくて困っていましたし、受光球を下げるだけで平面測光が可能は目から鱗でした。フラッシュを測ることは結局ほとんどなかったのですが、それはそれぞれのカメラバッグやアルミトランク、カメラザックにほぼ入れっぱなしだからです。
山で中判カメラに露出計がないか4×5など使えないものが多かったため、これらを忘れ物すると悲惨な現実が待ち受けます。山で最高の雲海なのに、え~とこの場合の露出は???と、思い出さなくてはならないのです。
後にシンプルにズームスポットのないモデルを購入するのもセコニックです。やはり受光部が下がり平面測光が可能なため掌でカットする必要はないのです。
ただ電池が単三でないモデルは嫌われた傾向ではあります。
L-508 ZOOM MASTERは単三電池1本です。2台購入は8×10用です。かなり使い込んだ方はズームレンズが曇っていました。雨の日もかなり使い込んだからなあ~。
6×7&4×5は同じザックに一台。これが一番酷使。もう一台は忘れると悲惨なので8×10のバッグに。もう一台は35mm一眼レフのカメラバッグに、ハッセルブラッドは忘れると恥なので必ず何かを入れっぱなしでした。
ズームマスターのOHは一度もしていません。壊れたことはなかったです。ずぶぬれでも。それでも点検には出すべきでしたでしょうか?これは会社にある日セコニックの営業マンが持ち込んだものを一目ぼれってやつで、「あの~、お安くしますんで」に対し、じゃあ二台ください。との時代でした。営業マンは一台でも多く結果を出さなくてはならないので大喜び。私は仕事にもライフワークにも使えるで大喜び(^^♪
特筆すべきはズームスポットが1°~4°です。一番使ったのはやはり4°でしょうか。個人的に1°は苦手ですが必要。で、雨の日の山でも必要。ならばズームマスターではないか!!これ一台で完結(⋈◍>◡<◍)。✧♡
他には舞台やライブコンサートの方にも好まれたようです。当時、フラッシュメーターと一体型はやはりどことなくお買い得感がありました。
ただフラッシュメーターⅣの5°は実際もう少し広く受光していたのかもしれません。あくまで推測で、もしかするとですが。

ズームスポットの時、ガンに例えるとトリガー部に相当する場所にメモリーボタン(グレー)があり、うっかりメモリーは多かったのが唯一の欠点でしょうか?何度測ってもおかしいときは大体メモリーしてしまっています。
メモリーしてアベレージはあまり使わなかったです。ただこれで比率を頭の中で演算するのがこんなにめんどくさいかとも思えました。フラッシュメーターⅣの良さを感じます。ただメモリーすると、ドットが横バーの絞りレンジに表示されるので単純な比率計算はしやすかったです。
そのうえ、生活防水です。(o^―^o)ニコ

赤い線がまず左側が定常光、中央部の三角のような覗いているを表すマークがズームスポットです。風景写真ですとこれらを一番使うでしょうか。(実際に赤い線は表示されません)
意外と便利だったのがISO感度設定が二つ。フィルムの使い分けが多かったのも銀塩時代です。マガジンの交換やフィルムホルダーで使い分けです。カメラにカラー、モノクロで感度が若干、若しくは大きく異なる場合が多かったのも銀塩時代ならではです。またスタジオではポラロイドと感度が異なる場合も多々で、まさにプロ仕様です。
それから、横方向表示の絞りはf128まであり、イメージサークルの広いレンズや古い大判レンズをカバーします。(レンズシャッターです)
右側のダイアルはシャッター速度と絞りを変えて表示させるときに使用します。絞りのドットはこれに合わせて動きます。見た目非常にわかりやすい露出計でしょうか。他にも「モード」「ISO」設定などで動かします。
シャッター速度は、長時間の30秒まで表示可能です。暗いと液晶モニターは自動で照明が点灯です。これも「相反則不軌」の補正なしを保証することではないです。
あくまで露出の横軸を絞りで見やすくする意味合いが大きいです。また実際30秒以上の長時間露光は多かったです。個人的には腕時計のストップウオッチは欠かせませんでした。今思えばカウントダウンのキッチンタイマーが楽でしょうか。相反則不軌はフィルムや露光時間によって異なります。昔は補正するメモがあったのですが。余談ですがー30℃とかに冷却すれば軽減されるのはデジタルカメラでも同様なのは不思議です。デジタルカメラの場合熱被りも厄介です。
ズームスポットのズームは対物レンズ側をくるくる回すだけです。トルクは軽いですが不用意には動きません。一応ドットの小さい大きいで1~4°を表しています。
対物レンズにはキャップがありますが紛失しないよう、最初から紐はついています。
スポット測光の受光部がどういう仕組みなのかはわからないのですが、全体的に小型化に成功でしょうか。
ただ生活防水、防水機能をあまく見てはいけません。雨天撮影後のお手入れがなっていなかったため一台はレンズが曇っています。
またOリングなど現在では対応年数を過ぎています。生活防水機能は中古で程度の良いものがあったとしても気持ち半分がよろしいでしょうか。
「ズームマスターのメモリーとアベレージ」

測光ボタンは、ミノルタ同様親指で慣れたままで助かったのですが、メモリーボタンは、トリガー的な位置に来るためうっかりメモリーは多いです。
台に置いたとき傾斜ができてしまうのは当時あまり気になりませんでした。
これは3点メモリー可能です。なおハイライトとシャドーを2点メモリーさせた場合、フラッシュメーターⅣとは異なりハイライトがやや立つように設定されているようです。それぞれ絞りの横軸にドットでも表示されます。
「受光球が沈み平面測光可能」
これは本当に目から鱗で、流石セコニックでした。よくスタジオでライティングの比率測光ですと掌で覆って余計な光をカットするのですが、セコニックのこれらの場合、平面測光用の板が不要になりますし測光も正確です。
昔の方は、手のかざし方が違う!とそれはいびられます。場合によっては掌をL型にしなくてはなりません。多灯ライティングでこのような測り方が可能ですとかなり助かりますし、角度を決めて測光するだけに専念可能です。
個人的にはトップライトやサイドライトでエッジを立たせることが多かったので、この平面測光は楽でした。現在はブログですと使っても一灯。手抜きもいいところですが、一応基本的なライティングとなります。
35mm一眼レフカメラバッグに入れていたセコニックの露出計は、相当使い込んでいたのですが売却してしまいました。シルバーの小ぶりなやつなんですが。使いやすかったです。やはり電池式で残ったのは全て単三電池タイプです。
現在はスピードマスター L-858Dのようです。ハイテク化は進んでますね。フラッシュメイト L-308X も高機能でびっくりです。(;゚Д゚)
フラッシュの閃光時間が計測可能なハイスピードシンクロ対応モデルなんだそうです。
露出計・カラーメーター・照度計:製品情報:株式会社セコニック
https://www.sekonic.co.jp/product/meter/download/pdf/manual/L-508.pdf

【COMET EX-1】
これはもうシンプルにハッセルブラッドのゼロハリ専用です。入れっぱなしで場所を取らないのが最大のメリットです。単三電池1本です!!
フラッシュ光もコードありなし、定常光が測れるほか、ざっくり受光球をスライドさせ反射光も測れました。
これは比較的価格が低く1万円程度でしたでしょうか?実売価格はもう少し安かったと思われます。このころ既に学生さん用に購入する場合、露出計で数万円はやはり負担が大きいです。
実際のところ一般的なスタジオや屋外のモデル撮影にはこれで十分です。
確かセコニックが本家だったように思われますがコメットブランドです。
起動時にバッテリー残量が表示されます。セットすることはISOとシンクロ、定常光、シンクロ設定でフラッシュが測れるようです。
この辺は大体、変更はなく使いやすいです。もうこれが仕事上使うには最低条件揃っていまして、不満な方はドット表記が気になるかどうかでしょうか?
何より、当時標準バッテリーは単三電池なのです。ボタン電池すら嫌われる傾向です。まあ露出計ですから電池は長持ちする方なのですが、例えば山に遠征とかですと入れ替えてしまいます。他にも結婚式で電池切れは当時多く、プロですとそういった意味でミスがすくないのは、まず電池をすべて新品にしてしまうからなんです。
現代に例えるなら、リチウムイオンのカメラの充電にエネループなども完全に充電することでしょうか?エネループなども使い切ってから充電が長持ちはするのですがカメラマンの場合プロアマ問わずそうはいきません。
まあスマホのバッテリーも限界まで使用してからゆっくり充電が望ましいのですが、災害列島日本です。なるべく寝る前には充電が望ましいです。
まあそんな訳で、これも比較的使用した割には綺麗です。

【セコニック・スタジオデラックス MODEL L-28c】
まず乾電池が不要なのと現在ではレトロな感覚が人気なのでしょうか?
久しぶりに引っ張り出しました。これはあまりコレクションしなかったです。買う人はこのセレン光電池式等でシリーズで買い集めるようです。新品もまだあり、人気のようですが、これはやや使用感あふれる方がレトロ感は自然にあって丁度よい感じです。

テーブルに置いたこの状態で計測。コメットはISO100、1/60秒、f5.6程度でしょうか。因みにドット表示が嫌いな方は頑なに買いませんが便利です。
スタジオデラックスは針でして。①ASA(ISO)をセットし、②センターボタンを押し、③針の測定値を見る、④ダイアルを合わせる、⑤露出一覧が合致するはず。
写真も大体合ってますでしょうか???ずれてる???(;^ω^)
お許しを。

平面、それから反射光測光用のグリッドでしょうか?当時はやはり、仕事の関係もあり一部の熱狂的なファン以外、どちらかと言えば液晶表示のフラッシュメーターの露出計が人気でした。

セコニックJL60 [スタジオデラックスシリーズ用スライドセット]が現在販売されているようです。このモデルに合うかは分かりませんが。ハイスライドは使用しないとき、通常背中に格納します。JISマークがあること自体古い日本製の証です。なんだか古いの欲しくなってしまいました。(;^ω^)

どんな金型か!?凄いレザーケースです。縫い目もほころびひとつ無いのはザ・昭和の高級機国産です!
スタジオデラックスⅢ L-398Aは現在販売されていますが、私のとは見た目は似ていても異なるのですねえ。絞りの表記幅が広くなったのと、露出補正時かPLフィルターなど使用時の補正も可能です。雪景色補正も可能では???受光素子としてアモルファス光センサーで、電池は不要だそうです。
これらはデジタルカメラ全盛期、人気もそれほどなく二束三文で中古販売されていました。
使いもしないのに購入。(;^ω^)
ただ、電池代も馬鹿にならずこういう時代になるとも思わずです。やはり原点回帰でしょうか?
ライカやローライフレックスなんかで気軽にネガフィルム詰めて、お散歩写真ともなればこのような露出計で豪華すぎるくらいです。
因みに人気の記事も多いようです。気になるようでしたら調べてみてください。

【ローライフレックスの内蔵露出計】
まあ、これが当時標準装備されていたのですから贅沢です。受光部がフレーミングした角度なら、絞りとシャッターが動くと針が合ったところが18%グレー露出でしょうか?間違っていたらごめんなさい。
当時、このような露出計が内蔵ってそうは無かったはずなんです。まあ現代では珍品カメラ中古市もあまり開催されず残念ではあるのですが。
これも無電源です。因みにこのカメラは程度は低く安かったですが、新品当時は大卒の初任給数か月分ではとてもとてもの部類です。
一応、入射光で気軽にと思い、当時ローライフレックスではない二眼レフを購入し、ついでにお店にあったのでスタジオデラックス MODEL L-28cの購入とはなりました。
贅沢な時間でした。現在のフィルムがいかがな物かを私は知りません。一応、スキャンして使用することが多いので引き伸ばし機を使用しないのであればそれはデジタルデータとなってしまうので、解釈と判断が難しいです。でも楽しんでいらっしゃる方々は多いようです。楽しみ方はそれぞれでしょうか。
それでも、このようなカメラや露出計が比較的低価格で中古市場に出回ることも私には信じられませんでした。昔のカメラはメカニカル機構が多く無電源。冒険家 植村 直己氏もF3は却下です。ニコンですとF2までです。なお氏の画像映像が現代でも見れるまで保存されているのは最良の銀塩フィルムを使用していたからにほかなりません。撮影も現代なら多くの方が、スチル&動画を回せますが氏は当時からプロ顔負けで、当時度肝を抜かれたことを思い出しますし、あるCMで近年前使用されたのも記憶に新しいです。(推定デジタルリマスタリング)8mmでしたでしょうか?あれもセルフで自撮りが多いです。
昔も今も冒険家や宇宙飛行士に写真が上手い方が多いですが、まずはそこへ行かなくてはなりません。やはり画像や映像は貴重でした。
【露出計もないカメラ&単体露出計もない場合】
実際昭和はそんな時代でした。フィルムの箱の内側とかに、まあ大体の露出設定が書いてあるのです。「山晴天」「晴れ」「くもり」「日陰」イマイチ思い出せないのですがそんなところでしょうか?
ネガフィルムでしたら、ほぼ外すことはありません。親のカメラにも露出計は内蔵されていません。思い返せば両親は露出の名手でもありましたでしょうか?日中はほぼ完璧です。望遠レンズがない、ズームレンズがない、フラッシュがない。ないないづくしでしたでしょうか。貧乏という訳ではないのですが、各家庭にカメラ一台必ずある時代でもなかったです。よく一緒に写っていたりすると、写真の紙焼きを焼き増しして贈呈するご時世です。
現代ですと、何よ!削除しなさい!!二段階で!!そんなところでしょうか???(;^ω^)
一般的に、露出計がカメラに内蔵されてから特に逆光時露出アンダーのフィルムが増えたのは事実です。
カメラメーカーが悪戦苦闘したのは言うまでもありません。当然内蔵させることは可能でしたがコストが半端なく、しかもカメラと連動させるのは悲願だったのです。よく売れていたのがレンズ一体型で、これも距離計すらないものがあり、「山」「人物3名」「バストアップ」のアイコンです。これでそれなりに写るから不思議です。
何も考えず、手振れもほぼ起こさず、綺麗な写真が撮れるようになったのは比較的近年の話でして携帯のカメラにしてみても、まあ綺麗になったよねはつい最近です。
それでも本格的カメラにはかなわない部分も残ってます。本格的な望遠レンズ、接写、ボカシ、フィルターワークです。それから自分の思うような写真も撮りやすいでしょうか。
SNSと連動させ、ちょちょい加工しネットに上げられる夢のような話ではないでしょうか?ただそれが故の課題も残ってはいますが、そもそも大きくプリントしたりが前提でないのもあるからでしょうか?実際はある程度伸びますが...。
【まとめ】
自分でもこんなに長文になるとは思いませんでした。反省しています。最初長くてもA42P程度だとは思っていたのですが。(;^ω^)
思い返せば、写真家先生も「露出計完全マスター」「スポット測光の極意」「入射光式露出計テクニック」「フラッシュメーター完全攻略」など、けっこう商売もありました。
まあ、今回書いてみて思ったのは説明しようとするほど話が長くなることです。
最初のフラッシュメーターⅣで、多くの方はスルーする日記だと思います。このご時世に何?って感じでしょうか。
現在では、本格的カメラでも、取り敢えずワンショットでしょうか?補正するにしても、まずそこからです。
それからGOSSENとか、まだあるのには衝撃です!!(失礼!)当時も今もお高いです。
やはり試しに電池を入れてみたりして思うのは、本格的露出計だな~としみじみです。ただ今後露出計を購入する方は修理の関係もありますので現行品があれば、それらの製品購入をお薦め致します。遊びなら中古品もありだとは思われます。
以上、長文お疲れさまでした。(*- -)(*_ _)ペコリ
 にほんブログ村
にほんブログ村