春に産卵・巣作りを始めたハチの活動が、最も活発になる時季になりました。ハチに刺されたというニュースは、6月頃からも聞こえてきています。
先日行った、花木が多いズーラシアの園内にもハチが何匹か飛んでいました。私達が木立の中でおにぎりを食べていると、
真後ろで“ぶぅ~~ん”・・・

そのまま固まって微動だにしないでいたら、どこかへ飛んでいきました。
その木立の中の休憩スペースに、他に人はいませんでしたが人が見たら「何やってるんだろう~」ってな図だったと思います

でも!
無用に動くとハチは攻撃されたと思って、襲ってくる可能性があるのです 手を横に振って追い払う動作は絶対NG。
手を横に振って追い払う動作は絶対NG。このことを知ったのは大人になってからですが子供の頃、田舎の親戚のオジサンがそうやって刺されたのを見たことがあります。(小さなハチで、刺した後なんとそのオジサンはハチを食べてしまい、ビックリしたのを覚えています)
静かにゆっくりその場を去るか、じっとしていること☆・・と、この時季の探鳥会(バードウォッチング)では必ずリーダーから言われます。
ハチに刺されないためには・・・
☆この時季、森林等では黒っぽい洋服・帽子は
着用しない(黒に反応するらしい)
☆出会っても手や体を横に振るべからず
☆出会っても大きな声を出すべからず
ハチも自分達の巣や仲間を守ろうと必死です。
理由も無く人を刺したりはしません。
元々、虫や動物のすみかだった所に人間が入ってきて、しかもハチから見た攻撃動作・・・
それは身を守る為に威嚇もしてくるでしょう。
特にスズメバチは威嚇性・攻撃性が強いそうです。キレやすいってことかな

アシナガバチは刺さないです。
実は10年くらい前、アシナガバチに営巣されたことがあります。
しかもベランダのヘリに

当時の森林仲間に相談したところ「アシナガは刺さないし、秋になったら出て行くし、同じ巣には戻ってこないから大丈夫だよ」と言われ、生活上支障も無いのでそのままにしておきました。
でも!たまに夜、部屋に入ってきてカーテンレールで夜明かしするやつが!ちゃっかりモノです

朝、窓を開けると出て行きました。ハチは夜に弱いらしく、夜はフラフラとしてちょっと面白かったです
 ハチは植物の受粉を助けたり、野菜・樹木の害虫を食べてくれたりと、立派な益虫
ハチは植物の受粉を助けたり、野菜・樹木の害虫を食べてくれたりと、立派な益虫 。
。
攻撃性の高いハチが軒先に営巣する等、日常生活において危険な場合は別ですが、見つけたら何でも駆除・・というのは無謀ですね。
そして普通に野山を歩いている時は、刺激せずにうまくかわしたいものです。
ハチがこちらへ寄ってくるのは
「近くに巣があるから近寄らないで!」という警告・アピールなのです。











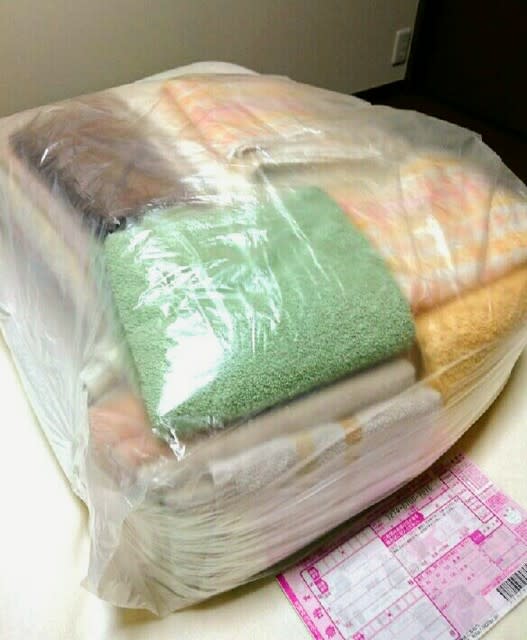


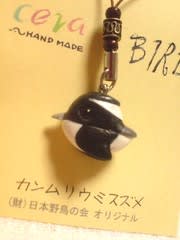



 )
)

 そして豊かな根がはっている森林は土砂崩れを防いでくれる。
そして豊かな根がはっている森林は土砂崩れを防いでくれる。










 ココにも・・・
ココにも・・・



 )
)




 初夏の頃には巣はぎゅうぎゅうになった雛で賑わっていました!
初夏の頃には巣はぎゅうぎゅうになった雛で賑わっていました!





 今年は「コチドリ」
今年は「コチドリ」


 「エナガ」と「キビタキ」
「エナガ」と「キビタキ」







 これらは腐らない人工ゴミです。
これらは腐らない人工ゴミです。



















 )
) !
!
 番組で見た
番組で見た 「素数ゼミ」といって13年ゼミもいるらしいが、それにしてもキッチリ17年・13年で出てくるんだからスゴイ
「素数ゼミ」といって13年ゼミもいるらしいが、それにしてもキッチリ17年・13年で出てくるんだからスゴイ






