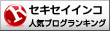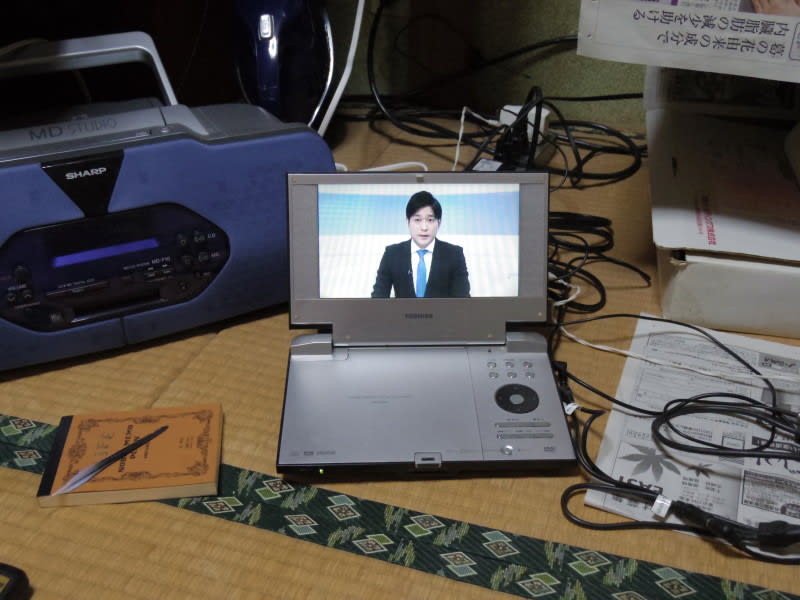ふるさとは遠きにありて思うもの・。
室生犀星詩集って、中学ぐらいのときに読んだと思うが。。あの頃何を考えてこの詩を読んだことやら。
その年齢では意味やニュアンスを理解できないことを、子供に習わせることが、果たして有益なのかどうか、専門家ではない僕にはわからない。
ただ、何かの状況が生じたとき、こうしてふと昔読んだ本の言葉が浮かんでくる、という意味では、とにかく記憶力のしっかりしていううちに、なんでも刷り込んでしまうという方法にも、何らかの効用があるのかもしれない。
室生犀星は文学を志して上京し、そこでふるさとに思いをはせる。
そこまではよいが、食い詰めて故郷に帰ってみると・・という話らしく、まあ夢は夢のままに、ということなのだろうね。
ケニー・ドリューでしたっけ、欧州で勇名をはせた後、アメリカに一時帰国して作ったアルバムが "Home Is Where the Soul is" というタイトルだった。まあ、意味としては似ていますね。。
久しぶりに帰ったアメリカは、ケニーにはどう映ったのでしょうね。。
音楽つながりで言えば、思い出のグリーングラス "Green,Green grass of Home" の歌詞、以前ここでも書いたことがあるけど、あれは夢の中で故郷に帰るという内容だ。
列車から降りたつと、町は昔のままだ。父母が迎えてくれる。幼馴染の、金髪のメアリーもこっちに駆けてくる。生家も、古くなったけど変わりないようだ。昔よく遊んだ樹もあるなあ・・などという歌詞が続くが、3番になると一転して、実は・・・というもの。この歌も一時期繰り返し聴いたな。
故郷は、その人が心の中に持つことができるユートピアだ。現実の世界とは何の関係もない。現実の「故郷」は、日々更新され新陳代謝していくもので、昔の「故郷」とは別のものと考えた方が良い。まあ、たいがいそんなところだろうな。。