スーバーにも行ったが、既に本体価格自体、先週よりあがっているようだ。
まあ、理屈では理解しても、明日になって高い税額を払うのは癪だなあ。
17年前はわざわざ直前にコンビニに見にいったが、もうそんな元気ないや。
実は25年前、消費税が初めて施行されたときのことも覚えている。お茶の水にあったファーストキッチンに行って食事をした。応対した子が新入社員だったらしく、あたふたしていたのが印象的だった。
 |
マイクロフォーサーズレンズ FANBOOK (インプレスムック デジタルカメラマガジンFANBOOKシリーズ NO.) 価格:¥ 1,890(税込) 発売日:2014-02-14 |
本屋で売られている書籍は再販制度があって、値引き販売はできないが、電子書籍には適用されない。 ちょうど先日、日経新聞にamazonについての記事が出ていて、その関係もあってピーター・ドラッカーの本をkindleストアで購入したところだ。けっこう、2-3割くらいかな、安い。
このムック本も最初から電子書籍化されていて、3月末現在で1,333円だ。書店では1.890円。増税後は1,944円かな。結構あがるなあ。
少し前なら、E-P1のムック本とかを買えば、MFTの全レンズの紹介記事が掲載されていたが、MFTレンズも増えて、近年発売のカメラのムック本では、とても全レンズを紹介するようなことはできなくなってきた。
なので、この本は重宝しそうな気がする・・。
ちらちらと読んでみたが、うちのLumix G3のキットレンズ、14-42mm F3.5-5.6のレビュー記事も載っている(キット専用で、市販はしていない)。絞らないと結構甘い、という評価だ。初期のレンズは14-45mm F3.5-5.6ASPH MEGA O.I.Sといい、今でも単体で市販されているが、外観やスペックは似通っているものの、こちらのほうが描写がよさそうだ。
14-45mmは中古なら1.2-1.5万、新品なら2万円台前半だ。デザインも合うし、中古の良品なら手を出しやすいぞ・・。
が、しかし、ここからせこい話になるが(いや、重要だ)、僕らは増税後も昇給しないのである。3%分は自分で浮かせないといけないのだ。よって、買っても腹の足しにならない本やレンズなどは、厳しく吟味しないといけないのである。
良く見ると、うちのキットレンズと同じだと思っていた14-42mmは、小型化されたⅡ型のものらしい。ので、うちのレンズの参考にはならないな。それに、ズームの描写を補う意味で単焦点の14mm F2.5や20mmF1.7を持っているのだから・・。
 |
中国は、いま (岩波新書) 価格:¥ 861(税込) 発売日:2011-03-19 |
国分良成編 岩波新書 2011年3月。執筆陣は豪華で、清水美和氏、浅野亮氏、田中均氏、コラムでは緒方貞子氏、小林陽太郎氏、エズラ・ヴォーゲル氏、ジョセフ・ナイ教授ほか。
国分氏個人の体験として、本書冒頭でふれられているが、日本人の対中感情というか、対中観の推移は、世代によって異なっているようだ。
僕にとって中国はパンダから始まっている。文革のことは全く知らなかった。テレビで中国残留孤児の紹介がされていたり、年配世代の人たちがツアーで中国旅行(視察旅行といっていいような感じ)に行ったりするくらいで、(同時代の中国には)ほとんど関心がなかったといってよい。
すぐ隣の国なのに、考えてみれば異様なことなのだが。
いくらか注意をひかれたのは’89年の天安門事件で、その頃は漠然と自由主義社会になった将来の中国を、想像したりしていた。中国製衣料品を店で見かけるようになったのは’90年代に入ってからだ。
’80年には、国民の8割の人が中国に「親しみを感じて」いたのだそうだが、2010年には全く逆転して、「親しみを感じない」人が8割、日中関係が良好でないと感じている人は9割に達しているという。
国分氏はこのどちらも極端に思えてならないとし、これを正すのは政治の責任であり、我々の責任(国分氏のような中国研究者を示すのか、日中双方の国民を示すのか?)である、と説く。
そして、このまま中国を「異質」なものとして排除しようとするのではなく、「個性」として認知し継続的な交流、対話が必要と述べ、それには中国の現状を知ることから始めよう、として各界の識者の方々の見解を紹介している。
内容は岩波新書らしくアカデミックなもので、僕が本書を選んだのもそれゆえである。中国、韓国に関する本も、書店では非常に扇情的で感情的なものが多くなった。これには出版界の事情も関係しているらしい。毎日新聞では、嫌中、嫌韓ものを見出しにあげると、その雑誌の売れ行きが全然違ってくるので、やめられなくなる、という業界事情を暴露していた。今日、マスコミというのは本当に罪深い存在になりつつあるな・。いや、昔からそうなのか。
具体的な内容には触れないが、中国という国家が、アヘン戦争後の「屈辱の百年」を克服しようと改革を進め、さまざまな変遷を経て、今日の表面的華美に過度に執着するような体制に至った(高橋伸夫「歴史を背負った自画像」)など、興味深く読んだ。
アメリカなんかもそうだが、国家とその国民は必ずしも見解を一にしているわけではない。ただ、自国の繁栄や、世界に誇れる何かを持つことは、素直にうれしいようだ(以前一緒に働いていた中国の人も、就航した「遼寧」の写真を、ウェブニュースでよく見ていた・・)。
行き過ぎたり、他の人を傷つけたりしなければそれも良いことだろう。
ただ、国家あっての国民という考え方はもはや通用しないし、どこの市民が不幸であっても、結局世界の市民全体にとって負担となったり、安定を損なう原因となったりする。大きな国家ほど、それを賢明に導いていくのは困難を伴うだろうが、大国を任ずるならその責務を負うべきだろう。それができないなら、地域を分けて、各自の自治に任せる選択肢もとれるはずだ。
いずれにしても僕たちはこれからも、中国の存在感を意識し続けていくことになるだろうし、彼らと触れ合う機会も減ることはあるまい。突出する軍事費など、いろいろ気になることもあるが(一番やめてほしいことだ)、予断を持たず、動静を見守っていきたい。

 | 日本人のための「集団的自衛権」入門 (新潮新書 558) 価格:¥ 714(税込) 発売日:2014-02-15 |
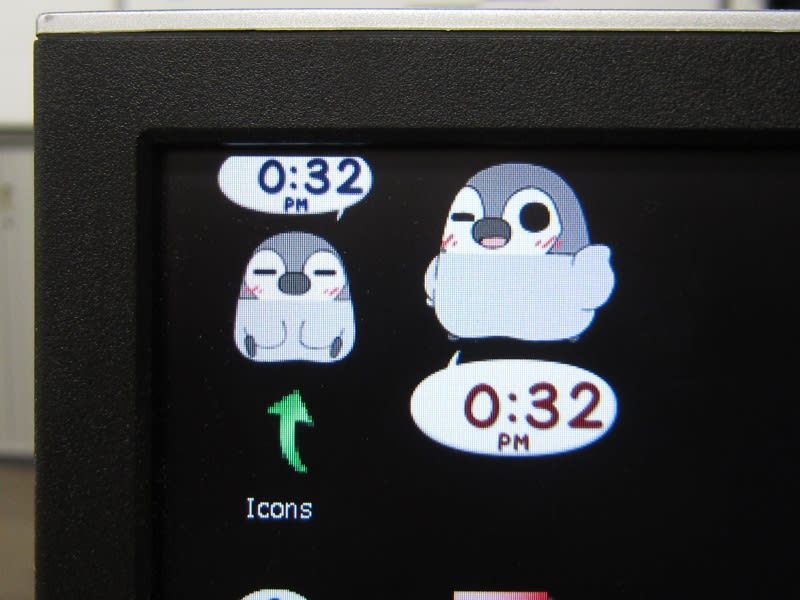
 | 時雨みち (新潮文庫) 価格:¥ 620(税込) 発売日:1984-05-29 |
![山桜 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ADRqFd-rL._SL75_.jpg) | 山桜 [DVD] 価格:¥ 3,990(税込) 発売日:2008-12-24 |








今年もまもなく3.11を迎えようとしている。3年がたち、震災の記憶の低下も懸念されているが、他方、当時の状況の検証や、復興に向けた根強い支援の動きもある。今日(9日)も、恩師主催の復興支援コンサートに行ってきた。
船橋氏のこの本も、この2月に発売された新刊である。船橋氏はこの前にやはり原発災害とその対応を取材したドキュメンタリー「カウントダウン・メルトダウン」を発表し、大宅賞を受賞されたという。カバーの紹介文は、「フクシマで日本は「あの戦争」の失敗を繰り返した。・・危機下にあるべきガバナンスとリーダーシップを探る」とある。
本書の視点はこの扉の言葉に言い尽くされていて、本文では事故対応段階での問題点と、先の大戦中の戦史ににおける事例を並行して紹介し、その類似性を表そうとしている。また、対応にあたった米国支援部隊、東電、自衛隊そして半藤一利氏らとの対話編があとに続く。
個々の事例紹介や見解などは大変面白く、示唆に富む。特に米国が日本の管理体制に驚き、不満を表明し、それに当時の日本政府が自ら国の統治に不安を感じたという記述には驚く。助けに来たアメリカが、政府や東電の対応のお粗末さに呆れて、この国との同盟を続けてよいものか、不安を覚えるほどだった、というのである。
ただ、事実関係の記述が最小限に抑えられているので、時間の経過した今では、やや分かりにくい記述がみられる。まるで、当時の事情は本書を読むまえに同氏の「カウントダウン・メルトダウン」を読んでくれといっているようだ。新聞の社説をあとからまとめ読みしているみたいだ。ちりばめられている大戦中の出来事(失敗事例)は彫りが浅く、現代の事例検証と釣り合っていない。全体に、ちょっと散文的で論理性に欠け、読者を情に流して説得しようとしているような印象がある。
読者を引き込むような文章力はさすがで、とても読みやすいし、読むものを飽きさせない。
何となく、上手にできたテレビのドキュメンタリー番組を見たような読後感だ(文春新書 800円+税)。
PCが使えなくなって4日たつ。タブレットNEXUS7等も使えるが(この記事もネクサスで書いている)、いろいろ不便なこともおおい。ブラウザはポップアップメニューなどが使えず、日本語入力も癖がある。
余談だが、このタブレットにはGoogle ChromeとFirefoxが入っている。FirefoxはPCでも使っていて、期待してインストールしたが、blogを書くとき、キーボード操作がおかしくなる。Chromeは動作が遅いという不満があったが、どちらも大差ないようだ。 PCは、なんとか今日中には手配するつもりだ。
タブレットと言えば、3年前の最初の週末に、ワコムのペンタブレットを買った。

なぜ急に買おうと思ったのか、よく覚えていない。保証書を見ると、3月5日になっている。翌日、これを使うとメモリが足りなくなるかと思い、増設メモリを買いに行った。もとの2ギガに1ギガ増設した。3月6日、日曜日のことだ。
使ってみるとこれが難しくて、ぜんぜん思うように書けなかった。ペンをおいている場所と、書いている絵を見られる場所が違う(タブレット本体と、液晶画面)のが、どうも馴染めなかったのだ。1万円と安価なので、書き味もそこそこなのかもしれない。
とにかく勉強しなければと思い、本屋に行って解説書などを買ってきた。SAIというソフトを前提としたものだったが、まずは手持ちのソフトでなれなければ、と思い、少しずつ練習することにした。
ところが、その週末には東日本大震災が発生してしまい、おえかきどころではなくなってしまった。 地震関係の話になるが、こんなぐあいに、地震の起きるまえ数日間のことは不思議とよく記憶している。
ペンタブを買ったのはヨドバシ新宿、翌日メモリを買ったのはヨドバシ吉祥寺で、たしかフォトプリンタの用紙も一緒に買った。3月10日、スマホを買おうかと、ヨドバシ秋葉原に行った。なぜかやたらとヨドバシにいっている・・。
(3/10追記:タブレットではレイアウトの崩れを直すことができず、オフィスでこっそり直した 。
。
Firefox(スマホ用)はHTMLの編集に難があるようだ。PCはまだ買っていない。XP移行と消費税増税で生産が間に合わず、納品まで時間がかかりそうだ。型落ち品はどんどん売りきれているようだ・・)。
うさぎA: というわけで、うさぎC君にヨドバシ秋葉原店に行ってもらいました。
うさぎC:お店を見てきました。ちょうどXPのサポート期限が近いこともあり、お客は多かったですね。割と年配の人も目立ちました。
売り場の目立つところには、外国製の5万円くらいのノートがおかれています。性能は押さえられているのでしょうが、値段は魅力的でした。
中心価格帯は、5、6年前と変わっていない印象でしたね。15万くらいから20万くらいかな。
うさぎB: 安いモデルは昔もあったとおもうけど、量販店にはあまり出てなかったかな?
うさぎA:5年前なら、台湾のメーカーはもう結構出していたね。ただ、あの頃は国内ブランド数社が、売り場の大半を占めていた。ほとんどが標準品で、オーダーメイドの製品は目立つところにはなかった。
うさぎC:前買ったときは、長い間検討して、お店にも何度も足を運んだからね。だんだん見慣れて、区別がつくようになっていた。今日みたいに、久しぶりに行くと、一度では全体の傾向はつかみにくい・・。あと、同じボディでもCPUなどが何種類もあって、価格が倍くらい変わる。むかしからそうだけど、じゃあ何を買えばいいのか、その場では判断しづらい。CPUの形式もまだ見慣れてなくて、よくわからない。
うさぎB: 前回はそれなりに予算があって、その価格の範囲で選べばよかったけど、今回は急なことで、予算をやりくりしないといけない。こういうときは選択が難しいな。急な出費は少ないほどいいけど、もっといいのを買えばよかったと、後悔したくもないし。
うさぎA: とりあえず安いのでいいや、落ち着いたらいいのを買おう、と思っていると、そのままずるずると使い続けてしまう。
うさぎB:それは、結局その程度のもので役に立っている、ということの証明だよね。なにも高いものを買うことはない。
うさぎ家のリビングルーム。急遽召集された家族一員が、緊張した面持ちで集まった。
うさぎA:皆さん、お忙しいところお集まりいただき恐縮です。ご存じの通り、本日未明、我が家のコンピュータがクラッシュしました。直前まで何事もなく使えていたのですが、ふと見たら画面がモザイクもようになっていて、HDDのランプがつきっぱなしになっていました。セーフモードで立ち上げたものの、次第に画面表示もされなくなり、チェックディスクもとちゅうで止まってしまいます。
うさぎB:リカバリしてから1ヶ月もたっていないのに!
うさぎC:あの頃から本当はおかしかったんだろうね。動作がおかしくなり、ソニーのサポートに電話して修理を頼もうとしたが、電話口であれこれ確認してもらった結果、ハードには問題ない、という結論になったのだが。
うさぎB:リカバリしてからは全く問題なく使えていたし、むしろ直前より調子いいくらいだった。設定やソフトも見直して、ブラウザのお気に入りも整理し直すなど、生まれ変わった気分で使っていたのに。ショックだなあ!
うさぎA:前回はセーフモードが有効だったので、ドキュメント等は不調になってから移動することができたね。今回はなにもできなかった。ただ、幸いリカバリから時間がたっていなかったので、本体にはほとんどデータが入っていなかった。
うさぎC:写真や音楽データなどは、外付けHDに保存しているからね。バックアップ用に、先週新しいHDDを買っていて、時間ができ次第バックアップするつもりだった。
うさぎA:今夜、リカバリできるかどうか、電源を入れてみたが、OSが立ち上がらなかった。修理は受け付けてはもらえるが、HDD換装は約6万円かかるらしい。もっと安いパソコンも売られている。うちのPCは5年半ほど前の製品なので、修理という判断はどうかなあ、という気もする。
うさぎC:量販店で見たが、4万円台のノートPCもあるようだ。しかし、性能はともかく、質感やトラブルの可能性など、安いPCはリスクがあることもたしかだ。直せるなら直した方が安上がりという考え方もあると思う。
うさぎB:僕らはPCの専門家でもマニアでもないので、性能のことはわからないが、いくら廉価版でも、5年前のパソコンよりはいいんじゃないか?
うさぎA:うちはパソコンを割りと長く使うからね。前のやつなんか、7年近く使ってなかった?
うさぎB:02年2月から、08年12月まで。もっと早く買おうと思ったんだけど、なかなか買えなかった。
うさぎC:ネットオーダーで買ったけど、価格の割に性能はよかった。ただ、当初は2ー3年ですぐ買い換えるつもりだった。
うさぎA:拡張性とかは犠牲になってたね。グラフィック性能も低かったし、いまから思うと結構頻繁に壊れていた。
いままで使っていたVAIOなんか、性能もそこそこ良くて、質感もよかったし、故障も少なかったよね。結局5年で壊れちゃったけど。
うさぎC:デジモノの最上級品と、最廉価版は不経済なんだよね。
駅までの通勤途中に、小さな林があり、そこに桜と楓の木がある。春になるときれいな花が、晩秋には真っ赤に染まった紅葉が、目を楽しませてくれた。
桜の花については2年前にふれたことがある。毎年花が咲くと、写真を撮っていた。
昨年春はこんな感じ。そろそろ葉桜になりそうな頃。
紅葉がきれいになるのは師走の初め頃のことだ。
鳩もお気に入りの場所だったようだ。春にはウグイスもきれいな声を聞かせてくれていたが、もう何年も聞いていないな。
葉桜もきれいだったが、この頃は少し遅かったようだ。それでも、青空によく映える。
沿道の人たちを和ませ、鳥たちには憩いの場を与えてくれたこれらの木々は、今週半ばに切られてしまったようだ。特に桜は、剪定ではなく、根元から切ってしまった。
いわゆる山林とはいえ、どなたかの土地なので、利用上の問題で切らざるを得なかったのだろう。ただ、沿道の住民としては寂しく思うことも確かだなあ・・。