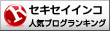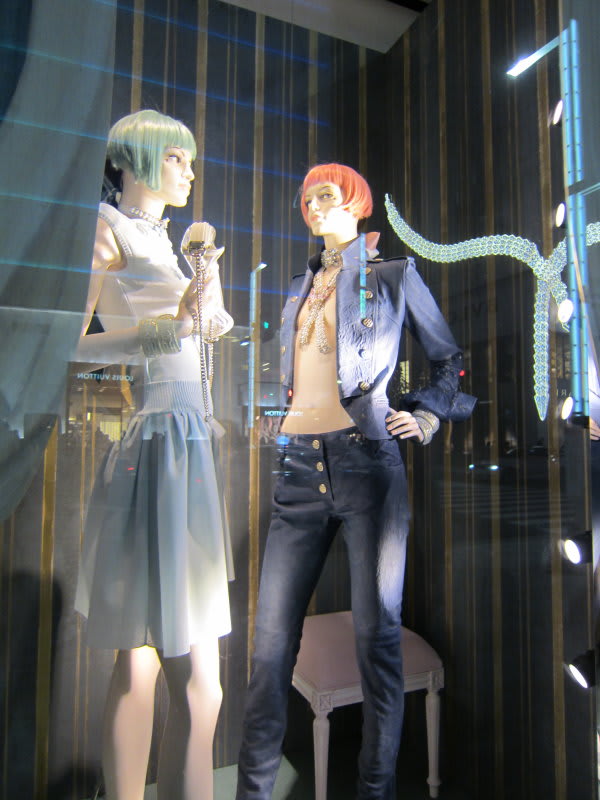D70sをリプレイスする方法はいくつか考えられるが、常識的にはD7000に置き換えることだ。少し古いが、機能は僕には十分すぎる程だ。
ボディだけなら6万5千円程度で買える。
昨年Lumix G3を買って、今年は大いに活躍させた。最初はGH2が欲しいと思ったが、値段が下がらない。G3は何しろ安いし、十分な機能とまとまりの良いデザインが気に入った。
その結果、今年はD70sを外に持ち出すことはなくなり、室内を中心に500枚ほど撮影しただけに留まっている。35mm F1.8をつけっぱなしにしているが、ボケがきれいだというメリットはあるものの、暗い場所は古いCCD機にはきびしい。
ときどき、MFTのズミルックス25mm F1.4を買うことを考える。まあ、20mm F1.7でもいい。買えば結構つけっぱなしにして使うんじゃないかと思うが、同時に、そういえばニコンの35mm F1.8Gを買ったのは去年だったしなあ、と思い直す。
僕の場合、今はほとんどMFTのカメラ2台で撮影している。GH3を買えば、ニコンのレンズ一式(6本だけだが)は処分してしまってもいいのではないか、とも思える。しかし、この先MFT一本に絞って良いのか、というとちょっとためらいがある。
まあ、どうせ今年はどうあがいてもカメラに予算は割けないのだ。いっそのこと、狙いをD600にしてもいいのかもしれない。大きさは今のD70sとそう変わらないし、DXレンズを使っても自動的にクロップされる。ということは、とりあえず今のレンズを違和感なく使うことはできるのだ。価格は18万弱だ。ブログや掲示板などでマニアの人が、やたらとフルサイズなどの大型センサーにこだわるのにはうんざりするが、大は小を兼ねると言うし。