
ご愛読ありがとうございます。
1周年を機に、レイアウトと色調を少し変えてみました(テンプレートを直しただけですが)。
気が向いたらまた直すかもしれません、。

良く晴れて、とても暖かな1日だった。
雨がちだった先週は知人の不幸があり、お別れを済ませたら、週末になって晴れた。この連休、とくに何も予定はなかったのだが、思い立って少し出かけてみた。
ここは鉄道撮影では有名な場所だ。東京近郊でこれだけ広々としてゆったり写真が撮れるところは(なおかつ電車がたくさん来るところは)少ない。
明治時代に開業したときは、街道沿いに大きく迂回していたものを、1968年にこの橋を架け、ショートカットした。

トラスが線路の下側にあるので、列車に乗ってるときは見晴らしが良い。ただ、特急列車に乗っていると、あっという間に通り過ぎてしまうので、あまり印象に残らないかもしれない。

このあと、廃線跡を見に行こうと歩いていて道に迷った。山中を迷ったのではなく、斜面に建つ住宅街で迷ってしまった。ようやく街道に出て、江戸時代の珍しい橋を撮影。
今日行った唯一の観光地らしいところだ。
街道沿いに歩いて行くが、だんだんくたびれてきて、廃線跡などどうでも良くなってきてしまった。探せば古い煉瓦造りのトンネルが残っているそうだ。
その代わりというか、古い水路橋を見た。
下に谷川があり、水路はトンネルから出てきてこれをまたいでいる。
4月23日(月)東京スカイツリー®よりNHK-FM、J-WAVEの送信が開始されます。
アナログテレビ時代、我が家の辺りは高層ビルの影響で難視聴地域に指定されていた。テレビは無償のケーブルテレビが配信されていたが、FM放送はノイズが多く、特にNHKは厳しかった。今聞いてみると、時報の音がきれいに聞こえるようだ。
ちょうど1年前に買って読んだ。書店の本棚に、表紙を手前にして陳列してあったので手にした。名前は聞いたことがあったが、読むのはじめて。
世の中は復興に向けて動き始めてはいたが、まだ重苦しい空気が抜けきれず、なにより自分自身がどうにも重苦しい気持ちを抱えていた。
ウェブで検索すると、バブル絶頂期の女性誌に掲載され、その華やかな雑誌の中では浮いた存在だった、という書かれ方をしている記事が多い。すこし浮世離れしたるきさんは、時代にかかわらずどこでも浮いてしまうような気がするが、たとえば中尊寺ゆつこさんなんかだと、はまっていた、と言うことなのだろうか。僕は女性誌は読んでないから、よくわからないけど。
ただまあ、今となってみると、るきさんは社会全体に余裕のあった時代だからこそ、書かれたような気もする。今、月に1週間診療報酬の計算をして、慎ましく生きるにしても生活できるのかしら。大体そういう職務って今でもあるのかな?
るきさんは92年12月に連載終了しているのだが、最後の頃になると「ボーナス減の不景気が・・」とか、「世間は景気が悪いらしいしね」「そうらしいわね」みたいな台詞が出てくる。お金に関する話とか、「贅沢」の話も、後半になって出てくる。よく見ると世相の動きが微妙に反映しているようだ。
本筋から離れた感想をもう一つ言うと、やっぱり時代の空気が随所に感じられて、懐かしいんだよね。えつこさんみたいな人はオフィスにいたし、僕はそのころ小川君のような若手(小川君のようにえっちゃんに思われていたという意味ではない)だったわけで、ついそういう視点からこれを読んでしまう。るきさんのようという意味ではないが、ひょうひょうとした人もいたしなあ。
昔が懐かしいなどと、言いたくはないが、毎日今の社会の状況を目にしていると・・いや、そんなことを言うのはやめよう。
絵がうまい。隅々の小道具に至るまで、手抜かりがないし、コマ割が一定の平板な構成なのに、アングルの工夫で見事にそれを補っている(漫画読みではないので、技術的なことはわからないけど)。絵柄は4年半のうちにはだいぶ変わっているが、純粋に絵だけ見ると、比較的初期の89年頃までが一番好きだ。
お話としては、やはり初期のクリスマス・パーティの巻からお正月、火鉢のはなしあたり(この辺は絵も好き)、服をみんな洗濯してしまい、エプロンする話、せんべいをくわえながら自転車に乗って落とす話、かな。ステーキ肉を買ってお米が買えなくなる話はかなり異色。そして最後の回は、文庫版解説の氷室冴子さんも書いているが、僕もとても好きだ。僕が思うに、こういう思い切り、そして後腐れのない人間関係というのは、男性にはなかなかできないものだと思う。
D3100の後継機種だ。ニコンのラインナップ中エントリークラスを受け持つ。大きさや重さはほとんど変わっていない。5月下旬の発売らしい。
ポイントは画素数の大幅アップ(1420万画素から2416万画素へ)、画像処理エンジンの進化(EXPEED3)、そしてオプションでワイヤレスモバイルアダプター「WU-1a」をつけることにより、画像の無線転送に対応していることだ。
普通の撮影画像転送なら別に気にならないのだが、これはAndroid端末を利用してのリモート撮影に対応していると言うことだ。
D3200の液晶は固定だが、これはフリーアングルモニターよりもさらにフリーだ。何しろモニターが本体から外れる(のと同じ事になる)のだから。
もっとも、撮影中の画面を見ると、ライブビュー画面は小さそうだし、AFはコントラストAFになるのだろうからD3200の場合、遅く迷いやすいかもしれない。
アダプターは安い(5250円)が、外付けにするのはコスト面の制約が関係あるかもしれない。将来は内蔵されることになるだろう。GPSも外付けユニットだが、色々つけていくとかなりごつい外観になってしまうのは、この種のボディにはどうだろう?
画素数インフレは一段と加速したかな。それにしても、D70sの4倍だからな・・。
色々と、忙しいというよりなかなか行き詰まることが多くて、だんだんと自分の心の動きが鈍ってきていることを実感するようになった。どこかに出かける事もしんどく思ったり、いろいろな事への好奇心が鈍ってきているようにもなってきて、危機感を感じる。
事態の進展というか、環境の変化は当分期待できないかもしれない。とにかく気持ちを切り替えて、仕切り直しをしたい。
と言うわけで(前置きが長いが)、すこし休もうと、早めの帰宅。
桜の川。普段帰るのは夜だから、公園は通らないのだが、今日はゆっくり風景を眺めながら帰宅。雨は地下鉄に乗っているうちに上がってしまったようだ。
桜は終わりだけど、菜の花はちょうど盛りできれいだ。
先週見に行ったらきれいだったろうが、近所の桜は毎年撮りに回っているし。
さくらのじゅうたん。
さくらの髪飾りをしたすずめ。
しばらくペンのことを書いていなかった。相変わらず元気で、放鳥してあげると良く飛ぶ。そして、全然しゃべってくれない。
余り連れて行きたくないんだけど、リビングから席を立つとき、肩に乗ってきてしまって、そのままキッチンに行くことがある。水道から水を出して小松菜とかを洗っていると、とことこと降りてきて、水を飲んだり、少しずつ体に水をかけてみたりする。
水浴びをしたいんだと思い、しばらくそのままにしてやるが、あまり体いっぱい浴びることは怖くてできないようだ。いちど足を踏み外して(しょっちゅうやっている)シンクにぶち落ちてしまい、それからしばらく怖がって近づかなかったが、また近づくようになった。
筆毛が出ると、かゆがって頭をはしごにこすりつけている。水浴びすると少しさっぱりするのかもしれない。
それで、ケージで水浴びできるように、こんなものを買ってきた。
アウターバードバスと書いてある。要するにかごに外付けするプールだかお風呂だか、そんなものだ。

取り付けるとこんな感じ。水差しの小窓を開いた状態にして、引っかけてある。お風呂場に行くには、水差しを超えて行かないといけないので、水差しはとってしまおうと思ったが、今のところそのままにしている。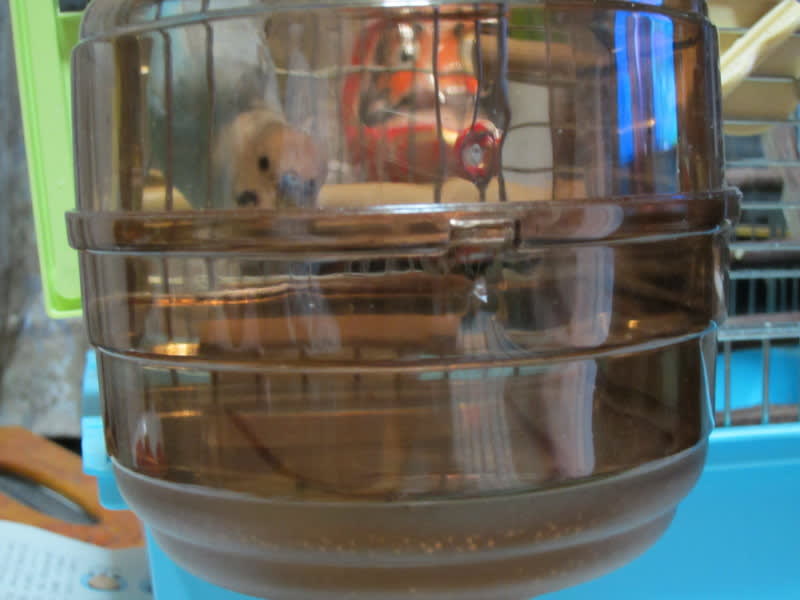
家にいるときはこれを使っているのを、まだ見たことがない。最初の頃、ここから表に出られると勘違いしたのか、足を踏み入れて慌てて出ていったのは見た。
その後、水のなかにシードのくずが落ちているのをいちど見たけど、それからは見てないので、使っていないのかもしれない。実は陶器の小判も置いてあるが、小松菜が入っていたりして、ここも使っていない、というか、水浴び用に使えないようになっている。前からずっと置いてあるのだが、ケージの床に置いておくとふんとかが落ちてしまい、あまりきれいではないし、使っているかどうかも判定がつかない。
まだ怖いのか、利便性が悪いのかわからないので、もう少し様子を見よう。
とりとめのない話だ。
日曜日、郊外に向かう電車だが、となりに座っている若い女の子はスーツに身を固め、さっきからノートに何か熱心に書いている。
別に盗み見するつもりはないが、つい目に入ってきた文字は「尊敬できる人物」「上司と意見が云々」などとある。今も、就職戦線はかなり厳しいようだ。
昨夜、こんな本がある事をウェブで知った。今の就職事情(新卒)というのは、正直言って知らないのだが、日本の社会は、いつからこんなになってしまったのかな。まあ、昔は昔なりに、僕も色々苦労したけど。
僕自身の仕事では、1から新人を育てるような事をもう長いことしていない。ある程度経験のある人と仕事をするのが普通だ。そのせいか、若い人にはあまり関心がないというか、縁がない。8年ほど前、司法関係の勉強をしている若い人と何度か話をしたことがあったが、そのとき思ったことは、若い人は意外と頭が固い、と言うことだった。
正確には若いと言うよりも、経験の少ない人の方が、自分の得た情報を鵜呑みにしやすい。そうすると、それに縛られて自由なものの感じ方ができなくなる。たとえば、本とか新聞とかで、刺激的な文体で書かれた文章を読むと、あたかもそれが自分の意見であるかのように人に言ったりする。もちろん、全ての若者がそうだという訳ではない。ただ、意外な経験だったことはたしかだ。
今の職場にも、さいきん若い人が入社した。部署が違うので、彼らがどのような日々を送っているのかは、間接的にしかわからない。
個人的には、今の職場に経験のないスタッフがいることが、労使双方にどれけのプラスになるのか、疑問を感じないでもない。下手をすると会社自体が職業訓練校となって、ビジネスがうまくいかなくなる恐れもある。お互いに不利益にならなければ良いが、と心配はしている。
ただ、新人の方は何でも良い経験、思い出になるはずだし、とにかく今仕事ができることは良いことなのだろう。
5年、10年したら、みんなどうなっていることか。
1年近く前に神の子たちは皆踊る の事を書いた。まだ世の中が震災の影響を抜けきっておらず、僕自身も重い気持ちを抱えたままだった。それにしても、あれからもう1年もたつんだな。
今回はそのときを思い出して、気分を変えたいと思い手に取った。
蛍、納屋を焼くは、ハードカバーの本を持っている。初版ではなかったかもしれないが、文庫になる前に買ったのかな。「蛍」は、「ノルウェイの森」の原型となる作品だが、今読むと何となく奥行きのないような、妙なイメージだ。これはやはり短編ではおさまりきれない内容だったのだろう。
「納屋を焼く」は村上らしい、切れ味の良い短編だ。つまんないこと言うようだけど、おいしいおつまみを食べたな、という満足感みたいなものを感じる。
「踊る小人」(関係ないけどATOKはこびとを小人と変換してくれない・・)は、村上のファンタジーにしては少し重い感じがする。何となく安部公房の作品を連想してしまった。「世界の終わり・・」につながる系列なんだろうけれど、それよりは小さくまとまっているところが良くも悪くもある。これ、以前に読んだという印象がないんだよな。
「めくらやなぎと眠る女」これも、数年前に英訳の本で初めて読んだような気がする。英語版はこれがメインタイトルになっていた。耳を悪くしたいとこを、通っていた高校の近くにある病院に連れ添っていく、休職中の若者の話だ。高校時代に通い慣れていたはずのバスルートなのに、感じる違和感、不安感、診察中のいとこを待ちながら思い出す、高校時代の入院見舞いのこと、帰り道でのいとことの会話。とりとめがないようだが、今の自分に対する違和感のようなものを、水彩画のように書いているような感じがした。優れた作品だと思うが、僕が今回読んで感じたことは、端正で古典的な構成の短編だ、ということと、もう一つは、主人公との世代差を強く意識してしまった、ということだ。作品が若者の不安定な気持ちをみずみずしく描いているからだと思う。
思えば村上作品を読み始めたのは20歳ぐらいの頃で、そのころから作中人物は20台から30台ぐらいの、社会に完全に絡め取られていないような世代の人たちが中心だった。それを僕は自分に投影しながら生きてきた。その頃と、今とでは感想の持ち方が違うのかもしれない。
有り体な言い方をすれば、なんだか自分の年を感じてしまった。
若い頃と今が違うのは、自分と現実社会との関わりがより強くなり、逃げ場がなくなっているところだと(今は)思う。というより、そうしないようにすればいいのだが、いつの間にかそうなっている。昔は簡単に夢の世界に浸ることができるような気がしたのだが。
発売されたのは3月16日だったそうです。すみません、気がつきませんでした。
なぜ取り上げたかというと、今までLumix G3のムック本というのが全然無かったからだ。
なぜかさいきん買ったものは、不人気?なものが多い。
去年買ったスマホはSHARPガラパゴス005SH。これ、003SHと言う姉妹版というか、先行発売されたモデルがあるが、サードパーティが発売したアクセサリーはこの003SH用ばかりで、005SH用は全然発売されなかった。
夏に買ったIXY31SはIXYシリーズの中でも不人気だったらしく、多少手直しした32Sでてこ入れを図ったが、結局この系列ごと消えてしまった。
Lumix G3は去年の暮れに買った。パナソニックのMFTシリーズ、G1からGF3にいたるまで、たぶん全部なんらかのムック本が出ているんじゃないかな。G3をのぞいては。
本屋で手に取ってみたが、各機種の紹介の中で、G3は「少し大きく重いけど、どんな撮り方もできる機種です、だから、この機種に撮り方のコツのようなものはありません」とある。これではなかなかムック本は作れないな・・。
寒かったとは言え、今年は梅がなかなか咲かなくて驚いた。やっと3月末くらいに咲いたが、後が使えているとばかりに桜が咲き始めた。
いつも通りかかるところ。数日前の写真なので、まだ満開になっていない。
ここ、毎年写真を撮っているな、と思い、データを探して見た。
2年前。カメラはRicoh GX200。天気のせいで真っ暗だ。
撮影は4月3日。この年も寒くて、4月中旬なのに雪が降ったりした。
3年前。カメラはIXY 800IS。雑誌では色再現は一眼レフ並みに正確という評価だったが、手前の生け垣はやけに派手だ。
撮影は4月2日だが、1週間ぐらい前から咲いていて、もうすぐ終わるところ。
4年前。カメラは上と同じ。3月29日。数年前は3月下旬に満開になるのが普通だったが、さいきん遅くなったのかな。
もっと前の写真もあるかもしれないが、同じような写真で退屈だから、これでおしまい。
いつもはそんなに遅くないのだが、3月から4月にかけて、だらだらと残業することが多くなった。まわりの人たちに影響されたような気もする。
残業はくせになる。夜になって、9時までまだ時間があると思ったら最後、すぐ終わる仕事もその分しっかり使って仕上げるようになってしまう。
仕事が増えれば時間はさらに上乗せになる。時間が遅いことに麻痺してしまい、早く帰るとサボっているような気になってくる。まわりのひとが残業していると、自分も競うようにして遅く残ってしまう。
長く働く事がいいことだと思う風潮は、日本人だけなのかと思っていた。いまの職場には外国人や、外国に長い人もいるが、そういう人も結構遅くまでいる。これも職場の雰囲気か。
以前いた職場で、若い人を管理していたが、彼は一生懸命働こうと意地になって夜中まで残り、年末年始も来たりしていた。おかげで周りからあいつはおかしい、能率悪いと散々文句を言われて弱った。早く帰れと言っても聞かないのだ。
しかしそれは、職場としては健全な意識だと思う。残業が推奨されるような職場は、ほめられたものではない。しかし、それを変えるのは容易ではない。
今日は定時にさっさと帰った。明日は朝早くオフィスに行くつもりだ。朝は時間のたつのがとても速い。お茶を入れたり、トイレに行っているうちにどんどん時間がたって、「普通の朝」に近づいてしまう。朝は時間の密度が違うのだ。だからこそ、有効に時間が使える。
僕は残業代がつかない。スタッフは一定時間以上は残業代がもらえる。僕と一緒にいればどうしても遅くなる。先日、上司がそのスタッフの残業代について「(その子には)払いたくないんだけど、しかたない・・」というようなことを漏らしていたと聞いた。だから、残業はしたくないのだ。
チラシ、と言うか、案内状が来たので、新設されるクリニックの内覧会に行ってみた。ちょうど社員の今年の健康診断の手配をしていたところだったので。
新築されるホテルのオフィス棟にできるクリニックで、外来診察などはせず、健康診断、人間ドック専門だそうだ。関西が拠点らしいが、これで東京進出という事のようだ。
とにかく内装が豪華で、フロントを見ているとクリニックにはとても見えない。どこかのホテルか外資系企業のフロントみたいだ。椅子や内装の調度品も、医療機関には全く見えない。
クロゼットのある場所がかなり広い。健診着に着替えるところだが、2y畳ぐらいの小部屋が7つぐらいある。クロゼットそのものは各部屋にいくつかあるが、順番に別の部屋に案内することで、受診者がお互いにかち合わないようになっている。普通は風呂屋みたいになっているところだが、これはゆったりしていて良い。男性は関係ないが、パウダールームもある。
待合スペースが数カ所あり、それぞれ、風の間とか、緑の間など、テーマを持ってデザインされている。ふつう、こうした健診用施設は中央に大きな待合室があり、それを取り囲むように健診施設が配置されている。ここは順路に従って少しずつ検診を受けて、その途中でそれぞれの待合スペースを使うように設定されている。椅子が、窓の外に向かって置かれており、座ると皇居が一望できる。
僕は専門家では無いので、担当者と話してもいやーきれいですね、豪華ですね、ぐらいしかいえなかった。まあ、この種の都心の健診施設はこぎれいなところが多いが、ここは飛び抜けて豪華で充実している。最後にアンケートを書いて、携帯型の体脂肪計をもらった。この体脂肪計も使ってみるとなかなか正確な数値が・・おっと、これは豪華すぎる・・。
日曜日、出先で時々行くラーメン屋に入り、遅い昼食をとっていた。
麺がゆであがるまで、スマホでニュースとかを見ていた。
そこから自転車で桜を見に行ったりしたのだが、携帯のことはすっかり忘れていた。
家に帰っても、どこかにあるのだろうと気に留めていなかったが、夜中になってどこにも無いことに気がついた。
最後に携帯を見たのはラーメン屋だ。考えて見ると店の名前も知らない。
食べログなどから店の名前とか、電話番号を突き止めた。
翌日、電話をしてみるとお預かりしていますという。お礼を言って寄る取りに伺います、と言った。
退社するのが8時過ぎになってしまったが、お店は10時過ぎまでやっているそうだ。店に着いたのは9時。とりあえず注文して、実は昼間電話したものです、と告げる。
夫婦でやっている、こぢんまりしたお店で、お二人ともとても親切な対応をしていただいた。チャーシュー麺を頼んだが、チャーシュー7,8枚は入っていてボリュームたっぷりだった。
オフィスの机に置き忘れたことはあるが、外で携帯を忘れてきたのは初めてだ。
会社の子に話したら、いろんなものを忘れてきますねえ、と言われてしまった。早退したとき、家に着いたら鍵をオフィスに忘れた事に気がついたり(途中まで届けてもらった)、小銭入れを机に置いて来たり、そんなことばかりしているなあ。
去年の秋、ジョブズの没後まもなく発売されて話題になった本。上下間合わせると4千円近いし、ジョブズの信奉者では無いので読み始めるのは遅かったが、やはり興味があったので。
Ⅰで生い立ちからアップル設立、最初の成功と転落が描かれている。ここは面白くて、どんどん読み進んでいった。Ⅱは、アップル復帰とiPodはじめとする製品開発の過程、そして病気との闘いの話が続く。90年代から昨年に至るまで、僕らは同じ時代を生きてきているので(もちろんアップル設立の頃から生きてはいたけど)、その過程を振り返ることは興味深くはあるのだが、これから15年、20年たってから読み返したとき、あるいはその頃の若い読者が読んだとき、この後半部分は少し長く書かれすぎて退屈に感じられるかもしれない。
iPod開発からiTunes storeを作るあたり、ソニーとの闘いに触れたところは、別にソニーの側にたっているつもりは無いけれど、ちょっと辛い思いをしながら読んだ。iPodを初めて知ったのはちょうど10年程前、週刊アスキーか何かの記事で、そのときは面白そうだとは思ったけど、その後この世界を席巻するとは全く思いつかなかった。音楽をパソコンで扱うのは、なんだか事務用カッターナイフと下敷きを使って机の上で料理するような感じがして、気持ちが悪かった。
実際にはソニーもPCオーディオに着手していたが及び腰で、2003年頃にはすっかり世界が変わっていた。あの頃、ソニーは結構敵意むき出しでiPod対抗製品を出していたが、どうも相手のペースに乗せられてしまった感じがあった。ハードとソフトを融合させて、音楽界の覇者であったつもりのソニーにはショックだったのだろう。ソニーミュージックとの確執みたいなことは、この本で初めて知った。一方、ソニーのハードのことは、本には余り出てこない。
ジョブズの好きな音楽が、ボブ・ディランやビートルズなどでクラシック音楽ではバロックぐらいだった、という事が、今のiPod-iTunesのつくりに影響しているように思う。ソニーの大賀典雄氏がカラヤンに助言を求め、CDの最長記録時間をベートーベン第9交響曲が収められる74分程度に伸ばした、と言うことを考えると、興味深い。
話がそれた。僕がジョブズに一番興味を持ったのは、その言葉だ。有名なハーバード卒業式でのスピーチをはじめ、引用したくなる言葉が本当にたくさんある。本を読み始めたのは1月頃だが、そのころやったプレゼンで何度か引用させてもらった。他人の人生を生きるなとか、死は人生の決断を助けてくれるとか、stay foolish, stay hungry などは、彼が話してこそ説得力を持つ。そこいらのなんとかコンサルタントが言ってることなんか・・。ましてや、お金が目当てで会社を始めて、成功した人なんか見たことがない、なんて、僕が言ったらすごくかっこわるいです・・。