
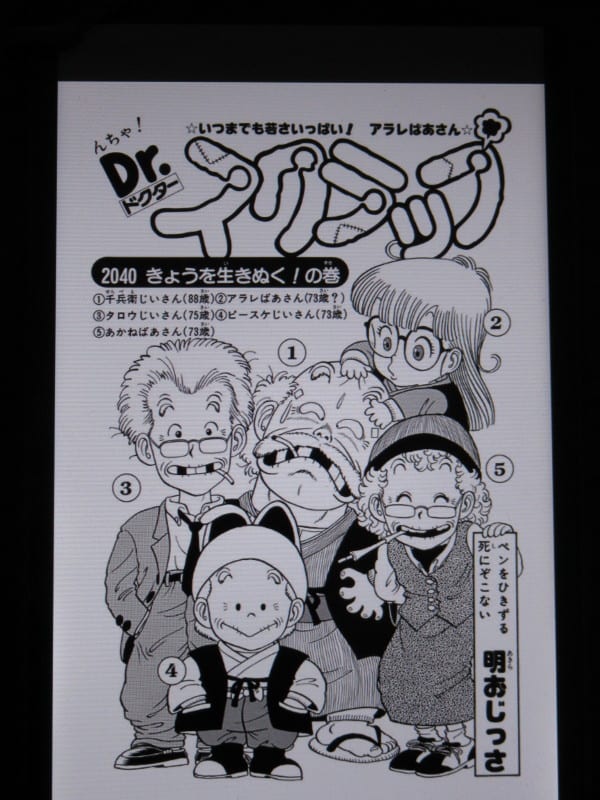

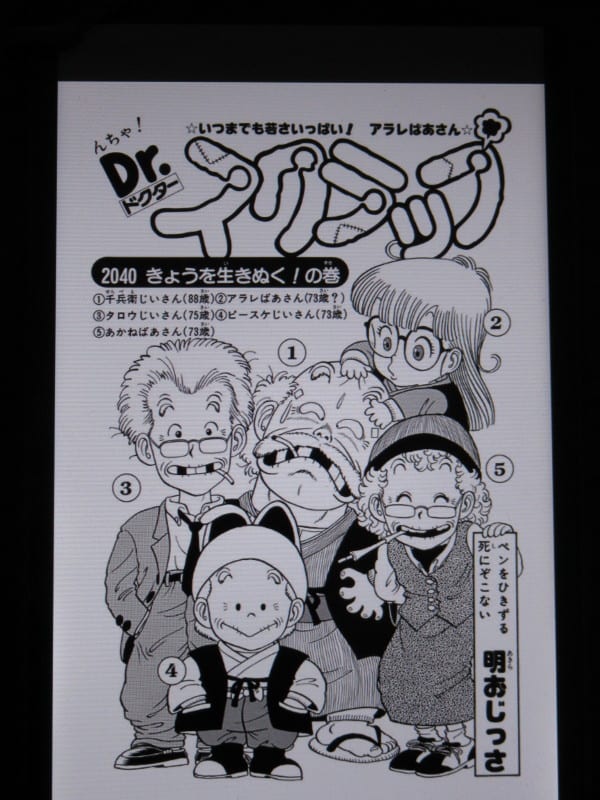







久しぶりにキャンバスに絵を描いている。15年ほど前まで、油絵の教室に通っていたが、油は描きやすく発色が良い反面、廃油や道具の処理、清掃が難しい。非常に強烈ではないが、それなりに匂いもするので、狭くて気密性の高い家では気になる。前宅から引っ越すとき、とってあったぺトロール類、筆洗用油などはぜんぶ処分してしまった。
アクリルは油に準じて使えるが、独特の癖がある。油をやっている頃は、使い勝手が油とアクリルで混同しやすいので、余計使いにくかった。イラストボードに描くことがほとんどだったが、一度頼まれて、2m x 1mの絵を描いたことがあった。
色々な使い方ができるが、メーカーごとに特性も違うようなので、以前はなるべくリキテックスのものを中心に使っていた(もっとも、絵具箱を見ると、結構違うメーカーのものも使っていたみたいだけど)。今回画材屋さんに行って、絵具を追加購入しようとしたら、メーカー、ブランドの数が増えていて、それも見慣れないものが多くなっていて驚いた。リキテックスもあるにはあるが、ふだん使うのにちょうどいい20mlのものが、世界堂にもユザワヤにもなくて弱った。その上の60mlかな?のは売っているが、単価がぐっと上がるのでちょっと買いにくいですよね。。リキテックスに準じて使っていたホルベインは、リニューアルしたらしく違う意匠になっている。今日、現宅の近く(といっても、車で20-30分ほど)の画材専門店に行ったら、20mlのものが揃っていてほっとした。製品としては現行なのだろうから、大型店の品ぞろえがどうしてそうなっているのかは、よくわからない。絵描きさんは絵具をたくさん使うので20mlは売れないのだろうか。
発色や透明度など、絵具によってずいぶん違うので、慣れないとなかなか書き進められない。忘れてしまったことも多い。しばらくは試行錯誤が続きそうだ。
音楽評論家の宇野功芳さんは、独特な語り口の文章で人気があった。
「宇宙が雪崩を打って落下するような第一主題、その後の32音符の下降音型が何という苦しみを訴えかけることか。第二主題への移行部における意味深いリタルダンドと、その後のものものしい神秘感、暗黒内でのまさぐり、すべてフルトヴェングラーならではの表現だ」(フルトヴェングラー ベートーヴェン「合唱」のライナーノートより)
いわゆる美文調だが、昔のクラシックレコードのライナーはこういうスタイルのものが珍しくなかったようだ。ともあれ、僕が宇野功芳と言う名前を知ったのはこのライナーからだ。
自著などでの過激な発言(この曲の演奏録音はこの1枚だけあれば、後はいらない、とか、誰それ指揮の演奏など、聞く方が悪い、など)は、「語録」としてすっかり有名になっている。ので、僕がここで繰り返すことはないだろうけど、個人的には大いに楽しんだ。もっとも、演奏の好みは違っていたけど。
単なる毒舌なわけではなく、その文章の随所に音楽への愛情や少年っぽい純粋さがあふれていて、それゆえに多くの人から愛されたのだと思う。音楽家としても合唱の指揮、交響曲の指揮などをされていたが、好きなことをやれるだけやれた、幸せな人生だったのではないか。
10日に86歳で亡くなられたそうだ。ご冥福をお祈りします。
連休最終日は、東京国立美術館で開かれている特別展「鳥獣戯画展」を見てきた。
連休最終日、展示内容が子供たちも喜びそうな鳥獣戯画とあっては、長い行列が生じるのは当然覚悟しなければならない。
朝早く行けば良いかというと、そんなことはないらしく、ツイッター(いずれリンク切れするでしょうけど)によると、会館と同時に場外での入場待ちが始まり、昼過ぎまでそれが続くようだ。というわけで、午後遅く行くことに。といっても、余り遅いと今度は閉館までに全部見られなくなってしまうので、4時頃から見始めた。

平成館は数百メートル先だが、こんなところに行列最後尾の看板が。

平成館前の広場で、幾重にも列を連ねて待つようにロープが張られていたが、この時間は待たずに入れた。
基本的にこの展覧会は、鳥獣戯画を所蔵している、京都高山寺の宝物展なので、鳥獣戯画以外の展示もたくさんある。
前半は高山寺を再興したとされる、明恵上人とその周辺の画家たちが描いた仏画や曼荼羅などの展示が続く。
うさぎやカエルの絵を期待していた子供たちは、ちょっと退屈してしまうかも知れない。とはいえ、仏画の中にはリスや鳥などのいきものが描かれていたり、馬や鹿、犬などの木像も展示されているので、子供もそれを見て喜んでくれるかな。
多くの人が期待する、鳥獣戯画(こんにちでは甲巻~丁巻にまとめられたものを鳥獣戯画と呼んでいる)は、順路の最終コースで、ここまでに既にたっぷり展示品を見て、ちょっと疲れた頃にたどりつく。順路は甲巻と、乙から丙巻の二つに分かれていて、どちらを先に見ても良い。
甲巻は後回しにして乙~丁を見たが、時代的には逆順で見ていくことになる。ひとくちに鳥獣戯画と言っても、その内容や画風はけっこう幅が広いようだ。うさぎとカエルが相撲を取っている、有名な絵は甲巻のものだ。このほか、人々の当時の遊びを描いたものも含まれていたり、獅子やバクなど、架空の動物を含む動物図鑑のような連作(乙巻)もある。
乙~丁はそれでもまだゆっくり見ることができたが、甲巻はかなり待たされた上、閲覧は列の動きを止めないように言われながら進んでいたので、ゆっくり見るどころではなかった。僕の前の一団(比較的年配の家族連れと、若い男性、なんだか挙動不審の中年男性-疲れたのか、列が止まるたびにしゃがみ込んでいた。かえって疲れそう・・)は、展示物を前にすると急に早足で先に進んでしまい、後を追わざるを得なかった。間が開くと注意されるのだ。なんだかパンダを見ているような慌ただしさだった。
甲巻はちょっと無念さが残るが、とにかく実物を見ることができたのでよしとするか。ついでに言うと、展示は会期半ばで一部変更になるが、後期に展示される分も原寸の写真図版で展示されている。これでも情報量としては十分とも言える。
というわけで、後半分をまた見に行かなくてもいいかな・・。
まあ、平凡な感想ですけど、日本人って、昔から同じような感覚(カワイイ )を持っているのね・・。
)を持っているのね・・。
ちなみに、列を待っているときは館内で配られていた鳥獣戯画クイズ(クロスワードパズルなど)をやっていた。すごく難しくて、ぜんぜん退屈はしていなかった。

12年前に舞台用に描いた、「マグダラのマリア」に再会した。
オペラ「トスカ」の冒頭で使用するために描いたものだ。
大道具の業者さんにお渡しして以来、お目にかかることがなかった。

この春、いくつか行っておきたいところがあった。ひとつはムーミンの映画、昨日は永青文庫、そしてこの岡崎京子展だ。
いろいろと忙しくて、行けるかどうか危ぶまれたが、とりあえずスケジュールを靴べらですべりこませた。

岡崎京子は僕と同世代だ。高校生の頃、「ポンプ」という雑誌があったが、彼女はそこに盛んに投稿していた。
僕はけっこう影響を受けていて、彼女のイラストを模写したりもしていた。ポンプではほかに、岡林みかんという人も良く投稿していたな。

ただ、80年代半ば以降、彼女の名をポンプ以外で見るようになると、だんだんと作品をフォローしきれなくなってくる。
何かを受け止めるにも才能が必要だ。僕はだんだんと保守的になり、噂程度にしか彼女の作品を見聞きしなくなった。
高校生の頃は、男子が少女漫画を読むのが「新し」かった。24年組とかは、時期的には後から「学んだ」かたちになるが、僕も粋がって読んでいたことがある。岡崎氏も萩尾望都などを読んで影響を受けたようだ。
その岡崎氏自身が漫画界の新潮流となっていくのだが、あの頃の女性は強かったなあ。内田春菊や桜沢エリカ、少し傾向はちがうけど、中尊寺ゆつこなど、癖のある描き手が多かった。まあ、時代時代でいつでも強い個性と才能の人が、新しい流れを作っていくのだろうけどね。
特に、性を前面に押し出した作品を、若い頃は読むことができなかったな。なんだか、とりとめのない不安感に襲われてしまう。今読めば、また違う感想になるかも知れないが・。
自分にはない、そして近づくことができない世界を見せられているような気がして不安だった。
高校生の頃は、自分と同じ世界にいると思っていた人だが、いつのまにか、それこそあっという間に、遠いところに行ってしまった気がした。まあ、もともと同じところにいると思っていたのが勘違いなのだろうけど。

若い人たちがたくさん来ていた。
彼らが岡崎作品を、どのように感じているのか興味がある。
漫画について、今なにが新しく、なにが古いもののか、もう僕にはわからない。
ただ、帰りにほろ酔い気分で図録のページをめくると、僕にはあの頃に直結しているような気持ちにさせられたが。
毎年この時期に行われるイベントだが、以前は何となく通り過ぎていた。
今回は昨年までとは趣向が違うようで、興味をひいた。会社の子が楽しめた、と言っていたので、僕も行ってみた。
Fine Artの方は、以前は大きな作品を共同製作していることが多かったように思うが、今回は個人の作品をいくつか並べている。いわゆる現代アートだが、こうした街の中でゆっくり眺めるのはなかなか楽しい。
僕は現代のファインアートの動向については詳しくないが、さいきんは観客とのコミュニケーションに関する工夫が進んでいるのかな、という漠然とした印象を持った。これからはもう少し意識して、各種のイベントや作品展を見て見ようかな、と思った。
音楽の方はまだ鑑賞していない。

15日は都内で美術展等をはしごした。

まず、この日が最終日のボストン美術館 華麗なるジャポニズム展。修復されたモネの「ラ・ジャポネーズ」が見もの。世田谷美術館は初めてだが、駅のところからポスターがたくさん張られている。
美術館は砧公園にある。駅からは20分ぐらいあるくそうで、直通の専用バスが片道100円で往復していた。
日本の広重、北斎が西洋美術家たちに与えた影響は相当のものであったらしい。影響を受けた印象派の画家達は、いわば西洋画の改革者なので、非西洋的なものを受け入れやすいという素地もあったのだろうか。
考えてみると、僕はこれまで広重や北斎などの錦絵をゆっくり眺める機会はなかったように思う。つい永谷園のお茶漬けについてた浮世絵カードを思い出してしまうが・・。
改めて東海道五十三次をはじめとする、一連の錦絵を見ていると、構図や色使いの独特さにはっとさせられる。また、当時の街の風景が生き生きと描写されているのをみると、そのまま時代小説の世界に入っていけそうな気がしてくる。
ラ・ジャポネーズはその大きさからして圧巻だが、後半に展示されている睡蓮や積みわらも大好きで、これだけでも見に来て良かったと思わせる。全くベタですが、ドビュッシーも好きで、よく画集みながらピアノ曲とか聞いていたものです。

帰りは駅まで歩こうかと思ったが、道がわかりにくそうなので結局バスで。
この後表参道に転戦。
先日石巻で知り合いになった写真家の方のグループ展をみる。
会場におられるという話だったが、僕が来たときは既に帰られたそうで、残念。
この界隈は以前仕事で通っていたことがあり(あまりいい思い出ではないが)、ちょっと懐かしくなって歩く。途中で出会ったネコ。見事な毛並み。僕に興味があるようで、僕の前でごろ~んとして見せてくれた。
通りに出て、やってきたバスに乗り込む。渋谷から青山、六本木、溜池、赤坂、虎ノ門と、都心の主要部を経由して新橋に行くバス。ちょっとした観光気分で乗った。
バスに乗ったのは、有楽町に用があったから(ビックカメラにフィルムを出したかった)だが、フィルムは忘れてきたことに気がついた。まあいいか(翌日出した)。
先日何気なくテレビをつけたら、バルテュスを扱ったアート番組をやっていた。そういや駅のポスターで見かけるバルテュス展、いつまでだっけ、と調べたら、もうすぐ終わりそう。
慌てて行こう、と思ったが時間がとれない。ようやく、金曜の夜(この日だけ8時までやっている)に無理矢理時間を作った。

ギリシャ戦の日でもありましたね。ここ(丸の内)も、一応パブリックビューの会場になっているようです。僕は通勤中に、前に座っている人がスマホで実況を見ているのを盗み見していた・ 。
。
都心部の駅などではかなり盛んに広告していたが、それにしても場内がかなり混雑していたのには驚いた。
バルテュスを知ったのは彼が存命中のことで、その頃の僕の印象(ちゃんと作品を見ていなかったので、大変失礼な印象だが)は、なんか変なじいさん、という 、ひどいものだった。ごめんなさい、って、誰に謝っているんだか。
、ひどいものだった。ごめんなさい、って、誰に謝っているんだか。
以前は現代の作家であり、評価も現在進行中、という感じだったが、没後13年を経て、すっかり大家の地位に落ち着いたような気がする。
大胆なポーズをとる少女の絵が今日でもとても衝撃的で印象に残るわけだが、絵を目の前にしてまず感じるのは、古典的な描画手法で描かれているな、ということだ。
僕の西洋画知識には限りがあるが、絵の具を何度も塗り重ねて行く手法は、印象派以前の室内画の伝統を感じさせる。様式的な、やや不自然な形にアレンジされたポーズからも、古典的な印象を強調したいという意図が感じられる。
こうした描法は、これの描かれた1930年代から50年代に人々の目にどう映ったのだろうか?
風景画はまた人物とは別の面を見せる。「窓」などは色調のせいか妙に印象派っぽいし、「モンテカルヴェッロの風景」など、また作風が変わっている。
いろいろ思ったこともあったけど、ここで書こうにもまとまらなさそうだし、この辺で。思ったより、心に残る展覧会でした。

夜8時まで見られるのはありがたいが、それでも後半はちょっと慌ただしかった。
昼の一番長い時期だが、午後8時には日が暮れている。心の底の記憶では、もっと日が長い国に昔いたような感じもする。一度夏の北欧にでも、しばらく滞在してみたいものだ
会社の子に川上哲治さんのことを話そうとして、ウェブのニュースを開いたとき、小林彰太郎さんの訃報が目に入った。
CAR GRAPHICの編集長として、ファンの間では伝説的と言って良いほどの名声を得た方だ。編集長を辞されてから既に四半世紀に近くなるが、その名声は衰えなかった。
自動車や、僕の知っている範囲では鉄道模型の山崎喜陽さんとか、オーディオの菅野沖彦さんなどがそうだが、おそらく昔は中流以上の、学歴の高い人でないと趣味活動などできなかったのだろう。外国語に堪能で、文学その他非常に広い教養を持つ方々が、趣味界のオピニオン・リーダーとなることが、昔は多かったようだ。
今だとオタクなどと呼ばれて、とても狭い世界観を持つ人が趣味人とされているが、小林さんの文章ににじみ出てくる深い教養とちょっと日本離れした、格調高い文体は、自動車趣味をとても洒落た、紳士の嗜みのようなもののように思わせた。こんな大人になってみたいなあ、とあこがれたものである。
先日車で久しぶりに遠出する機会があり、ちょっと興味が出たのでCAR GRAPHICを10数年ぶりに買ったり、本屋で小林氏の本を立ち読みしたりしていたところだった。不思議な、因縁めいたものを感じる。
小林氏の近著をぱらぱらと立ち読みしたが、近頃若者の車離れが顕著だと聞くが、良いことだ、都市の交通は見直して、路面電車のようなものにすべきかも知れない、などとあり、意外な感じがした。今日、あらためてその本を探そうとして、同じ本屋に行ったが、書棚になかった。訃報を聞いたファンが、買っていったのかも知れない。
ご冥福をお祈りします。
20年ほど前に買った本。「小林彰太郎の世界」表紙は、軽井沢を走る小林氏の写真。同じ写真をあしらったCGの記事を覚えている。「英語にはBusman's holidayというのがある、ぼくも平日はテストドライブをして車の記事を書き、休日には古い車を直して走る、この気持ちの良さはどうだ」という内容のことを書いておられた。
先日亡くなったやなせたかしさんと、糸井重里氏の対談(こちら)。
やなせさんが、晩年地方自治体に提供したキャラクターデザインの仕事のほとんどが無償だった、と語っている。
この対談を読んだ漫画家の吉田戦車氏が怒りのツイートをして、それが反響を呼んでいるそうだ(ニュース)。
この種の話はネットで時々議論になっているのを見る。自治体がイラストを公募し、但し無償としたことについて、その自治体の姿勢に職業作家として抗議すべき、とイラストレーターの方がつぶやいておられたのも見たことがある。
対談の中で、やなせさんは自治体などへの仕事は無償だったが、代わりにアンパンマンのキャラクター達が稼いでくれた、と語っておられる。また、別のところでは雑誌の編集長だったころ、スポンサーの会社(サンリオ)が、寄稿した作家の原稿料は払わないでいいだろう、と言われたことに反対し、代わりに自分の給料を削った、とも語っている。
やなせさんの言いたかったことは、仕事に対する対価の支払い、という行為が、世の中ではときには適切ではない、ということなのだと思う。対価の決定は世の中のあらゆる職業においても難しいものであり、公平で適切などという概念は存在し得ない。それでも、仕事を頼むときに、お金は払わないけどやってくれ、というのは、あまり一般的な状況ではない。ただ働きに甘えてきた自治体や組織は恥ずべき、という吉田氏の主張も理解できる。
役人が4人来て、キャラクターデザインをして欲しい。予算がないからタダで、という。
やなせさんは「私も仕事でやっているので、いくらかはもらわないと」というと、4人で小声で話し合って、わかりました、ではこれこれで、と言ったという。それじゃしょうがねえや、と思ったが、とにかくやった。「キャラクターに人気が出たので、着ぐるみを作るには予算が出るのに、俺はタダって言われるのは何でなんだ、よくわからない。」
こういう話になると、この感覚は民間企業にはないのではないかと思う。
ただし、やなせさんの場合、対談中述べておられるように、巨匠と思われることを避けたくて、小さな仕事でもなるべく断らずに引き受けようとした、という事情もあるようだ。
現実の世界には色々と大人の事情があるかも知れないわけで、そもそもこうしたことが言えるのも、やなせさんだから、という面もあるのかもしれない。
アンパンマンがヒットしたのは、やなせさんが50歳を過ぎてからのことだし、そもそもやなせさんは、子供向けの童話を書く気はなかったそうだ。他の漫画家やデザイナーを見て、これはかなわない、と思いながら生きてきたという。アンパンマンも最初は周りの大人達の評判は悪かった。ところが、3歳の子供達が争うように読むようになり、ブームに火が付いたとか。
対談ではいくつもの名言を残しておられる。
糸井 いやあ、この勢いでずっと仕事してそうですね。
気を丈夫に持つ秘訣があるんですか、心が丈夫だっていうのは、なにかあるんですか。
やなせ アホなんです。もう何ていうか、人よりもアホなんでしょうね。・それと、芸術家じゃないんだよね。
芸術をやろうと思ったことはない──あ、若い時はちょっとそういう感じがあったかな。
若い時はね、高級なやつをやろうと思ってね、
そういう時代がありましたけど、途中でイヤになりました。・やっぱりね、死んじゃうとおしまいなんだな、どんな天才でも。
だから水木しげると俺みたいに寝てるやつはね、死なないんだよ。あっはっは。
僕も頑張ってゆっくり寝ていようと思う。
ユリイカとか、やなせさんの単行本も注文したけど、到着はだいぶ先らしい。
(連休特集と言うことで?以下かなり長いです)
この週末は台風に祟られることになりそうだが、当地では雨は午前3時頃から降り始めた。延々降り続けて午後1時半頃にいったん止み、すこし晴れ間が出て来た。本格上陸は明日になると聞く。出かけるなら今だと思い、電車に乗る。
まず、渋谷に出てBunkamura ザ・ミュージアムのレオナール・フジタ展を見に行く。フジタは今日ではそれなりに人気があるようで、比較的よく美術展が開かれている。今回のはポーラ美術館の所蔵品を中心に展示されているが、周辺の画家や、交流のあった土門拳などの写 真まで展示された本格的なものだ。見ているうちに時の経つのを忘れてしまった。
フジタ(藤田嗣治)については僕はすこし思い入れがある。10数年前に見たテレビのドキュメンタリーとその感想について、以前にやっていたホームページでも書いたことがある。
かいつまんで言うと、パリで苦労の末名声を勝ち得たフジタは、第2次大戦中は日本に留まり、いわゆる戦争記録画を描く。そのことから戦後、画家仲間から戦争協力者の代表のように仕立てられてしまう。
更に、日本を離れ最初に渡ったニューヨークでも、現地の日本人画家から締め出しを食う。最終的にパリに落ち着いた藤田は、現地で暖かく迎えられる。やがて日本国籍を捨て、更にキリスト教の洗礼を受ける。名前もレオナール・フジタとなり日本に帰らぬ決心をするが、他方、夫人によると、晩年まで浪花節などのレコードを愛聴していたという。
藤田の戦争記録画「アッツ島玉砕」「サイパン島同胞臣節を全うす」は国立近代の所蔵で以前見たことがある。その凄惨な描写は、軍部から疑問の声が出されてた程だが、国民からは強く支持されていたようだ。藤田自身、(戦争画を描いたことを)その時代の日本人として当然のことをしただけだ、と後日手紙に書いている。
戦後、手のひらを返したように人々から厭われるというパターンは、息子を特攻で失い英霊の親族としてあがめられていた一家が、戦争後近隣から冷たいあしらいを受ける、という話とそっくりである。数年前まで敵国人であったフジタを、その芸術的才能で評価して温かく迎えたフランス社会とは、余りにも対照的だ。
このことを思い出すと僕は、日本人って信用ならねえなあ、と憤りを感じたりするのである。
・・などと、一人で熱くなっていないで、フジタ展に戻ると、ここではそんな戦中の彼の様子はすっぽり抜け落ちていて、「乳白色の肌」で勇名をはせた前半生と、後年の子供達を中心に描いた連作に重点が置かれた展示になっている。
子供達の絵をこれだけたくさん見るのは今回が初めてだ。
フジタの描く子供達は大人に向かって笑いかけていたりはしていない。みんな真剣な顔をして体操したり、いたずらしたりしている。
「職人達」シリーズでは大まじめに家具を作ったり、肉をさばいたりしているが、時に運んでいた瓶を割ってしまって泣いていたり、子供の歯医者さんが歯を抜こうとすると、やはり子供の患者さんが痛がって暴れていたりと、ユーモラスな表現があって、思わず頬が緩んでしまう。自信満々で大人の真似をする、というのも、子供の愛らしさであり、フジタはそんな子供達を愛したのだろう。
長くなったが、フジタ展の話はこれでおしまい。
大雨でずぶ濡れになってしまった御神輿。Bunkamuraに行く途中で。
外に出たら、天気は回復して青空が見えている。ついでだから、万世橋の新しいショッピングモールに行ってみることにした。渋谷からの行き方は色々あるが、地下鉄で淡路町を目指した。
ビルの3階から出る地下鉄。一連の工事が完了すると、この風景も見られなくなるとか。
昨日ニュースでやっていたが、JRが再開発した、マーチエキュート神田万世橋、というモール、中央線の古い煉瓦造りの高架橋を改装したものだ。戦前までここは、万世橋という駅だった由。7年前までこには、交通博物館があった。
今回は旧ホームを展望台として整備している。
駅名票も復活。
商店街は高架下にあるが、入り口も店内も狭く、最初はちょっと入りにくい。小物を売っている店が多い。
内部はこのようにつながっている。
喫茶店や食事のできるところもあったが、今回は見送った。今度行ってみよう。
万世橋はもとは駅だったので、JRの他の駅とは多少離れている。秋葉原、お茶の水、神田、それぞれ5-6分かかる。今回淡路町から行ったが、道を間違えてしまった(道が碁盤目状ではないのでちょっと複雑)。帰りは神田から中央線に乗り、次の目的地、新宿に向かった。
新宿で、中古のLPレコードを追加仕入れした。
前回はカラヤンのベートーヴェンだったが、盤質もよく値段も安かった。今回ベートーヴェンはさすがに飽きたので、別の作曲家、ジャンルを探してみた。LPはCDとはまた値付けが違うようだ。CDもさいきんの値付けはよくわからないが、LPは余計わからない。カラヤンのベートーヴェン全集(6枚)が1000円かと思えば、貴重盤は1枚1万円近いものもある。
門外漢としては、ふつうにお手頃で聞きやすいもの、を基準に探してみる。
ブルーノ・ワルター/コロンビア響のモーツァルト(3枚組。'62年頃発売された?国内盤)。先入観としては、わりと柔らかめの、脂身の多そうな演奏。リンツとプラハはそんな感じで、うさ耳にはちょっと、かな。でも、ジュピターは一転きりりと締まって、これは良かった。アナログで聞く価値はありそう。
シュライヤーの「水車小屋」。中古屋の状態区分はA。演奏してみるとまったくプチプチ言わない。ヴォーカルは中音域中心だからオーディオ的に無理がない反面、微妙なニュアンスの違いが出やすい(人は人声位の音域がもっとも敏感)。オペラは長いからCD有利だが、歌曲は実にアナログ向き、かも。実体験としては、カーペンターズをはじめてCDで聞いたとき、LPと声が違って聞こえるのでびっくりしたことがある。カーペンターズも欲しいな・。
4月末に始まり、ずっと行きたかったのだが、いよいよ15日が最終日になってしまった。
駅の看板。これは「我が唯一の望み」。この看板に惹かれた。それと、「一角獣」。
中世に作られた6枚のタペストリー(タピスリーと表記されていた)を巡る、展覧会である。
週末は遅くまでやっている。
「一角獣」といえば、どうしても「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」(村上春樹)を連想してしまう。
小説では一角獣について、作中の登場人物(図書館の女性)に歴史的な伝承を語らせている。僕の一角獣に関する知識はそこから来たものが全てだ(小説では、革命前のロシアで一角獣の頭骨が見つかったような論述があった。どこかにそんな話があるのかと、ググってみたが、さすがにこれはフィクションらしい・・。ほんとだったりして?)。
作中に出てくる一角獣について、形態的な記述はあまりないが、体毛の色については詳述されていている。春から秋口までは様々な色をしているが、秋になると一斉に金色の毛に覆われる。角の色は真っ白で、目は青空のように蒼い。この辺も作者のフィクションらしい。
小説も謎めいているが、この「貴婦人と一角獣」にも謎が多い・・、そうだ。中世の絵画には余りなじみがないが、これには様々な寓意が隠されているらしい。6枚のタピスリーはそれぞれ、触覚、味覚、嗅覚、聴覚、視覚、そして第六感を示しているそうだ。
また、そこかしこに描かれている動物たち。「触覚」に出てくる猿は、鎖でつながれいている。音声ガイドでは、これは男性の女性に対する忠誠を示すものだと、音声ガイダンスでは言っていた。
うさぎがやたらと出てくる。妙にかわいらしいが、うさぎは多産の象徴、と解説にある。貴族の婚姻を祝うためのものだからか。
学術的な研究はともあれ、この静謐な世界は、僕の好みとするところだ。
国立新美術館に来たのは久しぶりだ。TIFもおもしろい建築だが、ここの造形もかなりのものだ。
ジオラマ風で。
カフェはもう終わっているが、写真は撮りやすかったかも。
図録を買った。そのうち、これをヒントに何かの絵を描いてみたい気がする。
去年も関連する写真展が開催されいてた、相田みつを美術館で、今年も3.11に関連する写真展が開かれている。ホームページでは簡単な紹介しかされていない。
*さいしょ、複合機でスキャンしたのだが、転送した画像を見たら、部分ごとにばらばらにスキャンされていた(プリントスキャンのモードになっていたらしい)。
ひしゃげた鍋、花束、コンピュータの解説書らしき本などが、淡々と紹介されている。一つ一つのモノたちは、博物館の標本のように白い紙を背景に撮影されている。
モノには時間が堆積している、と六田氏はいう。生活の中で使っていた人たちとの時間。そして、3.11の津波の瞬間。更に、その後の時間。
2年が過ぎ、私たちにもそのぶんの時間が堆積している。人々の手を離れて、たどった道のりは変わったが、これらのモノ達は、実はそのことを思い出させようとしているのかもしれない。