二つの陶芸ランキングに参加してます。3位と2位です。応援クリックしてね! 人差し指や中指でこの ↓↓ バナーをトントン。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング 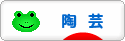 にほんブログ村
にほんブログ村
陶芸の基本 (元祖陶芸?! 目から鱗が落ちる!)/連載7
■ 手びねりの削り
手びねりの 「玉づくりシリーズ」 を 2、3回ほど掲載して、生徒さんの本焼き作品などをアップする予定でしたが、間があくと理解しにくいだろうと思って、連続して掲載して 6回にもなりました。こう言う記事ですのでブログへの訪問者が減っていますが、出来るだけ伝えておきたいし、残しておきたいので、きちんと書いています。ろくろの基本でもありますので、読んで実践してほしい。
「手びねりの削り」 についても少し触れておかないと区切りがつきませんので、引き続き今回も 「手びねりの基本」 シリーズを掲載します。削りについては、写真が何枚か残っていましたので、それをアップしましょう。
陶芸は、削りで形が出来上がります。器のよさも決まります。成形する時にも、あとで削るので、削りしろを考えて形を作るようにしましょう。
陶芸体験の場合には、先生が削りを行うケースが大半ですが、これでは先生の作品になってしまいます。自分で削って初めて自分の作品と言えます。削りも結構大変ですが、一つや二つを削るのは楽しいものです。出来れば削りも、釉薬掛けも行うようにしましょう。削りと釉掛けを行うことで、器づくりがどう言うものなのか、どういう工程を踏んで出来上がるのか理解できると思います。それを知ってほしいと思います。
手びねりの削りです。カキベラを後から手前に引きながら削ります、
下の 3枚の写真は体験者の削りです。最初に、高台の外側を削り出します。

そして、胴の外側を削って。最後に高台の内側を削ります。

削りの終了です。削りが使える器になるかどうかを左右します。大事な作業です。

レベルが上がってくると回転を入れて削ります。
下の 4枚の写真は生徒さんの削りです。回転を入れてます。
削りでは、胴周りは左回転、高台内は右回転です。




削りについても、拙著 『生活にうるおいを与える食器づくり』 に詳しく書いています。改訂版は売り切れましたが、初版が少し残ってますので、もし欲しい方がおられましたらお分けします。下記の特別セール欄をご覧下さい。
また、アマゾンで通信販売をしてる時に、クチコミに嬉しいコメントをいただいていますので記載させていただきます。
「陶芸の最も基本的な所から、比較的細かいポイントに焦点を合わせて紹介してあるので、かゆい所に手が届くといった感覚で非常に役に立ちます。少し学んだ経験がある人でも改めて得るものがあるのでは。作品集もどれも素敵ですね。」
どなたか存じ上げませんが、ありがとうございます!
↓↓ 励ましのクリックをしてあげてね!! 皆さんの 1日 1回の励ましのクリックが 10ポイントになります。にほんブログ村 陶芸ランキングが 2位、もう一つの人気陶芸ランキングが 3位です。
 にほんブログ村
にほんブログ村  陶芸ランキング
陶芸ランキング
 人気ブログランキング
人気ブログランキング 陶芸の基本 (元祖陶芸?! 目から鱗が落ちる!)/連載7
■ 手びねりの削り
手びねりの 「玉づくりシリーズ」 を 2、3回ほど掲載して、生徒さんの本焼き作品などをアップする予定でしたが、間があくと理解しにくいだろうと思って、連続して掲載して 6回にもなりました。こう言う記事ですのでブログへの訪問者が減っていますが、出来るだけ伝えておきたいし、残しておきたいので、きちんと書いています。ろくろの基本でもありますので、読んで実践してほしい。
「手びねりの削り」 についても少し触れておかないと区切りがつきませんので、引き続き今回も 「手びねりの基本」 シリーズを掲載します。削りについては、写真が何枚か残っていましたので、それをアップしましょう。
陶芸は、削りで形が出来上がります。器のよさも決まります。成形する時にも、あとで削るので、削りしろを考えて形を作るようにしましょう。
陶芸体験の場合には、先生が削りを行うケースが大半ですが、これでは先生の作品になってしまいます。自分で削って初めて自分の作品と言えます。削りも結構大変ですが、一つや二つを削るのは楽しいものです。出来れば削りも、釉薬掛けも行うようにしましょう。削りと釉掛けを行うことで、器づくりがどう言うものなのか、どういう工程を踏んで出来上がるのか理解できると思います。それを知ってほしいと思います。
手びねりの削りです。カキベラを後から手前に引きながら削ります、
下の 3枚の写真は体験者の削りです。最初に、高台の外側を削り出します。

そして、胴の外側を削って。最後に高台の内側を削ります。

削りの終了です。削りが使える器になるかどうかを左右します。大事な作業です。

レベルが上がってくると回転を入れて削ります。
下の 4枚の写真は生徒さんの削りです。回転を入れてます。
削りでは、胴周りは左回転、高台内は右回転です。




削りについても、拙著 『生活にうるおいを与える食器づくり』 に詳しく書いています。改訂版は売り切れましたが、初版が少し残ってますので、もし欲しい方がおられましたらお分けします。下記の特別セール欄をご覧下さい。
また、アマゾンで通信販売をしてる時に、クチコミに嬉しいコメントをいただいていますので記載させていただきます。
「陶芸の最も基本的な所から、比較的細かいポイントに焦点を合わせて紹介してあるので、かゆい所に手が届くといった感覚で非常に役に立ちます。少し学んだ経験がある人でも改めて得るものがあるのでは。作品集もどれも素敵ですね。」
どなたか存じ上げませんが、ありがとうございます!
↓↓ 励ましのクリックをしてあげてね!! 皆さんの 1日 1回の励ましのクリックが 10ポイントになります。にほんブログ村 陶芸ランキングが 2位、もう一つの人気陶芸ランキングが 3位です。
 陶芸ランキング
陶芸ランキング 大分市内にある数少ない 陶芸教室 「夢工房あすか」 です。
意外にも近くにあるのに気付かない人たちが多いですが、
下記の教室案内をクリックしてご覧下さい。
陶芸を基礎からコツコツと学ぼ~う。
電動ろくろもスムーズに習得できます。
意外にも近くにあるのに気付かない人たちが多いですが、
下記の教室案内をクリックしてご覧下さい。
陶芸を基礎からコツコツと学ぼ~う。
電動ろくろもスムーズに習得できます。
こういう本があるといい。こういう本が欲しかった。
アマゾンの陶芸ベストセラーでNo.1 にランクされたこともある実用書。
アマゾンへは、こちら をクリック。定価は1,400円です。
リユース本には、5,000円のプレミアムも付いてます!!
≪陶芸の基本シリーズ連載記念の特典≫
自費出版した 『生活にうるおいを与える食器づくり』 の
改訂版は完売しましたが、改訂前の初版が少し残っています。
ほしい方がおられましたらお分けします。
定価は @1,400円ですが、硬貨だとかさばるので、
お札で、送料込みで @1,000円としました。
初版ですが、ページ数は改訂版と変わりません。
アマゾンの陶芸ベストセラーでNo.1 にランクされたこともある実用書。
アマゾンへは、こちら をクリック。定価は1,400円です。
リユース本には、5,000円のプレミアムも付いてます!!
≪陶芸の基本シリーズ連載記念の特典≫
自費出版した 『生活にうるおいを与える食器づくり』 の
改訂版は完売しましたが、改訂前の初版が少し残っています。
ほしい方がおられましたらお分けします。
定価は @1,400円ですが、硬貨だとかさばるので、
お札で、送料込みで @1,000円としました。
初版ですが、ページ数は改訂版と変わりません。
※ 令和 2年1月16日から
「いいね」 などの表示ボタンもアップしてみました。
下のどれをクリックしてもブログ画面は変わりませんが、
Goo ブロガー以外の方は、ログインが必要になるようです。
誰でもオープンに参加できると、いいんですけどね ・・・。
又、「いいね」 ボタンなどをポチッとしていただいた後に、
陶芸のランキングバナーもクリックしていただけると深々と
最敬礼です!! 他の陶芸ブログも参考になると思いますよ。
「いいね」 などの表示ボタンもアップしてみました。
下のどれをクリックしてもブログ画面は変わりませんが、
Goo ブロガー以外の方は、ログインが必要になるようです。
誰でもオープンに参加できると、いいんですけどね ・・・。
又、「いいね」 ボタンなどをポチッとしていただいた後に、
陶芸のランキングバナーもクリックしていただけると深々と
最敬礼です!! 他の陶芸ブログも参考になると思いますよ。












































