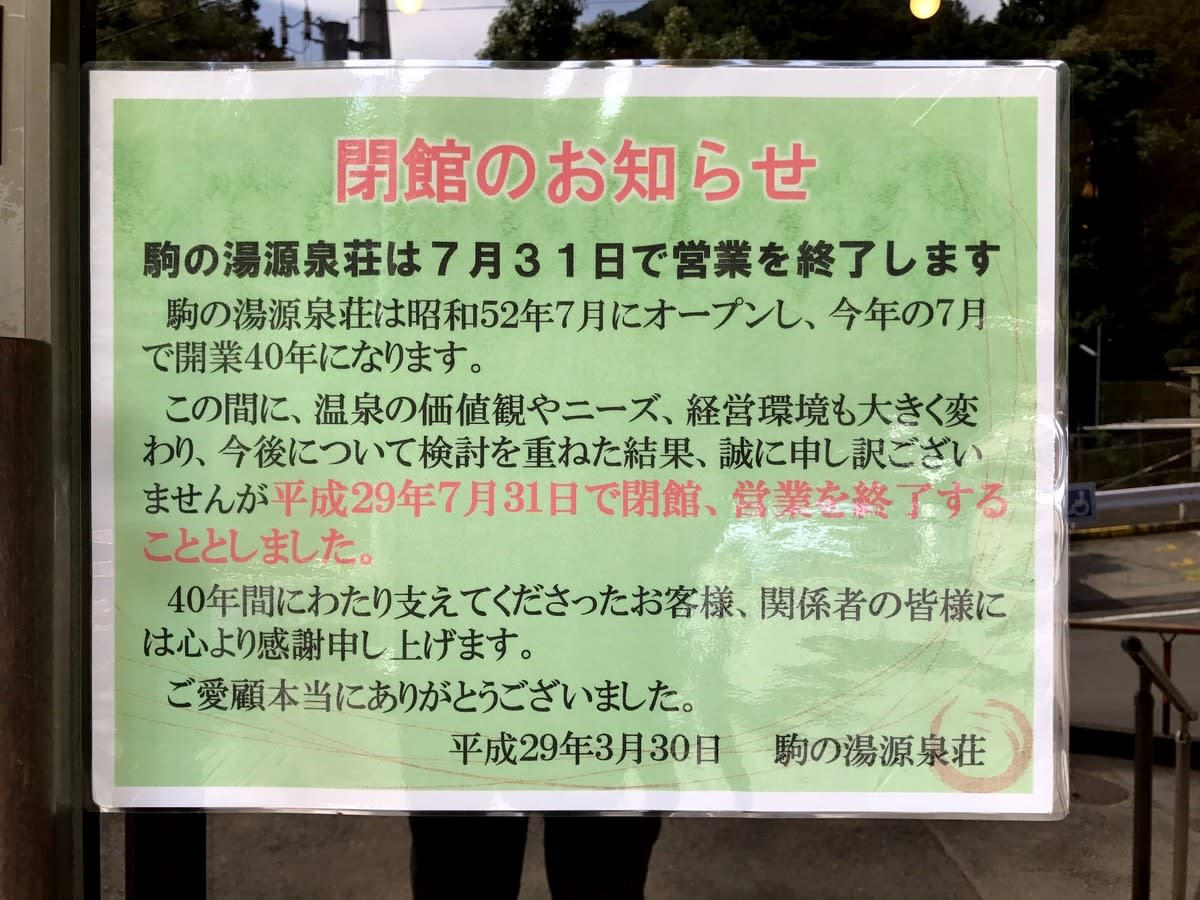(縁の下の力持ち@新潟交通モワ51)
旧月潟駅に、モハ11と並んで保存されている電動貨車モワ51。新潟交通は、信濃川の下流域である白根や月潟の農村地帯に路線を持ち、沿線で獲れるコメや野菜などの農産物の出荷ルートとしても重要な役割を担っていました。元々この地域一帯の物流は水運によって行われていましたが、大正時代に大河津の分水路が出来た結果、信濃川とその支流の中之口川の流量が激減。水運に代わる輸送手段を必要としたこの地区の有志によって設立された中ノ口電気鉄道によって、新潟市内から燕までの鉄道が開業しました。

国鉄の旧国クモユニを思わせる、鉄格子付きの両開き引き戸。新潟交通は燕で国鉄弥彦線と接続していたので、お米だけでなく白根の桃や月潟のナシ、そして燕の名産である刃物や洋食器などが、この電動貨車によって全国へ運ばれて行きました。モワ51は電気機関車兼荷物電車というポジションで、単行で荷物を運んだり、燕から継走された国鉄貨車を牽引して線内を行き来するのが主な仕事だったようです。

車内には廃線によって拠出された営業当時のお宝グッズが所狭しと置かれています。奥に架けられた看板には、「床下機器保護と危険防止のため、鮮魚芥類その他水気を含む荷物は取扱いに十分注意してください」。とありました。水気に弱いなら床板補修しておけよと思わんこともないけど、港で水揚げされた魚なんかを運ぶ時は、今とは違って木のトロ箱だから、床下まで染み出しちゃう事もあったんだろうね。


新潟交通の貨物輸送が廃止になった後、モワ51は除雪用貨車であるキ100の動力車として、廃線までその役割を全うしました。今でも弘南鉄道では同類の仲間が現役で使われている除雪用貨車キ100ですが、動力を持たない鉄道黎明期の除雪車両は保存車としてもその価値は貴重なもの。1915年国鉄大宮工場製造の御年103歳。鉄道車両も100歳を過ぎれば魂が宿るのか、前面窓に付けられた旋回窓が何かの意思を表しているかのように見えますよね。
最後の走り! 新潟交通 保存車自走シーン【鉄道アーカイブ #02】Niigata Kotsu -- Last run for Preservation
ちなみにここに保存されている新潟交通の旧車両は、1999年の4月5日、新潟交通の廃止当日に自走でここ月潟の駅まで回送され、そのまま保存車となって今に至ります。ビコムの映像がYoutubeに転がっていましたけど、11m電機(?)が大正生まれの古強者を押して関屋の分水路を渡っていく最後の姿は、絶妙なモワ51の吊り掛けサウンドとあいまって相当にカッコいい…
やっぱ、現役時代に来ておくべきだったね(そればっかw)