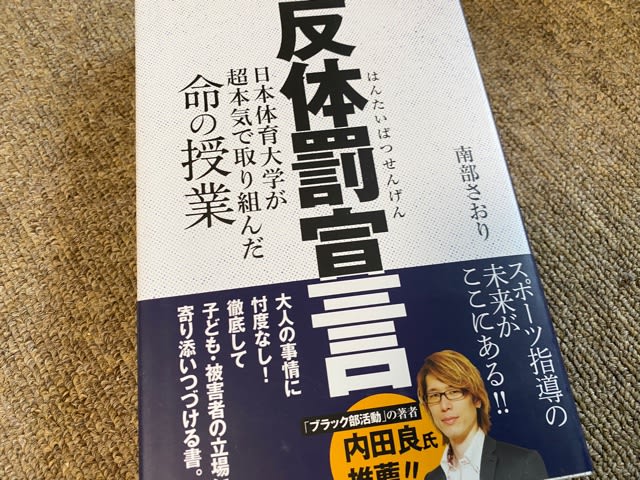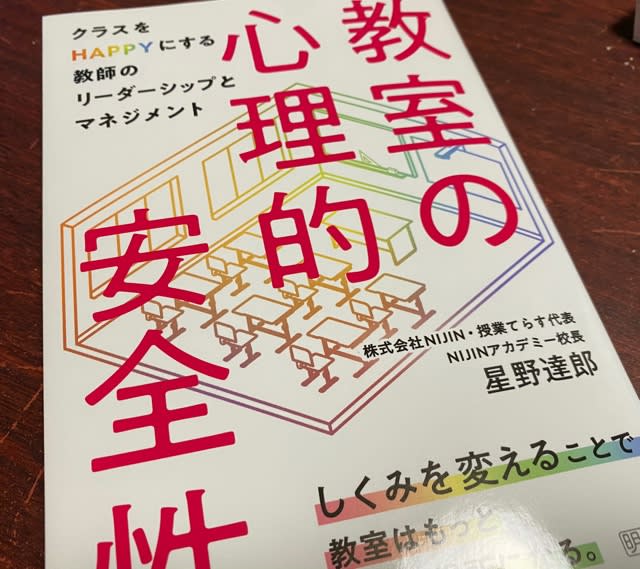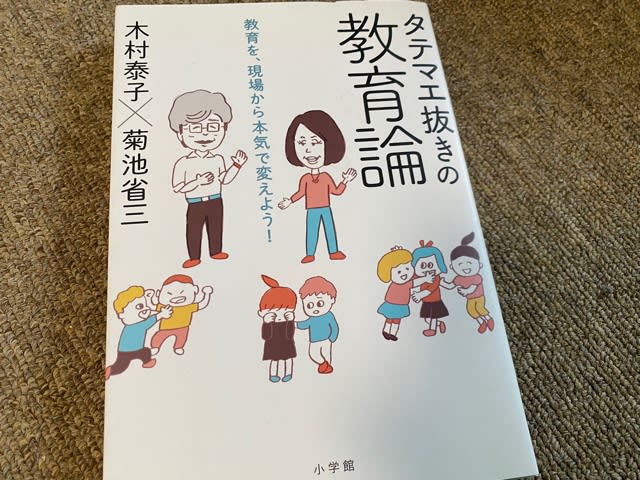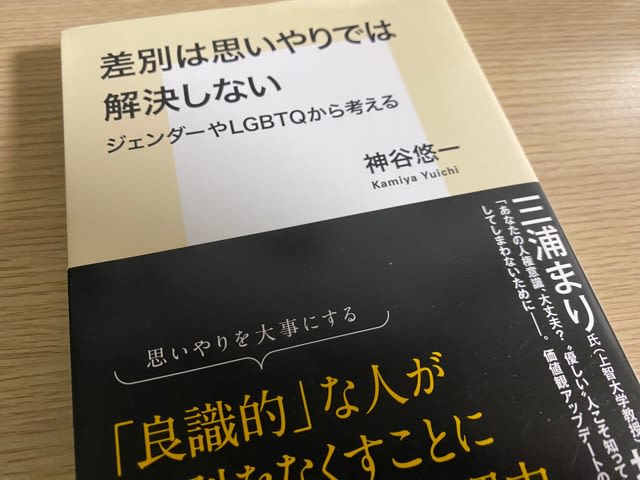部活動の場で命が奪われる現実。
「反体罰宣言」をした
日体大が企画した、「一生もの」の
講義には、学校の部活で
我が子を亡くした、親や遺族が登壇し、
聴衆は、主に体育教師やスポーツ指導者を
目指す日体大の学生や
今現在、指導者として活躍している
日体大の教職員。
顧問による不適切な対応、
顧問の「なぶり殺し」、
灼熱の中の執拗な「罰走」、
仲間が受ける体罰に耐えられなかった、
体育大学卒顧問の暴力、
「友だちにお菓子をもらって食べただけ」
で死に追い詰めた指導死、など、
教育現場で子どもが亡くなることの、
多いことに驚かされます。
しかも、ほとんどが、大人が
関わることで起こっている。
私たちは、重大事故・事件から、
部活動・スポーツ教育の在り方を
学ぶことしかできません。
興味のある方は、ぜひ一読を。