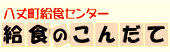今年最後の特売チラシの掲載が遅くなってしまいました。申し訳ございません。
明日の最終までの特売ですので、みなさま、どうぞご利用くださいませ。

年越し蕎麦におせち、お雑煮用のお餅、お肉に海老・蟹、お刺身、寿司種と、
お正月に欠かせない商品を幅広く取り揃えての年内最後の特売でございます。
大晦日のお買物もどうぞ「あさぬま」をご利用くださいませ。





















みなさま、今年も当ブログをご愛読いただきまして誠にありがとうございました。
島内のあちこちで、思いがけない方々から、「いつも見てるよ」とお声がけいただき、
いつも励まされたり嬉しかったりばかりの1年間でした。
来年は更に、みなさまのご期待に添えるよう、益々のおいしい暮らしを展開しますね!
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
明日は、当ブログはお休みです。次回は、新年の更新になります。
みなさま、どうぞ良いお年をお迎えくださいね!
 「あさぬま」は、元旦より営業いたします。
「あさぬま」は、元旦より営業いたします。
元旦 10:00~18:00 2日、3日 9:00~18:00
明日の最終までの特売ですので、みなさま、どうぞご利用くださいませ。


年越し蕎麦におせち、お雑煮用のお餅、お肉に海老・蟹、お刺身、寿司種と、
お正月に欠かせない商品を幅広く取り揃えての年内最後の特売でございます。
大晦日のお買物もどうぞ「あさぬま」をご利用くださいませ。






















みなさま、今年も当ブログをご愛読いただきまして誠にありがとうございました。
島内のあちこちで、思いがけない方々から、「いつも見てるよ」とお声がけいただき、
いつも励まされたり嬉しかったりばかりの1年間でした。
来年は更に、みなさまのご期待に添えるよう、益々のおいしい暮らしを展開しますね!
来年もどうぞよろしくお願いいたします。

明日は、当ブログはお休みです。次回は、新年の更新になります。
みなさま、どうぞ良いお年をお迎えくださいね!

 「あさぬま」は、元旦より営業いたします。
「あさぬま」は、元旦より営業いたします。元旦 10:00~18:00 2日、3日 9:00~18:00
































































 クリック
クリック