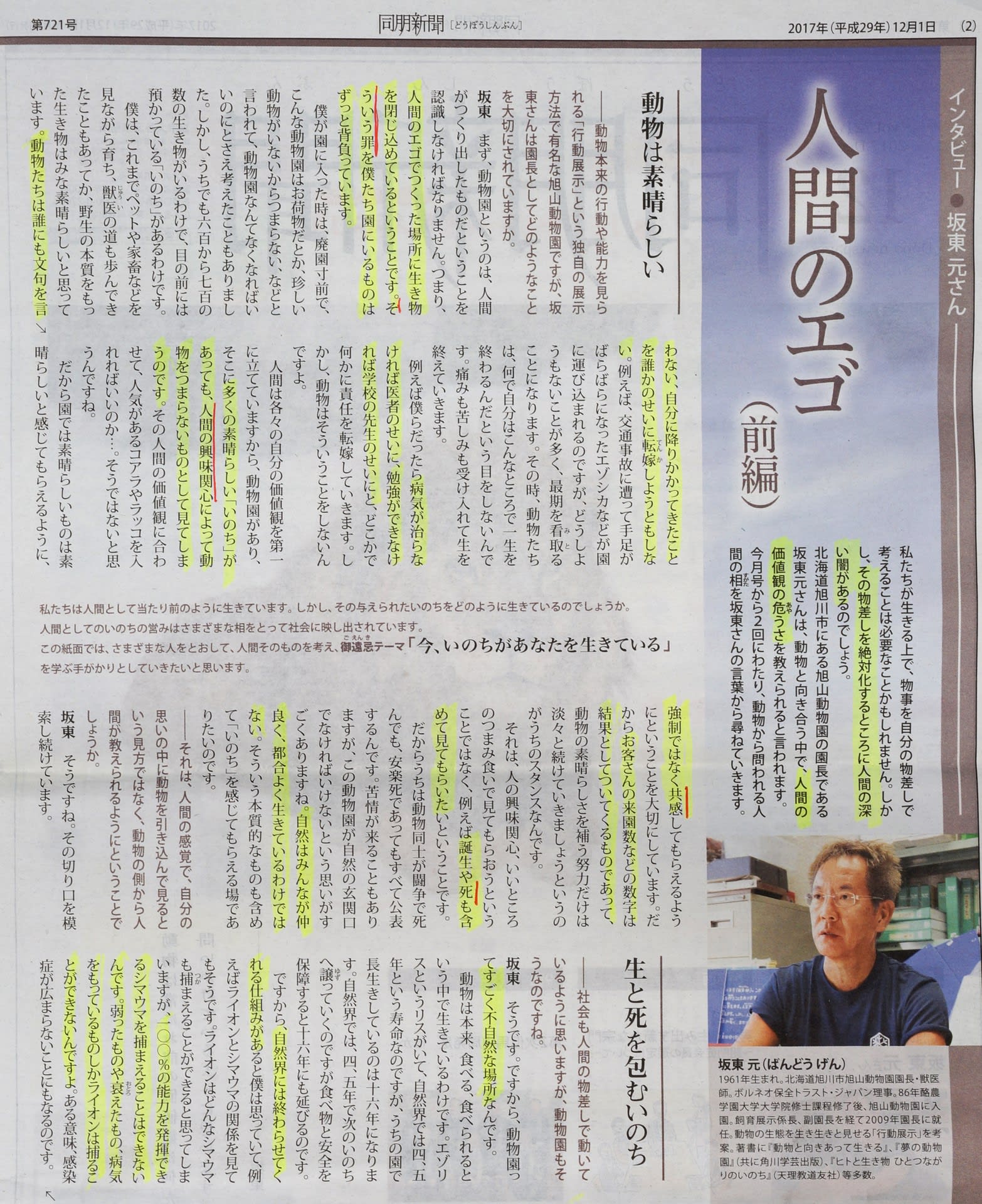以下は、凄まじい話ですが、わたしは不覚にも知りませんでした。ナチスでも北朝鮮でもなく、戦後の日本、1996年までのことです。
わが国の官僚政府の底知れぬ恐ろしさを改めて知り、衝撃を受けました。
人権とは、今も昔の建前にすぎないのが日本国なのでしょう。安倍内閣の中心ブレーンである八木秀次麗澤大学教授が、ちくま新書に「反人権宣言」を書き、戦後日本をダメにした最大の原因を「女性と子供の人権だ」と力説しますが、それが彼らの本音なのでしょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1/25(木) 16:24配信 河北新報
旧優生保護法下で強制不妊手術を受けた宮城県の60代女性が30日、国に補償を求める全国初の訴訟を起こす。本人の同意のない手術により全国で約1万6500人、宮城県で約1400人が子を持つ人生を一方的に奪われた。母体保護法への改定後、障害を理由に手術を強いられた人もいる。偏見への恐怖で、これまで声を上げられなかった東北の被害者の実態から、今なお残る優生思想の陰を探る。(報道部・畠山嵩)
【強制不妊・避妊手術】宮城県内859人 旧優生保護法 最年少は9歳
◎命ある限り 被害訴える
愛宕橋(仙台市太白区)を越え、路地に入った先に駐車場が広がる。ここには1962年6月から約10年間、宮城県が運営する強制不妊手術専門の診療所があった。
「何も知らされず子どもを産めない体にされた。人生が全て無駄になった」
飯塚淳子さん=70代、仮名=は16歳の時、卵管を縛る手術を受けた。軽度の知的障害を示す「魯鈍(ろどん)」が理由。「遺伝性の障害はなかったのに」。今でも怒りで声が震える。
7人きょうだいの長女として県沿岸部で生まれた。父親が病弱で家庭は貧しかった。民生委員から「生活保護を受けているなら、優生手術を受けないと」とでたらめな説明をされ、中学3年の時に仙台市内の特別支援学校に移された。
卒業後は知的障害者の職業訓練をする「職親」の下、住み込みで働いた。「他人の子だから憎たらしい」。背中に馬乗りになった職親の奥さんに言われた。ある晩、つらさのあまり逃げ出したが、すぐに連れ戻された。
63年1月、県の精神薄弱更生相談所(当時)で知能検査を受けさせられた。判定書は「身体的異状認めず」「態度良好」とする一方、「魯鈍」「優生手術の必要を認められる」とも記載。間もなく、行き先や目的を告げられないまま奥さんと愛宕橋を渡った。
診療所には、なぜか父親もいた。言葉も交わさず病室に入ると、注射を打たれた。気が付くと病室のベッドで寝ていた。その間の記憶はない。後日、実家で偶然、両親の会話を聞き、子どもを産めない体になったと知った。
生理のたびに耐え難い激痛に襲われた。仕事もままならず、介護職の夢も断念した。卵管の糸をほどくため東京都の病院を回ったが、縛るよりはるかに難しく、無理だった。子どもは諦めきれず、23歳の時に養子をもらった。
「国に補償と謝罪を求める」と決意し、20年ほど前に名乗り出た。日弁連に人権救済を申し立てるなどしたが、国は「当時は合法」の一点張り。他に訴え出る仲間も現れず、独りで声を上げ続けた。
昨年7月、宮城県在住の佐藤由美さん=60代、仮名=が被害を公表した。「新しい人に出てきてほしかった。頑張り続けたかいがあった」。涙が止まらなかった。由美さんは30日、国に補償を求める全国初の訴訟を起こす。
自分は訴訟に参加できない。手術理由などを記した「優生保護申請書綴(つづり)」を県が焼却処分し、証拠がないためだ。左胸には乳がんを抱えるが、訴訟に懸ける思いは誰よりも強い。
「人生を奪った国はきちんと責任を取るべきだ。自分が死んでも被害者が国を追及できるよう、命ある限り被害を訴える」
[強制不妊手術]「不良な子孫の出生防止」を目的に1948年施行の優生保護法の下、母体保護法に改定される96年まで実施された。優生保護法4条は遺伝性疾患を持つ患者に、都道府県設置の審査会が認めれば本人の同意なく不妊手術をできると規定。12条は遺伝性疾患以外でも、保護者の同意と審査会の決定があれば手術ができるとした。53年の国の通達は、手術のために身体拘束や麻酔の使用、被害者をだます行為も認めていた。