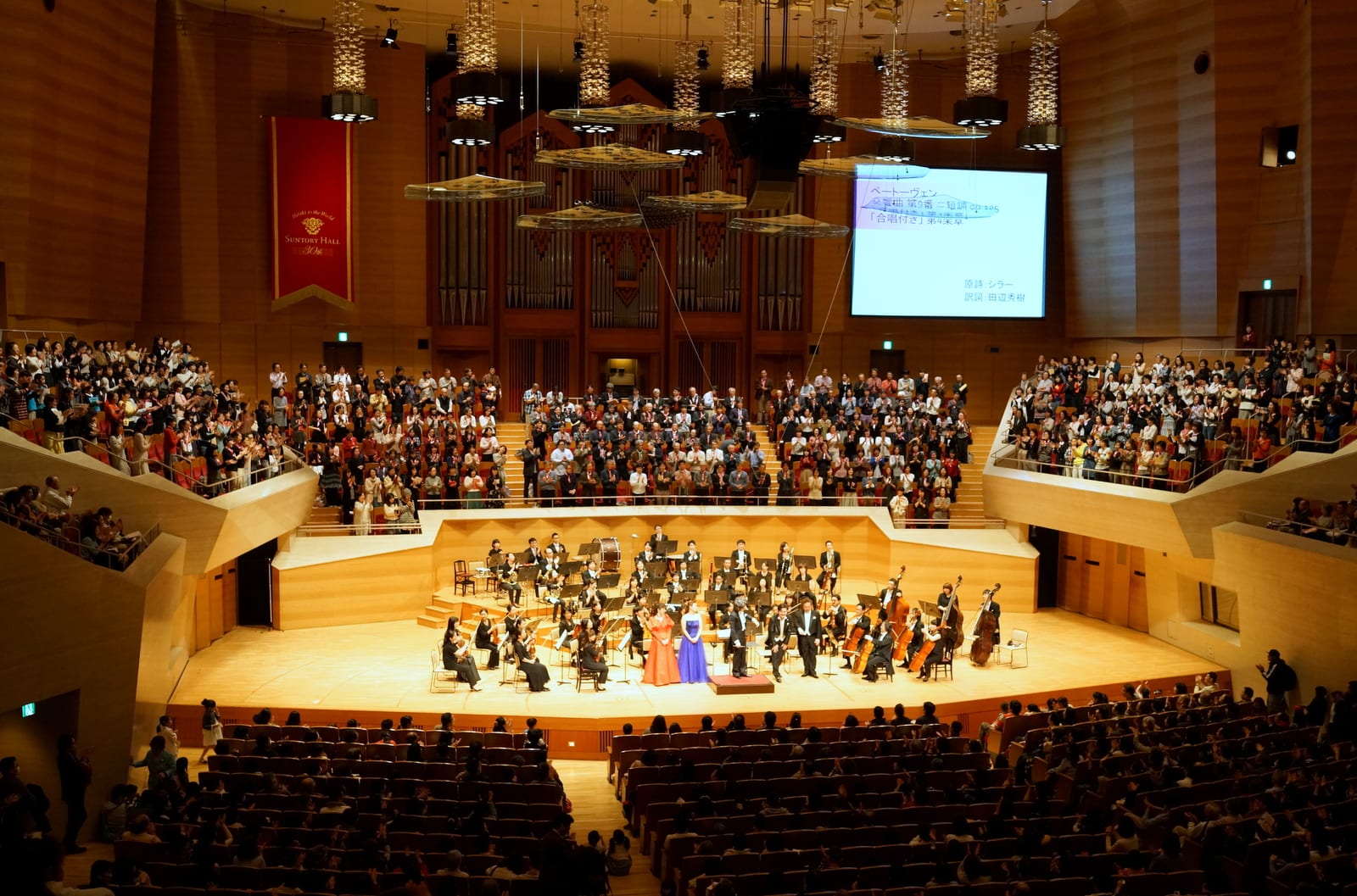来日して12年になるマーティン・ファクラー氏(C)日刊ゲンダイ
国の根幹が変わるのに、新聞が反論を載せない異常
相変わらず安倍政権の支持率は高いが、不思議なことだ。
庶民にアベノミクスの恩恵はまったくないし、
イスラム国の人質事件は最悪の結末に終わった。
政治とカネの醜聞が噴出し、大臣がまた辞任した。
そんな中で、安倍政権は平和憲法をかなぐり捨てる法整備を進めているのに、
世論は怒るわけでもない。
その理由を尋ねると、来日して12年になるニューヨーク・タイムズ東京支局長のマーティン・ファクラー氏からは明快な答えが返ってきた。
「報じない大メディアが悪いのです」――。
(※以下、青字がマーティン・ファクラー氏)
――この調子でいくと、今月中にも自衛隊が世界中に出ていって、
戦争協力する法案が提出されることになります。
国の形が完全に変わってしまうのに、日本人は関心も示さない。どう思いますか?
こうなっているのは2つの大きな要因がありますね。
ひとつは自民党一強、野党不在の政治状況。
もうひとつはメディアが安倍政権を怖がって批判を控えていることです。
――やっぱり、怖がっているように見えますか?
見えますよ。
日本はいま、これまでとは全く異なる国家をつくろうとしている。
憲法に基づいた平和主義を守るのではなく、米国や英国の仲間になろうとしている。
果たして、それでいいのか。
大きな岐路、重要な局面に立っているのに、そうした議論が何もないじゃないですか。
これは本当に不思議なことです。
恐らく多くの国民は、
戦後以来の大きな変化が起こっていることすら
知らないんじゃないですか。
私は何も新聞に反安倍のキャンペーンをやれと言っているわけではないんです。
安倍政権はこういうことをやろうとしているけれども、そこにはこういう問題点や危険性がある。
こういう別の意見もある。
せめてさまざまな立場の見方を紹介して、幅広い議論を喚起することが必要なんじゃないですか。
――しかし、それすら大新聞はめったにやらない。
何か安全保障の問題はタブー視されているような印象すらありますね。
なぜ、タブー視されるのでしょうか。
9・11の直後、米国では国を守るためには団結しなければダメだという危機感が
メディアの批判精神を鈍らせました。
これは大きな失敗でした。
あの時こそ、メディアは冷静になって、きちんとブッシュ政権に問うべきだったんです。
本当にイラクに大量破壊兵器はあるのか。
本当に、この戦争をしなければいけないのか。
しかし、それをやらなかった。
それと同じ失敗を日本のメディアは犯そうとしていますね。
いま、日本の国家はどういう危機に直面しているのでしょうか?
台頭する中国への不安や懸念ですか?
イスラム国の脅威ですか?
そんな小さなことでジャーナリズムが批判精神を失うのでしょうか。
――イスラム国の人質事件ではニューヨーク・タイムズ紙に掲載された風刺画が
非常に印象に残っています。
「イスラム国は平和主義から逸脱する日本を後押しするか」というタイトルで、車夫(=日本人)の鼻先にイスラム国の旗をぶら下げ、「憲法改正」の車を走らせる安倍首相が描かれていた。キャプションには「安倍晋三“大統領”は復讐を呼びかけた」とあった。
ニューヨークタイムズの風刺画 世界はわかっている。わかってないのは日本だけ? gataro
ニューヨーク・タイムズの論評を扱う部署には複数の風刺画家がいます。
そのうちのひとりがアイデアを提示した。
私が関わったわけじゃありません。
権力を見ない新聞を国民が信じますか?
――ということは、米国人は一般的に安倍首相のことを、
そういう目で見ているということですね?
そうだと思いますね。
ひとりがアイデアを出して、みんながそうだね、と賛同したわけでしょうからね。
――それなのに、日本の大メディアは風刺画どころか、
安倍政権が人質救出に何をしたのか、しなかったのか。
イスラム国と戦う国への2億ドル支援演説の是非もほとんど論じていませんね。
私は中東で調査をしたわけではありませんが、
東京から見ている限り、安倍政権はあらゆるルートを駆使したわけではないでしょう。
最初からあきらめていたように見えます。
身代金の支払いにしても早い段階から拒否しているし、この事件を政治的に利用し、
テロに屈しないと宣言して米英の一員であることを国内外にアピールするのが狙いだったように感じました。
――人質救出に全力を挙げると言っていましたけどね。
政治っていうのは、みんなそんなもんですよ。
オバマ政権も一緒です。
ただ違うのはメディアが政府の言い分をうのみにするかどうかです。
私は列強の仲間入りをしたいという安倍首相が悪いとは言いません。
彼は素直に自分のやりたいことをやっている。
それは就任前の言動から容易に推測できたことです。
問題はそれに疑問も挟まず、従って何の質問もせず、説明も求めないメディアの方です。
だから、安倍首相が積極的平和主義を唱えれば、
多くの国民が何の疑問も持たずに“そんなもんか”と思ってしまう。
ここが危険なところです。
――積極的平和主義で、米国と一緒になって戦う。それが日本を守ることになる。
こういう主張の政治家、官僚、学者、評論家たちは、米国がやっていることが正義であるという大前提に立っていますね。
ただし、そういう人々の多くは、アーミテージ元国務副長官に代表されるジャパンハンドラーと呼ばれる人としか付き合っていない。
このほど、ファクラーさんが出された孫崎享さん(元外務省国際情報局長)との対談本、「崖っぷち国家 日本の決断」(日本文芸社)の中には、こういうことが書いてあって、本当に驚きました。
ハンドラーという言葉は「犬を扱う」ようなイメージだというし、そのジャパンハンドラーの人々が米国を動かしているわけでもない。これは非常におかしなことだと思います。
ジャパンハンドラーの人々は非常に保守的で、オバマ政権にも入っていないし、
決して米国の意見を代表しているわけではありません。
それなのに、自民党の政治家や外務省の官僚はジャパンハンドラ―に頼ってしまう。
――対談本でファクラーさんは、
「ジャパンハンドラーは『既得権益集団』で、
コンサルティンググループなどをつくり、強欲な商売をしている」とおっしゃっていた。
鳩山政権の時に脱官僚を唱えた瞬間、日米関係がぶっ壊れたでしょ?
あんなにすぐ壊れるものかと驚きました。
このことは日米のパイプがいかに細いかの裏返しです。
一部の自民党の政治家や官僚とジャパンハンドラーとの付き合いしかないのです。
日米関係に関わっている人は非常に少数で、そういう人が同盟関係を管理している。
だから、普天間基地の移転問題にしても辺野古しかないという結論になってしまう。
もっと幅広い人脈と付き合っていれば、さまざまな意見、選択肢が出てくるはずです。
――集団的自衛権についても、それが日米同盟では当たり前ということになってしまう。
確かに戦後70年間、米国と一緒にやってきて、ある意味、安全だった過去の実績はあります。でも、今後もそれでいいのか。
平和憲法を捨てず、平和主義を貫く選択肢もあるし、
鳩山政権や小沢一郎氏が唱えたようなアジア重視の道もある。
どちらがいいかは国民が考えた上で決めるべきです。
――ところが、日本人には、それを判断する情報すら与えられていないんですよ。
新聞が選択肢すら報じないものだから。
日本のエリートの上の方で、物事が決まっている。
大きな新聞はそちらの方を見て記事を書いている。そんな印象ですね。
新聞社は読者の側に立って、権力を見ていない。
権力者の側に立って、国民を見下ろしている。
そんなふうに感じます。
こんな新聞を国民は信じますか?
――このまま米国追随路線をエスカレートさせたら、この国はどうなっていくと思われますか?
イスラム国のような事件がまた起こりますよ。
米英豪仏などと同じ一員になれば、彼らの敵が日本の敵にもなる。
日本人はそこまでの覚悟をしているのでしょうか。
いずれにしても、民主主義国家でこれほど異常な一党支配の国は
私の知る限り、見たことがない。
戦前と似ていると言う人がいますが、野党不在で政権と違う意見を許さないという雰囲気においては、似ているかもしれません。
健全な民主主義に不可欠なのは議論なのに、それを忘れているとしか思えません。
▽マーティン・ファクラー 1966年生まれ。ダートマス大卒業後、イリノイ大、カリフォルニア大バークレー校で修士。ブルームバーグ東京支局、AP通信東京支局、ウォールストリート・ジャーナル東京支局などを経て、ニューヨーク・タイムズ東京支局長。近著に「崖っぷち国家 日本の決断」(日本文芸社)。




















 みなさま、ぜひ
みなさま、ぜひ