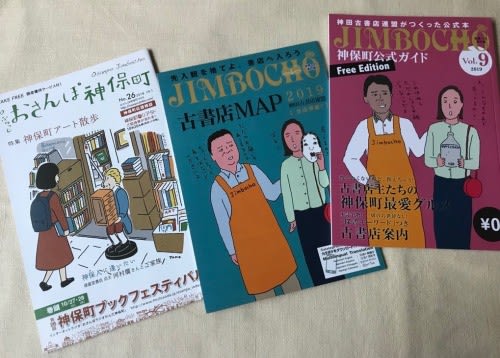奈良旅行記はしばしお休みします。
上野の森美術館で開催中の「フェルメール展」を見に行きました。東京は2019年2月3日まで、その後2月16日から大阪に巡回します。

バロック期を代表するオランダの画家フェルメール。17世紀に活躍し、その後忘れ去られた不遇な画家ですが、19世紀になってから作品が再び脚光を浴びるようになりました。寡作で知られ、現存すると考えられているのは35作品です。その希少性もあって日本でもかなり人気の高い画家のひとりです。
今回は35作品中9作品が東京で公開(大阪公開も含めると10作品が来日)という、過去最大規模のフェルメール展です。(途中で作品の入れ替えがありますので、詳細はご確認ください) また本展では、フェルメールと同時代に活躍したオランダ人画家たちの作品約40点も合わせて展示されています。
***
チケットは混雑緩和のため日時指定制となっていたので、前日にチケットぴあのサイトで購入しておきました。9時半からの回で10時頃に訪れ、待つことなく入場できましたが、会場内はそれなりに混んでいました。時間帯やタイミングでは日時指定でもかなり待つことがあるようです。各回の後半の時間が比較的すいているということです。
またチケットには音声ガイドと小冊子がついていました。音声ガイドはふだんはめったに利用しませんが、石原さとみさんの声は落ち着いていて聞きやすかったです。いつもは作品リストにメモをとりながら鑑賞していますが、小冊子がついているのでその必要もなく、作品を鑑賞することに集中できました。

ハブリエル・メツ―「手紙を読む女」 1664-1666年頃
まずは17世紀オランダ人画家の作品から。この作品はフェルメールから影響を受けたと考えられていて、構図や柔らかい色調、女性が着ている黄色い上着までそっくりです。同じメツ―の「手紙を書く男」と対になっていて、物語が感じられる作品でした。メイドが緑の布をめくって見ている航海の絵は、前途多難な愛を暗示しているそうです。

エマニュエル・デ・ウィッテ「ゴシック様式のプロテスタントの教会」 1790-1685年頃
実在する教会ではなく、異なる建造物の要素を組み合わせて描かれた、想像上の教会だそうです。音の反響が聞こえてくるような大きく荘厳な空間に引き込まれました。当時のオランダでは死者を教会に埋葬する風習があったそうで、手前にそれを示す墓穴が描かれています。

ヤン・ウェーニクス「野ウサギと狩りの獲物」 1697年
17世紀のオランダでは狩猟が貴族の特権で、獲物を描いた静物画は富を誇るものとして人気があったそうです。中央の野ウサギは頭から血を流していますが、毛並みがふわっふわでつややかで、まるで生きているようでした。

ヨハネス・フェルメール「マルタとマリアの家のキリスト」 1654-1655年
そしていよいよフェルメールの展示室へ...。本作はフェルメール唯一の聖書を題材にした作品で、かつ最も大きな作品だそうです。”ルカによる福音書”からの有名な一場面ですが、私は平野啓一郎さんの小説「マチネの終わりに」にあるやりとりを思い出しました。3人、特にキリストのお顔立ちが今どきの若者風?に見えて驚きました。

ヨハネス・フェルメール「手紙を書く婦人と召使い」 1670-1671年
この時代、恋人同士で手紙をやりとりするのが流行っていたそうで、手紙を読んだり書いたりしている作品が数多くありました。^^ 窓から入る柔らかい光、幸せな時間が満ちてくる美しい情景でした。

ヨハネス・フェルメール「ワイングラス」 1661-1662年
女性が口にあてているワイングラスはほとんど空で、男性が継ぎ足そうと待ち構えています。窓ガラスには馬の手綱を握る女性の姿が絵が描かれていて、女性に節制を促すメッセージがこめられているとか...。フェルメールといえばブルーの美しさで知られますが、私は今回、赤の美しさに魅せられました。

ヨハネス・フェルメール「手紙を書く女」 1665年頃
黄色い上着は本展で展示されている「真珠の首飾りの女」「リュートを調弦する女」にも描かれています。同じモデルさんでしょうか。前述のハブリエル・メツ―の「手書きを読む女」にも同じような黄色い上着が描かれています。

ヨハネス・フェルメール「牛乳を注ぐ女」 1658-1660年頃
フィナーレを飾るのは、ポスターにも描かれているこの作品です。ナビゲーターの石原さとみさんが、現代のSNSのような...とおっしゃていて、一瞬、え?と思いましたが、今まさに牛乳を注いでいる瞬間を切り取っているところや、小物の配置、光の捉え方など、なるほどインスタっぽい?うまいことを言うなーと、妙に納得しました。^^