毎週、日曜日にこのブログを更新しているが、伝えたいことを上手く文章化できないことも多い。
「うーん、うーん。どうやって書いたらいいかな」
試行錯誤を繰り返し、チャレンジすることは大切なのだけれど、決して弱音を吐くわけにはいかない。一緒に暮らす家族がウンザリするからだ。ときには厳しい言葉を投げつけられることもある。
「誰も頼んでいないよ。書いてくれなんて」
まあ、そりゃあそうだ……。
ひとり鬱々と悩み、参考になる本はないかしらと図書館をのぞいたら、文庫本の棚から「おおっ」と拍手したくなる本を見つけた。

『文章読本』三島 由紀夫著
世界中で評価されるミシマ文学とはいえ、氏の場合は「割腹自殺」が衝撃的過ぎて、実のところ、ほとんど読んだことがない。
(自決現場での記事はこちら)
せっかく出会えたのだからとページをめくってみた。意外なことに、思っていたより親しみやすい内容で、かなり共感できた。
たとえば、文章を書くときに「同じ語を繰り返し使わない」ルールである。「自分」という語だったら、「自己」「自ら」等に置き換えることができるので、同じ意味でもバリエーションをつけて書くとの件では、初心者を懇切丁寧に育成しようとする姿勢が見えた。
また、過去のことであっても、文末を「~であった」の過去形にとどめず、現在形を用いることが日本語文法ならば許されるとの説明にも大きく頷いた。語尾に変化をつけないと、読み手が退屈するととらえていたことは間違いでなかったのだ。
一番ありがたいと思った内容は、他の作家のすぐれた文章を掲載していた点である。この人のこういう表現が生き生きとしていてお手本になるとか、情景が浮かんでくる、美しい等の注釈とともに書かれていた。中には、「私だったらこう書きます、これを模範としてください」という指導者もいるので、氏の選んだ「この作家のここがスゴイ」が貴重なものに感じられた。時間のあるときに購入し、書き写しに使いたい。
次に、作家としての地位を確立したと言われる『仮面の告白』を読んでみた。
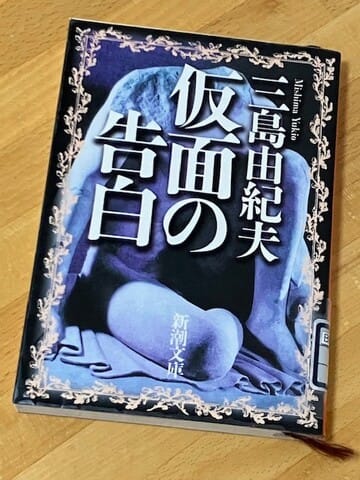
いやあ、素晴らしい描写だった!
たとえば、近江という不良少年が体操の授業の際、生徒全員の前で懸垂を披露する場面がある。「碇の刺青が似合いそうな二つの腕」と書くだけで、筋肉隆々の様子にどこか不健全な香りが漂っていることがわかり、「彼の肩の肉が夏の雲のように盛り上がる」のは、肥大化した筋肉が入道雲に似ているのだとイメージできるし、「生命力、ただ生命力の無益な夥しさが少年たちを圧服したのだった」となると、尋常ではないものに打ちのめされ言葉を失った生徒たちの静止画が浮かんでくる。氏は、五十音を自在に操り、その場、その場を切り取るのに最適の表現を次々と繰り出していた。こんな書き方があるだと驚き、文豪ならではの視点に、もっともっと触れたいと願うようになった。
先日、特急列車に乗る前に本屋に立ち寄った。『仮面の告白』を読み終えてしまい、他の文庫はないか探したかったからだ。立川駅構内にある小さな本屋で、数えたわけではないが、売り場に並んでいる文庫本は1000冊未満に見えた。果たして、三島由紀夫の著書は買えるのだろうか。
「あ、あった」
限られたスペースでも、なるべく多くの作家を揃えようとの心づかいだろうか。ミシマ作品は一冊だけ、『宴のあと』を見つけることができた。
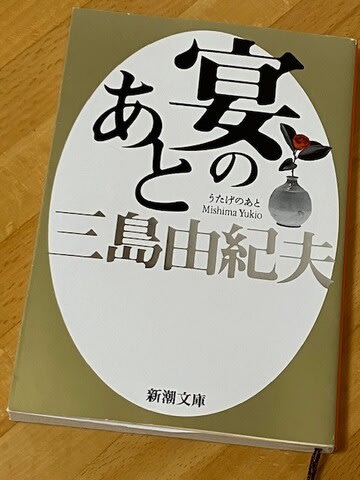
まだ50ページぐらいしか読んでいないけれど、料亭の女将であるかづが、このあとどのような人生を歩んでいくのか気になって仕方ない。
さーて、明日から新年度。
気持ちを新たに、通勤時の読書タイムでミシマ文学から学び、吸収したいものだ。
 エッセイ・随筆ランキング
エッセイ・随筆ランキング
↑
クリックしてくださるとウレシイです♪
※ 他にもこんなブログやってます。よろしければご覧になってください!
「いとをかし~笹木砂希~」(エッセイ)
「うつろひ~笹木砂希~」(日記)
「うーん、うーん。どうやって書いたらいいかな」
試行錯誤を繰り返し、チャレンジすることは大切なのだけれど、決して弱音を吐くわけにはいかない。一緒に暮らす家族がウンザリするからだ。ときには厳しい言葉を投げつけられることもある。
「誰も頼んでいないよ。書いてくれなんて」
まあ、そりゃあそうだ……。
ひとり鬱々と悩み、参考になる本はないかしらと図書館をのぞいたら、文庫本の棚から「おおっ」と拍手したくなる本を見つけた。

『文章読本』三島 由紀夫著
世界中で評価されるミシマ文学とはいえ、氏の場合は「割腹自殺」が衝撃的過ぎて、実のところ、ほとんど読んだことがない。
(自決現場での記事はこちら)
せっかく出会えたのだからとページをめくってみた。意外なことに、思っていたより親しみやすい内容で、かなり共感できた。
たとえば、文章を書くときに「同じ語を繰り返し使わない」ルールである。「自分」という語だったら、「自己」「自ら」等に置き換えることができるので、同じ意味でもバリエーションをつけて書くとの件では、初心者を懇切丁寧に育成しようとする姿勢が見えた。
また、過去のことであっても、文末を「~であった」の過去形にとどめず、現在形を用いることが日本語文法ならば許されるとの説明にも大きく頷いた。語尾に変化をつけないと、読み手が退屈するととらえていたことは間違いでなかったのだ。
一番ありがたいと思った内容は、他の作家のすぐれた文章を掲載していた点である。この人のこういう表現が生き生きとしていてお手本になるとか、情景が浮かんでくる、美しい等の注釈とともに書かれていた。中には、「私だったらこう書きます、これを模範としてください」という指導者もいるので、氏の選んだ「この作家のここがスゴイ」が貴重なものに感じられた。時間のあるときに購入し、書き写しに使いたい。
次に、作家としての地位を確立したと言われる『仮面の告白』を読んでみた。
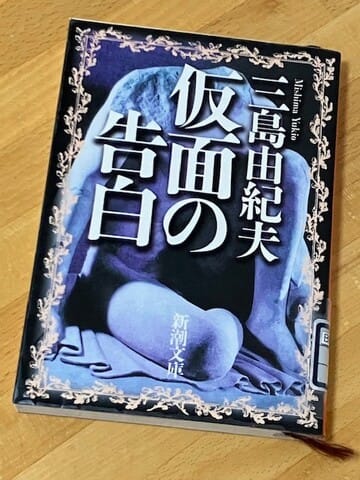
いやあ、素晴らしい描写だった!
たとえば、近江という不良少年が体操の授業の際、生徒全員の前で懸垂を披露する場面がある。「碇の刺青が似合いそうな二つの腕」と書くだけで、筋肉隆々の様子にどこか不健全な香りが漂っていることがわかり、「彼の肩の肉が夏の雲のように盛り上がる」のは、肥大化した筋肉が入道雲に似ているのだとイメージできるし、「生命力、ただ生命力の無益な夥しさが少年たちを圧服したのだった」となると、尋常ではないものに打ちのめされ言葉を失った生徒たちの静止画が浮かんでくる。氏は、五十音を自在に操り、その場、その場を切り取るのに最適の表現を次々と繰り出していた。こんな書き方があるだと驚き、文豪ならではの視点に、もっともっと触れたいと願うようになった。
先日、特急列車に乗る前に本屋に立ち寄った。『仮面の告白』を読み終えてしまい、他の文庫はないか探したかったからだ。立川駅構内にある小さな本屋で、数えたわけではないが、売り場に並んでいる文庫本は1000冊未満に見えた。果たして、三島由紀夫の著書は買えるのだろうか。
「あ、あった」
限られたスペースでも、なるべく多くの作家を揃えようとの心づかいだろうか。ミシマ作品は一冊だけ、『宴のあと』を見つけることができた。
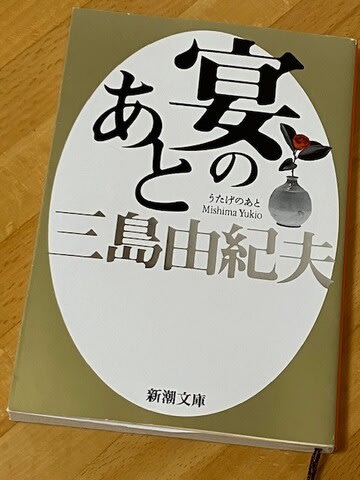
まだ50ページぐらいしか読んでいないけれど、料亭の女将であるかづが、このあとどのような人生を歩んでいくのか気になって仕方ない。
さーて、明日から新年度。
気持ちを新たに、通勤時の読書タイムでミシマ文学から学び、吸収したいものだ。
↑
クリックしてくださるとウレシイです♪
※ 他にもこんなブログやってます。よろしければご覧になってください!
「いとをかし~笹木砂希~」(エッセイ)
「うつろひ~笹木砂希~」(日記)















