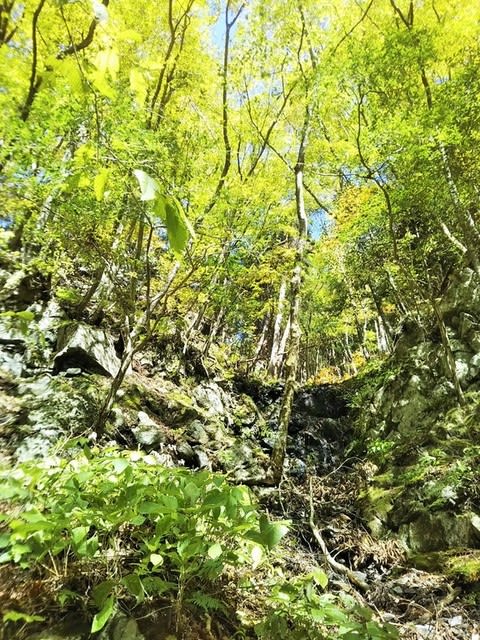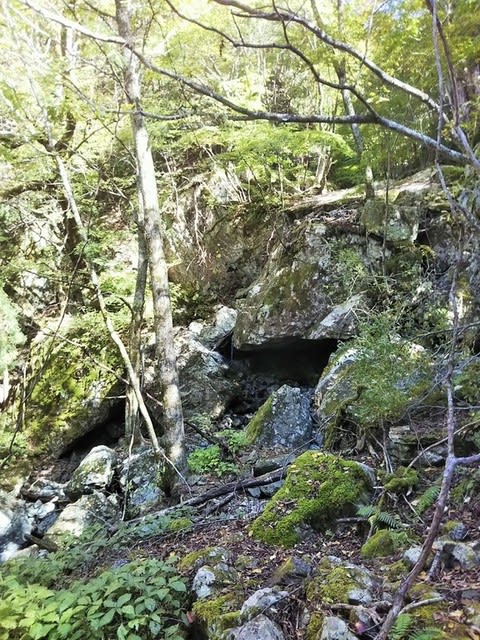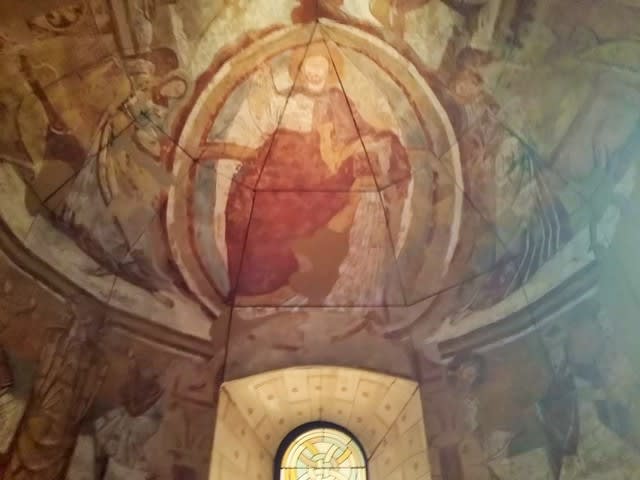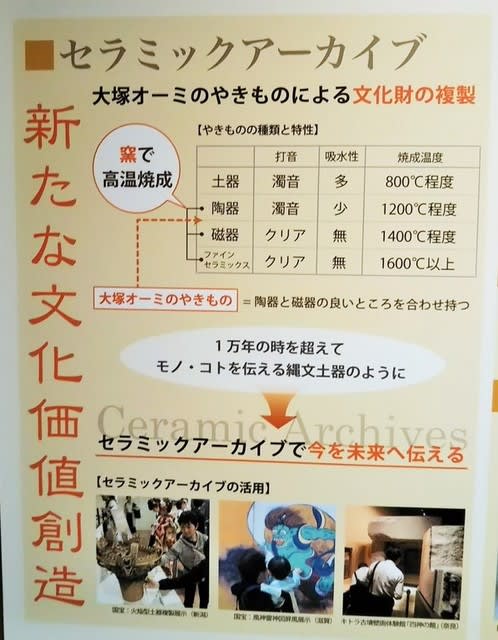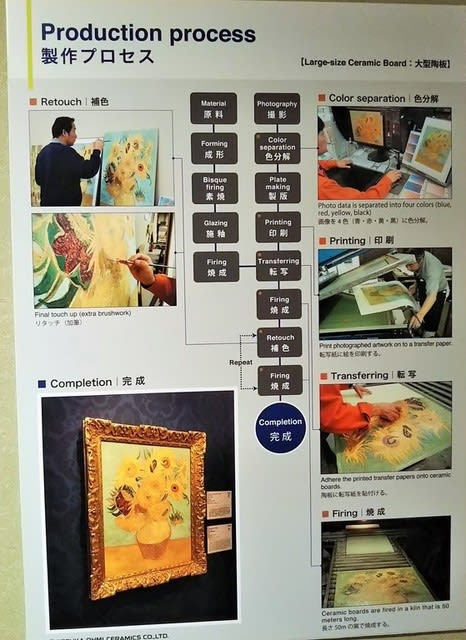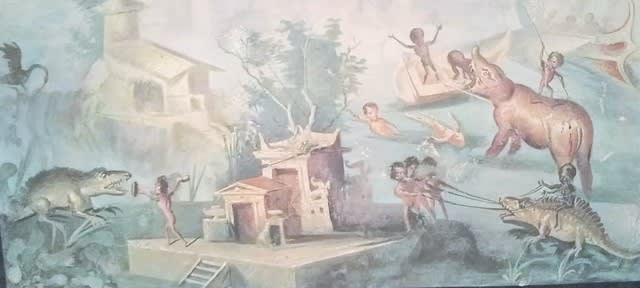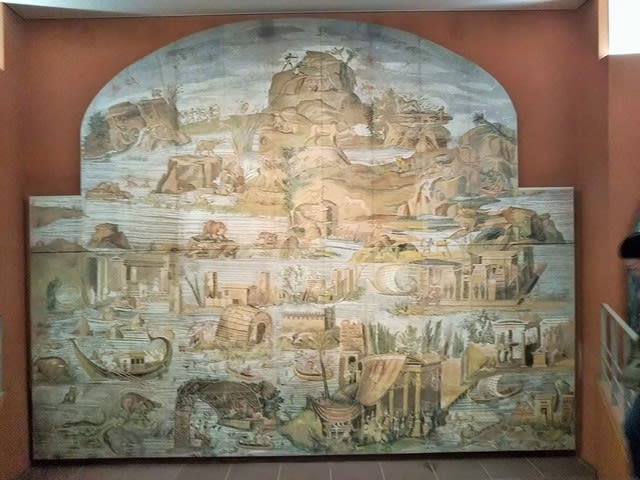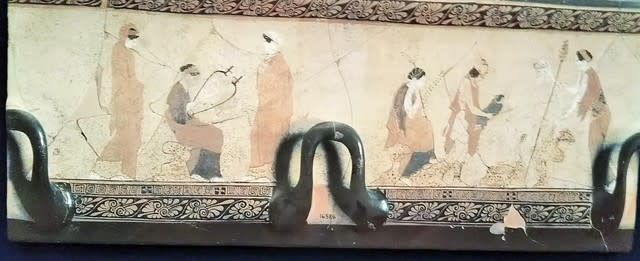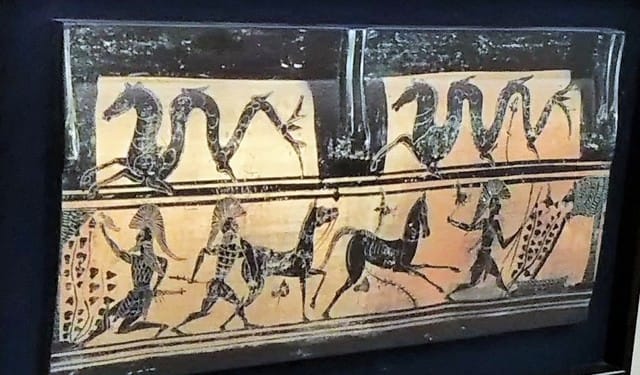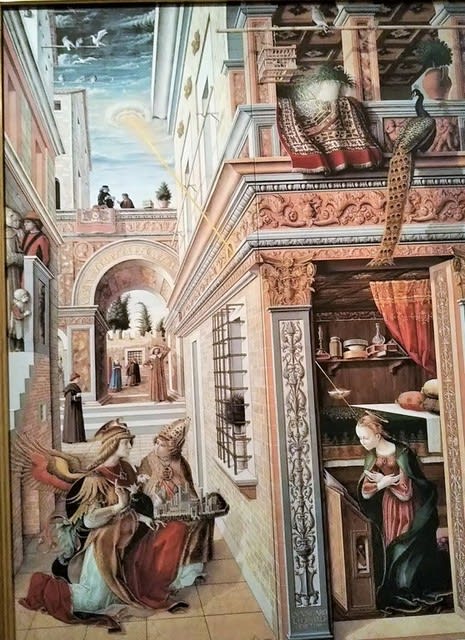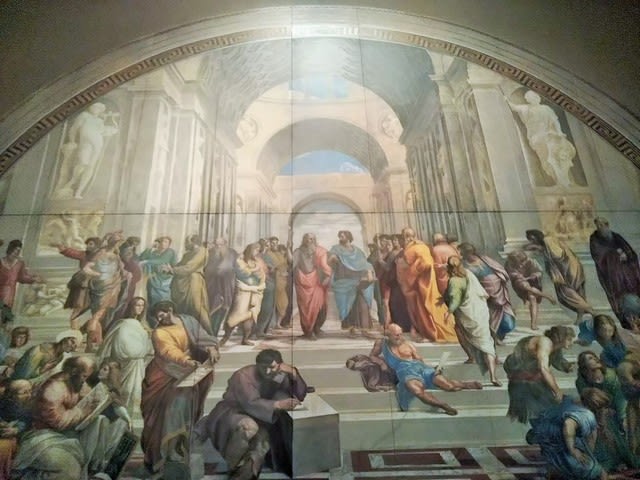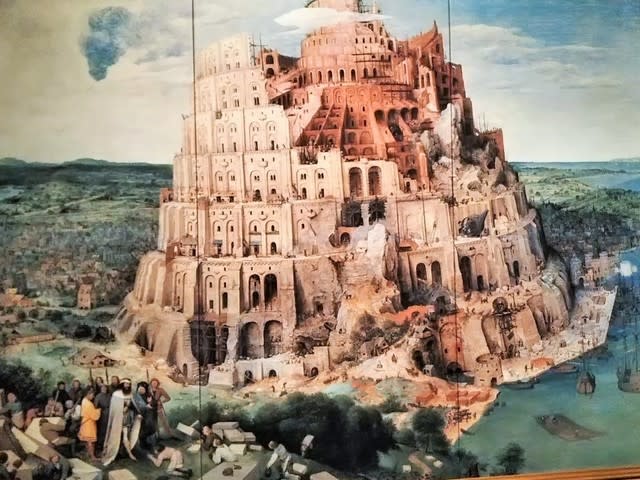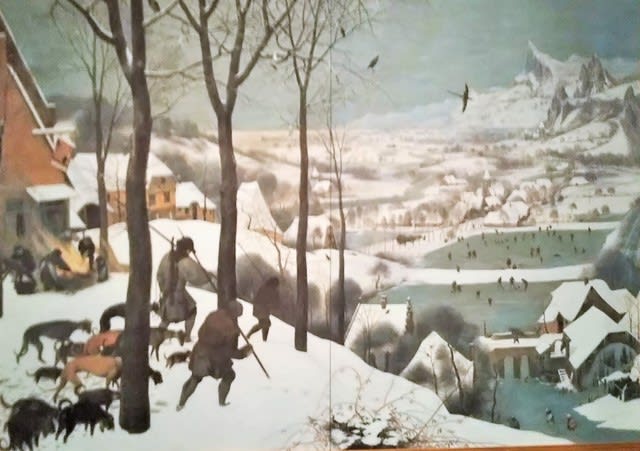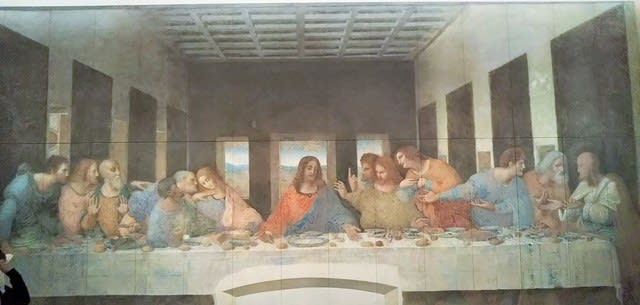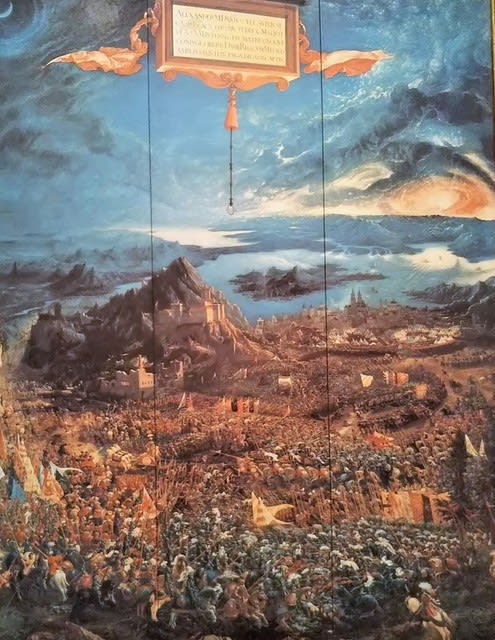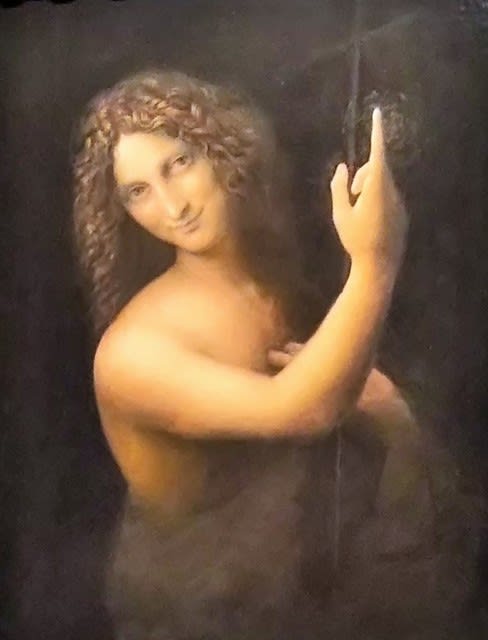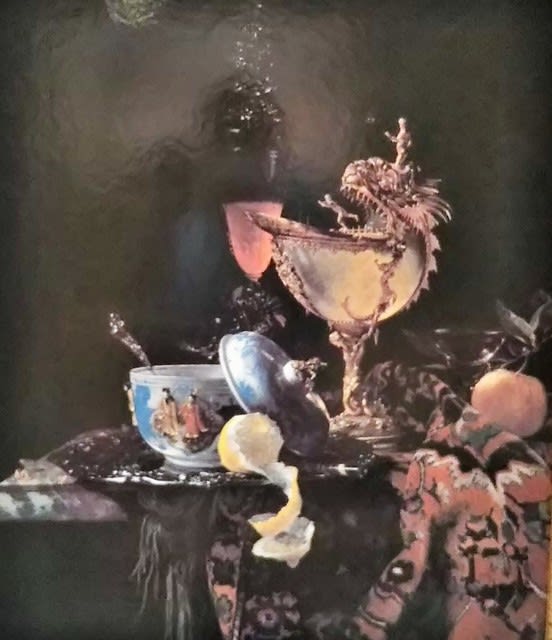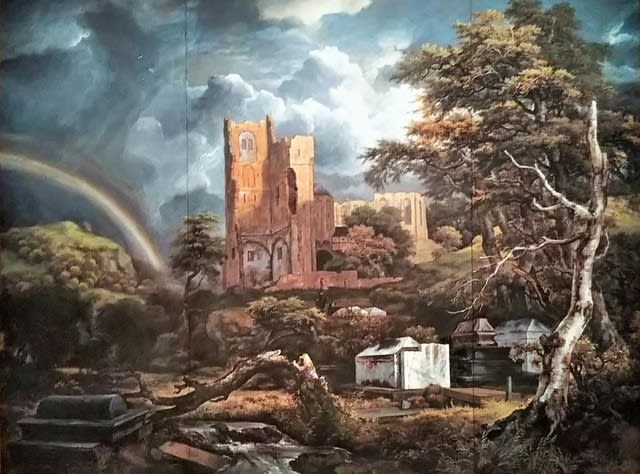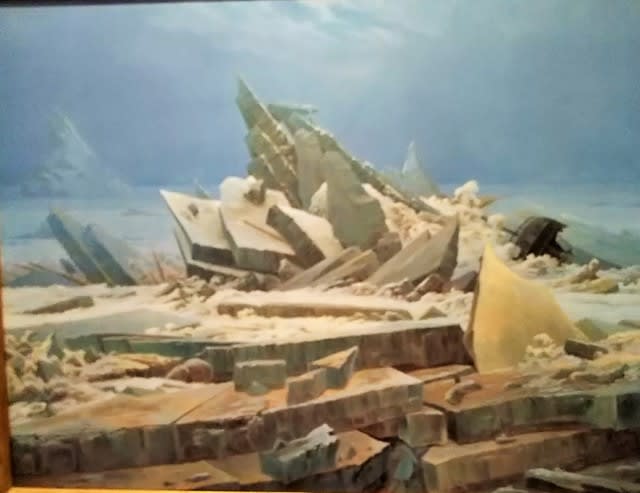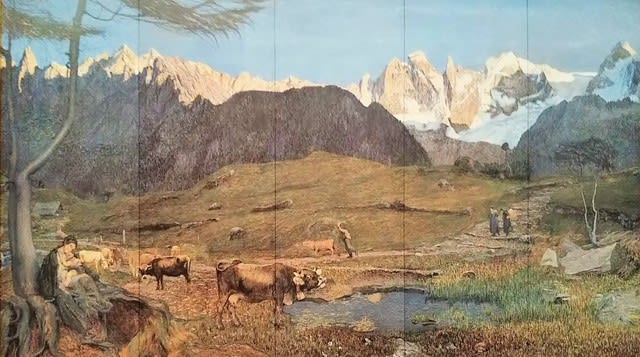ちょこちょこスマホで写真を撮りまくる。
肉眼では朱色の点々が、明瞭に確認出来ていたんですが、写真にするとちょっとわかりにくい。
良いカメラでしっかり残すより、また見に来るということで・・。

お花畑の端の岩の展望台でめし。
絶景かな。絶景かな。
こんな天気は滅多にない。




黄緑色に光ってるようなコケ。

















さて帰りますか。
レンゲ辻方面に降りる方が約二名。
初めてだけど、11時半からなんで何とかなるでしょ。
こちら側で大峯大橋まで降りてみる。


ごごごっと急降下。
一気に通過人数が減るせいか、道幅も一人で一杯です。



ちょこちょこ台風の爪痕を超えていく。



階段か梯子かわかんないものを、後ろ向きに降りたりしながら、女人結界門。

稲村が岳ピストンも考えたけど、時間計算すると、日暮れと競争になそうなので断念。
レンゲ辻を下る。





岩が目立ってくると、踏み後は微か。
1mも段差があるところに出ると、降りようと考える前に、サッと周囲を見まわすと、
大概、赤テープが真横の対岸にあります。50cmもない段差で収まるように、
左右にスイングしながらルートが構成されているので、おかしいと思ったら、
真横や対岸斜め後方まで首を回すことをお勧めします。
目印の木が倒れてたり、倒木の枝で見えにくかったりしていますが、
決して飛ばないように。


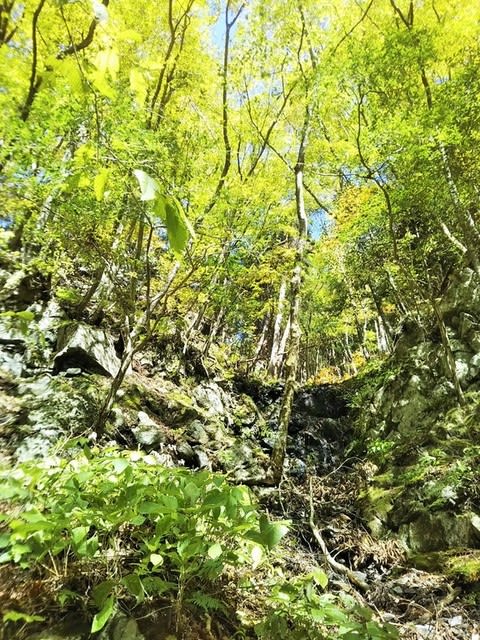
谷底はいいんですが、時々壁沿いに高度が上がる道が怖い。
幅がわずかでざらざら崩れるところもあります。



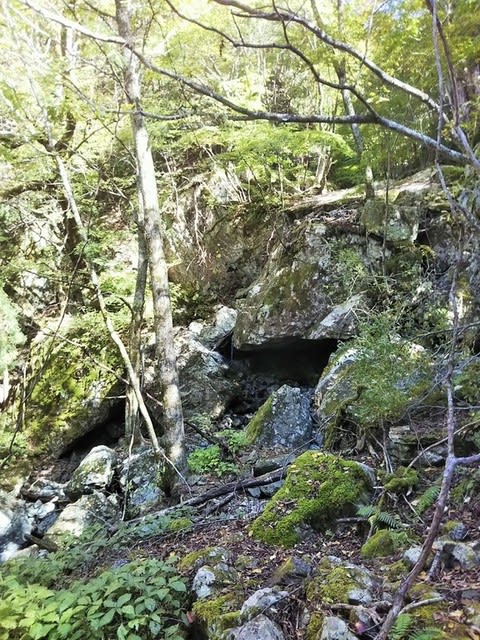



ようやく、水の音がして谷川が見える。
ここでようやく谷底。水平距離をGPSで確認すると、工程の1/4程度。
11時半ごろから、13時まで掛かってます。


水は清冽・透明。
地中からの湧水が短距離で集結するので、微生物で濁る時間もないようです。

素直に来た道を帰るより、はるかに時間がかかると想像しましたが、
ここから林道までの残りは傾斜がマシになり1時間で14時。
工程の半分の林道に入ってからは、たった20分で大峰大橋に着きました。
水平距離を4分割すると、1時間半、1時間、10分、10分。
通常のピストンと所要時間はほぼ変わらないと思います。

コケの壁。



無事、大峯大橋着。
レンゲ辻は登ろうとは思わないけど、変化が多くて楽しめました。
色んな顔の大峰山に感謝。

茶屋でノンアル。

洞川温泉センターは混んでるので、パス。
御手洗渓谷に寄り道し、車で滝の下に行ってまだ充分に色づいてないのを確認。
駐車場に止めずに移動し、帰路にある黒滝温泉に寄りました。
準天然温泉が眉唾でしたが、空いていて、ぬるめでゆっくり汗を流すことが出来ました。
道の駅に寄ったり、少し渋滞に捕まったものの、家に18時半に着。
のんびりゆったりの山旅でありました。