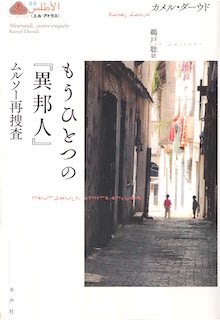 今春にルキーノ・ヴィスコンティ監督の1968年作品『異邦人』がデジタルリマスター版として公開された。私は今回この作品を初めて見たのだが、有名な増村保造監督による初公開時(1968年9月)における雑誌『映画芸術』での酷評をはじめ、本作の評価が芳しくないことは、かねてから知っていた。
今春にルキーノ・ヴィスコンティ監督の1968年作品『異邦人』がデジタルリマスター版として公開された。私は今回この作品を初めて見たのだが、有名な増村保造監督による初公開時(1968年9月)における雑誌『映画芸術』での酷評をはじめ、本作の評価が芳しくないことは、かねてから知っていた。ヴィスコンティ自身はアルベール・カミュのこの「世界一有名な小説のひとつ」(1942刊)の映画化に長年の夢を悲愴なまでに抱いていたらしく、それにしてはずいぶんと軽い風刺悲喜劇の域を出ていないようには思え、と同時に、ヴィスコンティらしからぬB級精神がかえって好ましさを覚えたことをここに告白しておこう。殊にアンナ・カリーナの哀願するような表情は印象的で、ゴダール映画の不敵ともリヴェット映画の嗜虐ともまったく様相を異にした彼女の貴重な姿を見ることができる。
「世界一有名な小説のひとつ」の主人公ムルソーによる世界一有名なセリフのひとつ、殺人の動機を検事に訊かれて「太陽がまぶしかったから」はよく分かるし、難解でもなんでもないけれども、イタリアのスーパースター、マルチェロ・マストロヤンニが演じたムルソーが太陽のまぶしさに目の眩んだ拍子に、救いようのないそそっかしさでピストルの引き金を引いてしまう瞬間が、私の網膜の裏側で何度もくりかえし再映写されるのだ。なぜあのアルジェリア人青年は銃口を向けられても無表情なのか? そしてなぜ白人をナイフでケガさせたのに逮捕を逃れるためにずらかろうともせずに、トラブル現場の海岸で暢気に寝そべっていたのだろうか? 彼は白人に殺してもらうためにそこにいたのだろうか? このアルジェリア人青年はいったい誰なのか? ムルソーの親友がもてあそんだ売春婦の兄ということらしいが、本当だろうか? そもそも、このアルジェリア人青年の名前は? マストロヤンニを裁く裁判シーンはやたらと長いが、なぜ被害者の名前がいちども言及されないのか?
本作は、カミュの、そしてヴィスコンティの自己への実存主義的な死刑宣告、近代精神批判があまりに雄弁に語られる一方で、アルジェリア人青年には名前もイニシャルもまったく言及されないという、考えようによってはひどく人種差別的な作品と言えるだろう。この被害者は主人公ムルソーに射殺される以前に、まずカミュによって、次にヴィスコンティによって抹殺されたのだ。
そうした思考の延長として、あるアルジェリア人作家による、『異邦人』の捏造された続編を読み終えたばかりである。カメル・ダーウド著『もうひとつの『異邦人』 ムルソー再捜査』(邦訳2019年 水声社刊)。ゴンクール新人賞を受賞している。太陽がまぶしいせいで殺害されたアルジェリア人青年の弟を名乗る男が、『異邦人』ファンの現地探訪ツーリストらしき人間をつかまえて、飲み屋のカウンターで毎日、兄の死後、自分と母親がいかに苛酷な運命を辿ったかを激白し続ける。
弟を名乗る主人公が、殺害された兄の名を「ムーサー」だと教えてくれる。冷血なフランス人によって血を流した「ムーサー」は民族の英雄として、アルジェの貧民街で数ヶ月くらいのあいだは祭り上げられ、弟と母親は英雄の遺族として遇された。しかし、当局は遺族に対しなんの情報も提供しなかったし、兄の亡骸も引き渡されなかった。遺族年金も受け取れず、兄の死は無に等しかった。代わりに、加害者の裁判と死刑宣告ばかりがレトリカルにショーと化した。「ムーサー」は何重にもわたり抹殺されたのだ。










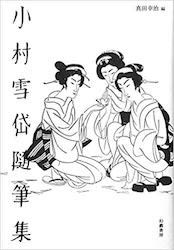 いま金沢の泉鏡花記念館で、特別展《日本橋──鏡花、雪岱、千章館》というのをやっている。今年の夏はぜひ金沢を訪れ、ついでに当地の味覚も味わえたらなどと考えていた。ところが5月に母方の伯母が、7月に父方の叔母が相次いで逝き、さらに今月は祖母の三回忌法要も控えているという事情も鑑み、北陸行きを断念した。
いま金沢の泉鏡花記念館で、特別展《日本橋──鏡花、雪岱、千章館》というのをやっている。今年の夏はぜひ金沢を訪れ、ついでに当地の味覚も味わえたらなどと考えていた。ところが5月に母方の伯母が、7月に父方の叔母が相次いで逝き、さらに今月は祖母の三回忌法要も控えているという事情も鑑み、北陸行きを断念した。 ウンベルト・エーコの最後の小説『ヌメロ・ゼロ』(河出書房新社)がイタリア本国で刊行されたのは、2015年1月。翌2016年2月にエーコは永眠している。ミラノで「ドマーニ」(明日)なる新聞が創刊準備を始める。しかしこれは、政財界に脅しをかけるための陰謀的な「商材」にすぎない。創刊準備号、つまりヌメロ・ゼロ(零号)の製作のために数人の経験者が雇われる。「ドマーニ」が永遠に創刊されることはないことを、彼らは知らない。
ウンベルト・エーコの最後の小説『ヌメロ・ゼロ』(河出書房新社)がイタリア本国で刊行されたのは、2015年1月。翌2016年2月にエーコは永眠している。ミラノで「ドマーニ」(明日)なる新聞が創刊準備を始める。しかしこれは、政財界に脅しをかけるための陰謀的な「商材」にすぎない。創刊準備号、つまりヌメロ・ゼロ(零号)の製作のために数人の経験者が雇われる。「ドマーニ」が永遠に創刊されることはないことを、彼らは知らない。 19世紀末から20世紀初頭にかけて、全米の劇壇で活躍したシェイクスピア悲劇の伝説的な女優ヘレナ・モジェスカ(1840-1909)の生涯にインスピレーションを受け、モジェスカと同じポーランドに一族の出自をもつスーザン・ソンタグが小説にしている(邦訳 河出書房新社)。
19世紀末から20世紀初頭にかけて、全米の劇壇で活躍したシェイクスピア悲劇の伝説的な女優ヘレナ・モジェスカ(1840-1909)の生涯にインスピレーションを受け、モジェスカと同じポーランドに一族の出自をもつスーザン・ソンタグが小説にしている(邦訳 河出書房新社)。 原田マハの新作『暗幕のゲルニカ』(新潮社)は帯文に「圧巻の国際謀略アートサスペンス」とある。たしかに、ピカソを専門領域とするキュレーターとしてMoMA(ニューヨーク近代美術館)に勤務する日本人女性の主人公・瑤子を中心に、MoMA、レイナ・ソフィア芸術センター(マドリード)、グッゲンハイム・ビルバオ美術館、国連、ETA(バスク過激派)などが地球規模でからんで権謀術数をめぐらすばかりか、スペイン内戦期の1937年から第二次世界大戦終戦直後の1945年にいたるパリ、オーギュスタン通りのアパルトマン4階(そう、ピカソのアトリエがあった場所であり、ここで大作『ゲルニカ』が描かれた)およびカフェ・ドゥ・マゴ、パリ万博会場といった過去の時空がパラレルに織り込まれていく。そして、大戦期のもうひとりの主人公はピカソの愛人ドラ・マールで、ドラと瑤子が合わせ鏡のような時間構造のなかで気丈に立ち回る。
原田マハの新作『暗幕のゲルニカ』(新潮社)は帯文に「圧巻の国際謀略アートサスペンス」とある。たしかに、ピカソを専門領域とするキュレーターとしてMoMA(ニューヨーク近代美術館)に勤務する日本人女性の主人公・瑤子を中心に、MoMA、レイナ・ソフィア芸術センター(マドリード)、グッゲンハイム・ビルバオ美術館、国連、ETA(バスク過激派)などが地球規模でからんで権謀術数をめぐらすばかりか、スペイン内戦期の1937年から第二次世界大戦終戦直後の1945年にいたるパリ、オーギュスタン通りのアパルトマン4階(そう、ピカソのアトリエがあった場所であり、ここで大作『ゲルニカ』が描かれた)およびカフェ・ドゥ・マゴ、パリ万博会場といった過去の時空がパラレルに織り込まれていく。そして、大戦期のもうひとりの主人公はピカソの愛人ドラ・マールで、ドラと瑤子が合わせ鏡のような時間構造のなかで気丈に立ち回る。