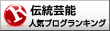芸術の秋がやって参りましたが、例年と些か(いささか)趣きを異にしております。
学校巡回が徐々に再開されましたのは、わたくし共にとりましても嬉しいことです。
授業時間の合間を縫って調弦するほかに、三味線および付随する小物類の消毒・除菌作業が加わったのが、令和二年度ならではの特記事項でありましょうか。
そのような手間を凌いで余りある感動…瑞々しい可能性に満ちた若人(わこうど)たちが、新しい知識や体験を吸収して、成長し羽ばたいてゆく(それが今すぐ、目に見える形でないとしても)…自分たちの蓄積を次世代に移し繋いでいくことは、人間として冥利に尽きることでもあります。
そこで近年増えました質問、伝統芸能における名前、芸名ということについて、ごくごく簡単に、お話ししたいと思います。
杵屋は、長唄(三味線含む)に携わる者の芸名です。
苗字帯刀…つまり、身分制度によって人民が区分けされておりました時代、苗字を持っていたのは特権階級の者のみでした。
ファーストネームだけでは、その者の人と成りが分かりません。
そこで、屋号などで、どこに属するものか、ごく簡単に申せば、何の職業をしている者か即座に分かるようにしたのが、屋号や芸名、号名です。
それぞれの業界で、特徴のある名称や漢字を使い、またどの師匠筋(教わった先生の系統)か、判るようになっております。
昭和のころは、三河屋(みかわや)さんといえば(木挽町界隈を除いて)酒屋さん、越後屋さんと言えば呉服商でした。
21世紀になってから、国が国民を管理する観点で、税務関連に於いて本名を必ず書類に記載する…という様式が採られるようになってから、この、わたくし共の芸名に対する認識が少しずつ失われ、ずれてきたように思います。
名取、つまり芸名を持っている者のことですが、
名前は栄誉称号ではありません。
やっと、自分が精進してきたその道で仕事をしていいよ、という、許認可を与えられたということです。
お医者さまで言えば、国家試験に受かって医師免許を得た、という免許状であります。
スタート地点にすぎません。
名取になってこそ、得られる体験、研鑽するべき局面に至れる状態になった、入山の許可を得、登山道の入り口に立てたということです。
ですから、名取になってから…いえ、名取になったからこそ勉強することは沢山あります。
山に登ると、上るごとに景色が変わる、そこで対応すべき事柄も変わり、対処する方法も変わります。
自分の仕事に対する責任感、提供できる品質向上、という点では他の職業と何ら変わりません。
芸名は、素人とプロフェッショナルの境界線です。
その名前で仕事、商売をしている者を、本名で呼ぶのは失礼にあたります。
また名前のない素人(つまり、師匠のお墨付きを得られていない、芸道半ばのもの)が、勝手にその道で商売、つまり報酬を得るのは反則、ルール違反です。
特に、伝統芸能に於いては、欧米式の、均され(ならされ)多人数での学校教育では修業することができない、経験則が必要です。
音楽は、また、紙に印刷された譜面から学べるものは一割…いや、1パーセントにも充ちません。
…ということを、常々感じておりましたので、昭和で言えば体育の日に、つらつらと綴ってみました。
言葉足らずで失礼いたします。
学校巡回が徐々に再開されましたのは、わたくし共にとりましても嬉しいことです。
授業時間の合間を縫って調弦するほかに、三味線および付随する小物類の消毒・除菌作業が加わったのが、令和二年度ならではの特記事項でありましょうか。
そのような手間を凌いで余りある感動…瑞々しい可能性に満ちた若人(わこうど)たちが、新しい知識や体験を吸収して、成長し羽ばたいてゆく(それが今すぐ、目に見える形でないとしても)…自分たちの蓄積を次世代に移し繋いでいくことは、人間として冥利に尽きることでもあります。
そこで近年増えました質問、伝統芸能における名前、芸名ということについて、ごくごく簡単に、お話ししたいと思います。
杵屋は、長唄(三味線含む)に携わる者の芸名です。
苗字帯刀…つまり、身分制度によって人民が区分けされておりました時代、苗字を持っていたのは特権階級の者のみでした。
ファーストネームだけでは、その者の人と成りが分かりません。
そこで、屋号などで、どこに属するものか、ごく簡単に申せば、何の職業をしている者か即座に分かるようにしたのが、屋号や芸名、号名です。
それぞれの業界で、特徴のある名称や漢字を使い、またどの師匠筋(教わった先生の系統)か、判るようになっております。
昭和のころは、三河屋(みかわや)さんといえば(木挽町界隈を除いて)酒屋さん、越後屋さんと言えば呉服商でした。
21世紀になってから、国が国民を管理する観点で、税務関連に於いて本名を必ず書類に記載する…という様式が採られるようになってから、この、わたくし共の芸名に対する認識が少しずつ失われ、ずれてきたように思います。
名取、つまり芸名を持っている者のことですが、
名前は栄誉称号ではありません。
やっと、自分が精進してきたその道で仕事をしていいよ、という、許認可を与えられたということです。
お医者さまで言えば、国家試験に受かって医師免許を得た、という免許状であります。
スタート地点にすぎません。
名取になってこそ、得られる体験、研鑽するべき局面に至れる状態になった、入山の許可を得、登山道の入り口に立てたということです。
ですから、名取になってから…いえ、名取になったからこそ勉強することは沢山あります。
山に登ると、上るごとに景色が変わる、そこで対応すべき事柄も変わり、対処する方法も変わります。
自分の仕事に対する責任感、提供できる品質向上、という点では他の職業と何ら変わりません。
芸名は、素人とプロフェッショナルの境界線です。
その名前で仕事、商売をしている者を、本名で呼ぶのは失礼にあたります。
また名前のない素人(つまり、師匠のお墨付きを得られていない、芸道半ばのもの)が、勝手にその道で商売、つまり報酬を得るのは反則、ルール違反です。
特に、伝統芸能に於いては、欧米式の、均され(ならされ)多人数での学校教育では修業することができない、経験則が必要です。
音楽は、また、紙に印刷された譜面から学べるものは一割…いや、1パーセントにも充ちません。
…ということを、常々感じておりましたので、昭和で言えば体育の日に、つらつらと綴ってみました。
言葉足らずで失礼いたします。