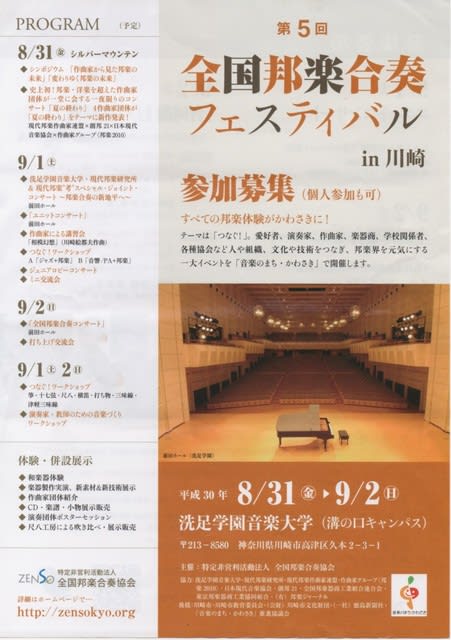皆さまご存知のように、平成の世にできました天空を凌ぐ塔・スカイツリーは、武蔵の国にあることを由来して、634メートルの高さに定められております。
武州。
武蔵の国にある五日市だから武蔵五日市、武蔵の国の小山だから武蔵小山、同じく武蔵小杉、武蔵村山、武蔵小金井…エトセトラ、etc.
武蔵の国にある野原で、武蔵野。
関東一円に広がります武蔵野台地。ひと昔前は、よく、時代劇のロケを山背の国=京都でやっておりまして、大川端、隅田川岸が琵琶湖河畔だったり、下賀茂神社が浅草奥山だったりしますが、関東の者には今一つ違和感がある。
それはね、とても美しい風景でほのぼのするのですが、空が狭い。後ろに山がある。
関東平野は見晴らしがいいんです。西に富士山、北に筑波山。
ですから、あまり瑕(きず)のないよくできた時代劇だったりすると、風景に茶々を入れたりする。
京の都の住人・武蔵坊弁慶が勧進帳で飲み干します大盃(おおさかづき、大阪好き、と変換されちゃいましたが…確かに好きですが…ちゃいます)、あれを俗に武蔵野(むさしの)と呼びますが、その心は?
はい、広くて野を見尽くせない→野見つくせない→のみつくせない、飲み尽くせない…正解です。
ひと口に武蔵野、と申しますが、どこら辺を指すかご存知でしょうか?
東京都心/練馬・板橋・北・中野/杉並・世田谷・大田/武蔵野・三鷹/調布・小金井/府中/立川・八王子・青梅/東村山・清瀬・所沢/平林寺/東武・西武・奥武蔵/秩父/奥多摩/葛飾・成田/多摩丘陵
…というような記述を、昭和50年に毎日新聞社から刊行されました風景写真集『武蔵野の四季』に見つけました。父の遺品整理の折、本棚にあった一冊です。
かように、関東に住む者には、武蔵野という言葉は切っても切れない心の風景のよりどころだったり致します。
そんなことがございます一方で、このところの2020東京五輪関連プロジェクトを拝察いたしますにつれ、自分たちの風土に根差した文化をもっと知り、実践すべきではないか、と思うに至りました。
さて、「むさしの」という和楽器オーケストラ向けの曲があります。
編成は尺八、箏、三味線。歌パートもございます。
国木田独歩「武蔵野」のイメージから、武蔵野市政30周年を記念して昭和52年に委嘱作曲されました。武蔵の野に陽が落ちるトワイライトタイム、雑木林を歩む者の目前に開けた原野を風が吹き抜けてゆく風景を描いた、詩情にあふれた曲です。
武蔵野を渡る風を表現する、尺八の名手になる独奏パートがオーケストラをリードし、箏が野の下草や梢の葉のうねりやさざめきを奏で音色をふくらませ、三味線が小気味よく歌パートとともに景色に陰影をつける素敵な曲で、さまざまな演奏会で再演を重ねてまいりました。
武蔵野市がルーマニアのブラショフ市と友好を結んだ数年後の記念の、ジョルジュ・デュマ・ルーマニア国立交響楽団の招聘公演で、日本側の返礼曲として演奏いたしました折も大好評をいただき、先方の楽団責任者の方からスコアを所望されるという、嬉しいエピソードもございます。
2013年には、花柳衛彦先生(彦六の正蔵師匠のご子息)が振付くださり、舞踊公演もいたしました。
作曲は、祖父の代から吉祥寺に住まいし、武蔵野四小、武蔵野一中を母校とする杵屋徳衛です。
音源はこちらにございますので、ご試聴くださいませ。
⇒ http://www.shamisen.org/musasino.htm
武蔵野市は、関東に棲むもの皆が共有したいであろう、この武蔵野という言葉を冠する都市です。
もっと武蔵野市が武蔵野であるゆえんを感じてほしい、というわけで、このたび武蔵野市教育委員会へ申請し、「武蔵野市でむさしのを弾こう!プロジェクト」という、こども対象の文化体験活動支援事業をさせていただく運びとなりました。
9月から始まる市内中学校での練習に参加していただき、11月11日、吉祥寺駅南口の武蔵野公会堂での演奏会で、その成果を発表するというものです。
なにゆえこのようなローカルな話題をインターネットで…とお思いになるかもしれません。
なんと!!
日本では、産土神、根生いである独自の盆踊り大会や子ども会などの衰退に見られるように、昭和末期から平成にかけて地域コミュニティが徐々に崩壊し、現在ではそうした経緯から巻き返した街おこしが結実している場所もあるようではありますが、地元のようで地元でないというような、中途半端に市街地な土地柄では、むしろ限定された地域に対するお知らせ・広報というものが、逆にむずかしい、ということを、身をもって思い知ったわたくしです。
そんなわけで、上記のようなプロジェクトがございます。
お知り合いに、武蔵野市に在住・在学する小・中学生がいらっしゃいましたら、ぜひにご喧伝くださいませ。
小・中学生とポスターには記載されていますが、武蔵野市に在住か在学、在勤の未成年者でしたら、どなたでも参加できます。
伏して乞い御願い申し上げ奉りまする。
武州。
武蔵の国にある五日市だから武蔵五日市、武蔵の国の小山だから武蔵小山、同じく武蔵小杉、武蔵村山、武蔵小金井…エトセトラ、etc.
武蔵の国にある野原で、武蔵野。
関東一円に広がります武蔵野台地。ひと昔前は、よく、時代劇のロケを山背の国=京都でやっておりまして、大川端、隅田川岸が琵琶湖河畔だったり、下賀茂神社が浅草奥山だったりしますが、関東の者には今一つ違和感がある。
それはね、とても美しい風景でほのぼのするのですが、空が狭い。後ろに山がある。
関東平野は見晴らしがいいんです。西に富士山、北に筑波山。
ですから、あまり瑕(きず)のないよくできた時代劇だったりすると、風景に茶々を入れたりする。
京の都の住人・武蔵坊弁慶が勧進帳で飲み干します大盃(おおさかづき、大阪好き、と変換されちゃいましたが…確かに好きですが…ちゃいます)、あれを俗に武蔵野(むさしの)と呼びますが、その心は?
はい、広くて野を見尽くせない→野見つくせない→のみつくせない、飲み尽くせない…正解です。
ひと口に武蔵野、と申しますが、どこら辺を指すかご存知でしょうか?
東京都心/練馬・板橋・北・中野/杉並・世田谷・大田/武蔵野・三鷹/調布・小金井/府中/立川・八王子・青梅/東村山・清瀬・所沢/平林寺/東武・西武・奥武蔵/秩父/奥多摩/葛飾・成田/多摩丘陵
…というような記述を、昭和50年に毎日新聞社から刊行されました風景写真集『武蔵野の四季』に見つけました。父の遺品整理の折、本棚にあった一冊です。
かように、関東に住む者には、武蔵野という言葉は切っても切れない心の風景のよりどころだったり致します。
そんなことがございます一方で、このところの2020東京五輪関連プロジェクトを拝察いたしますにつれ、自分たちの風土に根差した文化をもっと知り、実践すべきではないか、と思うに至りました。
さて、「むさしの」という和楽器オーケストラ向けの曲があります。
編成は尺八、箏、三味線。歌パートもございます。
国木田独歩「武蔵野」のイメージから、武蔵野市政30周年を記念して昭和52年に委嘱作曲されました。武蔵の野に陽が落ちるトワイライトタイム、雑木林を歩む者の目前に開けた原野を風が吹き抜けてゆく風景を描いた、詩情にあふれた曲です。
武蔵野を渡る風を表現する、尺八の名手になる独奏パートがオーケストラをリードし、箏が野の下草や梢の葉のうねりやさざめきを奏で音色をふくらませ、三味線が小気味よく歌パートとともに景色に陰影をつける素敵な曲で、さまざまな演奏会で再演を重ねてまいりました。
武蔵野市がルーマニアのブラショフ市と友好を結んだ数年後の記念の、ジョルジュ・デュマ・ルーマニア国立交響楽団の招聘公演で、日本側の返礼曲として演奏いたしました折も大好評をいただき、先方の楽団責任者の方からスコアを所望されるという、嬉しいエピソードもございます。
2013年には、花柳衛彦先生(彦六の正蔵師匠のご子息)が振付くださり、舞踊公演もいたしました。
作曲は、祖父の代から吉祥寺に住まいし、武蔵野四小、武蔵野一中を母校とする杵屋徳衛です。
音源はこちらにございますので、ご試聴くださいませ。
⇒ http://www.shamisen.org/musasino.htm
武蔵野市は、関東に棲むもの皆が共有したいであろう、この武蔵野という言葉を冠する都市です。
もっと武蔵野市が武蔵野であるゆえんを感じてほしい、というわけで、このたび武蔵野市教育委員会へ申請し、「武蔵野市でむさしのを弾こう!プロジェクト」という、こども対象の文化体験活動支援事業をさせていただく運びとなりました。
9月から始まる市内中学校での練習に参加していただき、11月11日、吉祥寺駅南口の武蔵野公会堂での演奏会で、その成果を発表するというものです。
なにゆえこのようなローカルな話題をインターネットで…とお思いになるかもしれません。
なんと!!
日本では、産土神、根生いである独自の盆踊り大会や子ども会などの衰退に見られるように、昭和末期から平成にかけて地域コミュニティが徐々に崩壊し、現在ではそうした経緯から巻き返した街おこしが結実している場所もあるようではありますが、地元のようで地元でないというような、中途半端に市街地な土地柄では、むしろ限定された地域に対するお知らせ・広報というものが、逆にむずかしい、ということを、身をもって思い知ったわたくしです。
そんなわけで、上記のようなプロジェクトがございます。
お知り合いに、武蔵野市に在住・在学する小・中学生がいらっしゃいましたら、ぜひにご喧伝くださいませ。
小・中学生とポスターには記載されていますが、武蔵野市に在住か在学、在勤の未成年者でしたら、どなたでも参加できます。
伏して乞い御願い申し上げ奉りまする。