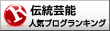新年早々、背に腹は代えられぬ仔細があって、20年以上も契約してきた携帯会社を替えることになった。汎用タイプの道具は代えが利くから仕方ない。
しかし、日本という北半球のガラパゴス生態系の中でも特にガラパゴス化してしまった私には、この新しい道具には痛痒しか感じない。パタパタンと半分に折れてプッシュボタンもあって、一見ガラケーだが、画面を押しても使えるスマフォである、というニューフェイスは、片手で操作できる、という秀逸な特徴を残して魅力であるが、その分、痒いところに手が届かないのだった。
ことにカメラ。ただ写すだけで何の設定もできない。これではピンホールカメラではないか、原始的な。泣く泣く別れたシャープの愛機を思う。
嗚呼、シャープ。なんという優れたメーカーであったことか。ワープロ時代、『書院』という素晴らしい日本語変換機能を備えた道具の製造販売元であった。道具は使う者の身に沿って、初めて道具たり得るのだ。今の商売第一主義は何たること。使う者が使う物に合わせなくてはならず不自由することを強要する、不遜な考えなのだ。
そんなわけで気の利いた写真が撮れず、そうだ、文章を書いてる時間がなければ写真を載せればいいじゃない!…という安直な発想を、折々の情景というカテゴリに目論んでもみたのだが、早々に挫折した。
表題は、ちょっとピンボケ…どころか、かなりピンボケな、彼岸の、昌平黌の情景である。
しょうへいこう…!! なんと心ときめく名称であろう。幕末に旗本の家に生まれていたら絶対通いたかった、お玉が池の千葉道場と同等…いや、文系の私には、それよりもっと憧れの昌平黌。
もう梅はこぼれてしまったし、まだ桜には早いし…いったい何の花だろうと近寄ったら、驚くまいことか、アンズの花の花盛りなのだった。梅に鶯、竹に虎、孔子廟には杏、の本寸法。
なんの思うところもなく気の向くまま、うららかな日差しを浴びながら今では湯島の聖堂と呼ばれるこの場所へ、二十数年ぶりに参ったのは、先述の観梅の心を引きずってのこともあったのかもしれない。
関東大震災であらかたが焼失したという、維新以降の有為転変の世の中を、ことごとく体現してしまったようなこの場所の不遇は、ぼんやりととりとめもなく咲き乱れる、薄紫の花ダイコンがはびこっている廟内の庭からもうかがい知れた。
花大根を、オオアラセイトウと表記したほうがカッコいいけれども、その花容にそぐわない。…そうだ、別名・諸葛采で呼ぶと、ぐっとこの場所には似合うのかもしれない。
大成殿に、面白い道具が展示されていた。「宥座の器」。
銅(あかがね)製の手のひらぐらいの寸法の壺が、ブランコのように、二本の鎖で中空に吊られている。
孔子の教えを改めて実感できるよう、見物者が水を入れて実験できるようになっている。
以下、殿内の解説にあった荀子の『宥座篇』から引用の一文を写す。
「…虚なればすなわち傾き、中なればすなわち正しく、満つればすなわち覆る…」
中庸の徳、謙虚の徳を説いたものだそうである。
…そいえば信長くんの行く末を、安国寺恵瓊が「高転びに、仰のけに転ぶ」だろう、とか言ってたっけなぁ、藤原道長も満月が好きすぎたよなぁ…などと、胸に去来した次第。