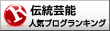馬が走っている姿は美しい。小学生のころは、愛読していた探偵小説『シャーロック・ホームズ』や、児童文学『メアリー・ポピンズ』の影響で、イギリスの文化に憧れていたから、貴族が馬主で、白いドレスを纏ったご婦人がやはり白いパラソルをさして、遠眼鏡でレースに見入る様子や、アスコット競馬場とかいう言葉だけは知っていた。
「マイ・フェア・レディ」や「メアリー・ポピンズ」の映画中に観る競馬場文化ってなんだか優雅ですなぁ。でも、競馬場にほとんど人がいない。…そういえば、これ以上はないであろう理想のホームズ君であったジェレミー・ブレットが「マイ・フェア・レディ」に出ていたのを知ったときは驚いた。それで、ジェレミー・ブレットの訃報を聞いて間もなく、観返してみたのだった。彼の歌う「君住む街かど」のなんと、ジーンとくることか。今思い出しても胸が熱くなる。
高校生のころ、NHKのラジオ・ドラマで、ディック・フランシスの『度胸』という競馬界を舞台にしたミステリーを、今は亡き広川太一郎が朗読していた。ものすごく面白かった。早川ミステリ文庫に収録されていたので、さっそくそのシリーズを何冊か読んだものだった。ディック・フランシス本人も騎手だったそうである。彼は今年のバレンタインデーに亡くなった。ご冥福をお祈りいたします。
馬券を買ったことが一度もない私が、何でこんなことを書いているのかというと、今日は東京優駿、ダービーを観てしまったからだ。そして、ダービーは三歳馬しか出走できない、ということをアナウンサーが話していて、おや…???と思った。
いかな馬券を買ったことがない私でも、昭和45年に大ヒットした「走れコータロー」はそらで歌える。たしか、あの歌詞の中では、「天下のサラブレッド、四歳馬」と言ってなかったかしら。…私の記憶違いかと思い、小声で唄ってみたが、どうも三歳馬だと語呂が悪い…そして、変だ。
どうにも納得がゆかず、さっそくインターネットで調べてみた。
…そこで、びっくり!
2000年まで、日本のお馬さんは、数え年で年齢を数えていたらしい。それだとどうも世界基準と違って紛らわしいので、21世紀から現行の数え方に変わったそうなのだ。
戦前までは日本の人間も数え年だったので、生まれた時点ですでに一歳ということになっていた。祖母や両親あたりまで、数え年で自分の年齢を数えていたような記憶がある。そういえば、小さいころ、年を訊かれるのに、やたらと「満でいくつ」とか答えさせられるのを不思議に思っていたのだった。
早生まれの私なんて、誕生日が来る前にお正月が来るから、零歳のときの最初のお正月で、昔だったら、すでに二歳になっていた勘定になる。コワイワ…。
そんなわけでもないだろうが、生きていくこと自体が緊張感の連続だった時代には、子どもは早く大人に成らざるを得なかった、のかもしれない…。
信長くんの好きだった幸若舞「敦盛」♪人間五十年…。信長は数えで享年四十九だったけれど、ホントは早生まれだったりしないだろうか…。
「マイ・フェア・レディ」や「メアリー・ポピンズ」の映画中に観る競馬場文化ってなんだか優雅ですなぁ。でも、競馬場にほとんど人がいない。…そういえば、これ以上はないであろう理想のホームズ君であったジェレミー・ブレットが「マイ・フェア・レディ」に出ていたのを知ったときは驚いた。それで、ジェレミー・ブレットの訃報を聞いて間もなく、観返してみたのだった。彼の歌う「君住む街かど」のなんと、ジーンとくることか。今思い出しても胸が熱くなる。
高校生のころ、NHKのラジオ・ドラマで、ディック・フランシスの『度胸』という競馬界を舞台にしたミステリーを、今は亡き広川太一郎が朗読していた。ものすごく面白かった。早川ミステリ文庫に収録されていたので、さっそくそのシリーズを何冊か読んだものだった。ディック・フランシス本人も騎手だったそうである。彼は今年のバレンタインデーに亡くなった。ご冥福をお祈りいたします。
馬券を買ったことが一度もない私が、何でこんなことを書いているのかというと、今日は東京優駿、ダービーを観てしまったからだ。そして、ダービーは三歳馬しか出走できない、ということをアナウンサーが話していて、おや…???と思った。
いかな馬券を買ったことがない私でも、昭和45年に大ヒットした「走れコータロー」はそらで歌える。たしか、あの歌詞の中では、「天下のサラブレッド、四歳馬」と言ってなかったかしら。…私の記憶違いかと思い、小声で唄ってみたが、どうも三歳馬だと語呂が悪い…そして、変だ。
どうにも納得がゆかず、さっそくインターネットで調べてみた。
…そこで、びっくり!
2000年まで、日本のお馬さんは、数え年で年齢を数えていたらしい。それだとどうも世界基準と違って紛らわしいので、21世紀から現行の数え方に変わったそうなのだ。
戦前までは日本の人間も数え年だったので、生まれた時点ですでに一歳ということになっていた。祖母や両親あたりまで、数え年で自分の年齢を数えていたような記憶がある。そういえば、小さいころ、年を訊かれるのに、やたらと「満でいくつ」とか答えさせられるのを不思議に思っていたのだった。
早生まれの私なんて、誕生日が来る前にお正月が来るから、零歳のときの最初のお正月で、昔だったら、すでに二歳になっていた勘定になる。コワイワ…。
そんなわけでもないだろうが、生きていくこと自体が緊張感の連続だった時代には、子どもは早く大人に成らざるを得なかった、のかもしれない…。
信長くんの好きだった幸若舞「敦盛」♪人間五十年…。信長は数えで享年四十九だったけれど、ホントは早生まれだったりしないだろうか…。