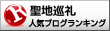「つるのふたせんさんびゃくろくじゅうごばん…」
毎月26日が鶴の日かどうかは知らないけれど、水屋の富とか、富くじの噺を聞かなくなったなぁ…と思ってみたものの、考えてみたら、わたくし自身が落語を久しく聞いてなかったことに気づいた。
それにああいう宝くじの話は歳の瀬に聞くのがシーズンというものでございましょう。
八月の間、お稽古が夏休みだったりする一方で、この季節ならではの講習、午前中に子ども教室…キッズ伝統芸能体験、へ伺う。常日頃では行かない街を訪れるのは愉しい。ホリデー快速なんという、登山支度の乗客で賑わう車両の中、まだ午過ぎの早い時間に仕事が終わって、私もついうかうかと、遊びに出掛けたい心持ちになっていた。
この時間からこの、ついふらふらしたい気持ちを昇華させるとすると…
先ほどの教室で、素敵な手ぬぐいを見かけた。紅色で、亀甲つなぎに鶴の丸。
いいなぁ。赤の鶴の丸といやぁ、泣く子も黙る国営の航空会社のトレードマークでしたね。
つーーーーーっ、と来て、る、と留まるのが、ツルってもんですね。
さて、鶴ならぬ身の落としどころは何処。
湯島の天神下の交差点に、つる瀬、という甘味処、あんみつ屋さんがあって、この時季はなんてったって、かき氷なのだ。練乳白玉のおいしいことといったら。杏も載せたかったのだけれど、予算オーバーになるのでやめて、デリーのカレー屋さんに行列ができてるのを横目で見ながら…本当は私、すし初さんに行きたかったのです。
このお鮨屋さんはもう30年来の想い出の場所なのだった。そのころ取引先だったデザイン事務所が、塗師屋の二階に間借りしていて、お昼時間を外れた私が案じながらまだ折れていない暖簾をめくったら、恰幅のいい河津清三郎似の旦那さんが、ちょうど若い衆と交代するところで…
それから上野方面に用事があると出来うる限り立ち寄るようにしていた…といっても時分時にこの辺りに来ることは滅多になかったのだが。父が生きてた頃、一度だけ連れてきたことがあって…その時は男前の大将は他界されて、女将さんが相手をしてくださった。
父と女将さんとは、学徒動員で駆り出されて、川崎の東芝の工場まで働きに行った話で盛り上がっていたのだ。
だから女将さんはご健在かと、店の様子が見たかったのだ。もう10年ぐらい、暖簾をくぐっていないのだった。
中途半端な時間帯なのと日曜で、お店は閉まっていた。休日の広小路に至る春日通りは閑散として、みつばちとデリーに行列ができて、不思議な雰囲気。
久しぶりに、鈴本に入った。
前座さんが「つる」を掛けたのだが、どうしたはずみか加減でか、とちってしまったのだった。それが場内の苦爆笑を呼び、そんなことがありながら淡々と番組が進み、中入り前だったかしら、喬太郎さんが「極道のつる」をかけた。
これはある意味禁じ手かもしれないけれど、そんなこたぁどうでもいいのだ。
あまりにも可笑しく面白かったので、身もだえする程に笑った。
隣席の若き青年が、「…すごい無茶苦茶だ…」と呆然として番組表に何か書きつけていたが(落研ですか?)、いやそれは違うなぁ、無茶苦茶どころか、なんと緻密に計算され尽くしたパロディな「つる」でありましょうか、君はまだ若いなぁ、とおばさんは思いました。
落語は研究して論ずるものではなく、仕手が実践したものを味わえばよいのです。
さらっと書いてしまったが、下がれ下がれ、下がりおろう! このお方を誰と心得る、今や日本中で一番チケットが取れない落語家とその名も高き柳家喬太郎師匠であらせられるぞ…とひいきの皆さまに怒られたらどうしよう…と不安になるのですが、寿限無を暗唱する一般的昭和の小学生だったわたくしは、長ずるに及び、昭和の終わりごろ落語と名の付くもの…高座はいうまでもなく、速記本、漫画、映画に至るまで見聞き尽くしていたマイナーなギャルになっていたのでしたが、毎日が落語だった私が見ていたのは、喬太郎さんの師匠が若手と呼ばれていた時代だったのです。そんなわけで……
思えば、私は喬太郎さんの大驀進をそんなに見ていない。
中野芸能劇場で殿は国入り…だったかしら、細川のお殿様が総理大臣だったころ、リアルタイムで江戸のかわら版ニュース実況中継のような新作を見た記憶があるのだ。
昭和の終わりから落語がなけりゃ夜も日もあけぬ私だったのに、平成の5年頃を最後に、私はバッタリと寄席に行くのをやめてしまった。
その理由はいつかお話することもあるかもしれないけれども。
だから、師匠と敬称をつけるべきフィーリングがこと喬太郎さんに対しては無いのだった。
そして、喬太郎さんを喬太郎師匠、と呼ぶと、私の中の落語世界はウソに転じる気がするのだ。そんなわけで…ごめんなさい。
有楽町のマリオンの前で、うっかり空を見上げたら、ビルを凌いでものすごい速さで流れていった雲とか、銀座セブン寄席の薄暗いガスビルから外へ出た銀座通りの眩しさとか、椀屋寄席の、店内を区切る御簾の中途半端なぶら下がりの丈とか……
…きっと同じ景色を見ていたのに違いないような気がして、旧友と昔話をしているようでなつかしい。喬太郎さんを媒介に私はあの時代にタイムトリップできるのだ。
昭和の終わりからのダントツに景気がよくて、でも、非力な若者が過ごした青春の裏通りを多分、同じような気持ちで見ながら過ごしてきたのじゃなかろうかと…
何の噺だったか、「池袋の人間が表参道へ行ったら撃たれるんですよ」という、言葉の端々が、もう、自分の分身じゃないかと思えるほどである。
それから私は寝た子を起こされ、どうにか日程が合った池袋演芸場の喬弟仁義に行ってみた。
そこでまた、これでもかという演題に廻り合わせていただき、笑い転げるしかなかった。
エンターテイナーが持つ、これほどまでにやってしまうのか…!というインクレデヴィルなサービス精神。先代の澤瀉屋を想い出した。
客席を観ながら、今日のお客さんにはどんな料理を出してやろうという、客のニーズを読み取る手練れならではのピタリの選球眼。
そんな喬太郎さんの独演会の切符が手に入るとも思えない。そしてまた、行きずりの寄席で、一期一会の、今日は果たして何を聴かせてくれるのかな…という緊張状態でもって巡り合いたいので、私は敢えて切符争奪戦に参加しない。
いつまた寄席に行けるかわからないけれど…ちょっとマカロニウエスタンなBGMが私の耳をかすめた。
それにつけてもほんの出来心で、つーーーーーーーっと来て、るっと着地した場所で、こんなに鶴尽くしの目に遇うとは……
毎月26日が鶴の日かどうかは知らないけれど、水屋の富とか、富くじの噺を聞かなくなったなぁ…と思ってみたものの、考えてみたら、わたくし自身が落語を久しく聞いてなかったことに気づいた。
それにああいう宝くじの話は歳の瀬に聞くのがシーズンというものでございましょう。
八月の間、お稽古が夏休みだったりする一方で、この季節ならではの講習、午前中に子ども教室…キッズ伝統芸能体験、へ伺う。常日頃では行かない街を訪れるのは愉しい。ホリデー快速なんという、登山支度の乗客で賑わう車両の中、まだ午過ぎの早い時間に仕事が終わって、私もついうかうかと、遊びに出掛けたい心持ちになっていた。
この時間からこの、ついふらふらしたい気持ちを昇華させるとすると…
先ほどの教室で、素敵な手ぬぐいを見かけた。紅色で、亀甲つなぎに鶴の丸。
いいなぁ。赤の鶴の丸といやぁ、泣く子も黙る国営の航空会社のトレードマークでしたね。
つーーーーーっ、と来て、る、と留まるのが、ツルってもんですね。
さて、鶴ならぬ身の落としどころは何処。
湯島の天神下の交差点に、つる瀬、という甘味処、あんみつ屋さんがあって、この時季はなんてったって、かき氷なのだ。練乳白玉のおいしいことといったら。杏も載せたかったのだけれど、予算オーバーになるのでやめて、デリーのカレー屋さんに行列ができてるのを横目で見ながら…本当は私、すし初さんに行きたかったのです。
このお鮨屋さんはもう30年来の想い出の場所なのだった。そのころ取引先だったデザイン事務所が、塗師屋の二階に間借りしていて、お昼時間を外れた私が案じながらまだ折れていない暖簾をめくったら、恰幅のいい河津清三郎似の旦那さんが、ちょうど若い衆と交代するところで…
それから上野方面に用事があると出来うる限り立ち寄るようにしていた…といっても時分時にこの辺りに来ることは滅多になかったのだが。父が生きてた頃、一度だけ連れてきたことがあって…その時は男前の大将は他界されて、女将さんが相手をしてくださった。
父と女将さんとは、学徒動員で駆り出されて、川崎の東芝の工場まで働きに行った話で盛り上がっていたのだ。
だから女将さんはご健在かと、店の様子が見たかったのだ。もう10年ぐらい、暖簾をくぐっていないのだった。
中途半端な時間帯なのと日曜で、お店は閉まっていた。休日の広小路に至る春日通りは閑散として、みつばちとデリーに行列ができて、不思議な雰囲気。
久しぶりに、鈴本に入った。
前座さんが「つる」を掛けたのだが、どうしたはずみか加減でか、とちってしまったのだった。それが場内の苦爆笑を呼び、そんなことがありながら淡々と番組が進み、中入り前だったかしら、喬太郎さんが「極道のつる」をかけた。
これはある意味禁じ手かもしれないけれど、そんなこたぁどうでもいいのだ。
あまりにも可笑しく面白かったので、身もだえする程に笑った。
隣席の若き青年が、「…すごい無茶苦茶だ…」と呆然として番組表に何か書きつけていたが(落研ですか?)、いやそれは違うなぁ、無茶苦茶どころか、なんと緻密に計算され尽くしたパロディな「つる」でありましょうか、君はまだ若いなぁ、とおばさんは思いました。
落語は研究して論ずるものではなく、仕手が実践したものを味わえばよいのです。
さらっと書いてしまったが、下がれ下がれ、下がりおろう! このお方を誰と心得る、今や日本中で一番チケットが取れない落語家とその名も高き柳家喬太郎師匠であらせられるぞ…とひいきの皆さまに怒られたらどうしよう…と不安になるのですが、寿限無を暗唱する一般的昭和の小学生だったわたくしは、長ずるに及び、昭和の終わりごろ落語と名の付くもの…高座はいうまでもなく、速記本、漫画、映画に至るまで見聞き尽くしていたマイナーなギャルになっていたのでしたが、毎日が落語だった私が見ていたのは、喬太郎さんの師匠が若手と呼ばれていた時代だったのです。そんなわけで……
思えば、私は喬太郎さんの大驀進をそんなに見ていない。
中野芸能劇場で殿は国入り…だったかしら、細川のお殿様が総理大臣だったころ、リアルタイムで江戸のかわら版ニュース実況中継のような新作を見た記憶があるのだ。
昭和の終わりから落語がなけりゃ夜も日もあけぬ私だったのに、平成の5年頃を最後に、私はバッタリと寄席に行くのをやめてしまった。
その理由はいつかお話することもあるかもしれないけれども。
だから、師匠と敬称をつけるべきフィーリングがこと喬太郎さんに対しては無いのだった。
そして、喬太郎さんを喬太郎師匠、と呼ぶと、私の中の落語世界はウソに転じる気がするのだ。そんなわけで…ごめんなさい。
有楽町のマリオンの前で、うっかり空を見上げたら、ビルを凌いでものすごい速さで流れていった雲とか、銀座セブン寄席の薄暗いガスビルから外へ出た銀座通りの眩しさとか、椀屋寄席の、店内を区切る御簾の中途半端なぶら下がりの丈とか……
…きっと同じ景色を見ていたのに違いないような気がして、旧友と昔話をしているようでなつかしい。喬太郎さんを媒介に私はあの時代にタイムトリップできるのだ。
昭和の終わりからのダントツに景気がよくて、でも、非力な若者が過ごした青春の裏通りを多分、同じような気持ちで見ながら過ごしてきたのじゃなかろうかと…
何の噺だったか、「池袋の人間が表参道へ行ったら撃たれるんですよ」という、言葉の端々が、もう、自分の分身じゃないかと思えるほどである。
それから私は寝た子を起こされ、どうにか日程が合った池袋演芸場の喬弟仁義に行ってみた。
そこでまた、これでもかという演題に廻り合わせていただき、笑い転げるしかなかった。
エンターテイナーが持つ、これほどまでにやってしまうのか…!というインクレデヴィルなサービス精神。先代の澤瀉屋を想い出した。
客席を観ながら、今日のお客さんにはどんな料理を出してやろうという、客のニーズを読み取る手練れならではのピタリの選球眼。
そんな喬太郎さんの独演会の切符が手に入るとも思えない。そしてまた、行きずりの寄席で、一期一会の、今日は果たして何を聴かせてくれるのかな…という緊張状態でもって巡り合いたいので、私は敢えて切符争奪戦に参加しない。
いつまた寄席に行けるかわからないけれど…ちょっとマカロニウエスタンなBGMが私の耳をかすめた。
それにつけてもほんの出来心で、つーーーーーーーっと来て、るっと着地した場所で、こんなに鶴尽くしの目に遇うとは……