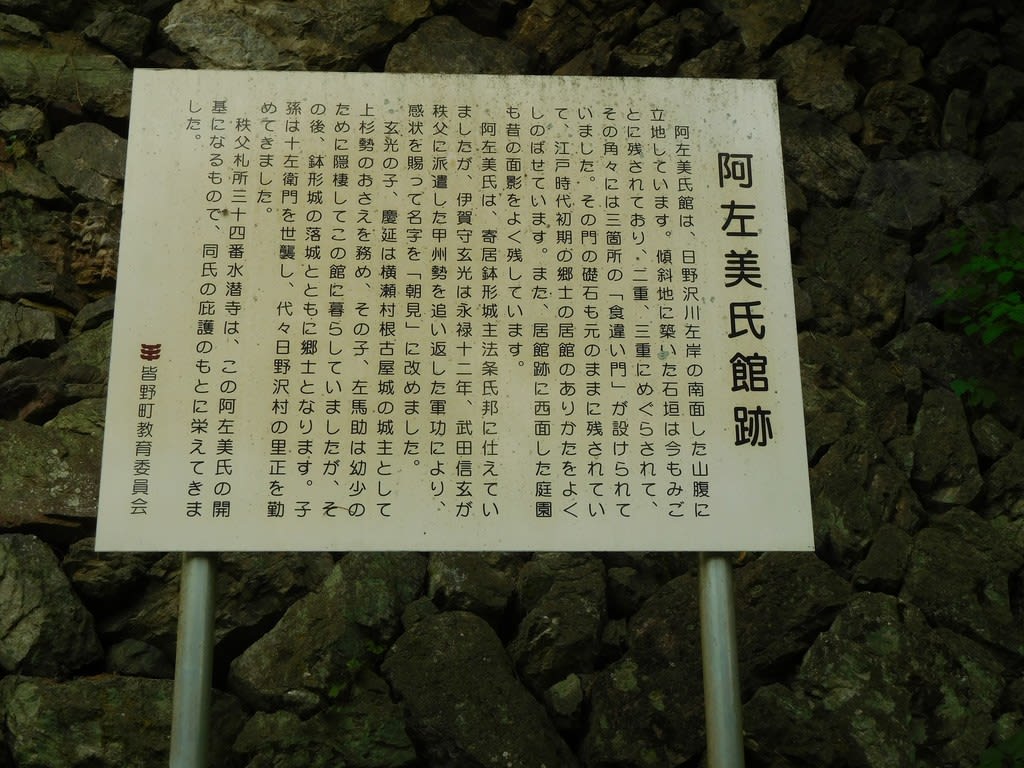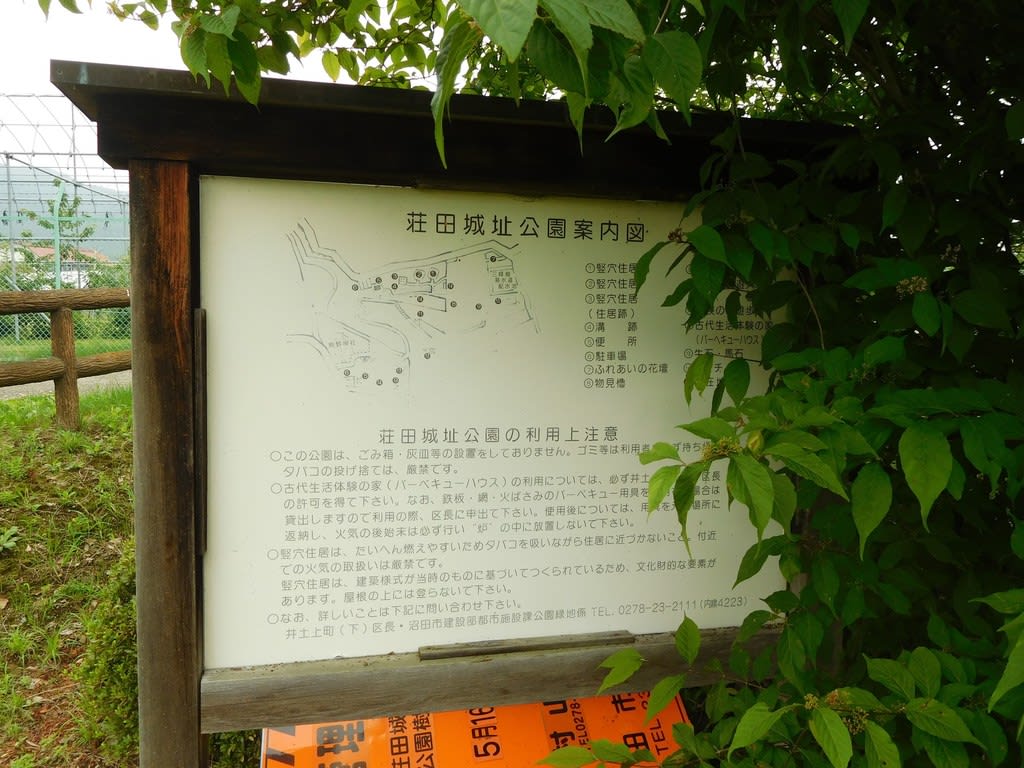【館山城】たてやまじょう
【別名】―
【構造】山城
【築城者】里見義康
【築城年代】1588年(天正16年)
【指定史跡】―
【場所】館山市館山 地図
地図
【御城印】館山市立博物館

館山城は、里見義頼が重臣に築城を命じ、1588年(天正16年)義頼の子である義康が
築城しました。
昭和57年に三層四階の模擬天守が建てられ、館山市立博物館になっています。
駐車場
麓には無料の駐車場とトイレが完備されています。
里見茶屋

前回来た時にはあったのかなあ?
全く気付かなかったお団子屋さんなのですが、テレビで見て寄ってみたかったのですが
朝なのでまだ開いていません。

孔雀園に行く道です。
台風15号の影響で立ち入り禁止になっていましたが、現在は開通しているようです。

本丸への道も立ち入り禁止とされていましたが現在は通ることが出来ます。
彫刻の径

台風15号により倒れた木です。
館山市立博物館本館

ここは、「館山市の歴史と民俗」をテーマとする博物館です。
日曜・祝日は甲冑の体験着用ができます。
※現在台風15号の影響により休館中です。10月1日より開館予定

本来は企画展をやっていて、館山駅開業100周年記念展「鉄道がやってきた」というテーマの展示をしていたそうです。
館山駅のお花の管理をされている女性の方が見て欲しかったなあと残念そうに語ってくれました。

こちらも災害時帰宅支援ステーションになっています。

道に倒れていた桜の木も徐々に撤去したりされているとのことです。
つばきの径
頂上へと続く「つばきの径」は、階段沿いに約900本の椿が植栽されています。
駐車場
本丸から一番近い駐車場です。
一般用ではなく、身体の不自由な方専用の駐車場が設けられています。
茶室「雁月庵」

茶会だけでなく会議や行事など多目的に利用が可能な会場です。

この階段を登って、いざ、本丸へ。
ちなみに正面の道はまだ立ち入り禁止のままです。
本丸跡

朝、ラジオ体操をするために地元の方々が集まって来ます。
いろいろな城跡を朝に巡っていると、ラジオ体操をしている光景をよく目にします。
これがとても羨ましい。
浅間神社
千畳敷

千畳敷と呼ばれる本丸の広場。
里見桜の由来

この桜は、里見氏が国替えとなり里見忠義の最後の地であり、
里見八犬伝の発祥の地である鳥取県倉吉市との交流として、
里見氏発祥の群馬県有志らと一緒に植えられたという桜の木です。
城跡碑
城跡碑の隣には説明の書かれた石碑と、里見の千万猿の像があります。
館山城(八犬伝博物館)

こちらも10月1日からの開館となる予定です。
以前訪れた時は里見八犬伝の話をして下さいました。
天守からの眺め

こちらは以前訪れた時のものです。
この時は晴れていました。

海無し県から来ると、やっぱり海は良いものです。
しかも、天守からこんな景色が見えていたのかと思うと良いよなあ
恋人の聖地
関東の富士見100景に選ばれている場所です。
館山市が、プロポーズにふさわしいロマンティックなスポットとして「恋人の聖地」
としても選定されています。
いつからあるのか知らないですが、こんなところがあったとは、
知っていたらここでプロポーズされるってもいいかなあ。
ちょっと、ここでやりなおしてくれないかなあ

結局この日は富士山は見えませんでした。
ラジオ体操終了とともに地元の方と一緒に下山することに。

途中に居たにゃんこ。
こちらの城主さまかと伺ってみましたが、そうではないとのこと。
普段見かけない迷いにゃんこだそうで…。
台風の被害に遭いながらも、ラジオ体操をするために本丸に集まる地元の方々といっしょに
ラジオ体操に参加させて頂きました。
みんな元気にしているかどうか、確かめ合っているかのようでした。
被害に遭われた方々も行政のもどかしさを責めるような発言をせず、むしろいろいろ言われて
大変なんだし、自分たちよりもっと大変な人がいっぱいるんだから…と言い、
毎日ゴミ拾いをしながら帰るんだよと話してくれました。
今回、桜の名所でもあり80年ものの桜の大木を沢山失ってしまったことを悲しんでいました。
復興と言っても東日本大震災や熊本地震などあちこちの自然災害での復興の遅れを
どうしてあんなに時間がかかるんだろうと思っていたけど、実際自分が被害を受けてみると
その理由が分かった気がする。時間がかかるものなんだって実感してると
おっしゃっていました。
もっともっと個人的なお話をしてくれた方などもいらっしゃいましたが、
ニュースを見ているのと、現地の生の声を聞くのとでは随分違うなあと感じました。
私に出来ることと言ったら話し相手になるとか現地のお店で金を落とすことくらいしかないですが
それでも歓迎してくれる温かい方が多いことに感動しました。
どこへ行っても、また来てねと言ってくれるのがとてもうれしかったです。
落ち着いたらまた必ず訪れますね!
平成18年1月1日登城
令和元年9月15日再登城
【別名】―
【構造】山城
【築城者】里見義康
【築城年代】1588年(天正16年)
【指定史跡】―
【場所】館山市館山
 地図
地図【御城印】館山市立博物館

館山城は、里見義頼が重臣に築城を命じ、1588年(天正16年)義頼の子である義康が
築城しました。
昭和57年に三層四階の模擬天守が建てられ、館山市立博物館になっています。
駐車場

麓には無料の駐車場とトイレが完備されています。
里見茶屋

前回来た時にはあったのかなあ?
全く気付かなかったお団子屋さんなのですが、テレビで見て寄ってみたかったのですが
朝なのでまだ開いていません。

孔雀園に行く道です。
台風15号の影響で立ち入り禁止になっていましたが、現在は開通しているようです。

本丸への道も立ち入り禁止とされていましたが現在は通ることが出来ます。
彫刻の径

台風15号により倒れた木です。
館山市立博物館本館

ここは、「館山市の歴史と民俗」をテーマとする博物館です。
日曜・祝日は甲冑の体験着用ができます。
※現在台風15号の影響により休館中です。10月1日より開館予定

本来は企画展をやっていて、館山駅開業100周年記念展「鉄道がやってきた」というテーマの展示をしていたそうです。
館山駅のお花の管理をされている女性の方が見て欲しかったなあと残念そうに語ってくれました。

こちらも災害時帰宅支援ステーションになっています。

道に倒れていた桜の木も徐々に撤去したりされているとのことです。
つばきの径

頂上へと続く「つばきの径」は、階段沿いに約900本の椿が植栽されています。
駐車場

本丸から一番近い駐車場です。
一般用ではなく、身体の不自由な方専用の駐車場が設けられています。
茶室「雁月庵」

茶会だけでなく会議や行事など多目的に利用が可能な会場です。

この階段を登って、いざ、本丸へ。
ちなみに正面の道はまだ立ち入り禁止のままです。
本丸跡

朝、ラジオ体操をするために地元の方々が集まって来ます。
いろいろな城跡を朝に巡っていると、ラジオ体操をしている光景をよく目にします。
これがとても羨ましい。
浅間神社

千畳敷

千畳敷と呼ばれる本丸の広場。
里見桜の由来

この桜は、里見氏が国替えとなり里見忠義の最後の地であり、
里見八犬伝の発祥の地である鳥取県倉吉市との交流として、
里見氏発祥の群馬県有志らと一緒に植えられたという桜の木です。
城跡碑

城跡碑の隣には説明の書かれた石碑と、里見の千万猿の像があります。
館山城(八犬伝博物館)

こちらも10月1日からの開館となる予定です。
以前訪れた時は里見八犬伝の話をして下さいました。
天守からの眺め

こちらは以前訪れた時のものです。
この時は晴れていました。

海無し県から来ると、やっぱり海は良いものです。
しかも、天守からこんな景色が見えていたのかと思うと良いよなあ

恋人の聖地

関東の富士見100景に選ばれている場所です。
館山市が、プロポーズにふさわしいロマンティックなスポットとして「恋人の聖地」
としても選定されています。
いつからあるのか知らないですが、こんなところがあったとは、
知っていたらここでプロポーズされるってもいいかなあ。
ちょっと、ここでやりなおしてくれないかなあ


結局この日は富士山は見えませんでした。
ラジオ体操終了とともに地元の方と一緒に下山することに。

途中に居たにゃんこ。
こちらの城主さまかと伺ってみましたが、そうではないとのこと。
普段見かけない迷いにゃんこだそうで…。
台風の被害に遭いながらも、ラジオ体操をするために本丸に集まる地元の方々といっしょに
ラジオ体操に参加させて頂きました。
みんな元気にしているかどうか、確かめ合っているかのようでした。
被害に遭われた方々も行政のもどかしさを責めるような発言をせず、むしろいろいろ言われて
大変なんだし、自分たちよりもっと大変な人がいっぱいるんだから…と言い、
毎日ゴミ拾いをしながら帰るんだよと話してくれました。
今回、桜の名所でもあり80年ものの桜の大木を沢山失ってしまったことを悲しんでいました。
復興と言っても東日本大震災や熊本地震などあちこちの自然災害での復興の遅れを
どうしてあんなに時間がかかるんだろうと思っていたけど、実際自分が被害を受けてみると
その理由が分かった気がする。時間がかかるものなんだって実感してると
おっしゃっていました。
もっともっと個人的なお話をしてくれた方などもいらっしゃいましたが、
ニュースを見ているのと、現地の生の声を聞くのとでは随分違うなあと感じました。
私に出来ることと言ったら話し相手になるとか現地のお店で金を落とすことくらいしかないですが
それでも歓迎してくれる温かい方が多いことに感動しました。
どこへ行っても、また来てねと言ってくれるのがとてもうれしかったです。
落ち着いたらまた必ず訪れますね!
平成18年1月1日登城
令和元年9月15日再登城
 | 図説 房総の城郭 |
| 千葉城郭研究会 | |
| 国書刊行会 |