【別府城】べっぷじょう
【別名】別府氏城・別府氏館・東別府館
【構造】平城
【築城者】別府次郎行隆
【築城年代】平安時代末期
【指定史跡】県指定史跡
【場所】熊谷市東別府北廓777 地図
地図
別府城は成田二郎行隆が別府の地に住み別府氏を名乗ることに始まります。
行隆の子太郎能行と次郎行助が領地争いをし、行隆の遺言により別府郷を
半分ずつ知行することになり、別府の地には城跡(城館)が三ヶ所伝承されています。
能行に引き継がれ11代長清まで続きましたが、天正18年豊臣秀吉の北条攻めで敗北。
別府城はその後廃城となりました。
入口

車はこの奥の空きスペースに駐車することが出来ます。
案内看板

東別府の館に能行、西別府の館に行助と相対して領地として分け与えられていたことが記されています。
近距離で館がふたつとは、兄弟の争いを丸く収めるための親心が垣間見られます。
石碑

東別府神社のあるこちらの場所が県指定史跡の別府城です。
隣接する香林寺境内にあるのが別府氏館跡になります。
更に西方に遺構は失われてしまったが、行助が居住したと伝わる西別府館跡があります。
東別府神社二の鳥居

東別府神社を正面に見る二の鳥居。
一の鳥居は石碑横にあります。
東別府神社

藤原鎌足の後裔であるところから別府氏の氏神として奈良の春日神社を勧請、
戦国期の廃城になるまで、城の鎮守だったといいます。
明治42年に春日神社から東別府神社と改称したといいます。

合祀された神社や神様たちが祀られています。
多くの神社が祀られているので鳥居の数も多いです。
八坂社・天満天神社・八幡社

八坂社・天満天神社・八幡社を合祀。
御嶽神社

御嶽神社も合祀されています。
「登山して参拝する」気分でお参りする場所ですね。
庭園

この庭園を造った当時はきっと池に水が入っていたのでしょうね。
東の鳥居

東虎口に建てられた鳥居。
東虎口

土塁がしっかり残っています。
横濠跡

濠や土塁の構築は15世紀から16世紀のものと考えられています。
横濠

防御としては浅いので廃城後ある程度埋められたのでしょうね。
濠と土塁

こちらも少し浅めですがはっきりと分かるほど遺構は残っています。

一番高い土塁で、ここで折れ曲がっています。

喰い違い虎口

見てすぐわかる、きれいな喰い違いの虎口。
西虎口

ここの土塁も良い感じの高さを保っています。
神明社の鳥居があります。
神明社

神明社は天照大御神を主祭神とし、伊勢神宮内宮を総本社とする神社と学んだのですが
神社にあまり詳しくないので東別府神社の境内にあるすべての神様がどのような神様なのか
また、なぜここに集結している(合祀されている)のかよく分かりません。
とにかく神様が沢山いらっしゃる城跡なのでここは凄いパワースポットなのかも!です。
標柱

西側からの入口には標柱が建てられています。
集会所に地元の方々が居て、カメラを持って歩いていた私(不審者に見えた?)に声を掛けて来ました。
城跡を巡っていることを話すと別府城の見所と別府城の他に中条(ちゅうじょう)氏館跡のことを
教えて頂きました。
「常光院というお寺なんだけど水堀や土塁が残ってるからそこに行ってみな」と
一生懸命説明して下さいました。
「近頃はスマホのアプリに出てるとかで来る人が増えてるんだよね」とおっしゃっていました。
ブログを書いていることを話すと、
「大勢の人に知ってもらって来てくれるのは良い事だからみんなに紹介してね」とも言われました。
地元の方には挨拶を忘れずに。これが良き情報源にも繋がります。
親切に教えて下さった地元の方に感謝です。ありがとうございました。
平成29年12月10日登城
【別名】別府氏城・別府氏館・東別府館
【構造】平城
【築城者】別府次郎行隆
【築城年代】平安時代末期
【指定史跡】県指定史跡
【場所】熊谷市東別府北廓777
 地図
地図別府城は成田二郎行隆が別府の地に住み別府氏を名乗ることに始まります。
行隆の子太郎能行と次郎行助が領地争いをし、行隆の遺言により別府郷を
半分ずつ知行することになり、別府の地には城跡(城館)が三ヶ所伝承されています。
能行に引き継がれ11代長清まで続きましたが、天正18年豊臣秀吉の北条攻めで敗北。
別府城はその後廃城となりました。
入口

車はこの奥の空きスペースに駐車することが出来ます。
案内看板

東別府の館に能行、西別府の館に行助と相対して領地として分け与えられていたことが記されています。
近距離で館がふたつとは、兄弟の争いを丸く収めるための親心が垣間見られます。
石碑

東別府神社のあるこちらの場所が県指定史跡の別府城です。
隣接する香林寺境内にあるのが別府氏館跡になります。
更に西方に遺構は失われてしまったが、行助が居住したと伝わる西別府館跡があります。
東別府神社二の鳥居

東別府神社を正面に見る二の鳥居。
一の鳥居は石碑横にあります。
東別府神社

藤原鎌足の後裔であるところから別府氏の氏神として奈良の春日神社を勧請、
戦国期の廃城になるまで、城の鎮守だったといいます。
明治42年に春日神社から東別府神社と改称したといいます。

合祀された神社や神様たちが祀られています。
多くの神社が祀られているので鳥居の数も多いです。
八坂社・天満天神社・八幡社

八坂社・天満天神社・八幡社を合祀。
御嶽神社

御嶽神社も合祀されています。
「登山して参拝する」気分でお参りする場所ですね。
庭園

この庭園を造った当時はきっと池に水が入っていたのでしょうね。
東の鳥居

東虎口に建てられた鳥居。
東虎口

土塁がしっかり残っています。
横濠跡

濠や土塁の構築は15世紀から16世紀のものと考えられています。
横濠

防御としては浅いので廃城後ある程度埋められたのでしょうね。
濠と土塁

こちらも少し浅めですがはっきりと分かるほど遺構は残っています。

一番高い土塁で、ここで折れ曲がっています。

喰い違い虎口

見てすぐわかる、きれいな喰い違いの虎口。
西虎口

ここの土塁も良い感じの高さを保っています。
神明社の鳥居があります。
神明社

神明社は天照大御神を主祭神とし、伊勢神宮内宮を総本社とする神社と学んだのですが
神社にあまり詳しくないので東別府神社の境内にあるすべての神様がどのような神様なのか
また、なぜここに集結している(合祀されている)のかよく分かりません。
とにかく神様が沢山いらっしゃる城跡なのでここは凄いパワースポットなのかも!です。
標柱

西側からの入口には標柱が建てられています。
集会所に地元の方々が居て、カメラを持って歩いていた私(不審者に見えた?)に声を掛けて来ました。
城跡を巡っていることを話すと別府城の見所と別府城の他に中条(ちゅうじょう)氏館跡のことを
教えて頂きました。
「常光院というお寺なんだけど水堀や土塁が残ってるからそこに行ってみな」と
一生懸命説明して下さいました。
「近頃はスマホのアプリに出てるとかで来る人が増えてるんだよね」とおっしゃっていました。
ブログを書いていることを話すと、
「大勢の人に知ってもらって来てくれるのは良い事だからみんなに紹介してね」とも言われました。
地元の方には挨拶を忘れずに。これが良き情報源にも繋がります。
親切に教えて下さった地元の方に感謝です。ありがとうございました。
平成29年12月10日登城
 | 関東の名城を歩く 南関東編: 埼玉・千葉・東京・神奈川 |
| クリエーター情報なし | |
| 吉川弘文館 |








































































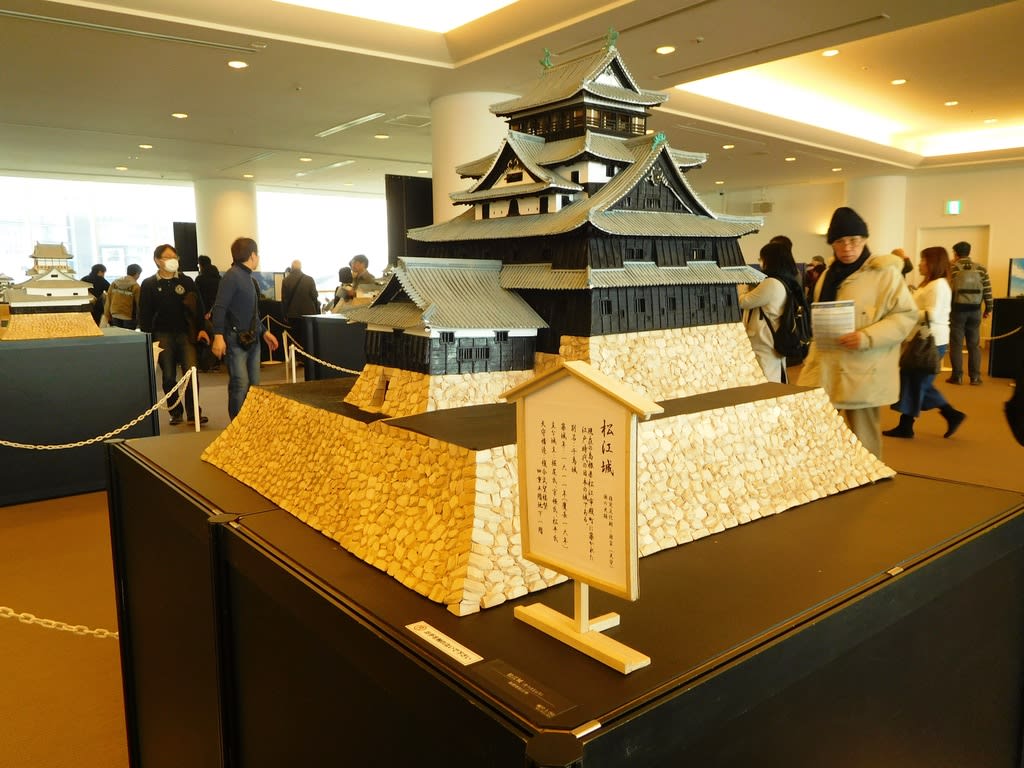
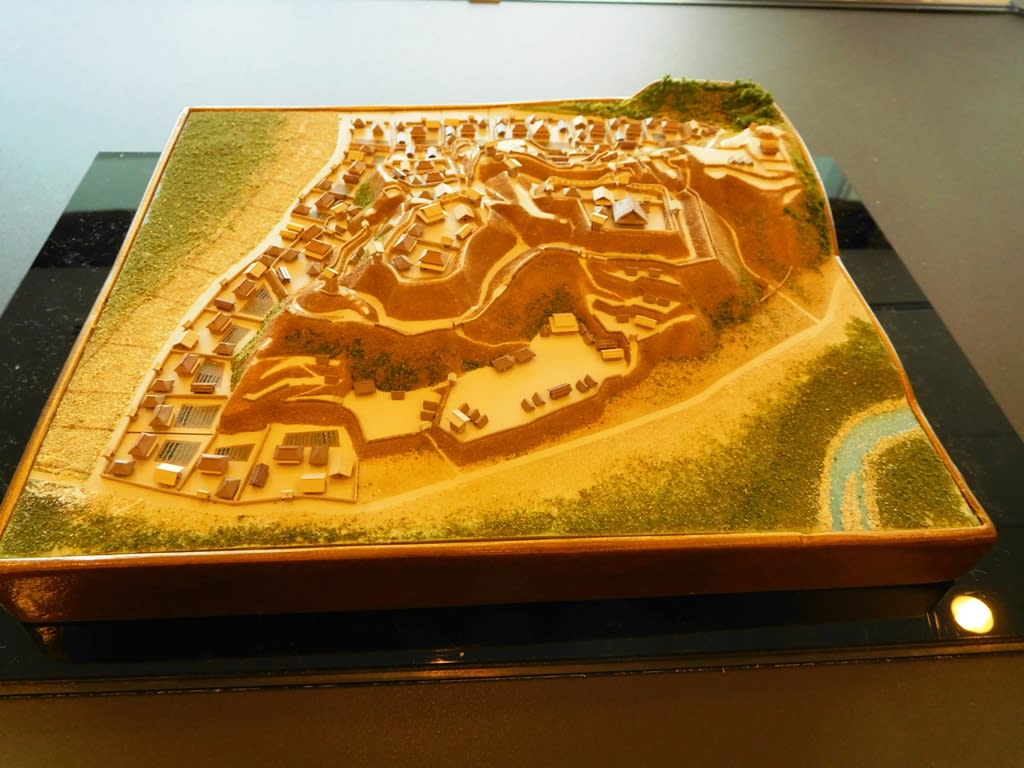















































 と思ってしまったことからなんだけど
と思ってしまったことからなんだけど






















































































































