【三方ヶ原古戦場】みかたがはらこせんじょう
【別名】味方ヶ原の戦い
【構造】古戦場
【合戦者】武田信玄VS徳川家康
【合戦年代】1572年(元亀3年)
【指定史跡】ー
【場所】静岡県浜松市北区根洗町 地図
地図

三方原の戦いは1572年に武田信玄が3万の軍勢を動員し、青崩峠・兵越峠から遠江に侵攻し、
二俣城を降伏させたあとに発生した武田信玄と徳川家康との合戦です。
この戦いで徳川家康は大敗し、その後の家康の人生観に大きく影響した戦いとして知られています。
三方ヶ原戦いの後、家康が戒めとして「しかみ像」という
自画像を描かせた有名なエピソードが伝わります。
三方原墓園

国道257号線沿いにある三方原墓園に古戦場の碑があります。
ここには駐車場やトイレもあるので立ち寄りやすい場所です。

井伊谷城へ向って車を走らせていたらこの看板が目に飛び込んで来ました。
テレビで見た覚えのある光景だったので慌ててUターンをして見に来ました。
案内看板

織田の援軍とここで武田軍を迎え撃つはずでしたが、
この戦いで徳川軍は約2000人もの死者を出しています。
古戦場拡大図

武田軍は3つに分かれて進軍しているのですが、甲府を出発した武田信玄と
武節城・長篠城を攻略した山県昌景と、高遠城を出発し岩村城を攻略した秋山虎繁の軍で
徳川家康の軍を追い詰めて、徳川軍は多くの戦死者を出して浜松城へ敗走しています。
三方原古戦場碑

ここが主戦場になったという特定はされていないのですが、ここ三ヶ方原での戦いがあったことを
後世にも伝えるために碑が建っています。
また、この辺りの地名には家康のいろいろな逸話がありそれを探るのも楽しいです。
ぜひ、地名に注目してみてみてください。
この日はものすごい蝉が発生していて、辺りは蝉の抜け殻だらけ。
車のエンジン音より大きい鳴き声でそれがとても印象に残る場所でした。
古戦場が墓地となっているのも、手を合わせるのにふさわしい場所になっているのが
多くの死者へのせめてもの弔いになるのかなと思う古戦場跡でした。
平成29年7月22日訪問
【別名】味方ヶ原の戦い
【構造】古戦場
【合戦者】武田信玄VS徳川家康
【合戦年代】1572年(元亀3年)
【指定史跡】ー
【場所】静岡県浜松市北区根洗町
 地図
地図
三方原の戦いは1572年に武田信玄が3万の軍勢を動員し、青崩峠・兵越峠から遠江に侵攻し、
二俣城を降伏させたあとに発生した武田信玄と徳川家康との合戦です。
この戦いで徳川家康は大敗し、その後の家康の人生観に大きく影響した戦いとして知られています。
三方ヶ原戦いの後、家康が戒めとして「しかみ像」という
自画像を描かせた有名なエピソードが伝わります。
三方原墓園

国道257号線沿いにある三方原墓園に古戦場の碑があります。
ここには駐車場やトイレもあるので立ち寄りやすい場所です。

井伊谷城へ向って車を走らせていたらこの看板が目に飛び込んで来ました。
テレビで見た覚えのある光景だったので慌ててUターンをして見に来ました。
案内看板

織田の援軍とここで武田軍を迎え撃つはずでしたが、
この戦いで徳川軍は約2000人もの死者を出しています。
古戦場拡大図

武田軍は3つに分かれて進軍しているのですが、甲府を出発した武田信玄と
武節城・長篠城を攻略した山県昌景と、高遠城を出発し岩村城を攻略した秋山虎繁の軍で
徳川家康の軍を追い詰めて、徳川軍は多くの戦死者を出して浜松城へ敗走しています。
三方原古戦場碑

ここが主戦場になったという特定はされていないのですが、ここ三ヶ方原での戦いがあったことを
後世にも伝えるために碑が建っています。
また、この辺りの地名には家康のいろいろな逸話がありそれを探るのも楽しいです。
ぜひ、地名に注目してみてみてください。
この日はものすごい蝉が発生していて、辺りは蝉の抜け殻だらけ。
車のエンジン音より大きい鳴き声でそれがとても印象に残る場所でした。
古戦場が墓地となっているのも、手を合わせるのにふさわしい場所になっているのが
多くの死者へのせめてもの弔いになるのかなと思う古戦場跡でした。
平成29年7月22日訪問
























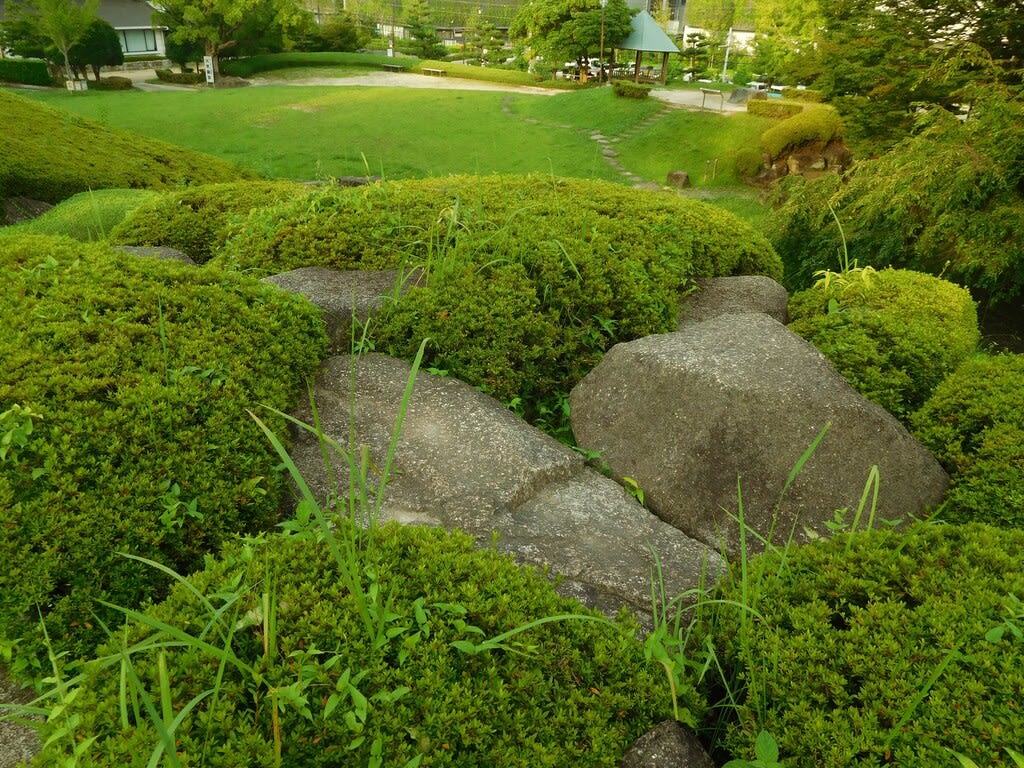















































 折戸浜古戦場
折戸浜古戦場