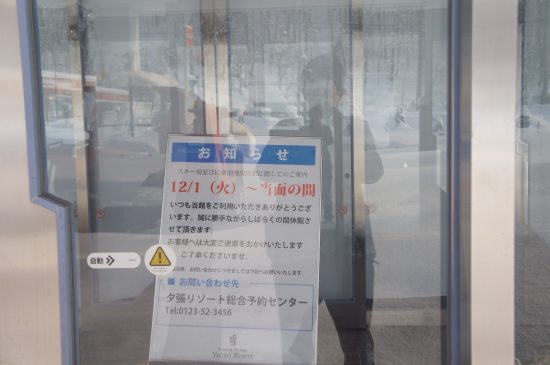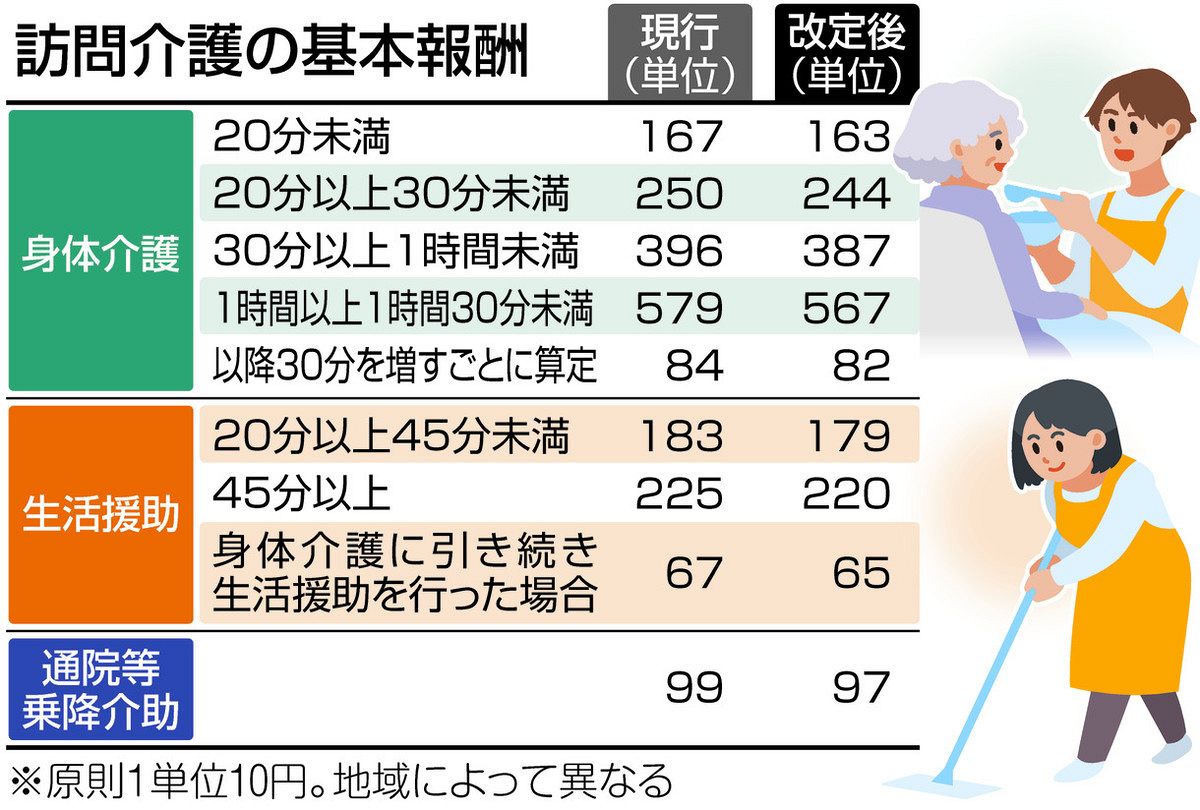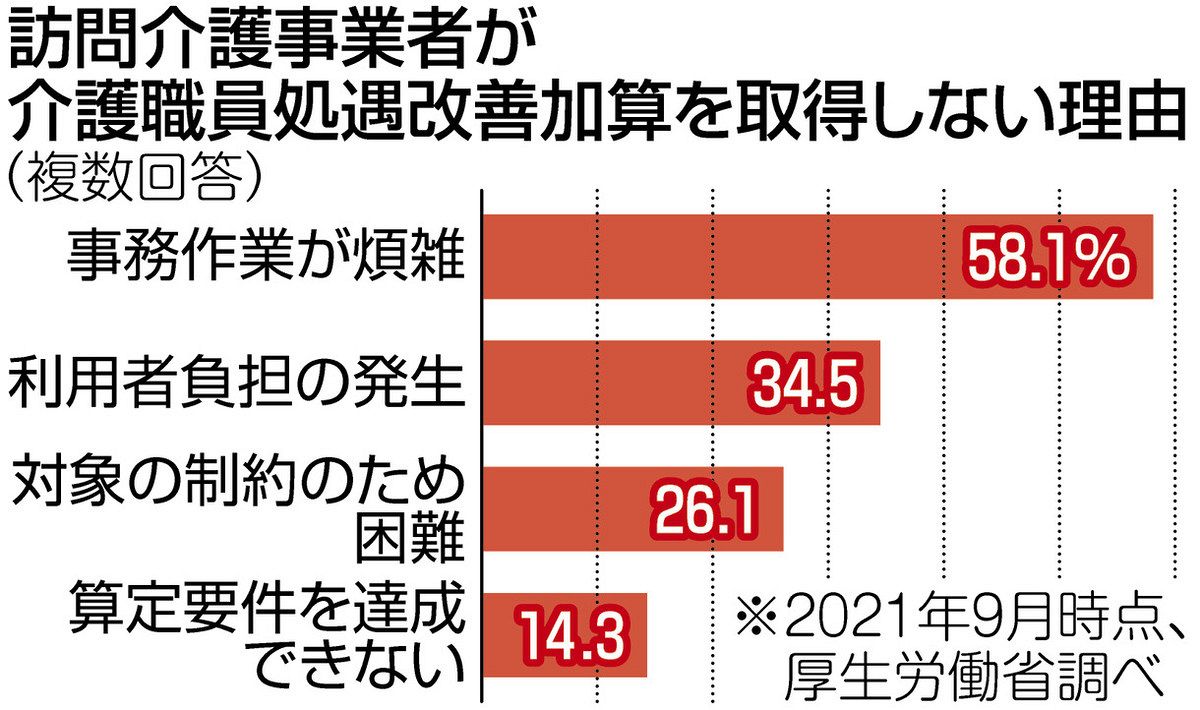(新外交イニシアティブ代表)
Imidas連載コラム 2024/02/27
2024年1月10日、石材を積んだ船が美しい海にそれらを投入する映像に、沖縄では悲痛な声が広がった。沖縄県宜野湾市の米軍普天間基地を名護市辺野古へ移設する計画で、日本政府が、長らく止まっていた大浦湾側の埋め立て工事に着手したのである。
この基地建設工事について、沖縄の人々は、移設計画が持ち上がった1996年から今日まで、28年にわたって反対の声を上げ続けてきた。多くの選挙で建設反対の候補者を当選させ、県民投票を実施してその意思を表明し、建設現場では工事を1分、1時間でも遅らせようと、1日も休むことなく座り込みによる抗議行動を20年続けてきた。
大浦湾側は、「マヨネーズ並み」ともいわれる軟弱地盤が水面下に広がっていることが18年に情報公開請求で明らかになった。国は埋め立て工事の設計変更承認を沖縄県に求めたが、沖縄県はそれを認めなかった。今回、大浦湾側の工事が再開されたのは、複数の訴訟を経て、国が県の権限を奪って沖縄県知事の代わりに埋め立て工事を許可したことによる。
知事の権限を奪うこの「代執行」は、憲法の保障する「地方自治の本旨」に反するのではないか。国民の権利利益の救済を目的とする行政不服審査制度を防衛局が利用して不服申し立てをしたのは適法なのか。地方自治法は国と地方の関係を「対等・協力」とし地方自治体の裁量を広く認めているにもかかわらず、国は県知事の権限を奪って許可できるのか。こうした多くの疑問が呈されながら、「何が何でも埋め立てを行うのだ」という国の姿勢に、沖縄では強い反発が起きている。
また、貴重な海洋生物が生息する美しい海を埋め立てること、国の予定を大きく上回る工期12年、事業費9300億円がかかるとされること、何よりも、長年にわたって強く反対し続ける沖縄県民の声を踏みにじって工事が開始されたことから、沖縄に留まらず、全国でも多くの批判の声が上がっている。
もう一つの苦難
埋め立て開始を受け、玉城デニー沖縄県知事は「沖縄の苦難の歴史に一層の苦難」とのコメントを発表した。
なぜ「沖縄の苦難の歴史に一層の苦難」なのか。
沖縄の強い反対を押し切って新基地建設が進められており、それは沖縄の人たちにとって苦難である。また、沖縄本島の面積の実に15%を米軍基地が占めており、米軍基地に起因する米兵の犯罪・事故や環境破壊、経済発展の阻害などの過剰な負担を強いられている。
そして、その基地が作られる原因ともなった、人口の4人に1人を失った悲惨な沖縄戦の歴史は苦難以外の何物でもない。その後、1972年まで続いた米国占領時代の圧政でも人々は苦しめられた。
さらに遡れば、500年にわたる独立国であった琉球王国を屈服させ、日本政府が「琉球処分」を行って沖縄県として日本に組み入れた明治維新以後の歴史も沖縄にとって現在につながる苦難の始まりであった。
加えて、現在はもう一つの苦難が沖縄を襲っている。
「沖縄が再び戦場になるかもしれない」という事実である。
米中対立が激しくなり、台湾有事の可能性が大きく取り上げられるようになった。故安倍元首相は「台湾有事は日本有事」と言い、その後もメディアなどによって台湾有事の際の日本関与がまことしやかに語られている。幾つもの台湾有事を想定したシミュレーションが日米等の研究機関から発表されているが、そのほぼすべてで、在日米軍基地からの米軍の出撃が予定されている。台湾と目と鼻の先の距離にある沖縄では、既に抱える膨大な米軍基地に加え、近年、幾つもの自衛隊の基地が新設され、米軍との合同軍事演習も強化されてきた。
台湾有事の際には、沖縄からは米軍、あるいは自衛隊もが出撃することになりかねない。そうなれば、反撃にあって沖縄は戦場と化す可能性が高い。その恐怖が、今、沖縄を覆っている。世論調査では、有事の際に沖縄の基地が攻撃対象になると考える人は沖縄において8割を超えている。沖縄の言葉「命(ぬち)どぅ宝(命こそ宝だ)」が再び人々に用いられるようになり、絶対に戦争は避けなければならないという想いが沖縄に広がっている。
沖縄における新たなうねり
台湾有事になれば、戦場になる可能性が高い。戦火に見舞われなくとも緊張関係が続けば、米軍や自衛隊の基地が強化され、沖縄の軍事による負担は増す。
そうした中で、沖縄は米中対立の緩和を強く求めている。
その結果、今の沖縄では新基地反対に加え、平和で安全な生活の実現に向けた新たな取り組みのうねりが起きている。
2023年3月、沖縄県議会は「沖縄を再び戦場にしないよう日本政府に対し対話と外交による平和構築の積極的な取組を求める意見書」を採択した。
また、玉城デニー知事の諮問機関「万国津梁(しんりょう)会議」に急遽設置された地域外交に関する会議からは、2024年1月18日、「沖縄県の地域外交に関する提言書」が発表された。(1)国際平和創造拠点となる、(2)強くしなやかな自立型経済、(3)国際協力活動と国際的課題に貢献する地域となる、等の提言がなされた。提言を受けた沖縄県は、23年度内には、地域外交の基本方針を発表する。
デニー知事の下、県庁には地域外交室が設置され、これを4月には平和・地域外交推進課に昇格させて外交に取り組む。既に進められている知事の諸外国訪問に留まらず、海外の県事務所の強化、県内各自治体・大学や経済界のつながりの促進、島嶼国(とうしょこく)支援など、様々な県の外交の可能性が提言には含まれている。
日本本土には、沖縄を、「基地に反対ばかりして政治を硬直させ続ける頑固者」と思っている人がいたりはしないだろうか。
しかし、それは大きな間違いである。
基地は日本の防衛のためにあり、日本への脅威が増しているから基地の強化が必要だ、とされている。
「そうか、であれば、基地負担を減らすには、地域の緊張緩和に努め、脅威を低減させていく努力が必要だ」
硬直化させるどころか、前を向き、クリエイティブに、自ら問題解決に向けた流れを作り出そうと一歩も二歩も踏み出しているのが沖縄なのである。
軍事予算の倍増や敵基地攻撃能力を含む防衛装備品の増強ばかりが進められるこのご時世において、沖縄ほど真剣に外交を実践しようとしている存在は、日本国内を見渡してもまず見つけることができない。沖縄が目指す地域外交の姿勢は、日本本土の他の自治体はもちろんのこと、日本政府を含めた日本全体の外交の指針となりうるものだ。
希望
さらに特筆すべきは、沖縄では多くの若者が声を上げ、社会の中で存在感を増しているということである。沖縄戦を直接語れる世代が減っていく中、平和学習の取り組みを引き継ぎ、本土から修学旅行に来た高校生に戦争体験を語り継ぐ団体が立ち上がり、また、台湾や中国との対話を定期的に行うプロジェクトが若い世代も多く参加して始まった。
日本本土では平和の問題に限らず、社会問題に声を上げる若い世代の姿が年々限られてきているが、それとはきわめて対照的である。
幾つもの苦難が加わった歴史にあっても、少しでも良い未来のために工夫を重ねながらしなやかに活動する沖縄のその様は、閉塞的な本土社会に比べ、むしろ希望すら感じさせる。
埋め立て開始の翌日に私は玉城知事とのシンポジウムに登壇した。その後、知事から聞いた言葉が頭から離れない。
「長い長い戦いがまた新たに始まったという気持ちを持っています。そのためには、気を張ってばかりではなく、飲みながら意見を交換し、笑いながら、歌を歌いながら、ガッとかかる時にはガッとかかる。この連帯感が私たちの気持ちのつながりをキープできる」
沖縄の戦いはまだまだ終わらない。
これこそ「積極的平和主義」だろう。
わたしも応援する。