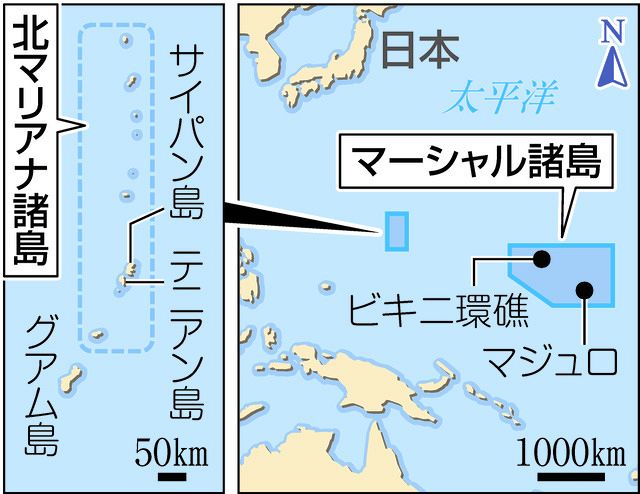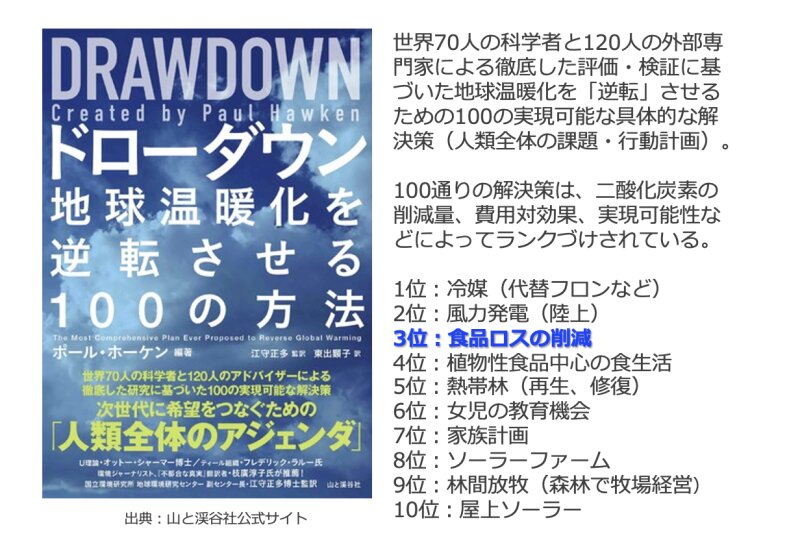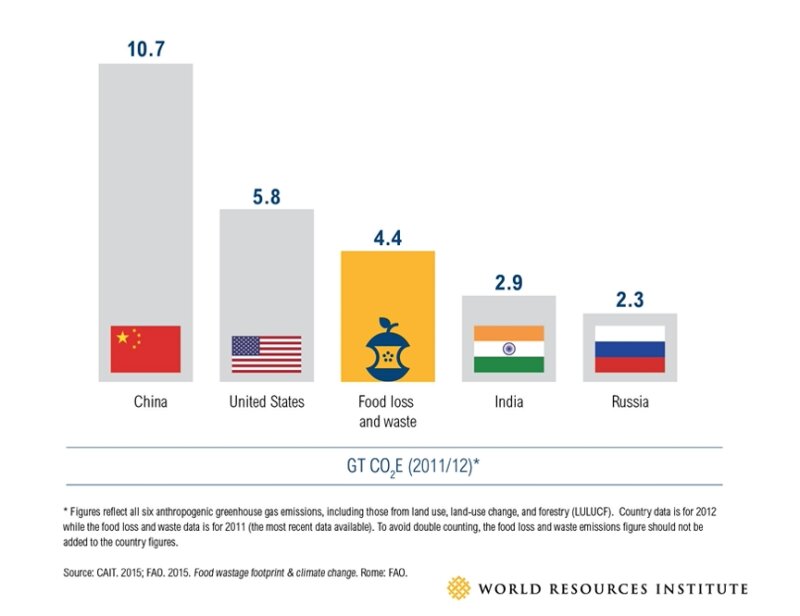ジャニー氏性加害 報告書から見る
「しんぶん赤旗」2023年8月31日
メディアの沈黙で隠蔽体質強化
ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川前社長による性加害問題を調査した「再発防止特別チーム」が公表した調査報告書には、被害のなまなましい実態が記されていました。夢を持った少年たちが苦しめられた背景に何があったのか。報告書から見えてきたものは―。(小林圭子)
「口腔性交をされ、性経験もなかったので体が硬直したが、これがジャニーズJr.(以下Jr.)としての洗礼だと思った(中学2年頃)」「『YOUはソロでデビューさせるから』と言われ、直接陰部を触られた(中学2年時)」「体や性器を触られ口腔性交された。翌日、1万円を渡された(中学3年時)」。ヒアリングでの被害者の声です。
ジャニー氏は自宅や合宿所といった“密室”で、当時小学生から高校生まで(多くは中学生)の未成年者に対し、性加害を繰り返していました。性加害は1950年代から2010年代半ばまで確認されており、「少なく見積もっても数百人の被害者がいる」という複数の証言が得られたとしています。
Jr.の間では「ジャニー氏から性加害を受ければ優遇され、拒めば冷遇されるという認識が広がっていた」といいます。被害を周りに相談できずうつ病になる人も。フラッシュバックや自殺願望、性依存症など加害の影響が多く出されています。
「無制約の専権」
ジャニー氏は、Jr.の誰をどのように売り出すかというプロデュースについて、ほぼ「無制約の専権」を有し、採用からデビューなどまで「Jr.の生殺与奪の権を握る」絶対的な立場にありました。
一方、事務所は採用時に契約を締結するなどはなく、Jr.の顔も人数も正確に把握していなかったというずさんな管理でした。Jr.が接するおとなは基本的にジャニー氏と振付師、マネジャーのみという状況だったといいます。
事務所スタッフに被害を訴えても「デビューしたければ我慢するしかない」と言われた被害者も。報告書は「事務所は何らの対応もしないどころか、むしろ辛抱させるしかないと考えていたふしがある」と指摘し、「被害拡大を招いた大きな要因となった」としています。
強い批判出れば
ジャニー氏の性加害について、1965年ごろに訴訟が起こされたり、過去にいくつかの週刊誌が報じたりしたものの、マスメディアが正面から取り上げなかったことは、「極めて不自然な対応」だと言及しています。
ジャニーズ事務所が日本でトップのエンターテインメント企業であり、ジャニー氏の性加害を報道すれば、所属タレントを自社のテレビ番組や雑誌に起用できなくなるのではないかという危惧から、性加害の報道を控えていたのではないかと指摘。「マスメディアの沈黙」により、事務所が性加害の実態を調査するなど自浄能力を発揮することもなく「隠蔽(いんぺい)体質を強化していった」と断じています。
会見(29日)で調査チーム座長の林真琴弁護士はこう指摘しました。「マスメディアから強い批判が出ていれば、ジャニーズ事務所も対応をかえたかもしれない」
⁂ ⁂ ⁂
ジャニーズ性加害問題何をいまさら? テレビ各局“手のひら返し”の茶番「癒着はまごうことなき事実」
日刊ゲンダイ 2023/08/31
ジャニーズ性加害問題を巡る「再発防止特別チーム」の提言を受け、テレビ各局が、ジャニーズ事務所に対する過去の報道姿勢について反省のコメントを発表している。報告書では、この問題に対する「マスメディアの沈黙」が被害拡大につながり、さらに多くの被害者を出すことになったと断罪。2000年初頭のジャニーズ事務所と文芸春秋の裁判についても、「訴訟結果さえまともに報道されていないようであり、報道機関としてのマスメディアとしては極めて不自然な対応をしてきたと考えられる」とある。
29日までに、テレビ各局はほぼ横並びでコメントを発表した。
「『マスメディアが正面から取り上げてこなかった』などの指摘を重く受け止め、性加害などの人権侵害は、あってはならないという姿勢で報道してまいります」(日本テレビ)、「報告書に記されたマスメディアの過去の報道に関するご指摘を真摯に受け止めております。性加害が決して許されないことは当然です。当社としてもあらゆる人権侵害を防ぐべく対処していく所存です」(フジテレビ)などと発表。TBS、テレビ朝日、テレビ東京もほぼ同じ内容で、“指摘を真摯に受け止め”“人権重視に努める”のオンパレードだ。
NHKに至っては
「性暴力について『決して許されるものではない』という毅然とした態度でこれまで臨んできたところであり、今後もその姿勢にいささかの変更もありません」
とこれまでのズブズブの関係はなかったかのように開き直りとも取れるコメントである。
「癒着はまごうことなき事実」
先日の国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会の会見でも、来日した専門家は「日本のメディア企業は数十年にもわたり、この不祥事に加担した」と非難し“人権デュー・デリジェンス”の必要性を訴えていた。
かつて裁判の契機となった、1999年の「週刊文春」の“ジャニーズホモセクハラキャンペーン”取材で、中心メンバーのひとりだったジャーナリストの二田一比古氏はこう話す。
「正直、何をいまさらと思わざるを得ませんね。なんであの時、やらなかったのかと。大手マスコミが自粛と忖度でジャニーズ事務所と癒着してきたのはまごうことなき事実です。テレビ局と同時に、御用メディアと化していたスポーツ新聞なども声明を出してもいいんじゃないですか。それと“反省”するのはいいですが、今後、具体的にどうしていくのかがわからない。取引先のトップが詐欺事件などの重大な犯罪に手を染めていたとして、それでもその企業と取引を続けるのですか、と。業界全体の体質改善を望みます」
今まで性加害の存在を知っていながら放置してきた大メディアの今さらながらの“声明”には、鼻白むばかりである。
ひどい!
一人や二人、数人というレベルではない。
数百人の子どもたちだ。
「権力」をかさに・・・
NHKがひどい。
もう一つの記事も紹介しておこう。
わたしは、竹内まりやの歌が好きでよく聞いていたが・・・・
松尾潔氏、山下達郎から離れるファンに呼びかけ「お考えを改める旨を表明したら…」
日刊スポーツ 2023.08.30
音楽プロデューサー松尾潔氏(55)が30日までにX(旧ツイッター)を更新。自身と“因縁”のあるシンガー・ソングライター山下達郎(70)と竹内まりや(68)夫妻のファンに向け、メッセージをつづった。
松尾氏は、ジャニーズ事務所がジャニー喜多川前社長(19年に死去)の性加害問題をめぐり、同事務所が設置した「外部専門家による再発防止特別チーム」(座長・林真琴前検事総長)が作成した、同事務所のガバナンス上の問題点の把握及び再発防止策の策定・提言に関する調査報告書を公表したことに言及。「再発防止特別チームの会見を受けて、山下達郎・竹内まりやご夫妻を責めたてる旨をぼくに訴えてくる方が多くて困惑しています」と明かし、「きっとおふたりとも会見内容に胸を痛めておられると思いますし、お考えを改めて正式に声明をお出しになるはずです。それまでは非難を控えて来週のサンソンを待ちませんか」と呼びかけた。
続く投稿では、「誤解を恐れずにあえて言いますが、山下達郎・竹内まりやご夫妻がお考えを改める旨を表明したら、先月以来おふたりの音楽から遠ざかっている長年のファンのみなさんも、どうか彼らを再び迎え入れて欲しいのです」との思いをつづり、「音楽が備えている自由の精神とは、本来そういうものでしょう?」と理解を求めた。
松尾氏は7月、15年間在籍した芸能事務所スマイルカンパニーとの契約が終了したことをXで報告し、「私がメディアでジャニーズ事務所と藤島ジュリー景子社長に言及したのが理由です。私をスマイルに誘ってくださった山下達郎さんも会社方針に賛成とのこと、残念です」と理由を明かして物議をかもした。
その後、山下は冠ラジオ番組「山下達郎のサンデー・ソングブック」(日曜午後2時)の番組内で、ジャニーズ事務所との関係について「自分は、あくまでいち作曲家、楽曲の提供者」とした上で、「ジャニーズ事務所の内部事情など全く、あずかり知らぬこと。ましては性加害の事実について、私が知る術は全くありません」と話した。松尾氏は山下の発言を「残念」とした上で、「絶大な影響力のあるカリスマミュージシャンに、子供たちが不幸にも性犯罪や性暴力の被害者になった時、『声を上げてもムダ』と諦めずにすむ社会を一緒に目指しましょうよ、とご提案しているのです」と、自らの思いを訴えていた。