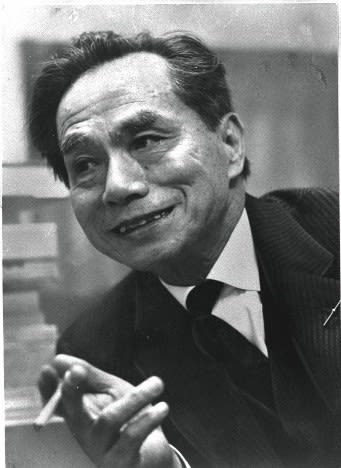仁藤夢乃“ここがおかしい ”第21回 2017/11/29
神奈川県座間市で起きた殺人事件
2017年10月、神奈川県座間市のアパートで9人の遺体が見つかった。死体遺棄容疑で逮捕された27歳の容疑者の男は、SNSに「死にたい」と書き込んだ女性たちに近づき、自宅に誘い入れて殺害したという。ツイッターのアカウントで「首吊り士」などと名乗って自殺志願者を探し、「楽にしてあげる」と言い、別のアカウントでは自身にも自殺願望があるかのようなふりをして、心中を持ちかけて女性たちに近づいた(17年11月6日、毎日新聞「神奈川・座間の9遺体:発覚から1週間 殺人容疑で追及『死にたい人いなかった』」)。
私は年間100人以上の生きづらさを抱えた少女たちと関わっているが、今回のように、理解者のふりをして孤独感や不安を抱える人の弱みにつけ込む手口を数多く見てきた。私とつながった中高生たちも、「家にいられない時、頼れるのは買春者や売春斡旋業者など、そういう人しかいなかった。頼れるのはその人だけだった」と話す。
この事件が起きた時、「あの子が被害者になっていないか」と思い浮かぶ顔がいくつもあった。誰もが被害者になり得る、そういう意味では特別ではない事件だと思った。
「死にたい」とつぶやくのはなぜか
この事件について、「被害者はなぜ身近な人に助けを求めなかったのか?」「どうして正体の分からない男について行ったのか?」という声がある。でも、死にたい気持ちを抱えている人は、すでに孤立していて、まわりには「助けて」と言えない状況にあることがほとんどで、だからこそ死にたいと感じるほどの状況に追い込まれているのではないかと思う。
以前、本連載で対談した精神科医の松本俊彦先生もおっしゃっていたように「死にたい」という言葉は、死にたいほどつらい気持ちを分かってほしいというSOSだ(17年6月22日「対談! 10代のあなたへ 第6回」)。容疑者も、「本当に死にたいと言う人はいなかった」と供述しているように、死にたいという気持ちを書き込む人は、本当はこの状況をなんとかしたい、誰かに聞いてほしいと思っている。しかし今の日本社会では、死にたいという気持ちを口にすれば「そんなこと言っちゃダメ」「命を粗末にしないで」「自分をもっと大事に」などと言われ、責められてしまうことも少なくない。そんな中で被害者は容疑者のことを、唯一話を聞いてくれる存在だと思ったのかもしれないと、私は想像する。
容疑者と接点のある、次の被害者になっていたかもしれない女性も、容疑者のことを「優しくしてくれた」と話していた。ネットで知り合ったばかりの正体不明の男でも、話を聞いて、理解者であるかのような発言をしたというその事実だけで「優しい」と感じてしまうほど、他に聞いてくれる人がいなかったのではないか。被害者には女子高生も数人含まれていた。
寄り添える人がいないという現実
あるインターネットテレビ番組では「死にたいと書き込むのはかまってちゃん」という女子大生のコメントが取り上げられた。さらに、容疑者や被害者が複数のアカウント(ID)を使っていたことから「今は誰でもSNSで複数のアカウントを作れるから、一億総多重人格社会だ」などというお笑いタレントの発言も放送された。
かつて「多重人格(障害)」と呼ばれた精神疾患は、今は解離性同一性障害と言い、複数のアカウントを使うこととその疾患による障害とは必ずしも一致しないのに、誤解を生む発言を簡単にしてしまうことにも憤りを感じた。
友だちや親に対して、また職場で見せる顔が違うのと同じように、SNSのつながりにも付き合いや社会がある。友だちが見ているかもしれないアカウントでは、書けないこともある。「死にたい」と書き込めば、「かまってちゃんなんじゃないの?」とか、「本気じゃないくせに」とか言われ、白い目で見られることもある。だから、そこにも気を遣う。
学校の友だちやアルバイト仲間に見せる「リア垢」(リアルな関係性のある人向けに発信するアカウント)、「趣味垢」(趣味について書き込むアカウント。同じ趣味の人とつながったり、リア垢で趣味のことをたくさん書いて周囲に引かれるリスクをなくすために作る)、「病み垢」(つらい気持ちなど、なかなか顔の見える関係性では言いにくいことを吐き出すアカウント)というように、様々なアカウントを使い分けている人は少なくない。
容疑者は「さみしくて話し相手がほしそうな女性を誘った」(17年11月21日、読売新聞「座間9遺体『話し相手求める人』標的」)という。そして「身の上話を少ししてから、隙を突いて殺害した」と供述している(17年11月20日、東京新聞「座間9遺体 23歳殺害容疑で再逮捕」)。寄り添える人が圧倒的に不足している中で、死にたい気持ちを抱えた人が狙われたのが今回の事件だと思う。
SNSを規制すれば解決するのか?
この事件をきっかけに「死にたい」などの書き込みを不適切なものとして削除させるなど、SNSを規制する動きも始まっているが、これも私には違和感がある。「SNSは危ない!」というようなメディアによる発信や、「ツイッターを使うルールを子どもと決めましょう」といった呼びかけは、大人が理解し、納得しやすい取り上げ方だというだけで、問題の本質を捉えているとは思えない。
確かにSNSには、危険な大人がたくさん存在し、人目につかないところで接近してくることがある。危ないこともあるけれど、大切なのは、危ないと気づいたり、困ったと感じた時に、誰に、どのようにして頼ればいいかを教えることだ。それをしないまま、「危ないからルールを決めましょう!」と言うのは、大人が安心したいだけであまり意味がない。
それでも「ルールを決めましょう!」的な講演は、保護者の方にウケるらしい。対策ができると思えるし、どうすればいいか分かった気になれるから、受け入れられやすい話なのだろう。そして、ルールを守れなかったら子どもを責める。そんなことばかりしていたら、子どもは困った時、「怒られるかな、迷惑がられるかな、自分が悪かったし」と思って助けを求められなくなる。
大切なのは、ルールを破ってしまった時でも、信頼して話せる、頼れる大人がいることだ。子どもを守るのは、ルールではなくて関係性だ。保護者や教員、地域の大人、子どもに関わるすべての皆さんに、それを忘れないようにしてほしい。
SNSの規制よりケアの充実を
SNSで同じ悩みを抱える人とつながって、励まし合いながらなんとか生き延びてきた人や、SNSでのつながりから女子高校生サポートセンターColabo(コラボ)につながってくれた人もいる。そのため「死にたい」と書き込むこと自体が悪いことであるかのような扱いを受けると、ますます当事者を追い詰めることにもなる。
規制以上に必要なのはむしろ、死にたいほどつらい気持ちを分かってほしいというSOSを発信している子たちへのケアの充実だ。SNSでも、顔の見える関係でも、SOSをキャッチして支えることができる大人が増えること。危険につながる以外の選択肢を増やし、死にたい気持ちを話せる人、否定しないで寄り添う人が、顔が見える関係性の中に増えることだと私は思う。




















 (ちなみに、カラー写真です)
(ちなみに、カラー写真です)