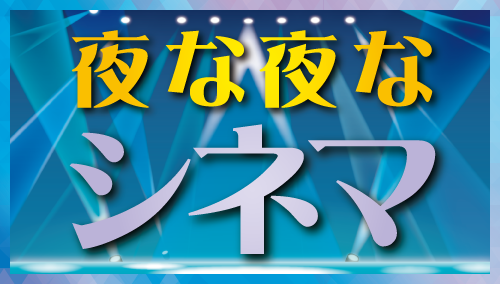『プロミスト・ランド』(原題:Promised Land)
監督:ガス・ヴァン・サント
出演:マット・デイモン,ジョン・クラシンスキー,フランシス・マクドーマンド,
ローズマリー・デウィット,ハル・ホルブルック,ベンジャミン・シーラー他
前述の『バルフィ!人生に唄えば』を観る前は晴れていたのに、
TOHOシネマズ梅田のエレベーターから見える景色は嫌な感じ。
北摂は嫌な天気どころか暴雨らしく、箕面市で避難指示が出ている場所があるらしい。
同窓会に参加している場合ではないのかもしれないけれども、
わが家は父のお墨付き、帰ることもないわと地下街を通って大阪ステーションシティシネマへ移動。
ガス・ヴァン・サント監督の作品で、マット・デイモン脚本・主演といえば、
すぐに思い出されるのが『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』 (1997)。
共演だったロビン・ウィリアムズの冥福を祈ります。
あのときはベン・アフレックとの共同脚本、本作はジョン・クラシンスキーと共同です。
ガス・ヴァン・サント監督の作品を眺めてみると、
『マイ・プライベート・アイダホ』(1991)、『エレファント』(2003)、『永遠の僕たち』(2011)など、
さめざめとした陰鬱さを感じる作品と、
『グッド・ウィル・ハンティング』や『小説家を見つけたら』(2000)のなど、
温かみを感じる作品があるような。
本作は後者で、私はこっちの監督のほうが好きです。
エネルギー開発の大企業グローバル社の幹部候補社員スティーヴ(マット・デイモン)は、
女性社員スー(フランシス・マクドーマンド)とともにペンシルヴェニア州の田舎町マッキンリーを訪れる。
農業しかなくて不況に喘ぐ町に、良質の天然ガスが埋もれている。
グローバル社は同業他社を出し抜いて、ガスの採掘権を得たい。
その目的を果たすため、スティーヴとスーは地主たちを説得すべくやってきたのだ。
子どもたちにちゃんとした教育を受けさせるためには金が要る。
グローバル社と契約を交わせば、寝ていても金が入る。
そう言えば、町ごと買収することなどたやすいはず。
地元民に壁をつくられぬよう、彼らを真似たダサい恰好で家庭を訪問。
楽勝モードで契約は進み、晩は飲み屋で歓迎を受けて酒を酌み交わす。
ところが翌朝、地元民を集めた説明会の席で、
老いた科学の教師フランクが水圧破砕という採掘法の危険性を訴え、状況が一転。
1週間後に採掘の可否を住民投票にかけることになってしまう。
しかもそこへ環境活動家ダスティン(ジョン・クラシンスキー)が現れ、
水圧破砕の恐ろしさを説きはじめたものだから、
スティーヴたちは大苦戦を強いられることになり……。
アイオワ州育ちのスティーヴは、自分が育った町が荒廃するのを目の当たりにした経験があり、
金を落とすことこそがマッキンリーを救うことになると信じています。
彼が複数の住民から「いい奴だ」と言われ、自身も「悪人ではない」と言うように、
悪徳大企業の口八丁なだけの社員ではない印象を最初に持ちます。
それでも、ガス採掘こそが町を救う善行なのだと考えていますから、
契約を取るために調子のいい話もすれば嘘もつきます。
観客は、きっと彼が心を入れ替えるのだろうと想像するわけですが、
はたしていつ、何をきっかけに彼が自分の行動に疑問を抱くのか。
そこに興味を引っ張られるとともに、地元の女性との恋愛も適度にからみ、とても面白い。
看板に偽りがあってはいけない。
そう思った瞬間のスティーヴの表情が秀逸でした。
上手い脚本に出逢えて幸せです。
監督:ガス・ヴァン・サント
出演:マット・デイモン,ジョン・クラシンスキー,フランシス・マクドーマンド,
ローズマリー・デウィット,ハル・ホルブルック,ベンジャミン・シーラー他
前述の『バルフィ!人生に唄えば』を観る前は晴れていたのに、
TOHOシネマズ梅田のエレベーターから見える景色は嫌な感じ。
北摂は嫌な天気どころか暴雨らしく、箕面市で避難指示が出ている場所があるらしい。
同窓会に参加している場合ではないのかもしれないけれども、
わが家は父のお墨付き、帰ることもないわと地下街を通って大阪ステーションシティシネマへ移動。
ガス・ヴァン・サント監督の作品で、マット・デイモン脚本・主演といえば、
すぐに思い出されるのが『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』 (1997)。
共演だったロビン・ウィリアムズの冥福を祈ります。
あのときはベン・アフレックとの共同脚本、本作はジョン・クラシンスキーと共同です。
ガス・ヴァン・サント監督の作品を眺めてみると、
『マイ・プライベート・アイダホ』(1991)、『エレファント』(2003)、『永遠の僕たち』(2011)など、
さめざめとした陰鬱さを感じる作品と、
『グッド・ウィル・ハンティング』や『小説家を見つけたら』(2000)のなど、
温かみを感じる作品があるような。
本作は後者で、私はこっちの監督のほうが好きです。
エネルギー開発の大企業グローバル社の幹部候補社員スティーヴ(マット・デイモン)は、
女性社員スー(フランシス・マクドーマンド)とともにペンシルヴェニア州の田舎町マッキンリーを訪れる。
農業しかなくて不況に喘ぐ町に、良質の天然ガスが埋もれている。
グローバル社は同業他社を出し抜いて、ガスの採掘権を得たい。
その目的を果たすため、スティーヴとスーは地主たちを説得すべくやってきたのだ。
子どもたちにちゃんとした教育を受けさせるためには金が要る。
グローバル社と契約を交わせば、寝ていても金が入る。
そう言えば、町ごと買収することなどたやすいはず。
地元民に壁をつくられぬよう、彼らを真似たダサい恰好で家庭を訪問。
楽勝モードで契約は進み、晩は飲み屋で歓迎を受けて酒を酌み交わす。
ところが翌朝、地元民を集めた説明会の席で、
老いた科学の教師フランクが水圧破砕という採掘法の危険性を訴え、状況が一転。
1週間後に採掘の可否を住民投票にかけることになってしまう。
しかもそこへ環境活動家ダスティン(ジョン・クラシンスキー)が現れ、
水圧破砕の恐ろしさを説きはじめたものだから、
スティーヴたちは大苦戦を強いられることになり……。
アイオワ州育ちのスティーヴは、自分が育った町が荒廃するのを目の当たりにした経験があり、
金を落とすことこそがマッキンリーを救うことになると信じています。
彼が複数の住民から「いい奴だ」と言われ、自身も「悪人ではない」と言うように、
悪徳大企業の口八丁なだけの社員ではない印象を最初に持ちます。
それでも、ガス採掘こそが町を救う善行なのだと考えていますから、
契約を取るために調子のいい話もすれば嘘もつきます。
観客は、きっと彼が心を入れ替えるのだろうと想像するわけですが、
はたしていつ、何をきっかけに彼が自分の行動に疑問を抱くのか。
そこに興味を引っ張られるとともに、地元の女性との恋愛も適度にからみ、とても面白い。
看板に偽りがあってはいけない。
そう思った瞬間のスティーヴの表情が秀逸でした。
上手い脚本に出逢えて幸せです。