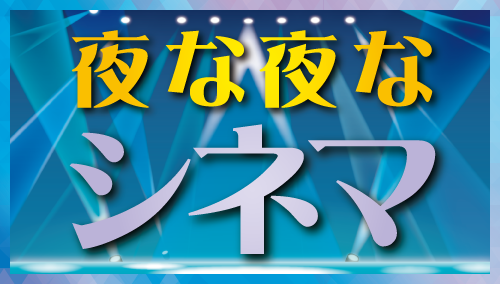『ブレイキング・ニュース』(原題:大事件)
監督:ジョニー・トー
出演:ケリー・チャン,リッチー・レン,ニック・チョン他
2004年の香港/中国作品。
日本公開は昨年末、今月初めにDVD化されたところです。
監督は『ザ・ミッション 非情の掟』(1999)のような
超硬派なヤクザ映画を撮るかと思えば、
金城武主演の『ターンレフト ターンライト』(2002)のような
ファンタジックな作品も。どちらも好きですが、
この監督の作品の醍醐味は「男泣き」。
香港の市街地の雑居ビル前。
若くて無鉄砲な警部補とその相棒が張り込み中。
その日、銀行を襲撃するであろう強盗団を捕まえるためだ。
ところが、ビルから出てきた強盗団が車に乗り込もうとしたとき、
事情を知らない交通巡査が駐車違反の取り締まりにやってくる。
交通巡査に邪魔されぬよう、別の張り込み中の刑事が画策するが、
異変に気づいた強盗団が発砲。警察との銃撃戦となる。
その場に偶然居合わせたTV局がカメラを回し、
強盗団に命乞いする警官の姿が報道される。
そのうえリーダーのユアンを含む4名を取り逃がした警察は
市民の信頼を失って非難の的。
やがてユアンらが高層アパートに籠城中との情報が入る。
警察は名誉回復のため、強盗団逮捕劇を生中継することに。
マスコミが押し寄せ、600万人の市民が見つめるなかで、
メディア戦略の発案者である組織犯罪課のレベッカが指揮を任されるが……。
緊迫感溢れる90分は携帯とパソコンを駆使した「ショー」。
ユアンらが籠城する一室に、同じアパートに住む殺し屋2名が転がり込み、
一触即発の雰囲気に。手を組むのが得策だと双方は考えます。
私がとても好きだったのは、その一室で食卓を囲むシーン。
腹が減っては戦はできぬと、ユアンが台所に立ちます。
そこへ手伝いにやってくるのは殺し屋のチュン。
初対面のユアンとチュンが一緒に料理を始めると、
ふたりとも実は食べることと料理が大好きで、
自分の店を持つのが夢であることが明らかにされます。
葱、茄子、胡瓜、肉、魚が手際よく切られ、中華鍋で跳ねる楽しげな油の音。
明日の生死はわからない状況で食卓に並べられた皿の数々を前にして、
人質のタクシー運転手が「ええい、このさい」と開ける、とっておきの酒。
そして、幼い子どもたちに言うには、「おまえたち、食えよ。
殺し屋さんと強盗さんの料理だ。滅多に食えんぞ」。
このシーンがあるからこそ、最後にいきる男泣き。
私、ホンマは男やろか。
監督:ジョニー・トー
出演:ケリー・チャン,リッチー・レン,ニック・チョン他
2004年の香港/中国作品。
日本公開は昨年末、今月初めにDVD化されたところです。
監督は『ザ・ミッション 非情の掟』(1999)のような
超硬派なヤクザ映画を撮るかと思えば、
金城武主演の『ターンレフト ターンライト』(2002)のような
ファンタジックな作品も。どちらも好きですが、
この監督の作品の醍醐味は「男泣き」。
香港の市街地の雑居ビル前。
若くて無鉄砲な警部補とその相棒が張り込み中。
その日、銀行を襲撃するであろう強盗団を捕まえるためだ。
ところが、ビルから出てきた強盗団が車に乗り込もうとしたとき、
事情を知らない交通巡査が駐車違反の取り締まりにやってくる。
交通巡査に邪魔されぬよう、別の張り込み中の刑事が画策するが、
異変に気づいた強盗団が発砲。警察との銃撃戦となる。
その場に偶然居合わせたTV局がカメラを回し、
強盗団に命乞いする警官の姿が報道される。
そのうえリーダーのユアンを含む4名を取り逃がした警察は
市民の信頼を失って非難の的。
やがてユアンらが高層アパートに籠城中との情報が入る。
警察は名誉回復のため、強盗団逮捕劇を生中継することに。
マスコミが押し寄せ、600万人の市民が見つめるなかで、
メディア戦略の発案者である組織犯罪課のレベッカが指揮を任されるが……。
緊迫感溢れる90分は携帯とパソコンを駆使した「ショー」。
ユアンらが籠城する一室に、同じアパートに住む殺し屋2名が転がり込み、
一触即発の雰囲気に。手を組むのが得策だと双方は考えます。
私がとても好きだったのは、その一室で食卓を囲むシーン。
腹が減っては戦はできぬと、ユアンが台所に立ちます。
そこへ手伝いにやってくるのは殺し屋のチュン。
初対面のユアンとチュンが一緒に料理を始めると、
ふたりとも実は食べることと料理が大好きで、
自分の店を持つのが夢であることが明らかにされます。
葱、茄子、胡瓜、肉、魚が手際よく切られ、中華鍋で跳ねる楽しげな油の音。
明日の生死はわからない状況で食卓に並べられた皿の数々を前にして、
人質のタクシー運転手が「ええい、このさい」と開ける、とっておきの酒。
そして、幼い子どもたちに言うには、「おまえたち、食えよ。
殺し屋さんと強盗さんの料理だ。滅多に食えんぞ」。
このシーンがあるからこそ、最後にいきる男泣き。
私、ホンマは男やろか。