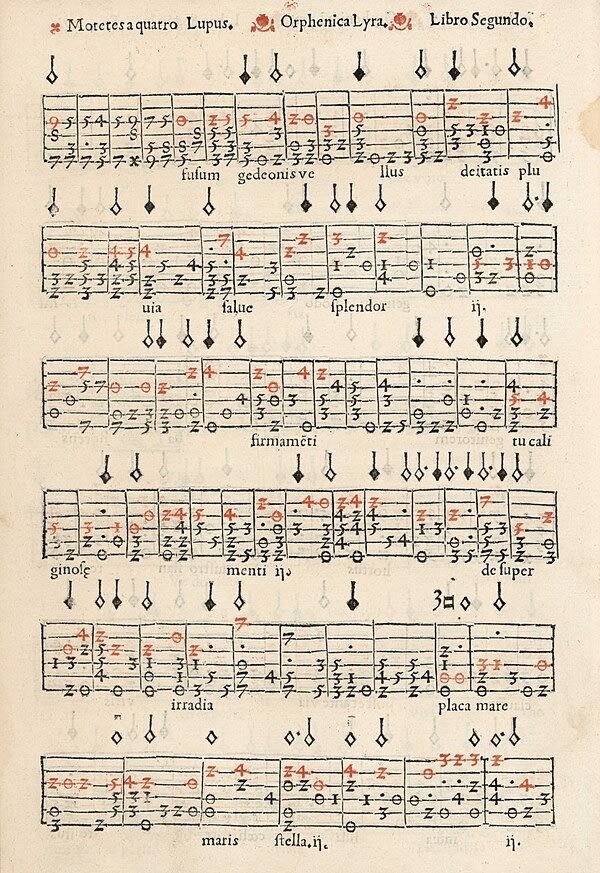4月29日は今田聡美さんのリサイタルてした。


ピアソラのタンゴエチュードから2曲。No.3No.4。



(リスト音楽院で1920年から1924年にかけてバルトークの指導を受けたピアニスト、イムレ・ワイスハウス(1905 - 1987年)は、1933年以降はフランスに活動の拠点を移し「ポール・アルマ」の名前で現代音楽や、バルトークに影響された民俗音楽を基にした作品を書く作曲家としても活動しました。)による編曲は、原曲第6番のバラードを省略し、いくつかの曲でくり返しを付けたりフルート・パートに変奏させている他、曲の本質に触れる変更はしていません。
ムラマツリサイタルホールでされました。
今田さんは伊藤公一セミナーで知り合ったセミナー仲間です。
素直で美しい音色は出会った頃から変わりません。
ピアノは造座千晴さん。
ゴーベールのロマンス。
一曲目というのに硬いところがなく、フレンチのキラキラした感じもあり素晴らしかった!

エラートの シンフォニッシユ カンツォーネ
コンクールの予選でよく使われる曲で、今田さんもこの曲で受けたことがあるそうです。
さすがによくこなれていて、素晴らしかったです。
今回はチェロ成川昭代さんも一緒です。
バッハのフルートソナタBWV1035は、ピアノもチェンバロに変えてチェロとの演奏でした。
優しい音色でフルートトラヴェルソのような感じに聞こえました。

ピアソラのタンゴエチュードから2曲。No.3No.4。
この優しい音色でどう演奏するのか?
興味がありましたが、どうしてなかなか、大人の雰囲気で、柔らかい良い意味で色気のあるピアソラでした。
タファネルのアンダンテ パストラルはゆっくりしたところはたっぷりと歌い、速いパッセージは丁寧で生き生きしてとても美しい演奏でした。
ムチンスキーは、今回のプログラムで一番現代に近い作曲家で、少し難解ですが、とてもお好きと言うことで、音色も近代に合わせて変化。
少し尖った感じで吹かれていて、幅広い表現力を感じました。

アンコールはチェロとピアノも出演して、ヴィヴァルディの「ごしきひわ」の第2楽章でした。最後にとっても癒やされました。
今回は曲を紹介したり、直接マイクで話しかけられるやり方でされました。
クラッシック音楽は、黙って出てきて黙って演奏して黙って帰るというスタイルが定番ですが、易しい解説などもあって、グッと客席と奏者の距離が近づいた感じでいいなと思いました。
話し方も親しみやすくて楽しかったです。
今田聡美さんのYouTubeチャンネル
さとみんチャンネル
肩のこらない楽しい曲を取り上げたり、アレンジ楽譜も売っています。
昨年3月のリサイタル最後の曲をアップされていました。
ベラ バルトーク(1881-1945年)ルーマニア スンニコラウ マレ生まれ、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク没

は、音楽院を卒業してから後輩コダーイと共に各地の民謡や民族音楽を収集しその方面の研究に大きな足跡を残しています。
作品のなかにその素材を活用し、西欧的な音楽伝統に留まらない独自の音楽を築きました。
ポール アルマ編曲版は、彼が民族音楽を用いた一連のピアノ曲のなかで最も重要な曲集の一つである 「15のハンガリー農民歌」 を原曲としています。
ポール アルマ

(リスト音楽院で1920年から1924年にかけてバルトークの指導を受けたピアニスト、イムレ・ワイスハウス(1905 - 1987年)は、1933年以降はフランスに活動の拠点を移し「ポール・アルマ」の名前で現代音楽や、バルトークに影響された民俗音楽を基にした作品を書く作曲家としても活動しました。)による編曲は、原曲第6番のバラードを省略し、いくつかの曲でくり返しを付けたりフルート・パートに変奏させている他、曲の本質に触れる変更はしていません。
使用された原曲民謡(フルート版は6番は無い)
1.Rubato (Megkötöm lovamat - 私は馬を繋ぐ)
2.Andante (Kit virágot rózsám adott - 私のバラの花は誰に捧げたのか)
3.Poco rubato (Aj, meg kell a búzának érni -ああ、麦は熟したに違いない)
4.Andante (Kék nefelejcs ráhajlott a vállamra - 肩には青い忘れな草)
5.Scherzo. Allegro (Feleségem olyan tiszta - 私の妻はとても純粋です)
6.Ballade(Tema con variazioni). Andante - Poco adagio - Più andante - Maestoso (Angoli Borbála - アンゴリ・ボルバーラ)
ベーケーシュ県のヴェーステー(Vésztő)において収集された歌「アンゴリ・ボルバーラ(Angoli Borbála)」を変奏曲として扱いました。
歌詞の内容は、結婚前に恋人の子を身ごもった少女アンゴリ・ボルバーラが、それを恥とする母によって死に追いやられ、それを知らされた恋人も彼女を追って自殺するというもの。
バルトークは妻・マールタに宛てた手紙の一つにおいて特別な言及をしています。
「...7つのハンガリーの歌に和声を付け終えた。その中にはエクレシュ・ローザ(Ökrös Róza)の有名なアンゴリ・ボルバーラもある。是非、これを聞いて欲しい、というのも、こんなハンガリー語で、それに加えてアルフェルドのちょうど中心地で、そして更にそれに加えて、7/8の拍節で、本当の感動を聞く事ができるのだから...」(1917年の夏の終わりに。)
7.Allegro (Arra gyere, amőrre én - 私が行くところへ来てください)
8.Allegretto (Fölmentem a szilvafára - 梅の木に登った)
9.Allegretto (Erre kakas, erre tyúk - こっちの雄鶏、あっちの雌鶏)
10.L'istesso tempo(quasi trio) (Zöld erdőben a prücsök - コオロギの森)
11.Assai moderato (Nem vagy legény - あなたは独身じゃないから)
12.Allegretto (Beteg asszony, fáradt legény - 病める女、疲れる男)
13.Poco più vivo - Allegretto (Sári lovam a fakó - 私の馬サーリは色褪せた)
14.Allegro (Ësszegyűltek, ësszegyűltek az izsapi lányok - イズサップの女の子たちが、集まっている、集まっている)
15.Allegro 歌詞のない旋律。バグパイプによって演奏されました。