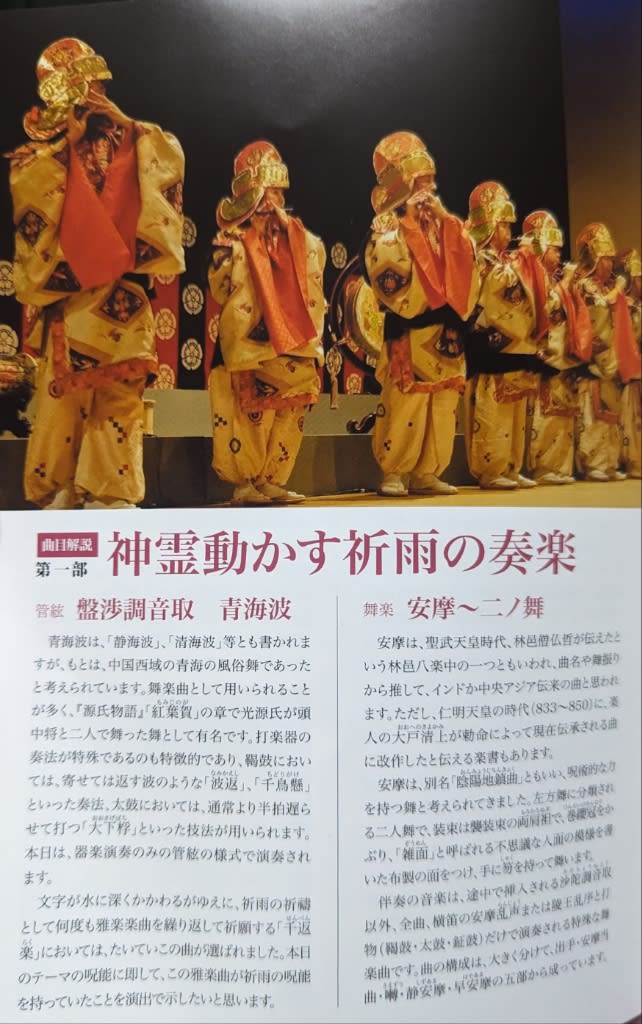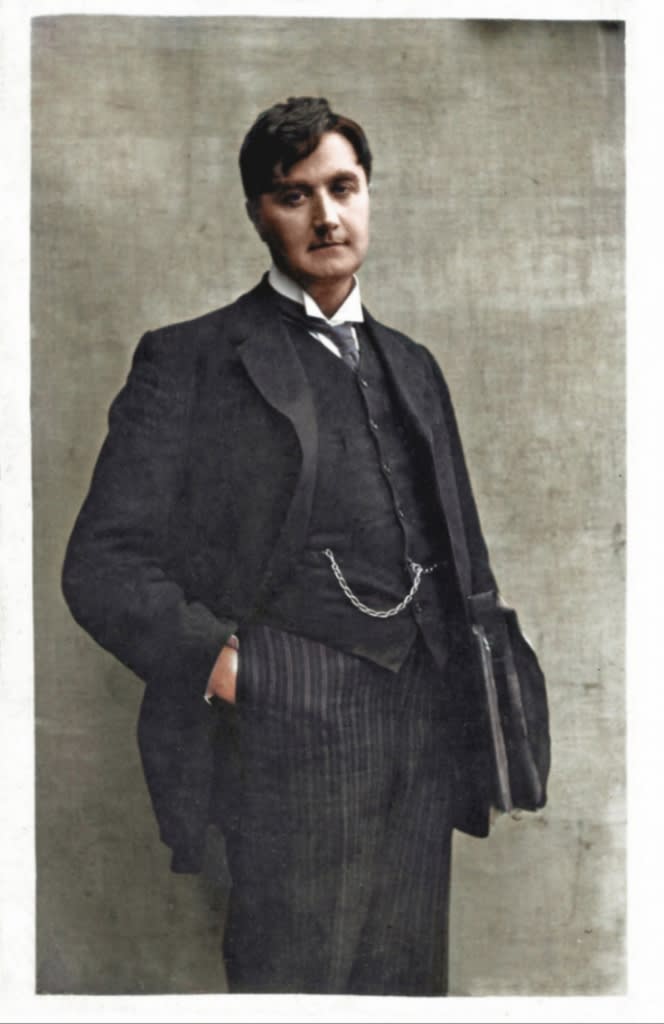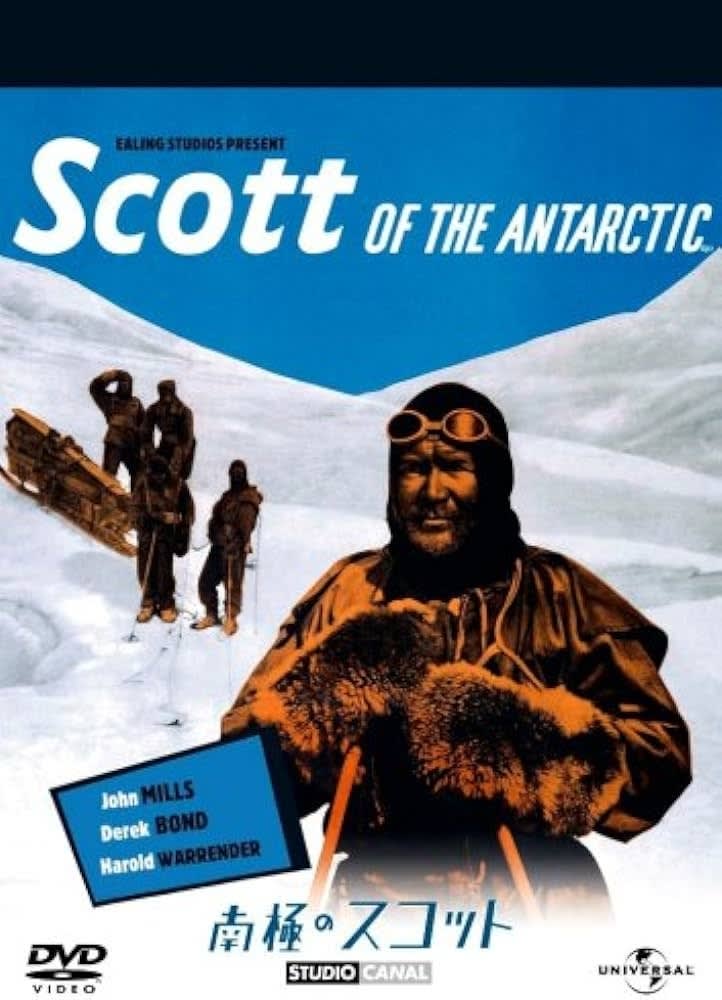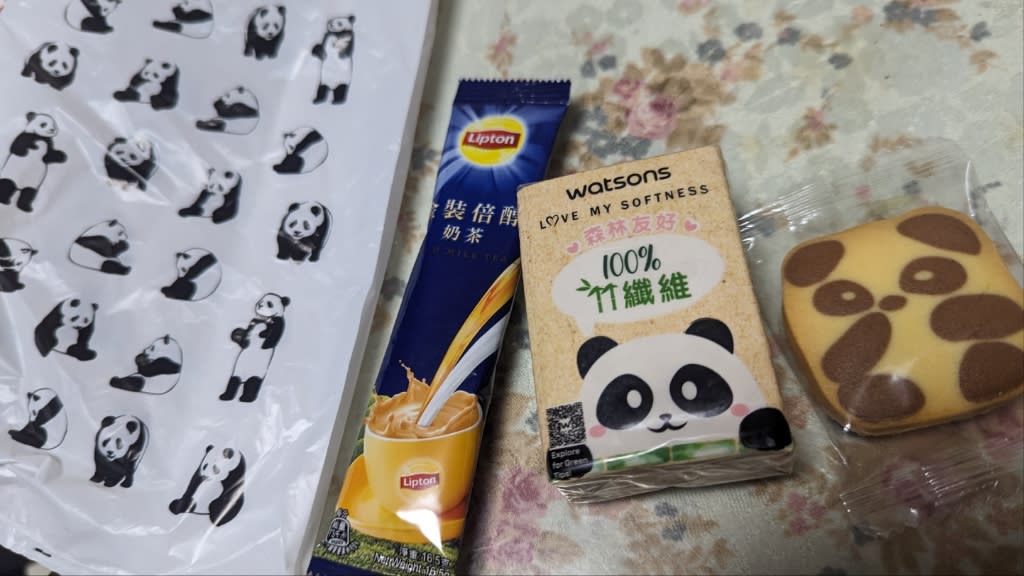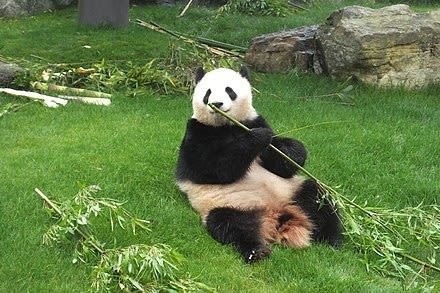水曜日は第6回聴き合い会てした。
 ななぬ
ななぬ

は、1780〜1785年の間、ハイドンのいたエステルハージの宮廷ヴァイオリン奏者でした。

テーブルに置いた楽譜の左右に2人の奏者が座り、両端から自分とは反対側から同時に読んでいくと、自分の側に来る頃には、二重奏の曲が一曲できています。
今回は、ヴァイオリン、ヴィオラ、ギター、フルート、ビウエラ奏者が集まってくれました。
このヴィオラの2人が演奏しているのは
ウォルフガング アマデウス モーツァルト(1756-1791年)神聖ローマ帝国ザルツブルク大司教領ザルツブルク生まれ、神聖ローマ帝国オーストリア大公国ウイーン没
 ななぬ
ななぬの「鏡のカノン」
モーツァルトの作った「音楽の冗談」の一部だと言われていました。
しかし、モーツァルトのカタログには掲載されていません。
「Mirror Canon」
「Table canons(for.2volins)」
「Der Spiegel」
「Spiegelkanons」
日本語では
「鏡」「鏡のカノン」
と呼ばれています。
K.Anh.C10.16の番号は、偽作を意味しています。
ハイドンの作品目録に「Ein musicalischer Scheltz」音楽の冗談(Group Ⅵ:G4)と呼ばれる曲があります。
メストリーノ氏による2つのヴァイオリンのための平易で奇妙な二重奏。と書かれています。
これが先程のモーツァルトの曲と同じです。
ニコラ メストリーノ(1748〜1789年)イタリア ミラノ生まれ、フランスパリ没

は、1780〜1785年の間、ハイドンのいたエステルハージの宮廷ヴァイオリン奏者でした。
「鏡のカノン」は

テーブルに置いた楽譜の左右に2人の奏者が座り、両端から自分とは反対側から同時に読んでいくと、自分の側に来る頃には、二重奏の曲が一曲できています。