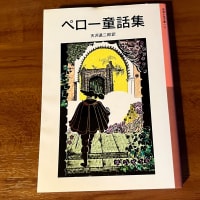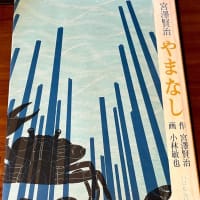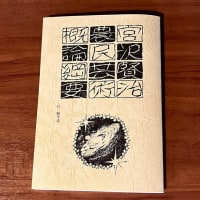3・11以後を生きる特集で精神科医の斎藤環が紹介していて知った本。
帯の推薦文が秀逸です。
「あの日」から私がもとめたのは、死者たちを「悼む」言葉ではない。彼らと「ともにある」ための言葉だ。そこにツェランの言葉があった。絶対的な脆弱、絶望的なまでの希望、そして戦慄的な優しさをはらむ言葉が。
パウル・ツェランという詩人の存在をそれまで知らなかった。
ユダヤ人であるがために強制収容所に送られ働かされ、両親を殺される。本人は助かるが、本当の意味で助かったと言えるのだろうか?
心に重すぎる傷を負ったまま、戦争後に残った唯一のもの、言葉だけを頼りに自分と向き合っていく。その過酷な過程で生まれた詩たち。
多くは抽象的で難解とも言えますが、その難解さが彼の人生そのものを現しているようでもあります。
ときにはっとする言葉が現れる。ぞっとする言葉も現れる。
彼はやはり生きたかったのだと思う。しかし、彼の最期は、セーヌ川への投身自殺という悲惨なものでした。
愛したはずの妻に凶器を向け、離婚していた。
絶望の中で、鬱は、虐待された体験は、彼を自殺へと向かわせる。
そこによき友人はいなかったか?
しかし彼の受けた暴力を思うと、痛ましさに苦しくなる。
ゴッホの自殺もそうだけど、なんとも言えません。ただ彼は彼の人生を全うしたのだと思う。
そうした納得が、しかし自然災害、まして人災の場合(原発事故)は得難い。
だからこそ、「ともにある」ための言葉が必要とされている。
刻々
刻々、だれの手まねき?
明るさはすみずみまで眠っていない。
おまえはのがれ出ることなく、
いたるところで、
心をあつめよ、
立っていよ。
76ページから詩を一遍引用させていただきました。
手まねきするのは誰でしょうか。犠牲となった死者(ツェランの場合は特に母親)でしょうか。
明るさはすみずみまで眠ってはいない。希望はあると彼はわかっている。
だから彼はのがれ出る(死ぬことだと思う)ことなく、いたるところで心をあつめ、立っていよと自らを鼓舞する。
心をあつめなければ生きていけない辛さ。
故郷を失ったことで揺らぐ自分の存在を取り戻そうと思い出の写真を探し求める人のように。
一度読んだだけではわかりません。
むしろ少しの時間だけでわかったと言ってしまう心は不遜と言うもの。
この本とともにあり、少しずつでいいからともにあるための言葉を身に着けたいと思います。
パウル・ツェラン著/飯吉光夫訳/白水社/2012
帯の推薦文が秀逸です。
「あの日」から私がもとめたのは、死者たちを「悼む」言葉ではない。彼らと「ともにある」ための言葉だ。そこにツェランの言葉があった。絶対的な脆弱、絶望的なまでの希望、そして戦慄的な優しさをはらむ言葉が。
パウル・ツェランという詩人の存在をそれまで知らなかった。
ユダヤ人であるがために強制収容所に送られ働かされ、両親を殺される。本人は助かるが、本当の意味で助かったと言えるのだろうか?
心に重すぎる傷を負ったまま、戦争後に残った唯一のもの、言葉だけを頼りに自分と向き合っていく。その過酷な過程で生まれた詩たち。
多くは抽象的で難解とも言えますが、その難解さが彼の人生そのものを現しているようでもあります。
ときにはっとする言葉が現れる。ぞっとする言葉も現れる。
彼はやはり生きたかったのだと思う。しかし、彼の最期は、セーヌ川への投身自殺という悲惨なものでした。
愛したはずの妻に凶器を向け、離婚していた。
絶望の中で、鬱は、虐待された体験は、彼を自殺へと向かわせる。
そこによき友人はいなかったか?
しかし彼の受けた暴力を思うと、痛ましさに苦しくなる。
ゴッホの自殺もそうだけど、なんとも言えません。ただ彼は彼の人生を全うしたのだと思う。
そうした納得が、しかし自然災害、まして人災の場合(原発事故)は得難い。
だからこそ、「ともにある」ための言葉が必要とされている。
刻々
刻々、だれの手まねき?
明るさはすみずみまで眠っていない。
おまえはのがれ出ることなく、
いたるところで、
心をあつめよ、
立っていよ。
76ページから詩を一遍引用させていただきました。
手まねきするのは誰でしょうか。犠牲となった死者(ツェランの場合は特に母親)でしょうか。
明るさはすみずみまで眠ってはいない。希望はあると彼はわかっている。
だから彼はのがれ出る(死ぬことだと思う)ことなく、いたるところで心をあつめ、立っていよと自らを鼓舞する。
心をあつめなければ生きていけない辛さ。
故郷を失ったことで揺らぐ自分の存在を取り戻そうと思い出の写真を探し求める人のように。
一度読んだだけではわかりません。
むしろ少しの時間だけでわかったと言ってしまう心は不遜と言うもの。
この本とともにあり、少しずつでいいからともにあるための言葉を身に着けたいと思います。
パウル・ツェラン著/飯吉光夫訳/白水社/2012