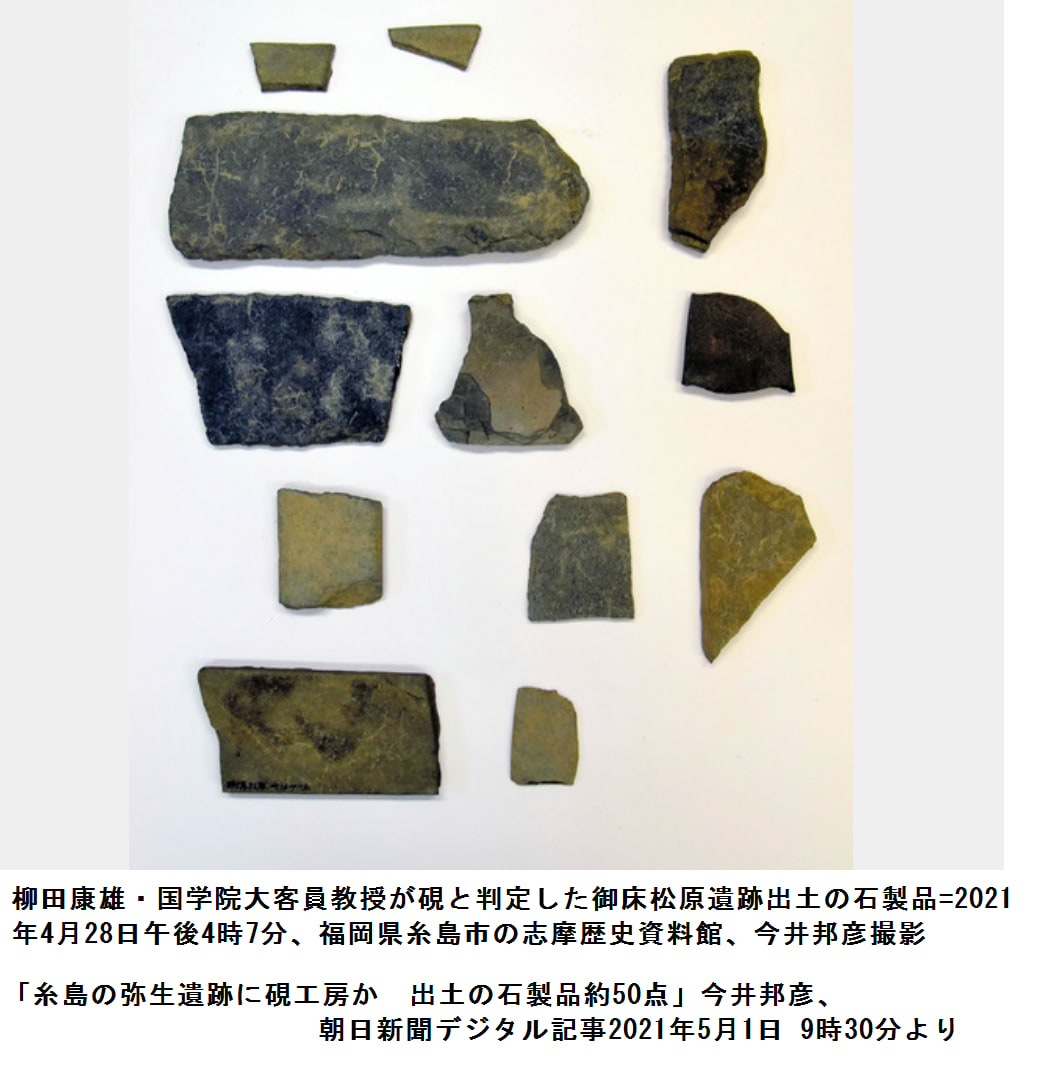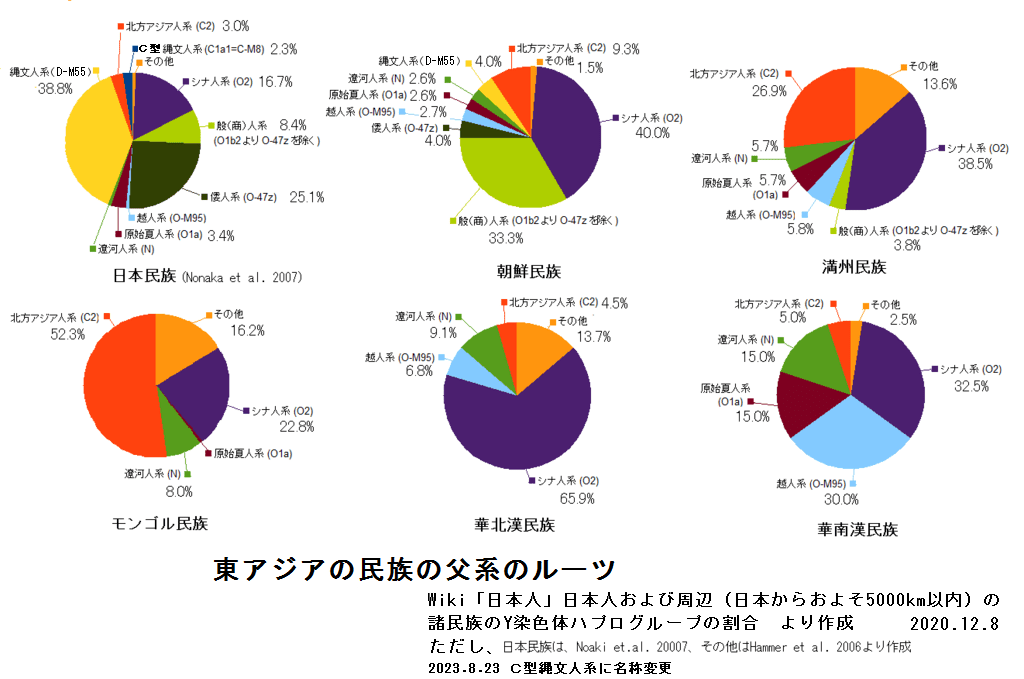いつも応援ありがとうございます。
よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和三年(2021)7月31日(土曜日)
通巻第7003号
(読者の声2)貴紙通巻第7001号に(読者の声4)として卑弥呼の遣使の年が景初3年であるとの再反論が寄せられました。
帯方郡太守の任期の前後という細かな点を問題としておられますので、考えられる可能性について検討した上で、景初3年説は成り立たないことを論じたいと思います。
まず、再反論者さまは、東夷伝序文から「景初年間、大規模な遠征の軍を動かし、公孫淵を誅殺すると、さらにひそかに兵を船で運んで海を渡し、楽浪と帯方の郡を攻め取った。」と主張されますが、「さらに」とされた箇所は原文では「又」であって、必ずしも前後関係を示すものではありません。
つまり景初年間の出来事として大軍を派遣して公孫淵を誅殺した話と、密かに海を越えて軍を派遣し楽浪・帯方両郡を収めた二つの話を、「又」で繋いでいるのです。
序文という大掴みに概要を述べる箇所では、重要度が大きい方を先に述べることは普通であり、公孫淵の誅殺が先に書いてあるから前後関係がこれで決まりとするほどのものでは無いと考えます。
念のため当該箇所の原文は「景初中、大興師旅、誅淵、又潛軍浮海、收樂浪・帶方之郡。」となっています。
また、「魏書 東夷伝 韓伝」に「明帝が景初中(237~239年)に密かに楽浪郡太守鮮于嗣と帯方郡太守劉?を送った」ことについて述べられます。これは公孫淵誅殺後のことであると理解されている様です。
原文には「景初中、明帝、密遣帶方太守劉?・樂浪太守鮮于嗣、越海定二郡」とありますから、前文同様、この文からは景初何年のことか確定はできませんが、明帝は景初3年早々に死去していますから、景初元年か景初2年のことであるのは間違いありません。
公孫淵誅殺は景初2年8月(都に知らせが届いたのは9月)のことですから、帯方太守劉?を海路派遣したのは、誅殺前とも誅殺後とも受け取ることができます。従って、普通に読めばどの様に読むことができるか判断しなければなりません。
公孫淵誅殺後に派遣したのであれば、何故わざわざ海路で密かに派遣する必要があるのでしょうか。
行く手を遮るものがいなくなったのですから、何も密かに海路で派遣する必要はなく、白昼堂々と陸路を行けば良いのです。
「海を越えて密かに派遣する」というのは、公孫淵に気付かれないように「密かに」海路で派遣し、韓を平定し退路を断った、と理解するのが普通では無いでしょうか。
魏は陸上の戦いでは強くても、水上の戦いはそれほど得意ではありません。
それゆえ、長江を隔てた孫権に手を焼いているのです。そのような魏の軍を苦手な海路で派遣するのですから、公孫淵に気付かれないように密かに行う必要があったのです。
明帝の周到な準備を窺う事ができます。おそらく背後固めは景初元年中には完了していたと思われ、景初2年になって討伐軍が派遣されることになったのです。
密かに背後を固めた後、正面から大将軍司馬宣王の軍勢が進軍したと、読むのが普通では無いでしょうか。
その後(景初2年6月に)卑弥呼の使いが来た時は太守は劉夏に代わっていました。劉?が劉夏に代わった事情についてはよく分かりません。再反論者さまの論によれば、9月に公孫淵誅殺の報告が届いた直後くらいに韓平定の軍を別に派遣したということですが、公孫淵が滅亡すれば慌てて韓を平定する必要はなく、ゆっくりと司馬宣王の帰還を待てば良いだけであり、この時点で密かに別軍を派遣して韓を平定する意味は戦略的にも政治的にも、何より経済的にも無いのでは無いでしょうか。
陳寿の文は簡潔であるため、解釈に幅が出るところは少なくありませんが、前後などの関係をよく読み解けば、難しくひねった箇所など無いと言って良いと思っています。
勝手な理解をして、難解で読み解けないので自己流の解釈を行う人たちが絶えませんが、反論者さまは良いところまで読み込まれていると思います。折角そこまで読み込まれているのであれば後一歩だと思います。
今一度冷静に思い込みを離れて読み直されることをお勧めしたいと思います。
(高柴昭)
貴誌第7003号(読者の声2)に景初三年説への反論が再度寄せられました。「東夷伝 序」に「景初年間(二三七 - 二三九)、大規模な遠征の軍を動かし、公孫淵を誅殺すると、さらにひそかに兵を船で運んで海を渡し、楽浪と帯方の郡を攻め取った。これ以後、東海のかなたの地域の騒ぎもしずまり、東夷の民たちは中国の支配下に入ってその命令に従うようになった。」(今鷹真・小南一郎・井波律子訳「三国志Ⅱ」世界古典文学全集24B筑摩書房1982、p.295)とある文章中で「さらに」と訳されている原文には「又」とあり、これは時間の前後関係を表すものではないと主張されています。また「公孫淵誅殺後に派遣したのであれば、何故わざわざ海路で密かに派遣する必要があるのでしょうか。」と主張されていますが、御自分で「そのような魏の軍を苦手な海路で派遣するのですから、公孫淵に気付かれないように密かに行う必要があったのです。
明帝の周到な準備を窺う事ができます。おそらく背後固めは景初元年中には完了していたと思われ、景初2年になって討伐軍が派遣されることになったのです。」とその答えを出されています。「ひそかに」と記された意味はおっしゃる通りなのかもしれませんが、卑弥呼の遣使(難升米)が写本に景初二年六月とあるからといって、それ以前に楽浪・帯方二郡を落したという根拠にはできません。もしも難升米が面会したのが、この時明帝が送った帯方郡太守劉昕(りゅうきん)だったならば、景初二年説は成り立つかもしれませんが、劉昕(りゅうきん)ではなく別の人物劉夏(りゅうか)ですので、おっしゃる通り、どういう経緯で劉夏に交代したのか貴説では全く説明できないからです。
そして、「晋書 四夷伝倭人条」に「宣帝之平公孫氏也其女王遣使至帯方朝見 其後貢聘不絶」とあります。つまり卑弥呼の帯方朝見は司馬懿が公孫氏を平定したからだと明記されています。刮目天は漢籍の専門家ではないですが、上記「三国志東夷伝序」の「又」とあるのは時間の前後関係を表していると「三国志」の翻訳者が深く考えて「さらに」と書いたのだと考えられます。すでに述べましたように「晋書 宣帝紀」にも「正始元年[二四〇年]春正月、東倭が複数の通訳を介して朝貢してきた。焉耆・危須等の諸国、弱水以南の地方、鮮卑の名王が、みな使者を遣わして来貢した。皇帝はこの威風を宰相の功によるものとし、宣帝に増封した。」とあります(「晋書 高祖宣帝懿紀」訳出担当 田中愛子/辰田淳一より)。卑弥呼の朝貢は、明帝ではなく司馬懿の功績であると魏の朝廷の人々は認識していたと考えられますから、司馬懿による景初二年八月の公孫氏滅亡後の景初三年六月に難升米が帯方郡に行ったと考えるのが正しいのです。お陰様で、これによって「邪馬台国問題」の謎が解明できるので非常に重要な議論でした。お付き合い心から感謝いたします。
(刮目天)
【参考記事】
「魏志倭人伝」の真相とは?!2021-07-29 11:25:03
【邪馬台国問題】魏志倭人伝は信用できるのか?(;´Д`)
邪馬台国への行程記事は司馬懿の功績を曹魏第一とするために、司馬懿の部下の帯方郡太守劉夏と倭国王難升米が談合して作られたものだと推理しました。帯方郡より東南万二千里の海上から魏のライバルの呉を挟み撃ちする位置に邪馬台国があるとして、邪馬台国への行程を以下の図のように改ざんしました。卑弥呼を倭国の支配者ということにして、自ら女王卑弥呼の男弟という設定にしたのも魏の朝廷の人々の注目を集めるためですよ(^_-)-☆
投馬国へ水行してみませんか?( ^)o(^ )倭国王難升米はパートナー赤坂比古の居城(宮ノ原遺跡)を邪馬台国(女王が住むヤマ国という意味)としました。そこへの実際の行程を基にして、戦略上重要な位置(呉の都の建業の東方海上)に持って行くために東を南に方角変更し、水行・陸行の日数を実際の10倍などにした行程だったと分かるのですよ(^_-)-☆

最後までお付き合い、ありがとうございます。
通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)
よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング
よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和三年(2021)7月31日(土曜日)
通巻第7003号
(読者の声2)貴紙通巻第7001号に(読者の声4)として卑弥呼の遣使の年が景初3年であるとの再反論が寄せられました。
帯方郡太守の任期の前後という細かな点を問題としておられますので、考えられる可能性について検討した上で、景初3年説は成り立たないことを論じたいと思います。
まず、再反論者さまは、東夷伝序文から「景初年間、大規模な遠征の軍を動かし、公孫淵を誅殺すると、さらにひそかに兵を船で運んで海を渡し、楽浪と帯方の郡を攻め取った。」と主張されますが、「さらに」とされた箇所は原文では「又」であって、必ずしも前後関係を示すものではありません。
つまり景初年間の出来事として大軍を派遣して公孫淵を誅殺した話と、密かに海を越えて軍を派遣し楽浪・帯方両郡を収めた二つの話を、「又」で繋いでいるのです。
序文という大掴みに概要を述べる箇所では、重要度が大きい方を先に述べることは普通であり、公孫淵の誅殺が先に書いてあるから前後関係がこれで決まりとするほどのものでは無いと考えます。
念のため当該箇所の原文は「景初中、大興師旅、誅淵、又潛軍浮海、收樂浪・帶方之郡。」となっています。
また、「魏書 東夷伝 韓伝」に「明帝が景初中(237~239年)に密かに楽浪郡太守鮮于嗣と帯方郡太守劉?を送った」ことについて述べられます。これは公孫淵誅殺後のことであると理解されている様です。
原文には「景初中、明帝、密遣帶方太守劉?・樂浪太守鮮于嗣、越海定二郡」とありますから、前文同様、この文からは景初何年のことか確定はできませんが、明帝は景初3年早々に死去していますから、景初元年か景初2年のことであるのは間違いありません。
公孫淵誅殺は景初2年8月(都に知らせが届いたのは9月)のことですから、帯方太守劉?を海路派遣したのは、誅殺前とも誅殺後とも受け取ることができます。従って、普通に読めばどの様に読むことができるか判断しなければなりません。
公孫淵誅殺後に派遣したのであれば、何故わざわざ海路で密かに派遣する必要があるのでしょうか。
行く手を遮るものがいなくなったのですから、何も密かに海路で派遣する必要はなく、白昼堂々と陸路を行けば良いのです。
「海を越えて密かに派遣する」というのは、公孫淵に気付かれないように「密かに」海路で派遣し、韓を平定し退路を断った、と理解するのが普通では無いでしょうか。
魏は陸上の戦いでは強くても、水上の戦いはそれほど得意ではありません。
それゆえ、長江を隔てた孫権に手を焼いているのです。そのような魏の軍を苦手な海路で派遣するのですから、公孫淵に気付かれないように密かに行う必要があったのです。
明帝の周到な準備を窺う事ができます。おそらく背後固めは景初元年中には完了していたと思われ、景初2年になって討伐軍が派遣されることになったのです。
密かに背後を固めた後、正面から大将軍司馬宣王の軍勢が進軍したと、読むのが普通では無いでしょうか。
その後(景初2年6月に)卑弥呼の使いが来た時は太守は劉夏に代わっていました。劉?が劉夏に代わった事情についてはよく分かりません。再反論者さまの論によれば、9月に公孫淵誅殺の報告が届いた直後くらいに韓平定の軍を別に派遣したということですが、公孫淵が滅亡すれば慌てて韓を平定する必要はなく、ゆっくりと司馬宣王の帰還を待てば良いだけであり、この時点で密かに別軍を派遣して韓を平定する意味は戦略的にも政治的にも、何より経済的にも無いのでは無いでしょうか。
陳寿の文は簡潔であるため、解釈に幅が出るところは少なくありませんが、前後などの関係をよく読み解けば、難しくひねった箇所など無いと言って良いと思っています。
勝手な理解をして、難解で読み解けないので自己流の解釈を行う人たちが絶えませんが、反論者さまは良いところまで読み込まれていると思います。折角そこまで読み込まれているのであれば後一歩だと思います。
今一度冷静に思い込みを離れて読み直されることをお勧めしたいと思います。
(高柴昭)
貴誌第7003号(読者の声2)に景初三年説への反論が再度寄せられました。「東夷伝 序」に「景初年間(二三七 - 二三九)、大規模な遠征の軍を動かし、公孫淵を誅殺すると、さらにひそかに兵を船で運んで海を渡し、楽浪と帯方の郡を攻め取った。これ以後、東海のかなたの地域の騒ぎもしずまり、東夷の民たちは中国の支配下に入ってその命令に従うようになった。」(今鷹真・小南一郎・井波律子訳「三国志Ⅱ」世界古典文学全集24B筑摩書房1982、p.295)とある文章中で「さらに」と訳されている原文には「又」とあり、これは時間の前後関係を表すものではないと主張されています。また「公孫淵誅殺後に派遣したのであれば、何故わざわざ海路で密かに派遣する必要があるのでしょうか。」と主張されていますが、御自分で「そのような魏の軍を苦手な海路で派遣するのですから、公孫淵に気付かれないように密かに行う必要があったのです。
明帝の周到な準備を窺う事ができます。おそらく背後固めは景初元年中には完了していたと思われ、景初2年になって討伐軍が派遣されることになったのです。」とその答えを出されています。「ひそかに」と記された意味はおっしゃる通りなのかもしれませんが、卑弥呼の遣使(難升米)が写本に景初二年六月とあるからといって、それ以前に楽浪・帯方二郡を落したという根拠にはできません。もしも難升米が面会したのが、この時明帝が送った帯方郡太守劉昕(りゅうきん)だったならば、景初二年説は成り立つかもしれませんが、劉昕(りゅうきん)ではなく別の人物劉夏(りゅうか)ですので、おっしゃる通り、どういう経緯で劉夏に交代したのか貴説では全く説明できないからです。
そして、「晋書 四夷伝倭人条」に「宣帝之平公孫氏也其女王遣使至帯方朝見 其後貢聘不絶」とあります。つまり卑弥呼の帯方朝見は司馬懿が公孫氏を平定したからだと明記されています。刮目天は漢籍の専門家ではないですが、上記「三国志東夷伝序」の「又」とあるのは時間の前後関係を表していると「三国志」の翻訳者が深く考えて「さらに」と書いたのだと考えられます。すでに述べましたように「晋書 宣帝紀」にも「正始元年[二四〇年]春正月、東倭が複数の通訳を介して朝貢してきた。焉耆・危須等の諸国、弱水以南の地方、鮮卑の名王が、みな使者を遣わして来貢した。皇帝はこの威風を宰相の功によるものとし、宣帝に増封した。」とあります(「晋書 高祖宣帝懿紀」訳出担当 田中愛子/辰田淳一より)。卑弥呼の朝貢は、明帝ではなく司馬懿の功績であると魏の朝廷の人々は認識していたと考えられますから、司馬懿による景初二年八月の公孫氏滅亡後の景初三年六月に難升米が帯方郡に行ったと考えるのが正しいのです。お陰様で、これによって「邪馬台国問題」の謎が解明できるので非常に重要な議論でした。お付き合い心から感謝いたします。
(刮目天)
【参考記事】
「魏志倭人伝」の真相とは?!2021-07-29 11:25:03
【邪馬台国問題】魏志倭人伝は信用できるのか?(;´Д`)
邪馬台国への行程記事は司馬懿の功績を曹魏第一とするために、司馬懿の部下の帯方郡太守劉夏と倭国王難升米が談合して作られたものだと推理しました。帯方郡より東南万二千里の海上から魏のライバルの呉を挟み撃ちする位置に邪馬台国があるとして、邪馬台国への行程を以下の図のように改ざんしました。卑弥呼を倭国の支配者ということにして、自ら女王卑弥呼の男弟という設定にしたのも魏の朝廷の人々の注目を集めるためですよ(^_-)-☆
投馬国へ水行してみませんか?( ^)o(^ )倭国王難升米はパートナー赤坂比古の居城(宮ノ原遺跡)を邪馬台国(女王が住むヤマ国という意味)としました。そこへの実際の行程を基にして、戦略上重要な位置(呉の都の建業の東方海上)に持って行くために東を南に方角変更し、水行・陸行の日数を実際の10倍などにした行程だったと分かるのですよ(^_-)-☆

最後までお付き合い、ありがとうございます。
通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)
よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング