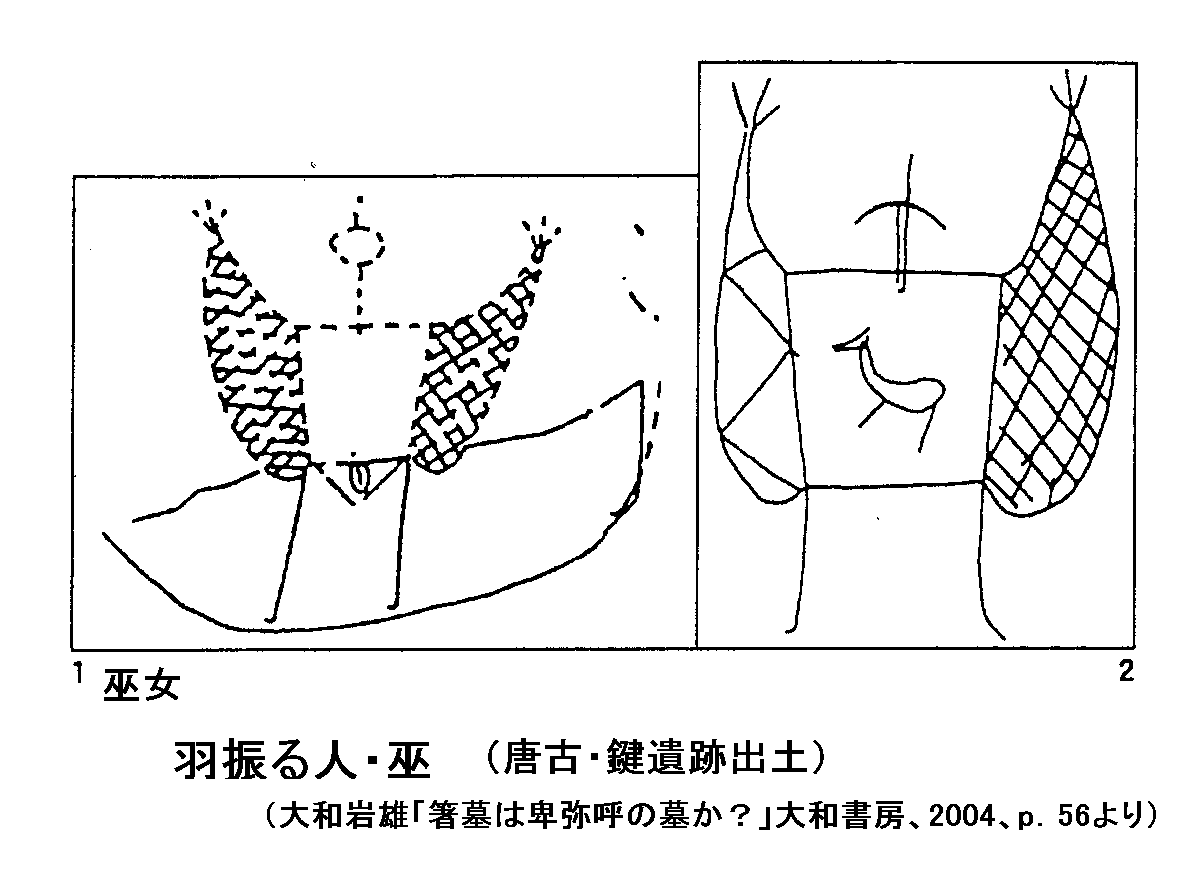いつも応援ありがとうございます。
よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング
多くの研究者は奴国について、いくつかあった当時の国々のひとつ程度と勘違いされています。恐らく漢書地理誌に「樂浪海中有倭人 分爲百餘國 以歳時來獻見云」という文や魏志倭人伝に紹介されているので、以下の動画にあるように、それが先入観となって考古学の大きな成果を見落としていたのでしょう。だから、「新唐書」や「宋史」に有る「日本は古の倭の奴国」であるとは考えられずに、ヤマト王権の成立まで正しくたどり着けなかったのだと思います。

弥生中期初頭ころの早良平野の吉武高木遺跡に日本最古の王墓が見つかっています。この遺跡が天皇家の祖先の天御中主(アメノミナカヌシ)が住んだ場所です。紀元前473年に滅んだ呉王夫差の一族です。二代目の天村雲尊(アメノムラクモ)から天八重雲尊(アメノヤエグモ)まで三代が王宮を構えていました。威信財として遼寧式銅剣や銅鏡や勾玉を手に入れており、江南系の海人アズミ族を部下として半島南部や列島各地などと盛んに交易して発展しました。(2021.6.30 赤字訂正)
4代目の天彌聞尊(アメノニニギ)から王宮を須玖岡本遺跡に遷し、那珂川下流域に列島最大の交易センターの建設を始めました。那珂・比恵遺跡群(面積約164ha)です。周辺には水田が作られています。中期後半がその最盛期で、日本最大の弥生遺跡と言われる吉野ヶ里遺跡(面積約117ha)の約1.5倍の広さになり大型井堰や長い直線道路などが作られています。この福岡平野一帯が魏志倭人伝で紹介された二万戸の奴国の領域です。同じころ楽浪郡との対外交易センターを伊都国に造り、奴国王族を王にしていました。筑紫平野へも進出し、平塚川添遺跡付近に王族を王として配置しています。(2021.7.3 赤字修正)
須玖遺跡群には青銅器(銅矛・銅戈・銅剣など)や勾玉などを製造する一大コンビナートが作られ、列島内交易センターに集まる各地の縄文系の人々の首長などに配布し、権威を保っていました。列島各地の縄文人などが奴国に無事に交易品を持って到着できるように津々浦々で支援するためです。ですから伊弉諾尊(イザナギ)の父第16代王沫名杵尊(アワナギ)あたりが後漢光武帝から金印を賜りました。西暦57年は後期初頭になります。後漢は列島の珍しい産物を入手するために華僑を伊都国に派遣し、倭人との交易を保護させるために倭国を冊封体制に組み込んだわけです。
奴国の王宮に住む倭国王を倭の奴国王と呼んだのです。奴(ナ)はナーガ=龍蛇神の意味です。金印のつまみの形から分かります。地名も那珂、那賀などとあり、現在の地名にある中山や長柄なども龍蛇神を祀る江南系の倭人が作った国名です。だから日本の最初の神は天御中主神なのです。「新唐書」・「宋史」に記載された日本の「王年代紀」に当てはまりますから、記紀神話の高天原のことだったのです。
よろしければ「古代史を推理する」をご覧ください!ヤマト王権成立過程を推理し、邪馬台国の所在や卑弥呼の墓も全て見つかっていますよ。突然長文で失礼しました。
【関連記事】
【検証9】奴国時代の話(その1) (その2)
天孫降臨と草薙剣の謎?(;´Д`)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)
応援をしていただき、感謝します。
よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング
よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング多くの研究者は奴国について、いくつかあった当時の国々のひとつ程度と勘違いされています。恐らく漢書地理誌に「樂浪海中有倭人 分爲百餘國 以歳時來獻見云」という文や魏志倭人伝に紹介されているので、以下の動画にあるように、それが先入観となって考古学の大きな成果を見落としていたのでしょう。だから、「新唐書」や「宋史」に有る「日本は古の倭の奴国」であるとは考えられずに、ヤマト王権の成立まで正しくたどり着けなかったのだと思います。

弥生中期初頭ころの早良平野の吉武高木遺跡に日本最古の王墓が見つかっています。この遺跡が天皇家の祖先の天御中主(アメノミナカヌシ)が住んだ場所です。紀元前473年に滅んだ呉王夫差の一族です。二代目の天村雲尊(アメノムラクモ)から天八重雲尊(アメノヤエグモ)まで三代が王宮を構えていました。威信財として遼寧式銅剣や銅鏡や勾玉を手に入れており、江南系の海人アズミ族を部下として半島南部や列島各地などと盛んに交易して発展しました。(2021.6.30 赤字訂正)
4代目の天彌聞尊(アメノニニギ)から王宮を須玖岡本遺跡に遷し、那珂川下流域に列島最大の交易センターの建設を始めました。那珂・比恵遺跡群(面積約164ha)です。周辺には水田が作られています。中期後半がその最盛期で、日本最大の弥生遺跡と言われる吉野ヶ里遺跡(面積約117ha)の約1.5倍の広さになり大型井堰や長い直線道路などが作られています。この福岡平野一帯が魏志倭人伝で紹介された二万戸の奴国の領域です。同じころ楽浪郡との対外交易センターを伊都国に造り、奴国王族を王にしていました。筑紫平野へも進出し、平塚川添遺跡付近に王族を王として配置しています。(2021.7.3 赤字修正)
須玖遺跡群には青銅器(銅矛・銅戈・銅剣など)や勾玉などを製造する一大コンビナートが作られ、列島内交易センターに集まる各地の縄文系の人々の首長などに配布し、権威を保っていました。列島各地の縄文人などが奴国に無事に交易品を持って到着できるように津々浦々で支援するためです。ですから伊弉諾尊(イザナギ)の父第16代王沫名杵尊(アワナギ)あたりが後漢光武帝から金印を賜りました。西暦57年は後期初頭になります。後漢は列島の珍しい産物を入手するために華僑を伊都国に派遣し、倭人との交易を保護させるために倭国を冊封体制に組み込んだわけです。
奴国の王宮に住む倭国王を倭の奴国王と呼んだのです。奴(ナ)はナーガ=龍蛇神の意味です。金印のつまみの形から分かります。地名も那珂、那賀などとあり、現在の地名にある中山や長柄なども龍蛇神を祀る江南系の倭人が作った国名です。だから日本の最初の神は天御中主神なのです。「新唐書」・「宋史」に記載された日本の「王年代紀」に当てはまりますから、記紀神話の高天原のことだったのです。
よろしければ「古代史を推理する」をご覧ください!ヤマト王権成立過程を推理し、邪馬台国の所在や卑弥呼の墓も全て見つかっていますよ。突然長文で失礼しました。
【関連記事】
【検証9】奴国時代の話(その1) (その2)
天孫降臨と草薙剣の謎?(;´Д`)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)
応援をしていただき、感謝します。
よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング