いつも応援ありがとうございます。
よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング
実は、万葉集も藤原氏に都合の良い歴史改ざんの事実を後世に密かに伝えるために大伴家持、山上憶良らによって作られたようなのだ。万葉集研究家の渡辺康則さんが中大兄皇子は「日本書紀」では中大兄とだけで、どこにも皇子とは書かれていないというヒントから皇太子でもない人物が即位したことにされたという衝撃的な事実を万葉集に隠された暗号を解読して突き止めたのだ(「捏造された天皇・天智」上・下 大空出版2013)。その続編「聖徳太子は天皇だった」(大空出版2014)ではもっと衝撃的なことが書かれていた。「隋書 倭国伝」にある倭国の大王アメノタリシヒコは推古天皇の時代と重なる。推古天皇だけではなく、「日本書紀」で言う用明天皇から斉明天皇までの時代は中大兄を万世一系の天皇に仕立て上げるための歴史ねつ造だったという結論なのだ。

しかし、もしもそういう大がかりな歴史改ざんが「日本書紀」によって本当に行われたのであれば、「宋書 倭の五王」の最後の武王とされる雄略天皇までは物証もあり実在と見ることができるが、その後の清寧天皇から、顕宗・仁賢・武烈・継体・安閑・宣化・欽明・敏達までの八代の天皇もすべてではないと思うが一部改ざんされている可能性が十分にあると思う(注1)。(202.1.23 赤字修正)

歴史ねつ造のやり方としては不自然なウソを隠すために先例を創作することが手っ取り早い。
例えば、天智天皇は都を近江として即位したので大和では即位していない。いきなり異例なことを書くと、天皇ではないかも知れないと怪しまれる(注2)。だから、同じく大和で即位していない継体天皇を登場させたのかも知れない。ヤマト政権が越前からオトド王を呼んだのであれば大和で即位しなければおかしい。継体天皇が応神天皇の五世孫だというのも何となく怪しく、新王朝ではないかとの説もある。清寧から継体即位までの話はかなり不自然だ(注3)。
また、歴史改ざんのもう一つの大きな目的は藤原氏が中大兄と共に追い落とした蘇我氏や物部氏の祖による日本建国の真相を隠すことだ。それはヤマト王権の基になる、由緒ある金印の倭の奴(ナーガ)国も当然隠蔽することになっている。
「日本書紀」では天武天皇は天智天皇の弟ということだが、違うのではないかという説が前からあった。万葉史観で舒明天皇も架空の存在ならば、天武天皇は武内宿禰を祖とする蘇我大王家の家系だとすれば壬申の乱の意味がスッキリするのだ。また天武天皇の皇后であった持統が女性天皇となることの異常さを隠すために、先代に推古だけでなく皇極(斉明)を登場させ、女帝はたまにあるんだよ、ということにしたのだ。持統は天智天皇の皇女鵜野讃良(ウノノサララ)でもあり、持統の孫の軽皇子を文武天皇として即位させたことの正統性のために、物部氏の祖である王年代紀第19代王天照大神尊ニギハヤヒから女神アマテラスに皇祖神をすり替えて天照大御神としたのだ。そのためにニギハヤヒも記紀神話で女神アマテラスの孫ニニギノミコトの兄弟神とすることによって真相を隠した。ニニギのネーミングの元ネタは第4代奴国王の天彌聞尊(アメノニニギノミコト)だろう(^_-)-☆
こうなると万世一系の皇統の男系男子によって継いできた今の天皇家も怪しい、どこかですり替わっているに違いないと考える人が出てくるかも知れない。実際、明治天皇のすり替え説もある。だがこれもデタラメだと直ぐに分かる。
日本における天皇の持つ意味、天皇の職務を考えると、すり替えは絶対にあり得ない。
天皇の本質は権力を持たない祭祀王としての権威だけの存在だったからだ。天皇は天変地異が起らないように皇祖神の魂と一体になるための厳しい修行をしなければならないのだ。長時間拘束される儀礼・式典にも先代から関わり、天皇教育されていないと絶対に務まるはずないからだ。もしもすり替えなどしたら国家の鎮護・安泰と国民の安寧を神々に祈り続ける、体力的・精神的負担が大きい宮中祭祀は、すり替わった本人にとってアホらしくなって耐えられず、とっくに簡素化され形骸化し、結局は天皇そのものが消えていたはずだからだ。
千年以上続く宮中祭祀の伝統が現代まで残っていることが、本物である証なのだ。
さて、建国神話に話を戻すと、初代天皇は第18代奴国王スサノヲ大王の直系である大国主ククチヒコ(多分スサノヲの六世孫)と縄文海人ムナカタ族の姫イザナミを母系とする台与(神功皇后)との間の子であるホムダワケ応神天皇であり、仲哀天皇は本当の父ではないことは既に何度も述べた。応神天皇はヤマトに殺された父の大国主の怨霊を鎮めるために即位した最初の祭祀王であり、呼称は後世だが本来の天皇の役割なのだ。大国主と台与が戦死したので、関祐二さんが推理したように南九州に逃亡し逼塞していたところ、ヤマトに呼び寄せられたのだろう(注4)。280年に西晋によってヤマトの後ろ盾の呉が滅んだので、追討を怖れたヤマトの大王(卑弥弓呼の次の世代か?)がホムダワケを呼び寄せて、王都の国名もヤマトゥ(邪馬台)とし、「母親の台与女王の代から西晋さんとはお付き合いしているヤマトゥ国なのですよ」としたというのが建国の真相なのだと推理した(【関連記事】参照)。
「日本書紀」では三輪山の大物主大神(大国主大神の和魂)が祟って、伝染病が発生し、民が半分以上死に、百姓は離流し、反逆するものも出たとある(崇神紀)。天皇は夢の中で、大物主が子のオオタタネコを呼び寄せて祀らせれば収まるぞと告げられたので、河内に探し出して大物主を祭らせたら国が収まったとある。
また、神武天皇の東征は武力ではナガスネヒコに撃退されたので、日の御子が太陽に向かって進んだのがよくないとして、熊野を回り、天香具山の赤土で平瓦などを作って天神地祇を祀り、呪いによって敵を撃退し即位できたというものだ。応神天皇の即位も神功皇后が、仲哀天皇の二人の皇子の謀略を見抜き、呪術で二人を滅ぼし即位させたとなっている。つまり神武天皇と応神天皇の話は時代設定も人物も変えてはいるが、内容的に似た話だった。
「神」の文字を諡り名に持つ4人の人物が日本建国に関わったことを、天智天皇の玄孫淡海三船が漢風諡号によって暗に示していた。神の命で武を以って葦原中つ国を統治した神武天皇。神に祟られたヤマトの大王崇神天皇。神の要請に応えて祭祀王に即位した応神天皇。神のような立派な功績を遺した神功皇后なのだ。
このヒントにより、謎がすべて解けるのだ。ヤマトにすでに降り立っていた天孫ニギハヤヒがトビのナガスネヒコを斬って神武天皇を即位させた話は、トビ(蛇)が化身である三輪山の大物主大神(大国主狗古智卑狗)がニギハヤヒの直系の崇神天皇(狗奴国王卑弥弓呼の次の王か?)によって殺された史実を示しているのだ。(2020.1.21 赤字追加)
「日本書紀」は初代大王の話をこのように時代も人物も異なる話を創作して歴史を改ざんし、スサノヲとニギハヤヒの子孫たち(由緒正しい蘇我氏と物部氏の祖)が行った日本建国の真相を隠したのだ。
通説・常識とまったく異なる話で、多くの方は混乱されたかも知れません。しかし、そのために「日本書紀」が建国の真相を神話に閉じ込めたのです。「日本書紀」成立から今年でちょうど千三百年、気の遠くなるほど長い年月でした。日本建国の真相を隠し通した藤原不比等の実力は大したものでした。最初に聖徳太子の謎が解明されて、それによって「日本書紀」のトリックがほぼ完全に解き明かされましたが、ほとんどが関裕二さんの功績ですよ(^_-)-☆
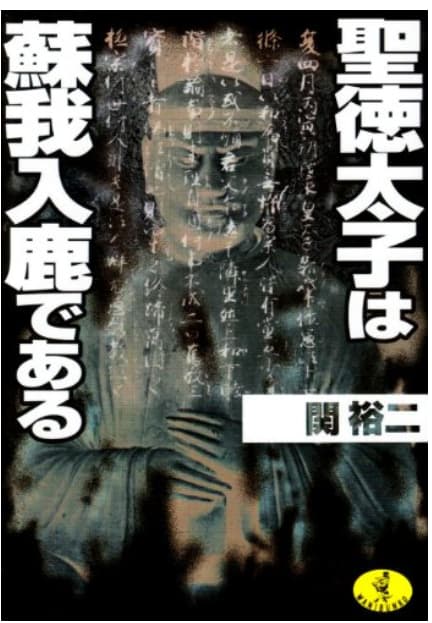
最後までお付き合いいただき感謝します。沢山応援いただき有難うございました。また、よろしくお願いしますね(*^^)v。
【関連記事】
古代史の謎を推理する(^_-)-☆

2020.1.21 210年頃築造の纏向石塚古墳を図に追加(石野博信「邪馬台国時代の王国群と纏向王宮」新泉社2019,p.47 より)
古代史を科学するには?(^_-)-☆
(注1)埼玉県の稲荷山古墳より出土した鉄剣と熊本県の江田船山古墳から出土した鉄刀に、ワカタケル大王雄略天皇の銘が刻まれているとされている。「日本書紀」では五王の事績を神功皇后の三韓征伐の話にして隠した。伊都国に逃げた女王台与がヤマト勢に追い詰められ、武器を取って戦った伝承を神功皇后の活躍の中に反映させ、戦死した台与の鎮魂のために女傑として持ち上げたと考えられる。
また、すでに述べたとおり初代天皇は神武と同一人物である応神として、280年の直後に即位したであろうと推定している。だから15代応神天皇までは10代崇神天皇を除きダミーなのだ。247年ごろ13歳で女王に立てられた台与の長子が応神天皇だとすると、子を産むには3、4年後だろうと考えると、即位は30歳代前半ということになる。そうすると、図に示したように応神天皇と五王の最初の倭王賛(履中天皇)まで間が空きすぎている。応神天皇と仁徳天皇の間、あるいは仁徳天皇と履中天皇の間に何代か存在するはずだなのだ。その解明も今後の課題だ。( ^)o(^ )
(注2)中大兄という名は奴(ナーガ)国の太子という意味だ。この場合ニギハヤヒの直系の人物を示すものと考えられる。ニギハヤヒの両親はイザナギ・イザナミだから、その直系の中大兄は皇統に繋がる人物なのだ。しかし、中大兄は天皇には即位しておらず、その孫が光仁天皇として即位して、以後光仁天皇の子の桓武天皇から今上天皇へとつながっているのだ。桓武天皇が大和の地から山背に都を遷した真意はこのことと関係しているはずだ。つまり大国主直系の天武天皇の曽孫氷上川継を反乱の容疑で捕らえ伊豆に流刑し、その他天武系皇族を抹殺して即位した桓武天皇は大和に居たら大物主に祟られる恐れがあるので、御霊が鎮座する三輪山から離れる必要があると考えたからではないだろうか。
平安遷都までの古代史は、とどのつまり、ヤマトの初代大王崇神天皇系と大国主の子応神天皇系の二つの大王家の権力争い・主導権争いが大きな流れだった。桓武天皇の登場によってこれが完全に終結したということなのだ。しかしこれによって兄スサノヲ系と弟ニギハヤヒ系の違いがあっても兄弟の両親はイザナギ・イザナミであるので皇祖神が変わったわけではないのだ。だから言わば大王家のお家騒動だった。これを策謀して権力を握り、外戚政治を行った藤原氏が栄華を極めるのだが、平城京から平安京に遷っても、民はそのまま怨霊に祟られて苦しんだようだ。最近活躍されている林千勝さんによれば、日本が戦争に引きずり込まれた原因の一つが藤原氏の謀略だったようだ。不比等の呪いが今の日本にも漂っている感じがするね。早く戦後政治を終わらせないと日本が終わりそうだ(;´Д`)

(注3)雄略天皇の崩御後の星川皇子の反乱の後に皇太子白髪皇子(清寧天皇)が即位し、5年後に崩御された。そのため皇嗣問題が生じ、ようやく履中天皇の孫の億計王・弘計王兄弟が播磨で見つかった。弟の弘計王(顕宗天皇)が兄より先に即位されるまで、短期間だが兄弟の同母姉の飯豊青皇女が天皇の役割を行った。最初の女帝飯豊天皇なのだが正式な代数には数えられていない。顕宗天皇が即位後三年で崩御され、兄の仁賢天皇の跡の武烈天皇のあり得ない御乱行は天皇家を貶める内容で、如何にも作り話のようだ。
継体天皇の即位は河内国樟葉宮、即位十九年後に大和の磐余玉穂宮に入っている。(2020.1.27 追加)
(注4)鹿児島神宮はかつて大隅正八幡宮と呼ばれ、「八幡神は大隅国に現れ、次に宇佐に遷り、ついに石清水に跡を垂れたと『今昔物語集』にも記載されている。」(wiki「鹿児島神宮」より)
最後までお付き合い、ありがとうございます。
通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)
よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング
よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング実は、万葉集も藤原氏に都合の良い歴史改ざんの事実を後世に密かに伝えるために大伴家持、山上憶良らによって作られたようなのだ。万葉集研究家の渡辺康則さんが中大兄皇子は「日本書紀」では中大兄とだけで、どこにも皇子とは書かれていないというヒントから皇太子でもない人物が即位したことにされたという衝撃的な事実を万葉集に隠された暗号を解読して突き止めたのだ(「捏造された天皇・天智」上・下 大空出版2013)。その続編「聖徳太子は天皇だった」(大空出版2014)ではもっと衝撃的なことが書かれていた。「隋書 倭国伝」にある倭国の大王アメノタリシヒコは推古天皇の時代と重なる。推古天皇だけではなく、「日本書紀」で言う用明天皇から斉明天皇までの時代は中大兄を万世一系の天皇に仕立て上げるための歴史ねつ造だったという結論なのだ。

しかし、もしもそういう大がかりな歴史改ざんが「日本書紀」によって本当に行われたのであれば、「宋書 倭の五王」の最後の武王とされる雄略天皇までは物証もあり実在と見ることができるが、その後の清寧天皇から、顕宗・仁賢・武烈・継体・安閑・宣化・欽明・敏達までの八代の天皇もすべてではないと思うが一部改ざんされている可能性が十分にあると思う(注1)。(202.1.23 赤字修正)

歴史ねつ造のやり方としては不自然なウソを隠すために先例を創作することが手っ取り早い。
例えば、天智天皇は都を近江として即位したので大和では即位していない。いきなり異例なことを書くと、天皇ではないかも知れないと怪しまれる(注2)。だから、同じく大和で即位していない継体天皇を登場させたのかも知れない。ヤマト政権が越前からオトド王を呼んだのであれば大和で即位しなければおかしい。継体天皇が応神天皇の五世孫だというのも何となく怪しく、新王朝ではないかとの説もある。清寧から継体即位までの話はかなり不自然だ(注3)。
また、歴史改ざんのもう一つの大きな目的は藤原氏が中大兄と共に追い落とした蘇我氏や物部氏の祖による日本建国の真相を隠すことだ。それはヤマト王権の基になる、由緒ある金印の倭の奴(ナーガ)国も当然隠蔽することになっている。
「日本書紀」では天武天皇は天智天皇の弟ということだが、違うのではないかという説が前からあった。万葉史観で舒明天皇も架空の存在ならば、天武天皇は武内宿禰を祖とする蘇我大王家の家系だとすれば壬申の乱の意味がスッキリするのだ。また天武天皇の皇后であった持統が女性天皇となることの異常さを隠すために、先代に推古だけでなく皇極(斉明)を登場させ、女帝はたまにあるんだよ、ということにしたのだ。持統は天智天皇の皇女鵜野讃良(ウノノサララ)でもあり、持統の孫の軽皇子を文武天皇として即位させたことの正統性のために、物部氏の祖である王年代紀第19代王天照大神尊ニギハヤヒから女神アマテラスに皇祖神をすり替えて天照大御神としたのだ。そのためにニギハヤヒも記紀神話で女神アマテラスの孫ニニギノミコトの兄弟神とすることによって真相を隠した。ニニギのネーミングの元ネタは第4代奴国王の天彌聞尊(アメノニニギノミコト)だろう(^_-)-☆
こうなると万世一系の皇統の男系男子によって継いできた今の天皇家も怪しい、どこかですり替わっているに違いないと考える人が出てくるかも知れない。実際、明治天皇のすり替え説もある。だがこれもデタラメだと直ぐに分かる。
日本における天皇の持つ意味、天皇の職務を考えると、すり替えは絶対にあり得ない。
天皇の本質は権力を持たない祭祀王としての権威だけの存在だったからだ。天皇は天変地異が起らないように皇祖神の魂と一体になるための厳しい修行をしなければならないのだ。長時間拘束される儀礼・式典にも先代から関わり、天皇教育されていないと絶対に務まるはずないからだ。もしもすり替えなどしたら国家の鎮護・安泰と国民の安寧を神々に祈り続ける、体力的・精神的負担が大きい宮中祭祀は、すり替わった本人にとってアホらしくなって耐えられず、とっくに簡素化され形骸化し、結局は天皇そのものが消えていたはずだからだ。
千年以上続く宮中祭祀の伝統が現代まで残っていることが、本物である証なのだ。
さて、建国神話に話を戻すと、初代天皇は第18代奴国王スサノヲ大王の直系である大国主ククチヒコ(多分スサノヲの六世孫)と縄文海人ムナカタ族の姫イザナミを母系とする台与(神功皇后)との間の子であるホムダワケ応神天皇であり、仲哀天皇は本当の父ではないことは既に何度も述べた。応神天皇はヤマトに殺された父の大国主の怨霊を鎮めるために即位した最初の祭祀王であり、呼称は後世だが本来の天皇の役割なのだ。大国主と台与が戦死したので、関祐二さんが推理したように南九州に逃亡し逼塞していたところ、ヤマトに呼び寄せられたのだろう(注4)。280年に西晋によってヤマトの後ろ盾の呉が滅んだので、追討を怖れたヤマトの大王(卑弥弓呼の次の世代か?)がホムダワケを呼び寄せて、王都の国名もヤマトゥ(邪馬台)とし、「母親の台与女王の代から西晋さんとはお付き合いしているヤマトゥ国なのですよ」としたというのが建国の真相なのだと推理した(【関連記事】参照)。
「日本書紀」では三輪山の大物主大神(大国主大神の和魂)が祟って、伝染病が発生し、民が半分以上死に、百姓は離流し、反逆するものも出たとある(崇神紀)。天皇は夢の中で、大物主が子のオオタタネコを呼び寄せて祀らせれば収まるぞと告げられたので、河内に探し出して大物主を祭らせたら国が収まったとある。
また、神武天皇の東征は武力ではナガスネヒコに撃退されたので、日の御子が太陽に向かって進んだのがよくないとして、熊野を回り、天香具山の赤土で平瓦などを作って天神地祇を祀り、呪いによって敵を撃退し即位できたというものだ。応神天皇の即位も神功皇后が、仲哀天皇の二人の皇子の謀略を見抜き、呪術で二人を滅ぼし即位させたとなっている。つまり神武天皇と応神天皇の話は時代設定も人物も変えてはいるが、内容的に似た話だった。
「神」の文字を諡り名に持つ4人の人物が日本建国に関わったことを、天智天皇の玄孫淡海三船が漢風諡号によって暗に示していた。神の命で武を以って葦原中つ国を統治した神武天皇。神に祟られたヤマトの大王崇神天皇。神の要請に応えて祭祀王に即位した応神天皇。神のような立派な功績を遺した神功皇后なのだ。
このヒントにより、謎がすべて解けるのだ。ヤマトにすでに降り立っていた天孫ニギハヤヒがトビのナガスネヒコを斬って神武天皇を即位させた話は、トビ(蛇)が化身である三輪山の大物主大神(大国主狗古智卑狗)がニギハヤヒの直系の崇神天皇(狗奴国王卑弥弓呼の次の王か?)によって殺された史実を示しているのだ。(2020.1.21 赤字追加)
「日本書紀」は初代大王の話をこのように時代も人物も異なる話を創作して歴史を改ざんし、スサノヲとニギハヤヒの子孫たち(由緒正しい蘇我氏と物部氏の祖)が行った日本建国の真相を隠したのだ。
通説・常識とまったく異なる話で、多くの方は混乱されたかも知れません。しかし、そのために「日本書紀」が建国の真相を神話に閉じ込めたのです。「日本書紀」成立から今年でちょうど千三百年、気の遠くなるほど長い年月でした。日本建国の真相を隠し通した藤原不比等の実力は大したものでした。最初に聖徳太子の謎が解明されて、それによって「日本書紀」のトリックがほぼ完全に解き明かされましたが、ほとんどが関裕二さんの功績ですよ(^_-)-☆
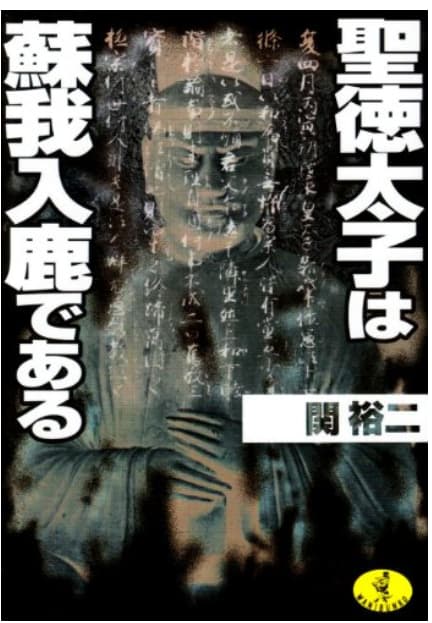
最後までお付き合いいただき感謝します。沢山応援いただき有難うございました。また、よろしくお願いしますね(*^^)v。
【関連記事】
古代史の謎を推理する(^_-)-☆

2020.1.21 210年頃築造の纏向石塚古墳を図に追加(石野博信「邪馬台国時代の王国群と纏向王宮」新泉社2019,p.47 より)
古代史を科学するには?(^_-)-☆
(注1)埼玉県の稲荷山古墳より出土した鉄剣と熊本県の江田船山古墳から出土した鉄刀に、ワカタケル大王雄略天皇の銘が刻まれているとされている。「日本書紀」では五王の事績を神功皇后の三韓征伐の話にして隠した。伊都国に逃げた女王台与がヤマト勢に追い詰められ、武器を取って戦った伝承を神功皇后の活躍の中に反映させ、戦死した台与の鎮魂のために女傑として持ち上げたと考えられる。
また、すでに述べたとおり初代天皇は神武と同一人物である応神として、280年の直後に即位したであろうと推定している。だから15代応神天皇までは10代崇神天皇を除きダミーなのだ。247年ごろ13歳で女王に立てられた台与の長子が応神天皇だとすると、子を産むには3、4年後だろうと考えると、即位は30歳代前半ということになる。そうすると、図に示したように応神天皇と五王の最初の倭王賛(履中天皇)まで間が空きすぎている。応神天皇と仁徳天皇の間、あるいは仁徳天皇と履中天皇の間に何代か存在するはずだなのだ。その解明も今後の課題だ。( ^)o(^ )
(注2)中大兄という名は奴(ナーガ)国の太子という意味だ。この場合ニギハヤヒの直系の人物を示すものと考えられる。ニギハヤヒの両親はイザナギ・イザナミだから、その直系の中大兄は皇統に繋がる人物なのだ。しかし、中大兄は天皇には即位しておらず、その孫が光仁天皇として即位して、以後光仁天皇の子の桓武天皇から今上天皇へとつながっているのだ。桓武天皇が大和の地から山背に都を遷した真意はこのことと関係しているはずだ。つまり大国主直系の天武天皇の曽孫氷上川継を反乱の容疑で捕らえ伊豆に流刑し、その他天武系皇族を抹殺して即位した桓武天皇は大和に居たら大物主に祟られる恐れがあるので、御霊が鎮座する三輪山から離れる必要があると考えたからではないだろうか。
平安遷都までの古代史は、とどのつまり、ヤマトの初代大王崇神天皇系と大国主の子応神天皇系の二つの大王家の権力争い・主導権争いが大きな流れだった。桓武天皇の登場によってこれが完全に終結したということなのだ。しかしこれによって兄スサノヲ系と弟ニギハヤヒ系の違いがあっても兄弟の両親はイザナギ・イザナミであるので皇祖神が変わったわけではないのだ。だから言わば大王家のお家騒動だった。これを策謀して権力を握り、外戚政治を行った藤原氏が栄華を極めるのだが、平城京から平安京に遷っても、民はそのまま怨霊に祟られて苦しんだようだ。最近活躍されている林千勝さんによれば、日本が戦争に引きずり込まれた原因の一つが藤原氏の謀略だったようだ。不比等の呪いが今の日本にも漂っている感じがするね。早く戦後政治を終わらせないと日本が終わりそうだ(;´Д`)

(注3)雄略天皇の崩御後の星川皇子の反乱の後に皇太子白髪皇子(清寧天皇)が即位し、5年後に崩御された。そのため皇嗣問題が生じ、ようやく履中天皇の孫の億計王・弘計王兄弟が播磨で見つかった。弟の弘計王(顕宗天皇)が兄より先に即位されるまで、短期間だが兄弟の同母姉の飯豊青皇女が天皇の役割を行った。最初の女帝飯豊天皇なのだが正式な代数には数えられていない。顕宗天皇が即位後三年で崩御され、兄の仁賢天皇の跡の武烈天皇のあり得ない御乱行は天皇家を貶める内容で、如何にも作り話のようだ。
継体天皇の即位は河内国樟葉宮、即位十九年後に大和の磐余玉穂宮に入っている。(2020.1.27 追加)
(注4)鹿児島神宮はかつて大隅正八幡宮と呼ばれ、「八幡神は大隅国に現れ、次に宇佐に遷り、ついに石清水に跡を垂れたと『今昔物語集』にも記載されている。」(wiki「鹿児島神宮」より)
最後までお付き合い、ありがとうございます。
通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)
よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング













