平安時代好きブロガー なぎ です。
2024年5月のこと。
大津市歴史博物館に併設するCafe Restaurant Inti(カフェ・レストラン インティ)にて「紫式部スペシャルランチ」をいただきました。
大河ドラマ「光る君へ」を意識してつくられたプレートです。

真上から見るとこんな感じ。
近江牛を使ったコロッケ、ジャンボ海老フライ、ソースやサラダは紫式部のイメージカラーの赤紫や紫色をが彩りに添えられています。
小鉢にスープも嬉しいですね。好きなもの満載!

そして、近江牛をつかったコロッケには紫式部イメージ(後ろ姿)の旗がさしてあるのでした。

食後にはコーヒーとデザートをいただきました。
(プラス200円で「紫式部スペシャルランチ」にプチデザートを付けることができました)
とってもおいしかったです!!
※「紫式部スペシャルランチ」は1日7食限定だそうですよ。

店内にIntiの紫式部プレミアムコーヒーのドリップバッグ(2種類5パック入り)があったので購入。
IntiのInstagram(@inti_0401)によると
『ほほえむ君』はエルサルバドルを主としたブレンドで上品な酸味の中に僅かな香ばしさが感じられるブレンド、
『ひらめく君』はコロンビアを主としたブレンドでフルーティな甘い香りの中に程良い苦みが感じられるブレンド
とのこと。

 『ほほえむ君』に書かれているのは『源氏物語』胡蝶巻において舟楽の場面で秋好中宮の女房が詠んだ歌。
『ほほえむ君』に書かれているのは『源氏物語』胡蝶巻において舟楽の場面で秋好中宮の女房が詠んだ歌。
春の日のうららにさして行く舟は
棹のしづくも花ぞ散りける
[訳:春の日のうららかな中を漕いで行く舟は 棹のしずくも花となって散ります]
 『ひらめく君』に書かれているのは『源氏物語』明石巻において光源氏が明石の君を初めて訪ねる前に紫の上を想って詠んだ歌。
『ひらめく君』に書かれているのは『源氏物語』明石巻において光源氏が明石の君を初めて訪ねる前に紫の上を想って詠んだ歌。
秋の夜の月毛の駒よわが恋ふる
雲居を掛けれ時の間も見む
[訳:秋の夜の月毛の駒よ、わが恋する都へ天翔っておくれ 束の間でもあの人に会いたいので]
【訳は、渋谷栄一 氏のwebサイト 『源氏物語の世界』より引用】
パッケージのイラストも可愛く、和歌のチョイスも素敵ですよね。
どちらのコーヒーもおいしくいただきました!
また買えないかしら…。


Cafe Restaurant Inti(カフェ レストラン インティ)
滋賀県大津市御陵町2番3号 市民文化会館内

















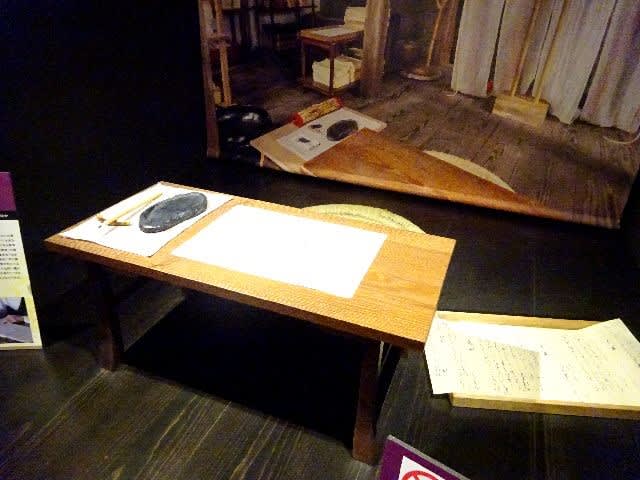









































 「光る君へ 宇治 大河ドラマ展」レポの続きは、
「光る君へ 宇治 大河ドラマ展」レポの続きは、












