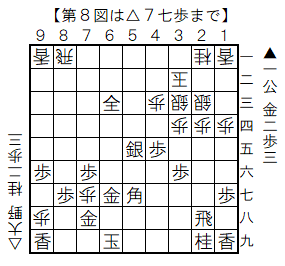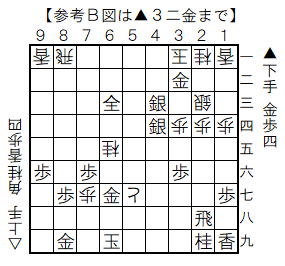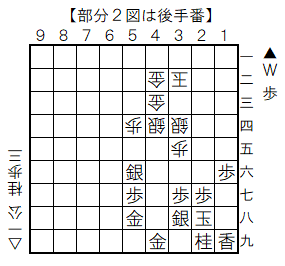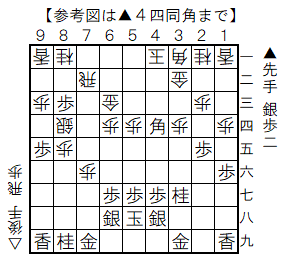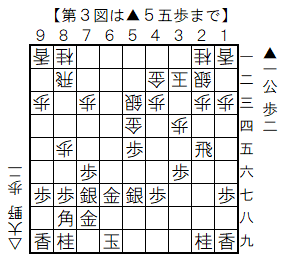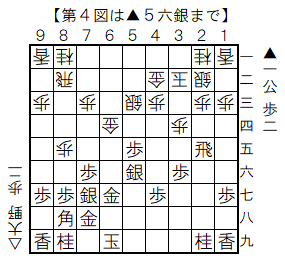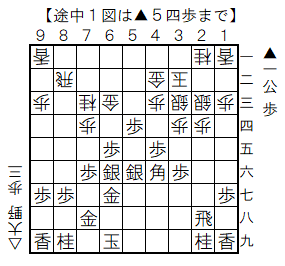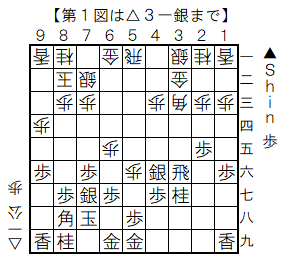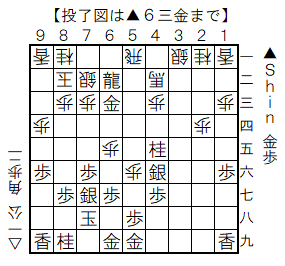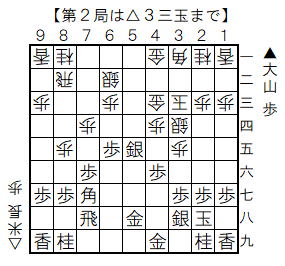おととい出題した「将棋クイズ50問」の解答です。
【第1問】カロリーナ女流初段の正式な名前はどれ?
A.カロリーナ・クリスティーナ・ステチェンスカ
B.カロリーナ・スカーレット・ステチェンスカ
C.カロリーナ・マクシミリアン・ステチェンスカ
【正解】A.
【第2問】次に掲げるのは、藤井聡太二冠が指して話題になった手です。古い順に並んでいるのはどれ?
A.小林裕士七段戦「▲5七玉」→中田宏樹八段戦「△6二銀」→石田直裕五段戦「△7七同飛成」
B.中田八段戦「△6二銀」→石田五段戦「△7七同飛成」→小林七段戦「▲5七玉」
C.石田五段戦「△7七同飛成」→小林七段戦「▲5七玉」→中田八段戦「△6二銀」
【正解】C.△7七同飛成は、2018年6月5日に指された、第31期竜王戦ランキング戦5組決勝戦。この一手は、第46回将棋大賞・升田幸三賞を獲得した。

▲5七玉は、2018年9月17日に指された第3期叡王戦七段戦。

△6二銀は、2019年3月27日に指された第32期竜王戦4組3回戦。

【第3問】協賛社とタイトル名の組み合わせで、違うものはどれ?
A.ALSOK杯王座戦 B.お~いお茶杯王位戦 C.ヒューリック杯棋聖戦
【正解】A.ALSOK杯は王将戦。今月から特別協賛となった。
【第4問】「米長玉」は、玉が「9八」や「1二」にいることをいいますが、1983年に何度か指された「新米長玉」は、玉がどこにいることをいう?
A.8九または2一 B.7七または3三 C.4八または6二
【正解】B.大山康晴王将との王将戦七番勝負では、2局現れた。
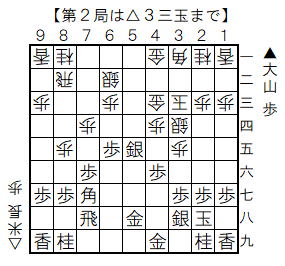

【第5問】デビュー戦の相手が加藤一二三九段でなかった棋士は誰?
A.谷川浩司 B.羽生善治 C.藤井聡太
【正解】B.谷川九段とは1977年2月5日、早指し将棋選手権戦のお好み対局で、公式戦扱いで指された。
藤井二冠とは2016年12月24日、第30期竜王戦ランキング戦6組1回戦で指された。
羽生九段の相手は宮田利男六段(当時)で、1986年1月31日に指された(第36期王将戦一次予選)。
【第6問】現在の女流棋士会とLPSA、フリー女流棋士で、名前に最も使われている字は、「子」の24。では、その次に多く使われている字はどれ?
A.愛 B.恵 C.美
【正解】C.「美」で、8名。甲斐智美女流五段、山田久美女流四段、上田初美女流四段、神田真由美女流二段、中倉宏美女流二段、大庭美夏女流初段、大庭美樹女流初段、山口絵美菜女流1級。
「恵」は7名。中井広恵女流六段、谷川治恵女流五段、森安多恵子女流四段、伊藤沙恵女流三段、石高澄恵女流二段、山口恵梨子女流二段、塚田恵梨花女流初段。
「愛」は6名。香川愛生女流四段、渡部愛女流三段、伊奈川愛菓女流二段、飯野愛女流初段、加藤結李愛女流初段、高浜愛子女流2級。ちなみに「香」も6名いる。
【第7問】順位戦の対局日に、寝坊で1時間遅刻してしまいました。この棋士はどうなる?
A.持ち時間から1時間引かれる B.持ち時間から3時間引かれる C.負け
【正解】C.現在のルールでは、1時間の遅刻は即負け。1時間未満は、遅刻ぶんの3倍の時間を引かれる。
【第8問】江戸時代、駒台の前身だったものは一般的に何?
A.扇 B.懐紙 C.蛤の貝殻
【正解】A.でも私は見たことがないので、何ともいえない。
【第9問】第38回NHK杯4回戦・加藤一二三九段VS羽生善治五段戦の解説者は誰?
A.大山康晴 B.米長邦雄 C.石田和雄
【正解】B.羽生五段の「▲5二銀」が指された瞬間、「おおーおおお、やった!!」と叫んだのはあまりにも有名。
【第10問】1981年にNHKで放送された、銀河テレビ小説「煙が目にしみる」を書いた脚本家は誰?
A.ジェームス三木 B.長坂秀佳 C.橋田壽賀子
【正解】A.このペンネームは「税務署行き」をもじったものとされる。
【第11問】藤井二冠は、デビューから何連勝した?
A.28連勝 B.29連勝 C.30連勝
【正解】B.竜王戦の決勝トーナメントで佐々木勇気五段に敗れ、ストップした。
【第12問】藤井二冠は、竜王戦ランキング戦で、何連勝継続中?
A.23連勝 B.24連勝 C.25連勝
【正解】B.6+5+5+4+4で、24連勝。
【第13問】「令和」になって、初めて公式戦で勝利した女流棋士は誰?
A.塚田恵梨花 B.藤井奈々 C.和田あき
【正解】C.清麗戦で長沢千和子女流四段に勝った。
【第14問】NHKで放送されたドラマ「盤上の向日葵」が、原作と違った設定になったのはどれ?
A.元奨励会三段の男性刑事が女性刑事になった
B.主人公が右利きから左利きになった
C.男性の遺体が発見されたのが、埼玉県の山中から千葉県の山中になった
【正解】A.「佐野直也」から「佐野直子」になった。
【第15問】NHKテレビドラマ「うつ病九段」で、先崎学九段を演じた俳優は誰?
A.音尾琢真 B.戸次重幸 C.安田顕
【正解】C.選択肢はいずれもTEAM NACSのメンバー。ほかのメンバーは森崎博之と大泉洋。
【第16問】次の中で、藤井二冠が最も早く達成したものはどれ?
A.公式戦100勝 B.朝日杯初優勝 C.順位戦でC級1組昇級を決める
【正解】C.100勝達成は2018年12月12日。朝日杯初優勝は2018年2月17日。順位戦C級2組は2018年3月15日の最終戦に勝って10勝0敗としたが、2月1日の9回戦に勝って昇級を決めたので、正解はCとなる。
【第17問】1947年、現・日本将棋連盟の初代会長に就いた棋士は誰?
A.木村義雄 B.渡辺東一 C.坂口允彦
【正解】A.木村名人のあとは、1948年に渡辺八段、1953年に坂口八段が就いた。
【第18問】将棋ペンクラブの初代会長は誰?
A.河口俊彦 B.東公平 C.山口瞳
【正解】A.現在の会長は木村晋介氏。
【第19問】現在の最年少棋士は誰?
A.藤井聡太 B.伊藤匠 C.高田明浩
【正解】B.藤井二冠は2002年7月19日生まれ。伊藤四段は2002年10月10日生まれ。高田四段は2002年6月20日生まれ。
【第20問】次のうち、実在しなかった棋戦はどれ?
A.早指し王位決定戦 B.早指し古豪戦 C.早指し新鋭戦
【正解】B.早指し王位決定戦は1954年から59年まで開催され、その後王位戦に発展解消した。
早指し新鋭戦は、テレビ東京で放送されていた、早指し将棋選手権戦の若手棋士バージョン。1982年度から2002年度まで開催された。
早指し古豪戦はないが古豪新鋭戦はあり、1957年度から73年度まで行われた。
【第21問】谷川八段が加藤一二三名人から名人を奪取した第6局の戦型は何?
A.角換わり腰掛け銀 B.ひねり飛車 C.矢倉
【正解】B.いまは絶滅している。
【第22問】その対局のあと、谷川新名人が述べた名ゼリフは何?
【正解】「1年間、名人位を預からせていただきます」。将棋史の、名ゼリフトップ10に入る。
【第23問】升田幸三実力制第四代名人の、戸籍上の正式な読みは?
A.ますだ・こうざん B.ますだ・こうそう C.ますだ・さちぞう
【正解】B.将棋界では「こうぞう」で通したそう。実は四男。
【第24問】礒谷真帆女流初段の正しい読みはどれ?
A.いそがい・まほ B.いそたに・まほ C.いそや・まほ
【正解】B.
【第25問】糸谷哲郎八段の正しい読みはどれ?
A.いとたに・てつろう B.いとだに・てつろう C.いとや・てつろう
【正解】B.
【第26問】東京・将棋会館がある所在地はどこ?
A.渋谷区 B.新宿区 C.千代田区
【正解】A.渋谷区千駄ヶ谷2-39-9
【第27問】東京・将棋会館の日本将棋連盟道場で、四段から五段に昇段するには、何勝すればいい?
A.12連勝or15勝2敗 B.15連勝or18勝2敗 C.18連勝or24勝2敗
【正解】C.Aは二段から三段へ。Bは三段から四段へ。ちなみに、五段から六段へは、25連勝or35勝2敗が必要。
【第28問】かつて東京・将棋会館の地下にあったレストランの名前は何?
A.歩 B.香 C.桂
【正解】A.あゆむ、と読む。1997年に惜しまれつつ閉店となった。
【第29問】鶴巻温泉「元湯陣屋」館内には、升田王将(当時)の色紙が飾られています。「強がりが 雪に轉んで ○○○○○」。○に入る言葉はどれ?
A.梅仰ぐ B.ベソをかく C.廻り見る
【正解】C.Aは、季重なりになる。
【第30問】かつてタイトル戦が指された施設はどこ?
A.蔵前国技館 B.新宿御苑 C.六義園
【正解】A.これはちょっと意地悪問題。1975年に「第1回・将棋の日」が蔵前国技館で行われ、第14期十段戦第2局・中原誠十段VS大山棋聖戦の一部が指された。
【第31問】将棋連盟御用達「ほそ島や」で人気の中華そばは、いくら?
A.600円 B.650円 C.700円
【正解】C.基本は蕎麦屋だが、蕎麦よりラーメンのほうが美味い?らしい。
【第32問】LPSA将棋サロンの変遷で正しいのはどれ?
A.麹町→駒込→芝浦 B.駒込→芝浦→麹町 C.芝浦→麹町→駒込
【正解】B.現在は1回の定員4名で、受講料は一般5,500円。要予約。
【第33問】2012年1月14日に指された、米長邦雄永世棋聖VSボンクラーズ戦。ボンクラーズの初手▲7六歩に、米長永世棋聖が2手目に指した手は?
A.△3二金 B.△6二玉 C.△7二金
【正解】B.当人は「これが新米長玉だよ」と言ったとか。
【第34問】次の3つの中で、最も新しく創設された研修会はどこ?
A.北海道研修会 B.東北研修会 C.九州研修会
【正解】B.北海道研修会は2020年10月11日、東北研修会は今月11日、九州研修会は2016年1月10日開講。
【第35問】関西将棋会館の最寄り駅はどこ?
A.大阪駅 B.福島駅 C.西九条駅
【正解】B.JR福島駅から徒歩3分。2023年に、大阪府高槻市に移転予定。
【第36問】渡辺明名人の奥様・伊奈めぐみさんが描いている「将棋の渡辺くん」が掲載されている雑誌はどれ?
A.ビッグコミック B.別冊少年マガジン C.グランドジャンプ
【正解】B.2013年6月号から連載されている。
【第37問】第1期叡王戦の優勝者は誰?
A.佐藤天彦 B.山崎隆之 C.高見泰地
【正解】B.高見七段は、叡王戦が公式戦になってからの初の覇者。
【第38問】昨年の第33期竜王戦・豊島将之竜王VS羽生九段の第1局では、珍しいことが起こりました。それは何?
A.駒柱が2回現れた B.千日手が2回成立した C.双方の玉が終局まで1回も動かなかった
【正解】C.52手で終了したが、これも短手数で珍しかった。
【第39問】今月3日、アマ九段位を授与された愛棋家は誰?
A.今西修 B.中戸俊洋 C.堀田正夫
【正解】B.堀田正夫氏は1人目のアマ九段授与者。今西修氏は、日本アマチュア将棋連盟理事長。
【第40問】正式な駒の並べ方は、大橋流と伊藤流になります。途中までは同じですが、分岐するのは何枚目から?
A.8枚目 B.10枚目 C.12枚目
【正解】A.大橋流は8枚目から香香角飛歩9となるが、伊藤流は8枚目に▲9七歩と置き、▲1七まで並べて、香香角飛となる。これは、飛び道具を敵陣に直射させるのは失礼、という考えがあるため。
【第41問】関浩七段が若いころ上げたお手柄は何?
A.泥棒を捕まえた B.溺れている子供を助けた C.老人を詐欺から救った
【正解】A.当時は新聞にも載ったが、それを貼ったスクラップブックを、私は棄ててしまった。
【第42問】「都詰」とは何?
A.玉が5一もしくは5九の地点で詰みあがる
B.玉が5三もしくは5七の地点で詰みあがる
C.玉が5五の地点で詰みあがる
【正解】C.
【第43問】第79期順位戦で、山崎八段がA級入りを決めましたが、B級1組には何期在籍した?
A.9期 B.11期 C.13期
【正解】C.第67期にB級1組入りしてから、一度も降級しなかった。
【第44問】第34期竜王戦の優勝賞金は4400万円。では、第1期はいくらだった?
A.1800万円 B.2200万円 C.2600万円
【正解】C.私には縁がない数字である。
【第45問】杉本昌隆八段が「週刊文春」にて4月から始めたエッセイのタイトルは何?
A.師匠日誌 B.師匠はつらいよ C.となりの師匠
【正解】B.
【第46問】渡辺名人は今年の3月に棋王位を防衛し、タイトル獲得を通算28期とし、谷川九段の27期を抜きました。歴代何位になった?
A.3位 B.4位 C.5位
【正解】B.1位は羽生九段の99期、2位は大山十五世名人の80期、3位は中原誠十六世名人の64期。
【第47問】2020年、ゲームソフト会社に就職した棋士は誰?
A.伊藤真吾 B.藤森哲也 C.星野良生
【正解】C.伊藤五段と藤森五段は、ユーチューバー。
【第48問】アマチュア時代、一公と対局していない女流棋士は誰?
A.室谷由紀 B.加藤圭 C.礒谷真帆
【正解】A.加藤女流二段も礒谷女流初段も、アマ時代に私と指している。
【第49問】あなたが思う将棋界の七不思議をひとつ挙げてください。
【解答例】羽生九段が十八世名人になれなかった。
【第50問】あなたがもし日本将棋連盟の会長になったら、何をしますか?
【解答例】「棋士と将棋ファンで行く船の旅」を復活させる。
いかがでしたか。第3弾をやれる日が来たらうれしいです。