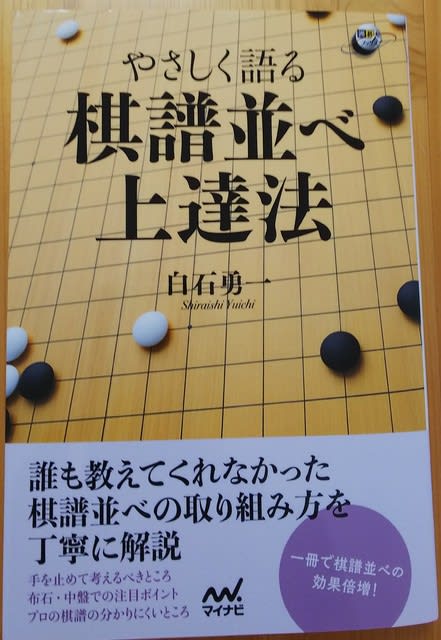皆様こんばんは。
本因坊戦第3局は本因坊文裕が勝ち、3連勝となりました。
予想外の展開になっていますが、勝負の怖いところですね。
とは言え、3連敗の4連勝は過去のタイトル戦で何度も起こっているので、これで決まりということはありません。
追い込まれた一力挑戦者の頑張りに注目しましょう。
さて、本日は5/24に出版された新刊、「やさしく語る 囲碁・石の攻め方」の内容について詳しく紹介していきたいと思います。
まず、本書は攻めに関する考え方を初歩の初歩から応用までしっかり学べる内容となっています。
何事も理解が曖昧な状態なままでは、練習してもなかなか上達できないものです。
攻めが得意でない方や関心が無かった方はもちろん、攻めが得意や好きと感じている方にも役立つでしょう。
<序章 攻めの意義と注意点>
「なぜ石を攻めるのか」
石の攻め方というのは手段ですが、そもそも目的が定まっていなければ正しい手段を判断することができません。
その目的とは当然ながら利益を上げることですが、では具体的にどんな得が考えられるでしょうか?
実は、この問いに正確に答えられる方は少ないのではないかと思っています。
そしてこの部分の理解が曖昧になっていると、攻めに関する考え方が全体的に大きくずれてしまいます。
そこで、本書では最初に攻めの意義から詳しく解説しています。
例えば、攻めの利益の中で最も分かりやすいものは石を取ってしまうことでしょう。
しかし、取ることによって具体的にどのような利益が得られるかとなると、やはり理解が曖昧になっている方が少なくありません。
その状態では、石を取りにいくべきかどうかを正しく判断することは困難です。
ですから、石を取ることの意義についても、具体的な数字なども交えて解説しています。
<第1章 石の攻め方と特徴>
ここからは具体的な手段について、問題形式で解説していきます。
「根拠を奪う」「閉じ込める」「分断する」「迫る」の4種類ですね。
相手の石を弱くするということに関しては共通していますが、その局面によってそれぞれの攻撃力は変わってきますし、利益への結び付き方も傾向が異なります。
それらを正しく理解しておくことで、はじめて正しい使い分けができるようになります。
また、手段より目的が先と書きましたが、実は目的より先にくるべきものがあります。
それが状況判断です。
状況が正しく認識できていなければ、正しく目的を決めることができません。
ですから、本章では状況判断を交えながら解説しています。
状況判断の中でも最も大切なのは石の強弱ですが、これについては特に詳しく解説しています。
<第2章 練習問題>
第1章の内容を踏まえたうえで、問題に取り組んで頂きます。
4種類の攻め方を正しく使い分けられるようになるには、練習が欠かせません。
また、単にその攻め方を選ぶかだけでなく、数手先の進行をイメージして頂くとより効果的です。
<第3章 応用的な攻め>
第1章と第2章で、基本的な攻め方を学んで頂きました。
最初は欲張らず、まずは基本をしっかりと身に付けて頂くことをおすすめします。
何度読み返して頂いても良いでしょう。
そして本章では、一段レベルの高い攻め方について解説しています。
基本的な攻め方は、一言で言えば弱い石を適切な方法で攻める、ということです。
これができるようになるだけでも、大きなレベルアップが期待できます。
しかし、時には基本的な攻め方では上手くいかないこともあります。
あらゆる局面に対応できるようになるためには、応用的な攻め方も学ぶ必要があります。
その1つが攻めを中断するタイミングです。
4つの攻め方のどれを選んでも、利益が得られないという局面があります。
そんなときの解答の1つが、攻めを中断するということです。
気持ち良く攻めていたつもりが、結果として利益が無かった、あるいは損をしてしまったというケースはどなたも経験があるでしょう。
その原因の1つとして考えられるのが、攻めを中断するタイミングを間違っていることです。
これ以上攻めても利益が上がらない、あるいはそもそも攻めが不可能な状況で攻めようとしてしまっているということですね。
それは大きな失点につながる可能性も高いのです。
石を取れる場合でない限り、必ずどこかで攻めを中断したり、場合によっては完全に放棄しなければいけませんね。
つまり、攻めを中断するタイミングは毎回の攻めで必ず問われるのです。
難易度を考えて応用には分類したものの、重要度は非常に高いと言えます。
しかし、実際にできている方は非常に少ないと思います。
本書で特にお伝えしたかったことの1つです。
応用的な攻め方のもう1つはモタレ攻めです。
直接攻めても上手くいかないとき、他の石に働きかけることで戦力を整えたり、場合によっては「王手飛車取り」のような状況に持ち込む技術ですね。
4つの攻め方と比べて、状況判断や数手先を読むということをより正確に行う必要があり、明確に難易度が高いと言えるでしょう。
ですが、これができるようになれば攻めがより楽しくなることは間違いありません。
最後はリスクを考えるということです。
囲碁では複雑な局面もありますし、棋力不足によってより難しくなってしまうこともあります。
それはプロであっても変わりません。
そのような成功するという確信が持てない状況では、リスクとリターンを考えることが勝率アップにつながります。
例えば、最善と思える攻め方があっても、失敗のリスクが大きすぎると判断すれば、次善の道で我慢した方が良いこともあるということですね。
応用という意味では、これが一番かもしれません。
囲碁は自分なりに最善手を目指すのが基本ですからね。
基本的な攻め方をしっかり学ぶことの方が優先されます。
私がリスクとリターンをしっかり考えて打つようになったのは、プロになって以降のことです(それはそれで遅すぎましたが・・・)。
とは言え、せっかく努力を重ねて築き上げた好局が、勇み足で台無しになってしまうのは悲しいことでしょう。
また、それを繰り返していると、攻めが怖くなってしまうこともあるかもしれません。
誰もがプロのように打たれ強いわけではありませんからね。
リスクとリターンを考え、大きな失敗を減らすことで安心して打てるようになるのであれば、それも大事な技術ではないかと思います。
<第5章 棋譜解説>
良い攻め方や中断のタイミングを学ぶためには、局面を切り取られた問題図だけでは不足でしょう。
やはり一局の流れから学んで頂くことも必要です。
そこで、お手本となるプロ同士の棋譜を収録しました。
お互いの着手の目的が分かりやすく、かつ難しい手が少ないものを厳選しています。
攻めの楽しさ、気持ち良さを体験できると思いますので、ぜひ実際に碁盤に並べて頂ければと思います。
余談ですが、プロの対局は戦いは多いものの、実はどちらかが一方的に攻めている対局は少なく、多くは乱戦模様となっています。
収録したのは7局ですが、そのために数千局の棋譜を見ました。
本書で最も苦労したところかもしれません。
以上で本書の内容を概ねお伝えできたかと思います。
皆様のお役に立てれば嬉しいです。
なお、本書を含む著書へのサインについてはお気軽にご依頼ください。
永代塾囲碁サロンでお待ちしています。
また、ご感想・ご質問など頂ければ、今後も何らかの形でお答えしていくかもしれません。
コメント欄を空けておきますので、お気軽にご投稿ください。
永代塾囲碁サロン・・・武蔵小杉駅徒歩5分です。2020年7月から共同経営者になりました。
☆「やさしく語る」シリーズ、好評発売中!
現在、「やさしく語る 碁の本質」 「やさしく語る 布石の原則」 「やさしく語る 碁の大局観」 「やさしく語る 棋譜並べ上達法」の4冊を出版しています。
5冊目も出ました!