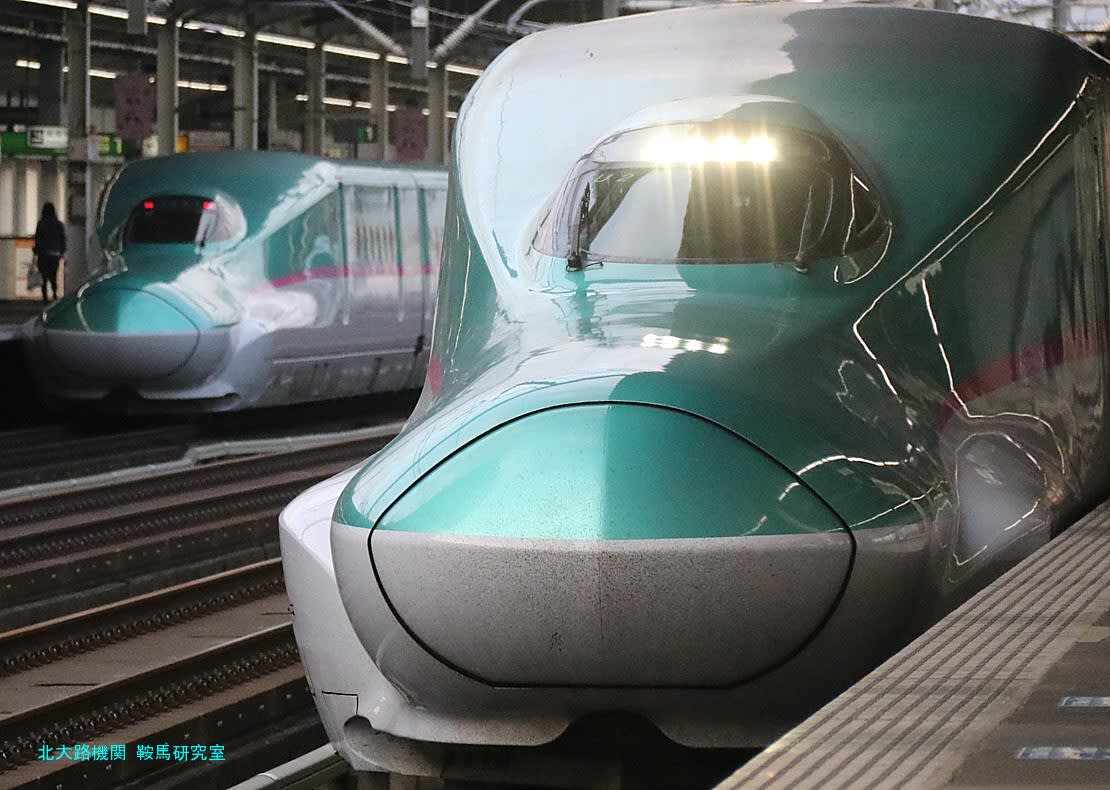■大晦日の自衛隊最新装備2016
大晦日となり今年もあと数時間、そこで本日は今年一年を振り返るべく、2016年に撮影し、Weblog北大路機関が紹介しました自衛隊の各種最新装備を紹介しましょう。

ヘリコプター搭載護衛艦くらま、と並走する曳船58号型YT-02, 舞鶴警備隊隷下舞鶴港務隊に所属する一隻ですが、YT-02は曳船58号型の後期型に当たります、2013年に就役、この後期型は一目瞭然として起倒式マストを採用しており、これこそがヘリコプター搭載護衛艦の従来型から全通飛行甲板型への世代交代を象徴する構造といえるかもしれません。

YT-02が起倒式マストを採用しました背景には、ひゅうが型ヘリコプター搭載護衛艦以降、上部構造物に加え全通飛行甲板の採用により曳船の入港支援作業に際しマストが護衛艦の張り出した飛行甲板へ接触しないよう配慮した構造です。くらま、は最後の従来型ヘリコプター搭載護衛艦、年度内に除籍予定で、この取り合わせこそ今年の象徴する一枚です。

X-2実験機、技術研究本部が開発し防衛装備庁として研究が継続されています将来戦闘機開発への技術を総合した実証機です。防衛省では様々な将来戦闘機構成技術を個々に開発していますが、これを全体として航空機の形状とし、総合的な技術試験へ応用します。開発費がかなり抑えられていますが、その予算には部分研究の費用は当然含まれていません。

ATD-X,先進技術実証機として高運動飛行制御システムの研究試作や実証エンジンの研究と高運動ステルス機技術のシステムインテグレーションの研究等々新技術が集成され、初飛行の時点でX-2実験機となっています。今後は更なる技術開発を経て実用航空機を新たに設計開発し、将来的に現在運用中のF-2支援戦闘機の後継機を国産開発する構想が進む。

三菱重工にて製造され岐阜基地防衛装備庁施設での試験を実施するため、県営名古屋空港と岐阜基地周辺は多くの航空愛好家と報道関係者がカメラを並べていましたが、無事初飛行しその後の地上試験を経て飛行試験を今冬より開始しました。X-2は早速岐阜基地航空祭にて地上展示となり、最長実に三時間待ちの大行列が伸びた事でも話題となりましたね。

16式機動戦闘車、統合機動防衛力整備の切り札として本年制式化となった陸上自衛隊の最新装備です。52口径105mm砲を搭載し路上最高速度100km/h以上、重量26tとして新開発のC-2輸送機による空輸展開も可能です。火器管制装置には10式戦車の技術が応用されており行進間射撃に加えスラローム射撃能力等も有し文字通り世界第一線級の性能を誇る。

機動戦闘車として今年一月に第1空挺団降下訓練始めにて初公開されましたが、富士学校祭や富士総合火力演習、そして中央観閲式本番でも公開されました。量産は開始されており、全国の機動連隊機動戦闘車中隊と仮称される部隊へ配備される計画です。陸上自衛隊では戦車定数400両を300両へ改め、代えて機動戦闘車200両を調達する計画とのこと。

統合機動防衛力整備に際し、機動戦闘車は本土戦車部隊を基本的に教育部隊以外全て置き換え、機動力を以て着上陸正面などに展開、事態拡大阻止に当たると同時に戦車部隊を集中する北海道より戦車部隊を海上自衛隊等の協力を受け緊急展開し、複合的な事態対処能力を整備する方針となっています、輸送手段確保は困難ですが、今後の展開を見守りたい。

輸送防護車、豪州ペリーエンジアニング社が1996年に開発し現在はタレスオーストラリア社が販売を担当する耐爆車両です。防衛省はアルジェリアガスプラント邦人襲撃事件を受け、従来の在外邦人保護任務に際し、紛争地域でも政府指定空港や港湾へ邦人の自力退避を求めてきましたが、紛争地では常識的に難しいとの指摘があり自衛隊任務へ加えました。

ブッシュマスターとして開発されている本車は、空港や港湾など退避拠点と邦人が退避する大使館領事館や宿泊施設等とを輸送する任務に充てられ、地雷など爆発物に対し横転しない等の設計を採っています。陸上自衛隊には96式装輪装甲車が配備されていますが、専守防衛下の野戦を想定し車高を抑えている為、紛争地での運用は最優先ではありません。

中央即応集団へ集中配備されていますが、車内容積が大きく歩兵部隊輸送用に加え救急車両や通信中継車両等へ豪州軍では1000両以上が配備され運用幅を広めています。陸上自衛隊では大量配備の計画は無いとの事ですが、国際協力任務の増大や専守防衛下での段列や戦闘支援任務にも必要な装備であり、もう少し広い部隊への配備が求められる装備の一つ。

新野外通信システム、自衛隊が従来の85式無線機などを基幹とする通信体系とその改良型からデータ通信などへ大きく一歩すすめたもの。新師団通信システム師団はサーバ計算機室装置と中央処理装置から構成され、周波数ホッピング機能と耐電子戦性能を向上させたほか、多種多様な装備体系とのデータリンク、戦術インターネット能力を付与しました。

えのしま型掃海艇はつしま、FRP船体を採用した新世代の掃海艇えのしま型の三番艇で今年三月に竣工したばかりのもの、並ぶのは掃海艦やえやま型三隻の最後の一隻、掃海艦はちじょう、でこちらも二番艦つしま、一番艦やえやま、は既に除籍されており、新掃海艦あわじ竣工を待って本艦も除籍予定、機雷戦艦艇世代交代を象徴する一枚といえましょう。

S-10 水中航走式機雷掃討具、ひらしま型掃海艇と、えのしま型掃海艇へ搭載されている最新の機雷処分具と自航式可変深度ソナーを同時運用する極めて汎用性が高い水中ロボットです。ただ、近年は高性能化と共に取得費用が増大する機雷掃討具を敢えて狙う新世代の機雷が開発されており、機雷との戦いは年々対抗手段に対抗手段を重ねる競争が続きます。

最後になりましたが、本日は大晦日、今年一年、ありがとうございました。本年は行事特集再開等の原点回帰に合わせ連載記事の強化等を進めてまいりました。防衛への関心と理解や討議へ資する記事の毎日更新の維持を目指し今後も勧めてい参ります、Weblog北大路機関は多くの読者の方に支えられています、今後度もどうぞよろしく。それでは、皆様、良いお年を。
北大路機関:はるな くらま
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
大晦日となり今年もあと数時間、そこで本日は今年一年を振り返るべく、2016年に撮影し、Weblog北大路機関が紹介しました自衛隊の各種最新装備を紹介しましょう。

ヘリコプター搭載護衛艦くらま、と並走する曳船58号型YT-02, 舞鶴警備隊隷下舞鶴港務隊に所属する一隻ですが、YT-02は曳船58号型の後期型に当たります、2013年に就役、この後期型は一目瞭然として起倒式マストを採用しており、これこそがヘリコプター搭載護衛艦の従来型から全通飛行甲板型への世代交代を象徴する構造といえるかもしれません。

YT-02が起倒式マストを採用しました背景には、ひゅうが型ヘリコプター搭載護衛艦以降、上部構造物に加え全通飛行甲板の採用により曳船の入港支援作業に際しマストが護衛艦の張り出した飛行甲板へ接触しないよう配慮した構造です。くらま、は最後の従来型ヘリコプター搭載護衛艦、年度内に除籍予定で、この取り合わせこそ今年の象徴する一枚です。

X-2実験機、技術研究本部が開発し防衛装備庁として研究が継続されています将来戦闘機開発への技術を総合した実証機です。防衛省では様々な将来戦闘機構成技術を個々に開発していますが、これを全体として航空機の形状とし、総合的な技術試験へ応用します。開発費がかなり抑えられていますが、その予算には部分研究の費用は当然含まれていません。

ATD-X,先進技術実証機として高運動飛行制御システムの研究試作や実証エンジンの研究と高運動ステルス機技術のシステムインテグレーションの研究等々新技術が集成され、初飛行の時点でX-2実験機となっています。今後は更なる技術開発を経て実用航空機を新たに設計開発し、将来的に現在運用中のF-2支援戦闘機の後継機を国産開発する構想が進む。

三菱重工にて製造され岐阜基地防衛装備庁施設での試験を実施するため、県営名古屋空港と岐阜基地周辺は多くの航空愛好家と報道関係者がカメラを並べていましたが、無事初飛行しその後の地上試験を経て飛行試験を今冬より開始しました。X-2は早速岐阜基地航空祭にて地上展示となり、最長実に三時間待ちの大行列が伸びた事でも話題となりましたね。

16式機動戦闘車、統合機動防衛力整備の切り札として本年制式化となった陸上自衛隊の最新装備です。52口径105mm砲を搭載し路上最高速度100km/h以上、重量26tとして新開発のC-2輸送機による空輸展開も可能です。火器管制装置には10式戦車の技術が応用されており行進間射撃に加えスラローム射撃能力等も有し文字通り世界第一線級の性能を誇る。

機動戦闘車として今年一月に第1空挺団降下訓練始めにて初公開されましたが、富士学校祭や富士総合火力演習、そして中央観閲式本番でも公開されました。量産は開始されており、全国の機動連隊機動戦闘車中隊と仮称される部隊へ配備される計画です。陸上自衛隊では戦車定数400両を300両へ改め、代えて機動戦闘車200両を調達する計画とのこと。

統合機動防衛力整備に際し、機動戦闘車は本土戦車部隊を基本的に教育部隊以外全て置き換え、機動力を以て着上陸正面などに展開、事態拡大阻止に当たると同時に戦車部隊を集中する北海道より戦車部隊を海上自衛隊等の協力を受け緊急展開し、複合的な事態対処能力を整備する方針となっています、輸送手段確保は困難ですが、今後の展開を見守りたい。

輸送防護車、豪州ペリーエンジアニング社が1996年に開発し現在はタレスオーストラリア社が販売を担当する耐爆車両です。防衛省はアルジェリアガスプラント邦人襲撃事件を受け、従来の在外邦人保護任務に際し、紛争地域でも政府指定空港や港湾へ邦人の自力退避を求めてきましたが、紛争地では常識的に難しいとの指摘があり自衛隊任務へ加えました。

ブッシュマスターとして開発されている本車は、空港や港湾など退避拠点と邦人が退避する大使館領事館や宿泊施設等とを輸送する任務に充てられ、地雷など爆発物に対し横転しない等の設計を採っています。陸上自衛隊には96式装輪装甲車が配備されていますが、専守防衛下の野戦を想定し車高を抑えている為、紛争地での運用は最優先ではありません。

中央即応集団へ集中配備されていますが、車内容積が大きく歩兵部隊輸送用に加え救急車両や通信中継車両等へ豪州軍では1000両以上が配備され運用幅を広めています。陸上自衛隊では大量配備の計画は無いとの事ですが、国際協力任務の増大や専守防衛下での段列や戦闘支援任務にも必要な装備であり、もう少し広い部隊への配備が求められる装備の一つ。

新野外通信システム、自衛隊が従来の85式無線機などを基幹とする通信体系とその改良型からデータ通信などへ大きく一歩すすめたもの。新師団通信システム師団はサーバ計算機室装置と中央処理装置から構成され、周波数ホッピング機能と耐電子戦性能を向上させたほか、多種多様な装備体系とのデータリンク、戦術インターネット能力を付与しました。

えのしま型掃海艇はつしま、FRP船体を採用した新世代の掃海艇えのしま型の三番艇で今年三月に竣工したばかりのもの、並ぶのは掃海艦やえやま型三隻の最後の一隻、掃海艦はちじょう、でこちらも二番艦つしま、一番艦やえやま、は既に除籍されており、新掃海艦あわじ竣工を待って本艦も除籍予定、機雷戦艦艇世代交代を象徴する一枚といえましょう。

S-10 水中航走式機雷掃討具、ひらしま型掃海艇と、えのしま型掃海艇へ搭載されている最新の機雷処分具と自航式可変深度ソナーを同時運用する極めて汎用性が高い水中ロボットです。ただ、近年は高性能化と共に取得費用が増大する機雷掃討具を敢えて狙う新世代の機雷が開発されており、機雷との戦いは年々対抗手段に対抗手段を重ねる競争が続きます。

最後になりましたが、本日は大晦日、今年一年、ありがとうございました。本年は行事特集再開等の原点回帰に合わせ連載記事の強化等を進めてまいりました。防衛への関心と理解や討議へ資する記事の毎日更新の維持を目指し今後も勧めてい参ります、Weblog北大路機関は多くの読者の方に支えられています、今後度もどうぞよろしく。それでは、皆様、良いお年を。
北大路機関:はるな くらま
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)