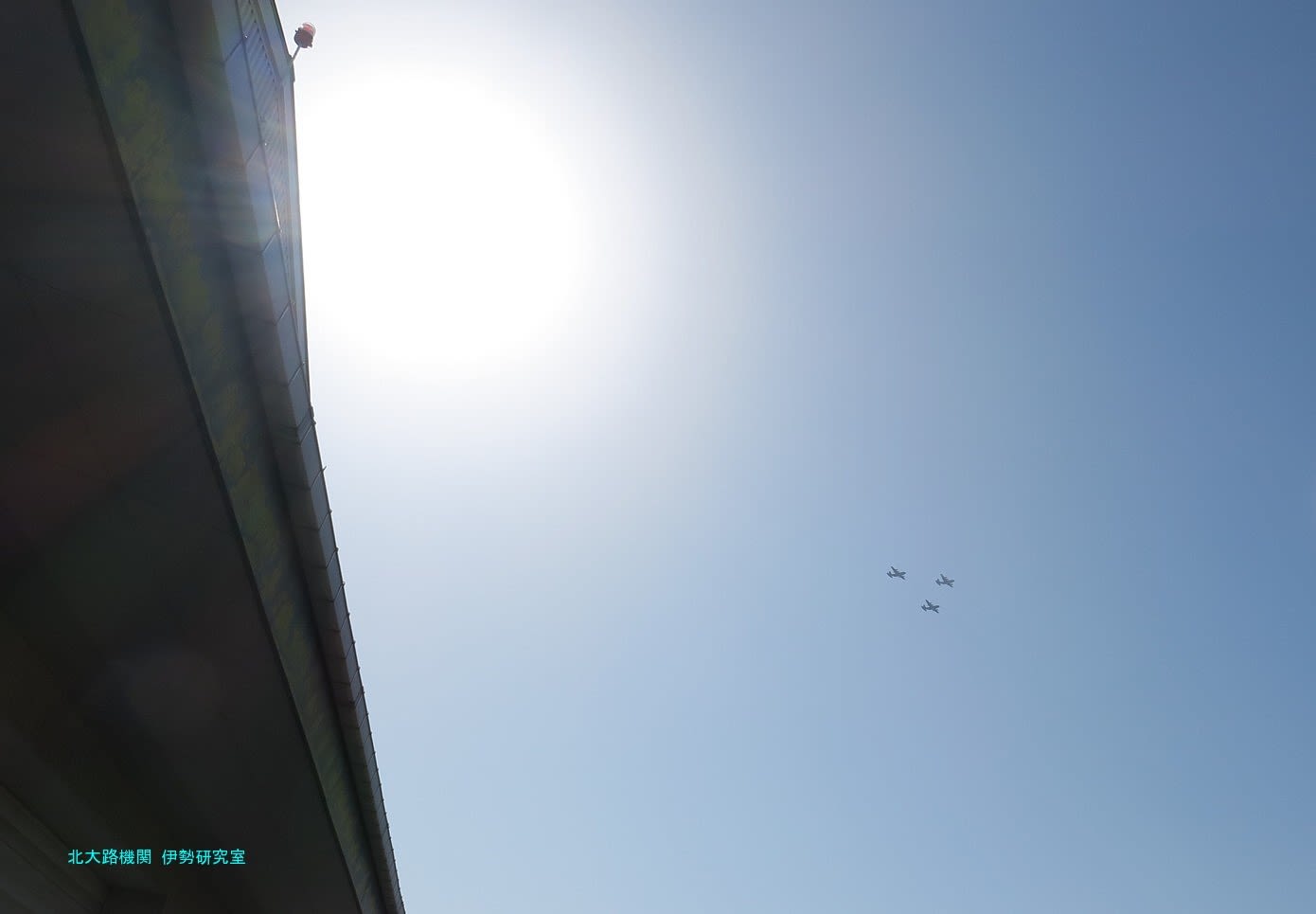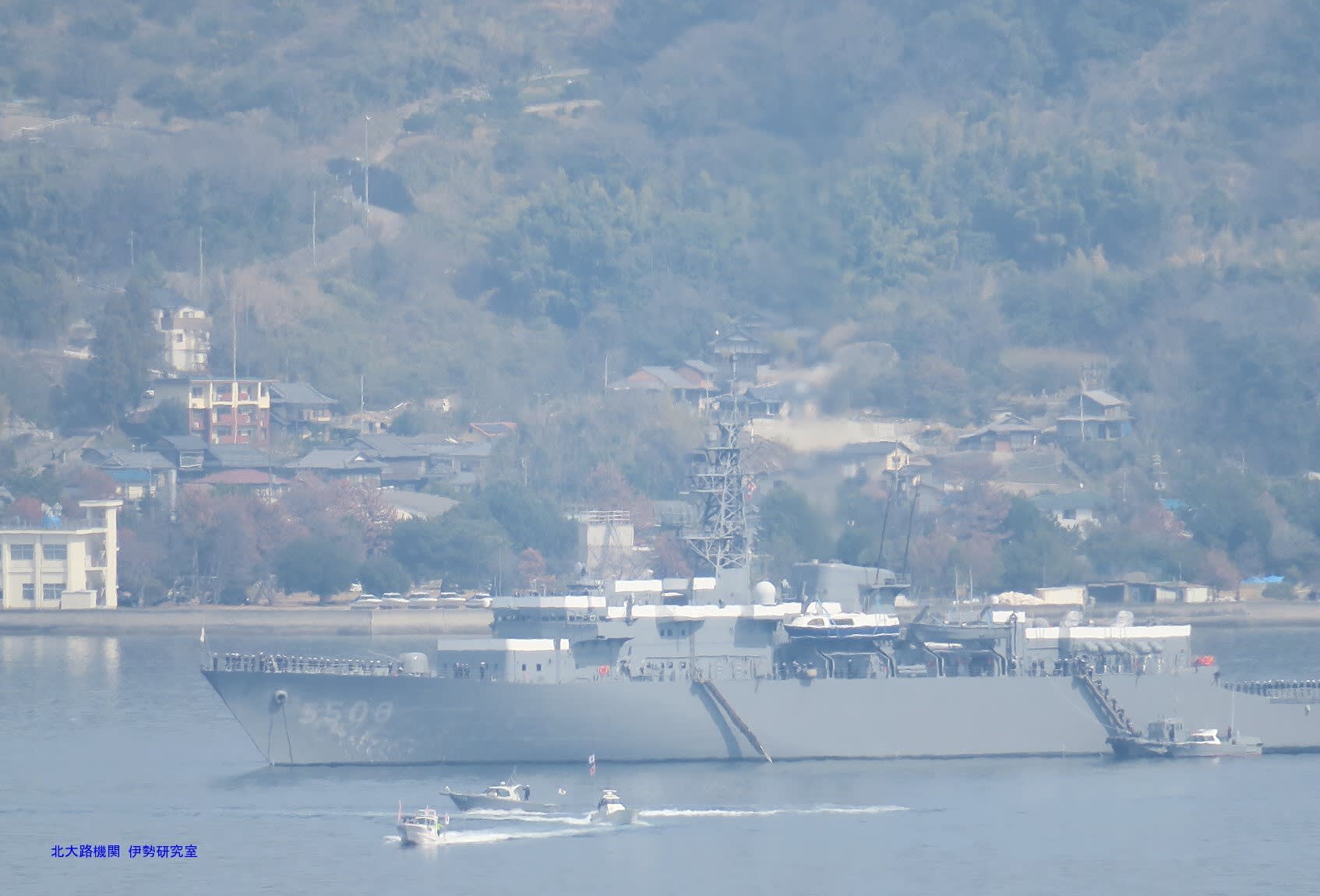■チヌーク大挙登場
チヌークことCH-47輸送ヘリコプターが続々と習志野訓練場に出動しますと展望台のまえを大きく旋回し着陸態勢へ。

CH-47輸送ヘリコプターが続々と飛来しました、C-130J輸送機が空挺降下可能な経路を飛行しつつそのまま航過したため、強風で降りられないらしいという事は分かったのですが、しかし自衛隊は降下したのに各国空挺部隊は降りれないとは、と思った矢先で。

自衛隊航空はUH-60JA多用途ヘリコプターの調達失敗によるUH-1JのUH-60JAでの置き換え中断、OH-6観測ヘリコプターのOH-1観測ヘリコプター調達失敗による観測ヘリコプターの形式消滅、続いてAH-1S対戦車ヘリコプターも同様の道を辿る。

AH-1S対戦車ヘリコプターのAH-64D戦闘ヘリコプターへの置き換えはミサイル防衛予算を捻出するために年間1機程度の調達鹿予算が確保できず62機予定を13機で打ち止めとし、富士重工との間で係争となり調達失敗、CH-47は例外的に調達できまして。

輸送ヘリコプターは第1ヘリコプター団の航空機で、アメリカの第101空中機動師団に次いで大規模な空輸能力を持つヘリコプター輸送部隊、川崎重工においてライセンス生産することで、旧型のCH-47D相当ですがCH-47Gの三分の一程度の費用で揃う。

ゴジラvsビオランテではV-107輸送ヘリコプターの大編隊が丹沢山地の防衛線へ輸送する様子が象徴的に描かれていましたし、ガメラ大怪獣空中決戦ではこれがCH-47の大編隊に置き換わり、言い換えればこの輸送ヘリコプターは自衛隊の象徴的装備なのか。

これだけの輸送ヘリコプターの数を揃えるのは簡単ではなく、川崎重工での生産に感謝したいところですが、政府がやはり新型のCH-47Gに切り替えるべきとの英断の結果、製造ラインを組みなおしたことで製造費が三倍、F-35より高くなったのは記憶に新しい。

CH-47Gは製造費が三倍になった事で、やっぱり国産は税金の無駄、と憤る方がいるようですが実はボーイングがドイツ陸軍に納入したCH-47Gと費用面では同程度で別段高くない、結局無理に最新型としたことで、普通の値段になっただけ、という。

各国空挺部隊の登場だ、そう、空挺降下する予定でした参加各国の空挺部隊が続々とヘリコプターから展開してきました訳です。そう、これを待っていた、なにしろ日本では89式小銃しか見られない、C7カービンやL-85にFA-MAS,全部見れるわけで。

FNCみたいな小銃持ってるぞ、AR-18っぽいな、SIG-550みたいなストックだ、と声が上がるのですが、わたしは一言、あれハチキュウのエアガンじゃないかな、と。とたん、周りが、言ってはならない事を言いやがった、と非難の視線が全周からとどく。

ああ、そういうことか、流石に多国籍空挺部隊の参加といっても全員日本に小銃を持ち込むのは旅客機で来日する場合の税関とか難しかったので、自衛隊が閉所訓練教材として導入していました東京マルイの89式小銃エアガンを全員に持ってもらったのかあ。

イギリス空挺兵とオランダ空挺兵が揃って89式小銃のエアガン、第16空中機動旅団と第11空中機動旅団、みんななかよくハチキュウを携行するというのは、時代も変わったものだなあ、と感じます。しかしオランダのボディーアーマー、軽快そうで羨ましい。

各国空挺部隊の戦闘加入により仮設敵は撤退を強いられ状況終了となった、という感じ。展示演習は図上演習と違い勝利まで明確に示されている。しかしこれまさに連合国軍という印象で、時代も変わったものなのだなあ、としみじみ思うのですね。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
チヌークことCH-47輸送ヘリコプターが続々と習志野訓練場に出動しますと展望台のまえを大きく旋回し着陸態勢へ。

CH-47輸送ヘリコプターが続々と飛来しました、C-130J輸送機が空挺降下可能な経路を飛行しつつそのまま航過したため、強風で降りられないらしいという事は分かったのですが、しかし自衛隊は降下したのに各国空挺部隊は降りれないとは、と思った矢先で。

自衛隊航空はUH-60JA多用途ヘリコプターの調達失敗によるUH-1JのUH-60JAでの置き換え中断、OH-6観測ヘリコプターのOH-1観測ヘリコプター調達失敗による観測ヘリコプターの形式消滅、続いてAH-1S対戦車ヘリコプターも同様の道を辿る。

AH-1S対戦車ヘリコプターのAH-64D戦闘ヘリコプターへの置き換えはミサイル防衛予算を捻出するために年間1機程度の調達鹿予算が確保できず62機予定を13機で打ち止めとし、富士重工との間で係争となり調達失敗、CH-47は例外的に調達できまして。

輸送ヘリコプターは第1ヘリコプター団の航空機で、アメリカの第101空中機動師団に次いで大規模な空輸能力を持つヘリコプター輸送部隊、川崎重工においてライセンス生産することで、旧型のCH-47D相当ですがCH-47Gの三分の一程度の費用で揃う。

ゴジラvsビオランテではV-107輸送ヘリコプターの大編隊が丹沢山地の防衛線へ輸送する様子が象徴的に描かれていましたし、ガメラ大怪獣空中決戦ではこれがCH-47の大編隊に置き換わり、言い換えればこの輸送ヘリコプターは自衛隊の象徴的装備なのか。

これだけの輸送ヘリコプターの数を揃えるのは簡単ではなく、川崎重工での生産に感謝したいところですが、政府がやはり新型のCH-47Gに切り替えるべきとの英断の結果、製造ラインを組みなおしたことで製造費が三倍、F-35より高くなったのは記憶に新しい。

CH-47Gは製造費が三倍になった事で、やっぱり国産は税金の無駄、と憤る方がいるようですが実はボーイングがドイツ陸軍に納入したCH-47Gと費用面では同程度で別段高くない、結局無理に最新型としたことで、普通の値段になっただけ、という。

各国空挺部隊の登場だ、そう、空挺降下する予定でした参加各国の空挺部隊が続々とヘリコプターから展開してきました訳です。そう、これを待っていた、なにしろ日本では89式小銃しか見られない、C7カービンやL-85にFA-MAS,全部見れるわけで。

FNCみたいな小銃持ってるぞ、AR-18っぽいな、SIG-550みたいなストックだ、と声が上がるのですが、わたしは一言、あれハチキュウのエアガンじゃないかな、と。とたん、周りが、言ってはならない事を言いやがった、と非難の視線が全周からとどく。

ああ、そういうことか、流石に多国籍空挺部隊の参加といっても全員日本に小銃を持ち込むのは旅客機で来日する場合の税関とか難しかったので、自衛隊が閉所訓練教材として導入していました東京マルイの89式小銃エアガンを全員に持ってもらったのかあ。

イギリス空挺兵とオランダ空挺兵が揃って89式小銃のエアガン、第16空中機動旅団と第11空中機動旅団、みんななかよくハチキュウを携行するというのは、時代も変わったものだなあ、と感じます。しかしオランダのボディーアーマー、軽快そうで羨ましい。

各国空挺部隊の戦闘加入により仮設敵は撤退を強いられ状況終了となった、という感じ。展示演習は図上演習と違い勝利まで明確に示されている。しかしこれまさに連合国軍という印象で、時代も変わったものなのだなあ、としみじみ思うのですね。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)