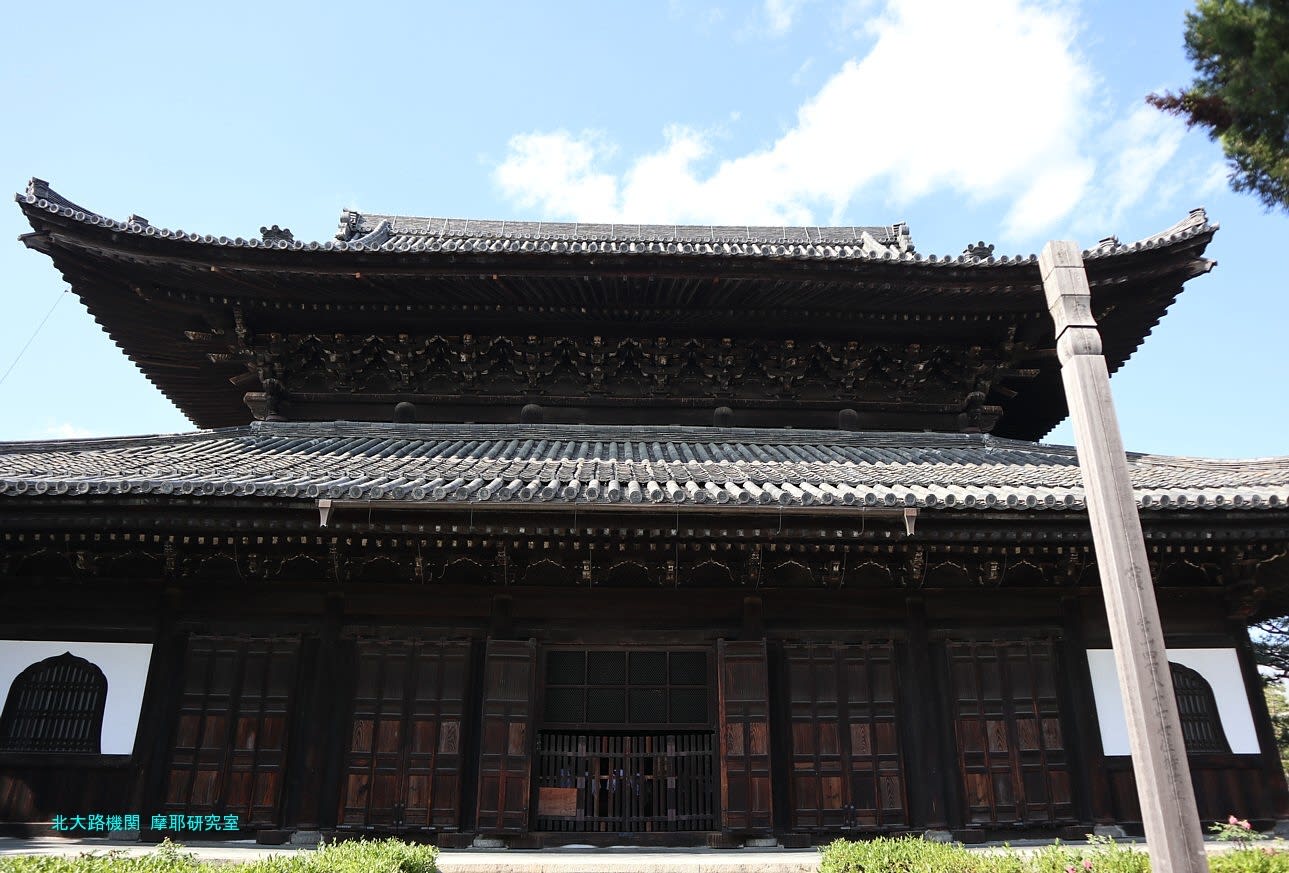■五穀豊穣を問う神事
迫力があるなあと写真を観返しましても。

賀茂別雷神社の賀茂競馬、ゴールデンウィークの真っ最中に執り行われる神事なのですが、この五月五日の馬が駆ける勇壮な祭事こそ人の心ひく神事ではあるのですが、しかし祭事そのものは実は五月一日から始められているもので、長い神事であるのです。

足汰式、これも古式にの鳥取執り行われているものでして、あしぞろえしきと読むのですが、神事に参加します馬は20騎、そのうち一斉に走るのではなく2騎を組み合わせてはりしますので馬を各々走らせ、同じ走りの早さ同士の馬たちで組み合わせを定める。

騎手の組み合わせというのは重要で、それは騎手は左右に二人が並び、左の騎手には緋闕腋袍に緋色裲襠、右の騎手は黒の闕腋に青の裲襠を身につけたうえで上衣としまして獅子の繍が描かれた袍を身につけます、故に騎手は組み合わせで装束が決まるという。

饗食という神事は、3日に騎馬の騎手が親族を持て成す神事として祭事に組み入れられていまして、その饗食を終えて明けて4日に騎手たちは上賀茂神社ではなく下鴨神社を参拝するという祭事の取り決めがあります、そして5日の神事に臨むのですね。

午刻に一番太鼓が響き神事が始まります、競馬をケイバと読むならば騎手は機能的な装いで臨むのでしょうがこれは神事であり、競馬太刀という、真剣ではなく模造刀なのですけれども、身に付けまして、神事に臨みます装束も歴史的な伝統衣装となっています。

桜から楓に。賀茂競馬では桜の一から馬を駆りまして遥か御阿礼所があります方角に向け走るのですが、数百mさきの楓の木までの競いにより鉦鼓と太鼓のどちらかが勝敗を告げるという。鉦鼓が響けば右の騎手、太鼓が轟けば左の騎手が勝ったことを示す。

鉦鼓が響けば右の騎手、太鼓が轟けば左の騎手、という競いなのですが、その進発は横並びではなくたて並びであり、走り始めるとともにその離隔距離が開いたか縮んだかにより勝敗が決まるというところでして、足汰式で先ず先か後かがきまるということ。

勝敗というのは、左右の馬は並ぶのではなく一頭分の距離を離隔して走りまして、そのきょりが開いたかどうか、そしてこれは先を行く馬が有利に思われますが六組の騎馬は前に並ぶのが前の競馬での勝敗により決まるため、左右の勝敗は全体に繋がる。

幄舎からも勝敗を示す扇が掲げられまして、幄舎は東西に設けられていて左の騎手が勝てば朱の日の丸、右の騎手が勝った際には白い日の丸の扇が掲げられるという、この勝敗は合議制であり、勝敗が双方から見え方が違った場合には両方掲げ引き分け、と。

白絹が勝者の騎馬には与えられまして、騎手はその白絹を乗馬鞭に結び付け高らかに記すとともに、帰路鳥居の前に馬上から鳥居と上賀茂神社本殿より祭事に併せて神霊がうつされています屯宮という祭礼の壇に向けまして神前の報告と共に最敬礼する。

勝敗、左の騎手が勝てば五穀豊穣という神事なのですが、六組の騎馬が走り抜ける中、一番組は一頭駆けという習わしであり、基本的に五穀豊穣を念頭としているように、六度の競馬を経て古都委は五穀豊穣かそうでは無いかを競うとのことでして。

貴船神社に、この神事の翌日6日には騎手全員が貴船神社、もともと上賀茂神社の末社という歴史があります、ここに詣でまして、神前の報告と共に勝敗をそのまま貴船川に流して翌年に向けての五穀豊穣と国家安寧を祈る、ここまでが賀茂競馬です。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
迫力があるなあと写真を観返しましても。

賀茂別雷神社の賀茂競馬、ゴールデンウィークの真っ最中に執り行われる神事なのですが、この五月五日の馬が駆ける勇壮な祭事こそ人の心ひく神事ではあるのですが、しかし祭事そのものは実は五月一日から始められているもので、長い神事であるのです。

足汰式、これも古式にの鳥取執り行われているものでして、あしぞろえしきと読むのですが、神事に参加します馬は20騎、そのうち一斉に走るのではなく2騎を組み合わせてはりしますので馬を各々走らせ、同じ走りの早さ同士の馬たちで組み合わせを定める。

騎手の組み合わせというのは重要で、それは騎手は左右に二人が並び、左の騎手には緋闕腋袍に緋色裲襠、右の騎手は黒の闕腋に青の裲襠を身につけたうえで上衣としまして獅子の繍が描かれた袍を身につけます、故に騎手は組み合わせで装束が決まるという。

饗食という神事は、3日に騎馬の騎手が親族を持て成す神事として祭事に組み入れられていまして、その饗食を終えて明けて4日に騎手たちは上賀茂神社ではなく下鴨神社を参拝するという祭事の取り決めがあります、そして5日の神事に臨むのですね。

午刻に一番太鼓が響き神事が始まります、競馬をケイバと読むならば騎手は機能的な装いで臨むのでしょうがこれは神事であり、競馬太刀という、真剣ではなく模造刀なのですけれども、身に付けまして、神事に臨みます装束も歴史的な伝統衣装となっています。

桜から楓に。賀茂競馬では桜の一から馬を駆りまして遥か御阿礼所があります方角に向け走るのですが、数百mさきの楓の木までの競いにより鉦鼓と太鼓のどちらかが勝敗を告げるという。鉦鼓が響けば右の騎手、太鼓が轟けば左の騎手が勝ったことを示す。

鉦鼓が響けば右の騎手、太鼓が轟けば左の騎手、という競いなのですが、その進発は横並びではなくたて並びであり、走り始めるとともにその離隔距離が開いたか縮んだかにより勝敗が決まるというところでして、足汰式で先ず先か後かがきまるということ。

勝敗というのは、左右の馬は並ぶのではなく一頭分の距離を離隔して走りまして、そのきょりが開いたかどうか、そしてこれは先を行く馬が有利に思われますが六組の騎馬は前に並ぶのが前の競馬での勝敗により決まるため、左右の勝敗は全体に繋がる。

幄舎からも勝敗を示す扇が掲げられまして、幄舎は東西に設けられていて左の騎手が勝てば朱の日の丸、右の騎手が勝った際には白い日の丸の扇が掲げられるという、この勝敗は合議制であり、勝敗が双方から見え方が違った場合には両方掲げ引き分け、と。

白絹が勝者の騎馬には与えられまして、騎手はその白絹を乗馬鞭に結び付け高らかに記すとともに、帰路鳥居の前に馬上から鳥居と上賀茂神社本殿より祭事に併せて神霊がうつされています屯宮という祭礼の壇に向けまして神前の報告と共に最敬礼する。

勝敗、左の騎手が勝てば五穀豊穣という神事なのですが、六組の騎馬が走り抜ける中、一番組は一頭駆けという習わしであり、基本的に五穀豊穣を念頭としているように、六度の競馬を経て古都委は五穀豊穣かそうでは無いかを競うとのことでして。

貴船神社に、この神事の翌日6日には騎手全員が貴船神社、もともと上賀茂神社の末社という歴史があります、ここに詣でまして、神前の報告と共に勝敗をそのまま貴船川に流して翌年に向けての五穀豊穣と国家安寧を祈る、ここまでが賀茂競馬です。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)