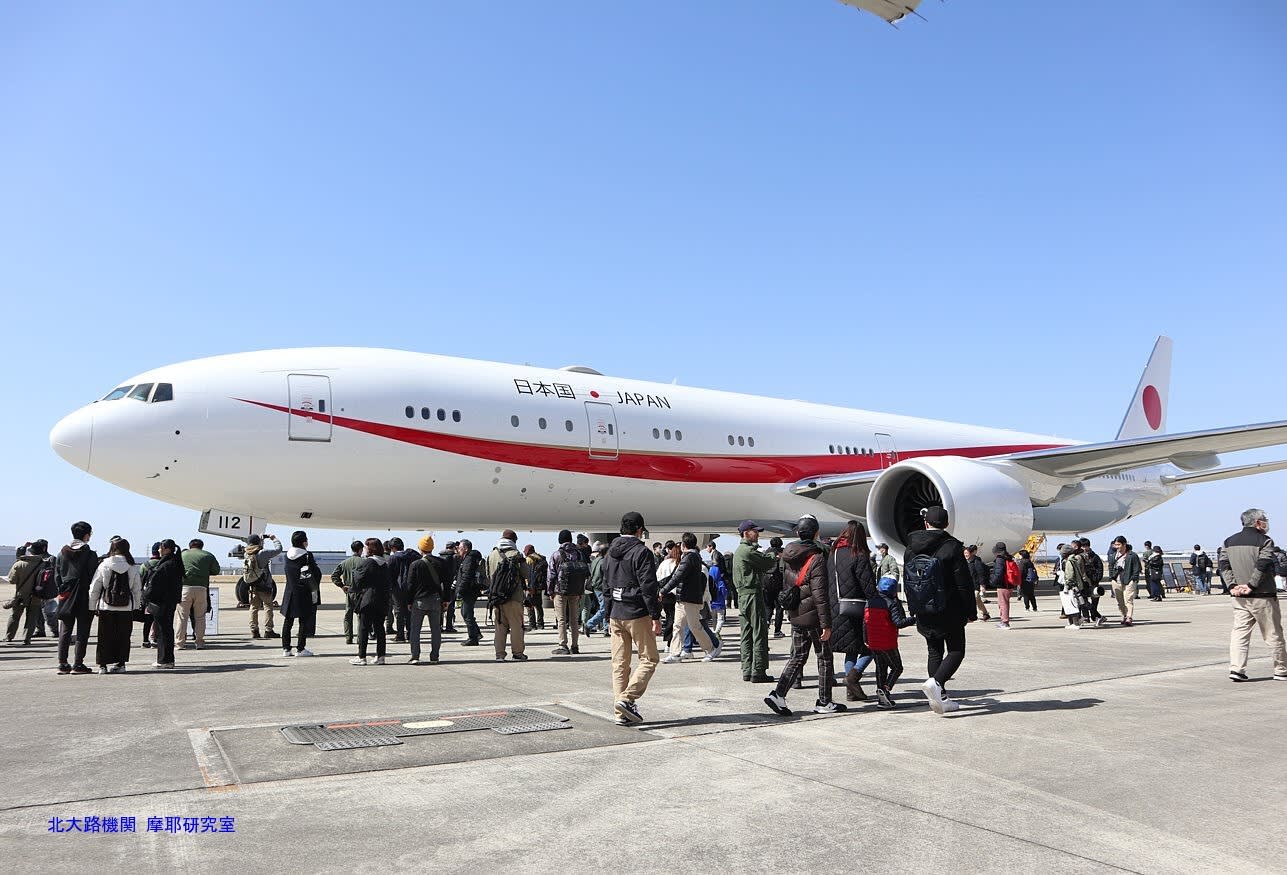■C-1FTB飛行訓練
C-1は撮影出来る時に撮影しておこう。

岐阜基地に隣接する三井山の三井城跡に少しだけ時間がありましたので上って参りました。こういいますのも、そろそろC-1輸送機の完全退役という時代が見えてきましたので、COVID-19新型コロナウィルス禍下でのファントム撮影を少し思い出した構図で。

T-4練習機、岐阜基地では定番のように飛行しています。考えれば岐阜の飛行開発実験団でも運用されていますがそもそもT-4を開発したのは川崎重工であり、そして川崎重工岐阜工場においてT-4は製造さえているのだから本場といえばT-4の本場なのです。

C-1FTBが動き始めた。この写真だけをみますと雪山を背景にT-4練習機が力強く浮き上がっている様子しかみえないのですが、よくよく注目しますと誘導路を進んでいますC-1FTBがみえています、つまりこれから離陸するという状況でもあるのですね。

T-4練習機の旋回、タッチアンドゴーを繰り返しているのですが三井山からはその滑走路にタッチしてゴーの為に離陸した直後の旋回をよく、眼下とはいわないまでも、地上で撮影するよりも若干近い位置から撮影できてしまう、だから山に登りました。

C-1FTB,離陸準備のために滑走路エンドに進入しました。岐阜基地を眼下に納めることのできる撮影位置としてはここ三井山のほかに東海自然歩道という山の稜線に沿った遊歩道がありまして、実はその道をたどると比叡山まで続いているのですけれども。

とんだ、飛び上がったC-1FTB,川崎重工岐阜工場と岐阜工場で定期整備としてはいっていますP-1哨戒機とともに構図に収めました。C-1は短い滑走距離でふわりと舞い上がるように離陸しますから、動き始めたC-1はファインダーからはずさないように。

三井山から撮影できる構図というのは、各務原市街地の一部を順光の構図で航空機写真とできるところでして、基地から離陸する航空機を眼下に納められる構図、岐阜基地以外だと、小牧山と小牧基地は遠く小松基地と白山は遠すぎるため、貴重な立地、か。

東海自然歩道から撮影する場合は、実はかなりこの三井山よりも標高が高いために名古屋市のビル群を背景に構図に収められるというのですが、逆光なんですよねえ、というのは建前の言い訳、標高が高い分三井山よりも上るのに時間がかかり、そして疲れる。

EOS-M5で撮影したものなのですが、実はこの日、このほかに一眼レフを持っていませんし2400mm超望遠を誇るG3Xも手元にありません、所用ついででしたので本当にミラーレスだけをもって、しかし身軽でしたので三井山頂上まで10分で上ってしまえた。

ミラーレスには十年近く放置していた55-250mmISという、EOS-KissX7を2014年に購入した際のダブルズームキットのキットレンズにEF-Mレンズコンバータを取り付けて無理矢理M-5で使っているものなのですが、250mmレンズは無いよりマシ以上の性能が。

雪山とC-1FTB,ちょっと雪山にしては雪が少ないですけれども上々といえるところか。EOS-7Dほどの性能はないものの軽量なので行ける機会と身動きが身軽というものは撮影機会を増やせることにつながるのか、実際短時間でこうした構図を撮れたのだし。

C-1輸送機、日常風景に溶け込んだといいますか基地間輸送から空挺部隊や実任務まで便利に使われていました航空機なのですけれどC-2輸送機の数がそろってきましたので、そろそろ、という時代がきてしまいました。悔いのないよう、写真に収めよう。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
C-1は撮影出来る時に撮影しておこう。

岐阜基地に隣接する三井山の三井城跡に少しだけ時間がありましたので上って参りました。こういいますのも、そろそろC-1輸送機の完全退役という時代が見えてきましたので、COVID-19新型コロナウィルス禍下でのファントム撮影を少し思い出した構図で。

T-4練習機、岐阜基地では定番のように飛行しています。考えれば岐阜の飛行開発実験団でも運用されていますがそもそもT-4を開発したのは川崎重工であり、そして川崎重工岐阜工場においてT-4は製造さえているのだから本場といえばT-4の本場なのです。

C-1FTBが動き始めた。この写真だけをみますと雪山を背景にT-4練習機が力強く浮き上がっている様子しかみえないのですが、よくよく注目しますと誘導路を進んでいますC-1FTBがみえています、つまりこれから離陸するという状況でもあるのですね。

T-4練習機の旋回、タッチアンドゴーを繰り返しているのですが三井山からはその滑走路にタッチしてゴーの為に離陸した直後の旋回をよく、眼下とはいわないまでも、地上で撮影するよりも若干近い位置から撮影できてしまう、だから山に登りました。

C-1FTB,離陸準備のために滑走路エンドに進入しました。岐阜基地を眼下に納めることのできる撮影位置としてはここ三井山のほかに東海自然歩道という山の稜線に沿った遊歩道がありまして、実はその道をたどると比叡山まで続いているのですけれども。

とんだ、飛び上がったC-1FTB,川崎重工岐阜工場と岐阜工場で定期整備としてはいっていますP-1哨戒機とともに構図に収めました。C-1は短い滑走距離でふわりと舞い上がるように離陸しますから、動き始めたC-1はファインダーからはずさないように。

三井山から撮影できる構図というのは、各務原市街地の一部を順光の構図で航空機写真とできるところでして、基地から離陸する航空機を眼下に納められる構図、岐阜基地以外だと、小牧山と小牧基地は遠く小松基地と白山は遠すぎるため、貴重な立地、か。

東海自然歩道から撮影する場合は、実はかなりこの三井山よりも標高が高いために名古屋市のビル群を背景に構図に収められるというのですが、逆光なんですよねえ、というのは建前の言い訳、標高が高い分三井山よりも上るのに時間がかかり、そして疲れる。

EOS-M5で撮影したものなのですが、実はこの日、このほかに一眼レフを持っていませんし2400mm超望遠を誇るG3Xも手元にありません、所用ついででしたので本当にミラーレスだけをもって、しかし身軽でしたので三井山頂上まで10分で上ってしまえた。

ミラーレスには十年近く放置していた55-250mmISという、EOS-KissX7を2014年に購入した際のダブルズームキットのキットレンズにEF-Mレンズコンバータを取り付けて無理矢理M-5で使っているものなのですが、250mmレンズは無いよりマシ以上の性能が。

雪山とC-1FTB,ちょっと雪山にしては雪が少ないですけれども上々といえるところか。EOS-7Dほどの性能はないものの軽量なので行ける機会と身動きが身軽というものは撮影機会を増やせることにつながるのか、実際短時間でこうした構図を撮れたのだし。

C-1輸送機、日常風景に溶け込んだといいますか基地間輸送から空挺部隊や実任務まで便利に使われていました航空機なのですけれどC-2輸送機の数がそろってきましたので、そろそろ、という時代がきてしまいました。悔いのないよう、写真に収めよう。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)