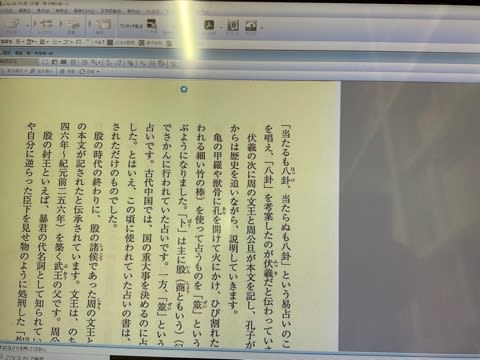こんにちは☔️ 今日はよく降りましたね☔️☔️☔️☔️
連休初日に、こんな雨だと☔️切ないですね😭😭😭
私も今日は、夏野菜の苗を買いに行くつもりでいましたが
そんな気になれず、読みたい本を家内に読めるようにしてもらいながら
本を読んで一日を過ごすことになりました🫢
さて、目の見えない私が本を読むとはどんなことか?と
疑問に思われる方がいらっしゃいますので、今日は世代交代した
点字ディスプレイの画像をトップ画像にいたしました😊
今日、私が読書や仕事をするときにどうしても手で確認しなくてはいけないものを
(目が見えないので、ほとんどは音声で読書をしますが、細かい文字(難しい漢字・特に古典医学書の文字)
や間違えてはいけない数字など)、点字で確認するための機器を世代交代させました🥺
パソコンの画面に出ている文字を点字で触読できるようにする機器を、点字ディスプレイと言います。
(ピンディスプレイとも呼びます。点字がピンで出てくるからです🙃)
30年以上使用していた、この機器がとうとう壊れてしまったので
本日、新しいものに買い替えて、設定してもらいました🤩🤩🤩
以前のものより、うんと読みやすくとても嬉しい気持ちになりましたよ🥹🥹
大きさも重量も思い切り軽量化していましたね‼️昔の携帯電話とスマホほどの差でしょうか⁉️
さて、この機器さえ使えば本が簡単に読めるというわけではなく
一般的に販売されている書籍を、全て文字情報(テキストデータ)にすることにより、
音声や点字に変換することが可能になります。つまり、みなさんお馴染みの電子書籍や
スキャナーで読み込んだ画像ファイルを文字情報に変えないと読めないのが現実です。
この作業を、目の見える家族やスタッフの力を借りて、やっと本を読むことができるので
(本を聴く?かなぁ)、本を買ってもすぐに読めないのが現実です🥲
こういうスキャナーで先ず、書籍を読みこみます(先ずはPDFにします)
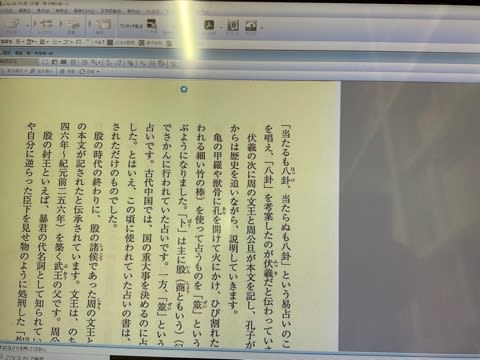
パソコンに取り込んで(取り込む際に、不要なものを編集してもらっています)

OCR変換ソフトを用いて、テキストデータに変換して
(画像をご覧いただくとお分かりかと思いますが、ふりがななどが入っていたり
外字などが入っていると変換がうまくいかないことが多く🫢
これを1ページずつ、目の見えるスタッフに修正してもらってテキストデータにすることによって

やっと本を読む段階に至ります😊😊😊😊
(画像は、パソコンに入っている本のデータを点字で探している様子です)
ということで、待合室に置いてある本をなぜ、私が読めるのか⁉️という
仕組みを、少しお分かりいただけたでしょうか❓
時々、「先生!目が見えないのにどうやって本を読んでるの⁉️」と訊ねられますので
お話しさせていただきました😉
以前は、こういった機器がありませんでしたから、どうしても急ぎで読みたい本は
家族に読んでもらう(これは、家族が文字を間違えて読んでいたらそのまま読む感じになります😅)
朗読ボランティアの方にお願いする(好きなときには読めないことが多いのと、
2時間までという制約があるので、1冊を読むのに数ヶ月かかってしまう)
点訳ボランティアの方にお願いする(これは約1年以上かかることも)
ということしかできなかったので、機器の発達で本当に読書環境がガラッと改善しましたが、
まだまだ誰かの手を借りなくてはすぐに本を読むことができないのが現状です😢
最近はオーディオブックと言って、音声で本を聴くこともできるようですが
1文字1文字を点字で確認することはできないために、古典医学書などは
やはり、自分でゆっくり読み返すためにもこうした作業をしてもらっています。
(古典医学書はオーディオブックがないかもしれませんね😅)
目の見えない私が本を読む⁉️謎が解明されたでしょうか?
最近では、みなさんが図書館で本を借りるのと同じように
私たちは、こういったデータ図書をインターネットや郵送で借りることも
できるようにもなってきていますが(視覚障がいである証明などが必要となっています)、
一般の図書館の蔵書数と比べると、うんと少なく借りられたら奇跡‼️(データ化されていて
貸出リストにあったら奇跡‼️)という印象です🥹
明日からは、お天気も回復するようですね🌞
週末は、夏野菜が植えられるように‼️今夜は、家庭菜園の本を読みたいと思います😉