千 葉 県 短 歌 大 会
期日:平成18年10月29日(日)
会場:ホテルポートプラザちば
主催:千葉県歌人クラブ

鶴岡先生より次期大会 松戸市への引継セレモニー
本年は千葉市において開催。
大会実行委員の先生方(敬称略)のご紹介
会 長 秋葉 四郎
副 会 長 松下總一郎 久々湊盈子
事 務 局 長 清宮 紀子
実行委員長 鶴岡美代子
総 合 司 会 戸田 佳子
以上の先生方の他にも多くの先輩委員の先生方が早朝より参集してのご尽力に敬意を表しました。

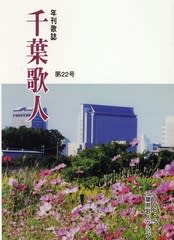
受付業務 ・ 詠草集 ・ 関係書籍の配布などにご尽力されていらっしゃいました。
10時開会宣言に続いて 実行委員長 挨拶は吾が師 鶴岡美代子先生 
の素敵なご挨拶を拝聴することが出来ました。 

秋葉会長ご挨拶はご講演いただいた「作家・文芸評論家 葉山 修平先生」について詳しくご紹介をいただきました。
演題は「海ー旅の歌」でしたが、冒頭にいくつかの結社のご紹介に私たちの「軽雪」もご紹介くださり、又演題の「海」の歌として鶴岡先生の「緑風抱卵」より


突堤に海鵜ら日を浴み鵜になれぬ鴎は下段にひしめきあへり
刃を受けて喘ぐ赤エヒ捨て置けず息止まるまで浜に見つむる の二首をご紹介いただきました。
嬉しい  やらビックリ
やらビックリ  やらでしたが、実行委員長をお務めになられた鶴岡先生へのねぎらいのお気持ちだったのでは
やらでしたが、実行委員長をお務めになられた鶴岡先生へのねぎらいのお気持ちだったのでは  と先生のお優しいお心配りにひととき幸せをいただきました。
と先生のお優しいお心配りにひととき幸せをいただきました。
本題は、千葉県の生んだ歌人「伊藤左千夫」の海を詠んだ歌をきっかけとして「海ー旅の歌」について考えてみたいと思う。
に始まり、万葉集にみえる「海ー旅の歌」について、「土佐日記」等々から、近代・現代歌人は「海」をどのように読んでいるかに広くお話をいただきました。
千葉ご出身の先生にとても親しく拝聴することが出来ました。
表彰式には一般の部の皆様・学生の部の皆様方が胸に大きなお花を付けていただき、友人からの祝福に又、小学生の皆さんはご両親とご一緒に臨まれたお幸せのお姿が印象的でした。
入賞者の皆さんに心からのお祝いを申し上げ、初めての参加に大変意義深い一日となりました。











 ~ 27日(金)
~ 27日(金) 時々
時々 一泊二日
一泊二日 ~ 首都高・外環道・関越道 を走り、最初の目的地
~ 首都高・外環道・関越道 を走り、最初の目的地 
























 のご様子でしたが、鈴木事務局長を初め添乗員さんのご配慮をいただき、皆さんが無事に楽しい親睦の旅を
のご様子でしたが、鈴木事務局長を初め添乗員さんのご配慮をいただき、皆さんが無事に楽しい親睦の旅を



























 では
では
















