
明治31年12月築の木造駅舎が健在ですが、平成10年3月にコンパクト化されています。無人化されており、窓口ブースもありません。(但し、自動券売機あり)
調査を始めて間もなく、自転車に乗った爺ちゃんがワンカップを浴びながら駅舎に遊びに来たので、たまらず周辺散策開始。

1つ津山方の踏切から見た駅構内。交換可能駅で対面式ホームを有し、両者は構内踏切で結ばれています。周辺は、田園風景が広がっています。
12時22分発の950D(キハ120 335+キハ120 355)に乗車して玉柏を後にしました。㈱カバヤの工場を見て、12時37分に野々口駅に到着。ようやく桃太郎祭寿司にて昼食タイム。

昼食終了後、ようやく調査タイム。平成10年頃改築の木造駅舎ですが、駅員も居なければ窓口もありません。(乗車証明書発行機あり)
野々口駅での滞在時間は30分で、そのうち昼食に15分費やして残り時間は15分。駅前通を往復して終わりでしたが、周辺は山間の閑静な住宅街です。某女性演歌歌手のコンサートのポスターがあったし。

時間が近付き駅構内に入ります。申し遅れましたが、この駅も交換可能駅で対面式ホームを有しています。駅名板周辺のツツジがちょうど満開でした

 。乗客が多数集まり、13時7分発の2927D(キハ47 1038+キハ47 44)に乗車して、津山線全駅下車達成の地へ。
。乗客が多数集まり、13時7分発の2927D(キハ47 1038+キハ47 44)に乗車して、津山線全駅下車達成の地へ。
13時14分に牧山駅に到着。もともと信号場として設置された駅で、対面式ホームの交換可能駅となっており、両者は屋根無しの跨線橋で結ばれています。

牧山駅は、駅員の配置も無ければ駅舎というものが無く、両ホームとも待合所となっています。脇に乗車駅証明書発行機あり。入口に駅名を示すものが無く、外からでは分からないですね。これにて津山線全駅下車達成

 。
。
35分の滞在時間を利用して、沈下橋を渡って旭川の雄大な流れを体感してきました
 。これは岡山方の光景。
。これは岡山方の光景。 津山方には小舟が停泊してます。
津山方には小舟が停泊してます。
橋の向こうは長閑な田園風景が広がっていました。「桃源郷」は言い過ぎでしょうか。

再び橋を渡って牧山駅に戻ります。あ、言い忘れましたが、これは歩行者専用橋です。増水した時には絶対に渡らないで下さい。
急速に倦怠感に襲われましたが、13時49分発の953D(キハ120 329+キハ120 334)にて岡山に戻りました。
続きはこちら
参考サイト さいきの駅舎訪問


















 置き場となっており最も撮り難い駅舎とされていますが、この時は奇跡的にも立ち位置が空いており、
置き場となっており最も撮り難い駅舎とされていますが、この時は奇跡的にも立ち位置が空いており、 のようにスッキリ収められました
のようにスッキリ収められました







 。
。


 です。7:10頃に朝食をとれたので、部屋で少しくつろいでも余裕でした。
です。7:10頃に朝食をとれたので、部屋で少しくつろいでも余裕でした。
 。
。



 。
。










 。
。






 も飼っているようです。
も飼っているようです。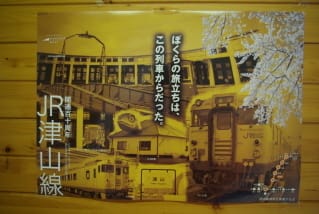



 。このキハ120系2連(952D)と交換した957D(キハ48 5+キハ48 6)に乗車して亀尽くしの町を後にしました。
。このキハ120系2連(952D)と交換した957D(キハ48 5+キハ48 6)に乗車して亀尽くしの町を後にしました。



 言葉にならぬほど美しいです
言葉にならぬほど美しいです
 もあったので、分かってさえいればわざわざ高額な寿司を買わなくて済んだのに。尚、津山方に行くと、右派系とおぼしき企業があり、その中に海軍資料館があります。
もあったので、分かってさえいればわざわざ高額な寿司を買わなくて済んだのに。尚、津山方に行くと、右派系とおぼしき企業があり、その中に海軍資料館があります。 かいた後、12時51分発の953D(キハ120 341+キハ120 338)で2駅引き返しました。
かいた後、12時51分発の953D(キハ120 341+キハ120 338)で2駅引き返しました。


























