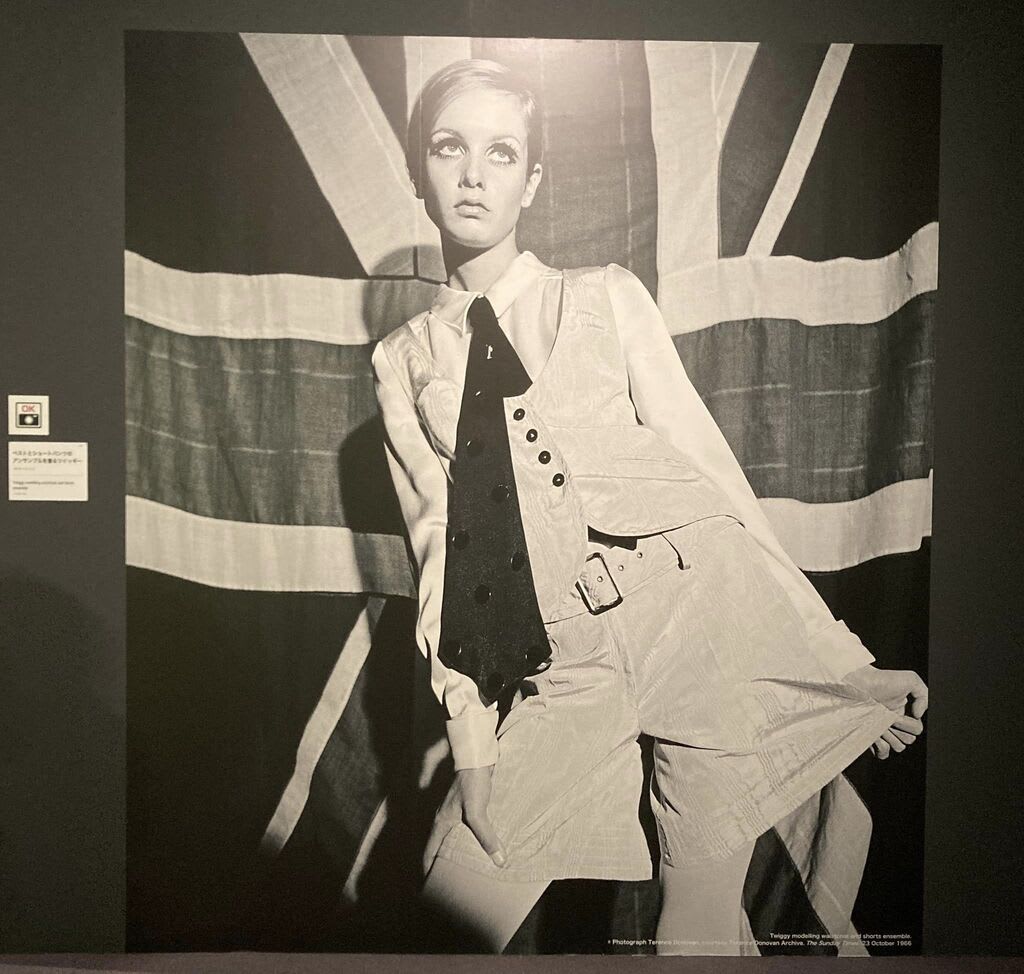(2015年インドで震えていた仔犬)
アフガン・ハウンドを取り上げた日記に、ブロ友さんがこんな記事を見つけたとコメント下さいました。
NewsWeek先月号の”「犬を殺せば賞金」「公園散歩は犯罪」イスラム教で嫌われる犬たちに変化の時が”という記事。
それによると、パレスチナ自治区ヘブロンでは、市長が「犬を殺せば賞金を与える」と言い、犬が殺されたり虐待されたりする様子を収めた写真や動画がSNSで広く共有されたのだそうです。
イスラム教において犬は不浄で不吉な動物とされ、一般に忌み嫌われてきたからと。
NewsWeek先月号の”「犬を殺せば賞金」「公園散歩は犯罪」イスラム教で嫌われる犬たちに変化の時が”という記事。
それによると、パレスチナ自治区ヘブロンでは、市長が「犬を殺せば賞金を与える」と言い、犬が殺されたり虐待されたりする様子を収めた写真や動画がSNSで広く共有されたのだそうです。
イスラム教において犬は不浄で不吉な動物とされ、一般に忌み嫌われてきたからと。

(2014年ミュンヘン)
その根拠というのが、預言者ムハンマドが「狩猟や放牧に使われる犬を除き、全ての犬を殺すように命じた」とか「犬を飼う者は、農耕や放牧のための犬を除き、日々の善行から一部を差し引かれる」などといった犬についての伝承(ハディース)が数多くあるからだというのです。
その根拠というのが、預言者ムハンマドが「狩猟や放牧に使われる犬を除き、全ての犬を殺すように命じた」とか「犬を飼う者は、農耕や放牧のための犬を除き、日々の善行から一部を差し引かれる」などといった犬についての伝承(ハディース)が数多くあるからだというのです。

(2015年インド)
インドネシアでは、モスクに犬を連れて土足で入った女性が冒瀆罪で起訴されたり、イランの首都テヘランでは、警察が公園での犬の散歩は犯罪になると発表したりと、もう訳が分からないイスラム圏の犬蔑視。
この記事の最後に、サウジアラビアやアラブ首長国連邦(UAE)は「犬に優しい国」へと変貌を遂げており、サウジやドバイにドッグカフェがオープンしたりしたという記述がありましたが…
逆に言えば、それ以外のイスラム圏の国ではまだまだ犬は虐げられているのですね。

(2015年ギリシヤ)
色々な国を旅して犬を見てきました。
路上にウンチ箱まで設置してあるドイツやイギリス(地域によるようですが)、自由にその辺でゴロゴロしているギリシヤ。
痩せこけてゴミ捨て場を漁っていたインドの犬(人間の乞食が漁りつくした後で食べられるものなんて残ってないのに)は悲しかった。
それでも、イスラム圏の犬よりは幸せなようにように思います。
それでも、イスラム圏の犬よりは幸せなようにように思います。

(2016年ニューヨークの犬連れホームレス)