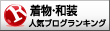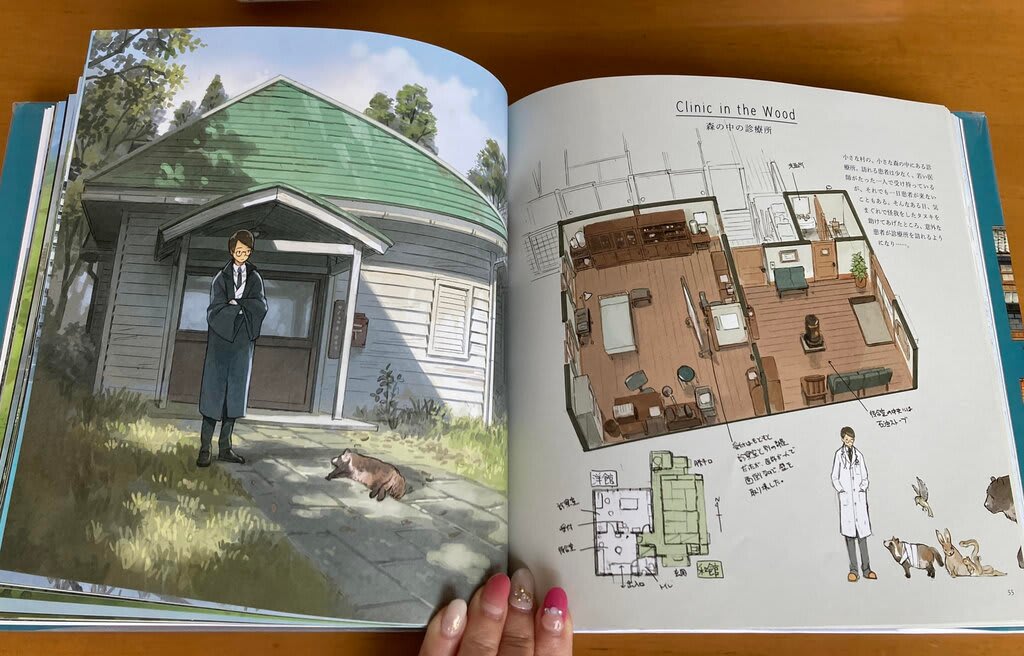黒人初のグランドスラム・テニスプレイヤー、ビーナスとセリーナ・ウイリアムズ姉妹を育て上げた父リチャードの奮闘を描いた実話物語です。
カリフォルニア州コンプトンに暮らすリチャード・ウィリアムズ(ウイル・スミス)は、2人の娘を最高のテニスプレイヤーに育てると決意し、そのための78ページの計画書(ドリーム・プラン)を作成する。
特記すべきは、リチャードはテニスをしたことがないということです。
貧困家庭に生まれ、食べるのがやっとだった彼は、テニスどころではなかったのでしょう。
それでも専門書を徹底的に読み、人体力学からテニスの技術まで研究し、詳細なプランを作り上げる。
家計を支えるために警備の仕事などしながら、一日も休むことなく娘たちにテニスの特訓をする。
カリフォルニア州コンプトンに暮らすリチャード・ウィリアムズ(ウイル・スミス)は、2人の娘を最高のテニスプレイヤーに育てると決意し、そのための78ページの計画書(ドリーム・プラン)を作成する。
特記すべきは、リチャードはテニスをしたことがないということです。
貧困家庭に生まれ、食べるのがやっとだった彼は、テニスどころではなかったのでしょう。
それでも専門書を徹底的に読み、人体力学からテニスの技術まで研究し、詳細なプランを作り上げる。
家計を支えるために警備の仕事などしながら、一日も休むことなく娘たちにテニスの特訓をする。
リチャードという男は、一言で言うなら「ものすごく熱くてあり得ない程にウザい」男です。
どんなに断られても、ピート・サンプラスやジョン・マッケンローを指導したポール・コーエンにコーチを依頼する。
そして「出世払い」で無償のコーチを勝ち取ってしまったのです。
そしてビーナスとセリーヌも又、親の期待に応えて必死に練習し、めきめきと頭角を現します。

典型的なスポ根サクセス・ストーリーなのでしょうが、正直言って私はこの父親があまり好きにはなれませんでした。
そもそもの動機が、優勝したテニスプレーヤーが4万ドルを受け取る姿をテレビで目撃したからだというのです。
それで娘を二人作り、幼い時からテニスを教え込んだとは。
娘たちの為でも勿論あるのでしょうが、それって自分が金持ちになりたいからでもあるのじゃないの?
リチャードが娘に「ビーナス・ウィリアムズ、お前の一番の親友は誰だい?」と尋ねるシーンがあります。
そしてビーナスは「パパだよ」と答える。
セリーヌも同じ。
娘たちにこんなに愛され、そして実際、見事にテニスの女王に仕立て上げたのだから、我々はもう彼を批判などできなくなってしまうのですが。
あんなに厚かましく理屈っぽく描かれたリチャードの、何処までが本当なのだろうと思いましたが、映画を観たビーナス本人が「父の魂が乗り移っていたかのよう」と感心したのだそうです。
とにもかくにもコンプトンの貧困地域のアフリカ系アメリカ人が、娘たちを自力でテニスの女王に育て上げたということが、どんなに凄いことかということなのでしょう。
原題の「King Richard」の方が、映画の内容をよく表しているように思います。
ウイル・スミスはアカデミー賞主演男優賞にノミネートされています。
公式HP